| 10/20(水) |
「風船」と「紐」の正体が分かった! |
前回、「爪先立ち」&「前のめり」を同時にやるとき、風船( )がふくらむ・・・と報告した。 )がふくらむ・・・と報告した。
太ももの裏、半腱様筋(■)と大腿二頭筋(■)の硬直が、「下腿の深筋膜」を引っぱって、筋膜がふくらむのでは・・・?
そう仮定して、両方の筋肉の硬直をを徹底的にほぐした。 |
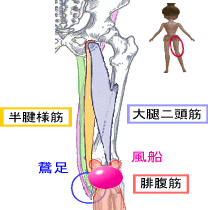 |
風船( )は少し縮んだけど、膝を曲げて坐るだけで痛みが出た! )は少し縮んだけど、膝を曲げて坐るだけで痛みが出た!
まるで悪化したみたい???
仮説のやり直しである。
ここで「膝裏の痛み」についてネットで検索したら、「ベーカー嚢腫」というものがあった。
関節包に溜まった水が後方に流れて溜まってしまう。
弁があるので逆流することができずに、貯留してふくらんでしまうとのこと。
「走り過ぎが原因」と書いてあるサイトもあった。。。
・・・ゾ~ッとした。走れなくなったら私のテニス人生は「お終い」である。
「水を抜いてもまた再発するので、安静にして自然治癒を待つ」と書いてある。
関節包に溜まった水は鍼とお灸で流れてくれる。
自然に抜けるものなら、地道に治療をつづければ、いつかは治るはず・・・と気を取り直した。
それに、私の風船( )はふくらんだり縮んだりするんだから、「ベーカー嚢腫」とは違うはず、と思った。 )はふくらんだり縮んだりするんだから、「ベーカー嚢腫」とは違うはず、と思った。
膝の裏とふくらはぎに徹底的に鍼を打つことにした。
足を上げてみたり、右に向いてみたり、左に向いてみたりして、いろんな角度から打ったので、ものすご~く大変だったんだよ。
前々回のブログで、<「紐」の硬直をほぐせば、「風船」の炎症が引いてくれるかもしれない>と思って、「足底筋」を目がけて鍼を打った話をしたよね。
最後の最後に、膝の裏からふくらはぎへと、細くて硬い「糸」のような筋肉の塊が手に触れた。 |
|
|
風船( )を引っぱっている紐(―)が、確かに存在していたのである。 )を引っぱっている紐(―)が、確かに存在していたのである。
膝裏の中央からふくらはぎの中央の、そのライン上にズラリと鍼を打った。ズシン、ズシンと鍼が響いた。
『この紐(―)の正体は何だろう?』と、筋肉の図をつぶさに調べて、長母指屈筋(■)を見つけた。
母指球で地面を蹴って踵を上げる(=足関節底屈)ときに使われる筋肉である。
膝痛がはじまった頃から、爪先立ちで地面を蹴るときに、足の母指から下腿の骨を通って、違和感が膝関節に伝わることに気づいていた。
ストレッチのときに母指がつりそうになったし。。。
先月やっと母指からつながる足底には鍼を打った。
足底はほぐしたんだけど、ふくらはぎの下方、中央の深部での硬直が残っていたのだ。 |
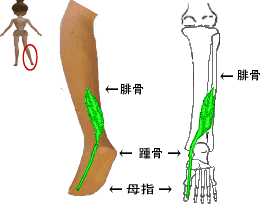 |
| 長母指屈筋 |
| 腓骨の後面の下2/3、骨間膜、隣接する筋間膜中隔と筋膜 |
| ↓ |
| (アキレス腱の下にもぐり、内果の後を通って) |
| ↓ |
| 母指の裏の付け根 |
|
長母指屈筋(■)は母指を屈曲する(親指を曲げる)筋肉だけど、「この屈曲動作をつづけると足関節底屈の補助をする」と本に書いてあった。
鍼でほぐしたあと、とりあえず、風船( )は出なくなった。 )は出なくなった。
翌朝、脛骨に沿って、内くるぶしから膝まで、ズシ~ンと重だるい不快な「冷え」で目が覚めた。
以前から、「脛骨が痛む」症状があったのだけど、筋肉がないのに何で?と不思議に思っていたのである。
長指屈筋(■)が、脛骨の裏側で骨を引っぱっていたのである。
足の外側4本を屈曲する筋肉だけど、「この屈曲動作をつづけるときは足関節底屈が起こる」と書いてあった。 |
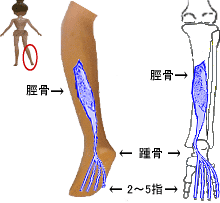 |
| 長指屈筋 |
| 脛骨中部3/5の後面、後脛骨筋(■)をおおう筋膜 |
| ↓ |
| (アキレス腱の下にもぐり、内果の後を通って) |
| ↓ |
| 4本の指の裏の付け根 |
|
脛骨の上にズラリとカマヤミニを並べてお灸をしたら、とりあえず不快な冷えと鈍痛は消えてくれた。
なんと、長指屈筋(■)は後脛骨筋(■)にもくっついていた! |
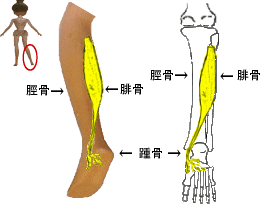 |
| 後脛骨筋 |
| 脛骨後面の外側、腓骨の内側面の上部、深横筋膜、隣接する筋間膜中隔、骨間膜の後面 |
| ↓ |
| (アキレス腱の下にもぐり、内果の後を通って) |
| ↓ |
| 足底のあちこち |
|
ふくらはぎの筋肉を並べてみた。
みんなで協力して「踵を上げて」「爪先立ちになる」運動(=足関節の底屈)をしているのである。
(他にもあるけどここでは省略した) |
|
|
|
|
| 上の筋肉たちを重ねてみると、ほとんどすべてが巨大で強力な腓腹筋(■)におおわれている。 |
|
|
| 歩行に問題がなかったのは「リョコちゃんウォーク」で歩いたからだろう。 |
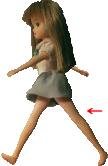 |
膝を伸ばして地面を蹴るときには、二関節筋である腓腹筋(■)が活躍する。
他の筋肉たちは楽して動け、血流が促される。
『爪先立ちで痛みが出るのでは?』と不安に駆られながら歩いたんだけど、治療効果があった!
次々に筋肉の硬直をほぐしつづけて、風船( )が少しずつ縮んでいったんだけど、最後に残ったのが、鵞足(○)につながる内側だった。 )が少しずつ縮んでいったんだけど、最後に残ったのが、鵞足(○)につながる内側だった。 |
|
|
太ももの内転筋、半腱様筋(■)と薄筋(■)と縫工筋(■)は膝の内側の下で、腱が融合して鵞足(○)となって脛骨に張り付いている。
三筋が融合しているので、とても治しにくい。
腓腹筋(■)の内側頭がそこで交差している。
ふくらはぎの内側の筋肉の硬直が激しく、そして治しにくい理由が分かった。
上から下から引っぱられるので、この部位での関節の変形が起こりやすい理由も納得できる。
膝を曲げて「夢中」になって作業をするときは、無意識に足の指で床を何度も握りしめるのだろう。 |
|
|
長母指屈筋(■)と長指屈筋(■)が酷使され、骨に張り付いて固まってしまう。
腓腹筋(■)とも固まって、鵞足(○)を引っぱる。
筋肉たちが固まって、団子になって動くせいで、このラインが激しく硬直するのだろう。
長母指屈筋(■)、長指屈筋(■)、後脛骨筋(■)など、骨や筋膜に付着している部分の多い筋肉は、鍼を打っても治しにくい。
骨に垂直に当たってしまい、「点」で治療することになってしまうからである。
私は透熱灸で治療するけど、自分のふくらはぎにはそれは無理。
ついでに言うと、膝窩筋(■)も骨に付着している部分が多い。自分では治療できないうえに、触ることすらできなかった。
私がもうひとりいて、私の膝の治療をしてくれたら、とっくの昔に治っていただろう。
膝の裏もふくらはぎも、上から触ってツボを取り、硬直をほぐせるのだから。
苦労したおかげで、硬直しやすい筋肉に名前がついて、筋肉と動作の関係が明確になった。
気分は超スッキリ、爽快である。
このまま「完治」してくれれば、「終わりよければ、すべて良し」になるんだけど。。。
私の膝は治る寸前で、あとちょっと・・・である。
でも、歩行で痛みが出たのはほんの一瞬だったし、階段昇降で痛かったのはたったの1日、テニスで痛かったのもたったの1日。
まあまあだった・・・ということかもしれないね~(笑) |