|
症例33・ひざ痛 new1 (2021)
|
|
|
膝関節の構造と治療:テニスプレーヤーを中心に
|
|
|
鍼灸+運動+ストレッチで完治をめざす
|
|
最初の更新(2006/10/18)から15年が経過し、この間にたくさんの患者さんを治療してきました。かなり重症の患者さんもいましたが、「膝痛は治療しやすい」というのが感想です。
肩や肘や手首の関節は可動域がほぼ360度あります。多方面からつながっている筋肉が複雑に入り組んでいるので、問題のある筋肉を見つけるのに苦労します。
でも膝は「伸ばす」と「曲げる」だけなので、筋肉の構造が単純です。
患者さんの訴えを聞きますが「ニュアンス」も大切です。動作と痛みの関連から障害部位を推測します。視診と触診で患部を見つけ、そこにつながる筋肉の硬直を探して治療をします。
関節のどこかに損傷があると、つながっている筋肉が患部を守ろうと硬くなります。硬くなると縮んで患部を引っぱります。引っぱられて悪化し、悪化すると筋肉が硬直し、引っぱられてまた悪化・・・、という悪循環がおこります。
硬直した筋肉をほぐすと、患部への圧が減って痛みが軽減されます。膝の場合はつながる筋肉を見つけやすいので、治療がしやすいのです。
筋肉内部には血管が通っているので、鍼を打った効果が持続していきます。腱には血管がないので、根深い損傷は透熱灸で治療します。
膝関節は「歩く」「走る」という動作だけでなく、体重を支える働きもしています。荷重に耐えなければならない点が、膝関節治療の一番の課題です。 |
|
| 鍼灸治療 |
| *患部の痛みを取る |
| *患部につながっている筋肉の硬直をほぐす |
| *経絡&筋肉の全身のバランスを調整する |
|
| 運動 |
| *強くて柔軟な筋肉は関節を守ってくれる |
| *筋ポンプ作用で血流を促進し、患部の滞りを浄化する |
|
| ストレッチ |
| *可動域の維持はとても重要 |
| *痛みをこらえてストレッチする=治療になる |
| *痛みの出る角度で患部を推定できる |
|
|
|
「運動」は治癒に向かう大きな要素で、「動く人は治る」けど、「動かない人は治らない」のが現実です。力強くて柔軟な筋肉を身につけると、いろんな動作や負荷に対応して関節を守ってくれます。
動いて筋肉が収縮をくり返すと、「筋ポンプ作用」で内部の血流が良くなります。新しい血は温かくて治療能力を持っていますし、澱んだ古い血や小さな邪魔者を押し流してくれます。
きれいに治すためには「ストレッチ」も重要です。
骨や関節への筋肉の付着部は腱になっています。経年劣化でどうしてももろくなっていくのですが、筋肉が柔軟だと圧力が分散され、付着部を守ることができます。
関節には多数の筋肉がつながって、みんなで共同運動をしています。患部につながる筋肉が硬直すると、自由に動けなくなります。同時に動く他の筋肉たちに過負荷がかかって、次々に硬直していきます。
何本もの筋肉が固まってでしか動けなくなると、可動域が狭まります。長くつづくと癒着してしまうこともあって、はがすのに大変な時間がかかります。
可動域が狭まると関節が歪んでいきます。ひとつの関節の歪みは全身の関節に波及していき、ついにはあっちもこっちも「痛い」ことになってしまいます。
人体には百以上の骨格筋があって、それぞれが別個に動きながら、みんなで共同運動をするように構成されています。(神様の設計図どおりに)それぞれが自由に動けるようになると、どんどん治っていくのです。ストレッチはそれを助けてくれます。
「360度リョコちゃんストレッチ」、正しい歩き方は「リョコちゃんウォーク」で紹介してありますので、みなさんも実践してください。
膝関節の構造と鍼灸治療の詳細はそれぞれの症例で順に言及していきます。 |
|
| <→次ページ「ひざ痛・2」では、変形性膝関節症を中心に紹介しています> |
|
|
膝には高校のバスケで痛めた古傷があった
|
|
膝痛の患者さんは多いので、誰の症例からはじめようかと迷っていたのですが、つい最近テニスで自分の膝を痛めてしまいました。膝の内側痛の解説にちょうどいいので、私の症例からスタートすることにしました。
私は高校時代に部活のバスケで膝を痛めました。ダッシュ、ストップ、方向転換をくり返すので、バスケットで膝を痛める女子は多いそうです。
日常生活にもスポーツにもほぼ問題なしでしたが、車の長距離運転ができませんでした。アクセルを踏んでいると、途中で右ひざがガクガクしてしまうのです。一定の角度を保てないのは治っていなかった証拠です。
30歳からの2年間はスポーツウーマン。PTAのバレー部とバドミントン部に入り、バスケのチームも作りました。毎日のようにやっていたら、32歳のときに右太ももの肉離れを起こし、2ヶ月近くも治らなくて、筋肉がすっかり細くなってしまいました。
再開してすぐにバスケで左足首、バドミントンで右足首と、両足とも捻挫をしてしまいました。そのせいで両膝の痛みがぶり返し、台所に立つのは10分が限界という悲惨な状態になりました。
痛みがおさまったあとも腫れが引きません。両足首と両膝がブワブワしていたのですが、33歳で鍼灸と出会ったあとは、すっきりした形に戻ってくれました。
友人に隔週で全身治療をしてもらい、合間にちょこちょこ自分で鍼を打つというパターンをつづけていました。たまに膝に違和感を感じても、浅い鍼を患部に数本打つだけですぐに治ってくれました。
10年前にテニスにはまってからも、膝にはほとんど不都合がありませんでした。壁打ちのやり過ぎで膝が痛んだときも、ストレッチだけで治ってくれました。痛みをこらえてしばらくがんばると、終わったあとに膝がスッと軽くなるのです。
数年前にK先生に「ちょっと痛いから右膝にも鍼を打って」と頼んだら、「こんなにきれいな膝なのに、どこが悪いんですか!」と驚かれたほどだったのです。
テニスクラブには膝を痛めて走れない人、ガニ股で歩いている人がゾロゾロしてます。
「あんだけガンガン走っても、テニスで膝を痛めたことは1回もないよ~」と、ずっと自慢していたのですが・・・ |
|
|
シングルス試合のあと古傷→膝全体に波及
|
|
シングルスをはじめてから6年ぐらいになります。ラウンドロビンでは1日5試合とかやるのですが、全力疾走しても膝にはまったく問題がありませんでした。
去年からJOPのベテランのシングルスの試合に出るようになりました。今年の6月、4回目の出場でやっと1回戦に勝利しました。翌日の2回戦は40位との対戦になり、スコアは1-8で負けたのですが、えんえんとラリーがつづいて、1時間ぐらいの長い試合になりました。(→2021/6/11)
翌日、「あれ?膝が痛い?」と驚きました。
患部(■)は右膝の内側です。つながっている内転筋(■)がガチガチに硬直して、患部を引っぱっていたのです。
太ももの内側と外側(■)が激しく硬直していました。 |
|
 |
|
ダブルスは半面を守ればいいので、ほとんどが前後の動きになります。鍛えてあるので問題なしです。
シングルスは全面をひとりで守らなければなりません。左右に走らされて、地面を蹴っての方向転換、そしてダッシュをくり返します。
内転筋(■)の酷使で付着部(■)へ圧がかかり、そのせいで痛みが出たのでした。
内転筋(■)にズラリと置鍼して硬直をほぐしたら、患部(■)の痛みは2日でなくなりました。ついでに言うと、全身のあらゆる筋肉が硬直していて、次から次へと悲鳴をあげました。公式戦のトーナメントでは、全力以上の力を使う・・・ということですね。
2週間後、長々とシングルスをやった翌朝、また右膝の痛みがバクハツ、今度は右ひざ全体がダメになっていました。
故障部位をかかえて走ったので、共同運動をしている筋肉たちに過負荷がかかってしまったのです。 |
|
|
|
|
| ■ |
患部=古傷がバクハツ |
| ■ |
大腿四頭筋が腫れて、全体に脆い感じで、膝関節の支持力が低下 |
| ■ |
裏側全体は渋い感じの不快感 |
| ■ |
ベッドへの前傾姿勢で圧がかかる |
| ■ |
パソコンの前で長時間坐ると固まる |
|
|
『これは古傷(■)だったのか!』とはじめて気がつきました。故障を侮ってしまいました。シングルスで膝を痛めてチャレンジをあきらめた人がたくさんいます。
なんとしても完治を目指したいと思ったので、テニスを休んで治療に専念することにしました。 |
|
|
|
最後に残った薄筋がメインの患部と判明
|
|
日常生活は仕事も家事も普通にこなしました。安静にすると筋力が落ちてしまいます。安静状態で「治った!」と思っても、動けばすぐに再発してしまうからです。
360度リョコちゃんストレッチで痛む角度は念入りに。10秒ずつこらえて痛みが薄れるまでがんばりました。痛みを眠らせずに掘り起こすのです。筋肉が固まると、元通りにするのは至難の業なので、可動域を維持しながら治します。
犬の散歩はリョコちゃんウォークです。ストレッチと筋トレを兼ねているので、痛みが出てもがんばって正しく歩いて「治療」します。
3年前から自分の治療はすべて自分でやっているので、客観的に外から全体を診ることができません。ストレッチで痛むところが要治療のポイントです。
硬直した筋肉には鍼を打って、古傷(■)には透熱灸をしました。
歩くのも階段昇降も問題なしで、正座も「うんこ坐り」もできました。ただ、ふいに床にしゃがもうとするときにブレーキがかかりました。
ゆっくりやればできるのですが、潜在意識が「要注意」と言っています。「ふいにしゃがめる」かどうかを目安にしました。 |
|
|
|
|
右膝全体が腫れっぽくなっていました。「形」が左膝と同じになるまではテニスはお休みです。
日常生活になんの問題もなくなってから再開するほうが、治癒への早道です。故障をかかえて激しいスポーツをすると、他の部位に障害が波及してしまいます。
こじらせると長引いてとてもやっかいなことになるし、フォームも崩れてしまいます。
「壊し」てから2週間後、発症から1ヶ月で、右膝の腫れが引き、膝裏の「渋い」感じも、膝関節の支持が不安定な感じもなくなりました。
「あとから悪くなったところから順に治っていく」ので、最後に残るのが最初に悪くなったところと分かります。
軽い痛みが古傷(■)に限局されて、「やりながら治す」時期がやってきた(と思いました)。テニスのときは用心に前後左右に4本、テーピングをしました。
完全に治るまでは練習とダブルスだけにして、シングルスはお預けです。
テニスの間は痛みもなく、ガンガン動けました。でも翌朝に痛みが戻ってしまうのです。膝全体が腫れぼったくなる日もありました。
それでもなんとかテニスをつづけ、治っていく過程で、メインの患部が薄筋(■)の付着部だったことがわかりました。 |
|
| <*薄筋(■)中心のテーピングはブログで紹介してあります→2021/8/11> |
|
|
|
|
膝の内転筋である、薄筋(■)、縫工筋(■)と半腱様筋(■)の三筋は、腱膜様に広がって、最後は膝の内側に癒合して終わります。停止腱がガチョウの足に似ていることから、鵞足(○ガソク)と呼ばれています。
膝の内側が痛めやすく、そして治しにくいのは、鵞足で腱が融合(■+■+■)しているせいでしょう。
私の古傷は薄筋(■)でしたが、連鎖反応で障害がみんなに波及してしまいました。
骨や筋肉のイラストは解剖学の教科書からスキャンして、自分で組み合わせたものなので、おおよその位置です。
ついでに「リョコちゃんストレッチ」での、それぞれの筋肉に対応したストレッチのやり方も紹介します。 |
|
| 大腿前面 |
| ■薄筋は(骨盤の)恥骨結合→脛骨内側(○=鵞足) |
| ■縫工筋は(骨盤の)上前腸骨棘→脛骨内側(○=鵞足) |
|
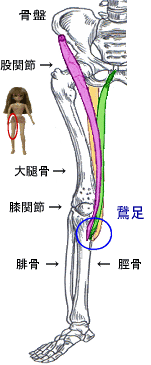 |
|
|
| ■薄筋のストレッチ |
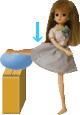 |
|
 |
| 太ももの内側 |
手で足を押す |
|
|
|
|
|
| 大腿後面 |
| ■半腱様筋は(骨盤の)坐骨結節→脛骨内側(○=鵞足) |
| ■大腿二頭筋は(骨盤の)坐骨結節→脛骨外側 |
|
|
|
|
|
| ■半腱様筋のストレッチ |
| *鵞足を構成している筋肉なので、ここにも痛みが波及します。 |
|
|
 |
| 足先を外に |
|
 |
| 足をそろえて前屈 |
|
|
 |
| 開脚で前屈 |
|
| ■大腿二頭筋のストレッチ |
*半腱様筋と同じ坐骨結節にくっついているので、
膝裏の外側にも痛みが波及します。
|
| *この筋肉の治療も必須です。 |
|
|
 |
| 上体を倒す |
|
|
 |
| 足をそろえて前屈 |
|
|
|
|
|
|
|
膝の裏側: ふくらはぎの治療は必須
|
|
内転筋の付着部の古傷(■)を治療すれば、私の膝痛が「完治」するかな・・・と期待したのですが、大きな間違いでした。
自分では手の届きにくい膝の裏側の痛みが日に日に悪化して、膝関節全体に波及してしまいました。
ふくらはぎは裏側で下から膝関節を支えているのですが、こんなにたくさんの筋肉があって、みんなで協力して足関節の底屈、「踵を上げる」「爪先立ちになる」「地面を蹴る」「床を踏みしめる」などの運動をしていたのです。 |
|
|
|
|
|
|
ふくらはぎの筋肉たちを重ねてみると、ほとんどすべてが大きな腓腹筋(■)におおわれています。
使わずにいると、ゆるゆるになって筋力低下します。腓腹筋を鍛えましょう! |
|
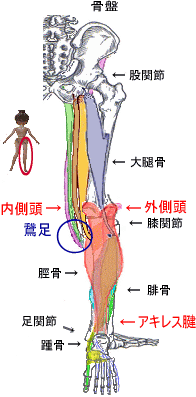 |
|
腓腹筋(■)は大腿骨の下方、膝の裏側からはじまっています。
内側頭は太ももの内転筋である鵞足()と交差しています。
外側頭はハムストリングスの大腿二頭筋(■)と交差しています。
下腿の裏側を通って、、アキレス腱になって踵にくっついています。
腓腹筋(■)を柔軟に保ち、筋力をつけることが重要です。
膝関節の上からはじまって踵骨にくっつく「二関節筋」なので、膝を曲げると収縮できません。
しっかりと膝を伸ばして、爪先立ちで地面を蹴って歩くと、筋トレもできるし、ストレッチにもなります。
膝を曲げてペタペタ歩いたり、ドカドカ走ったりはNGです。
パソコンに向かうなど、長時間坐りつづけるのもNGです。 |
|
| ふくらはぎのストレッチ |
ストレッチと筋トレを兼ねた「リョコちゃんウォーク」で歩きましょう。
しっかりと膝を伸ばして、爪先立ちになって地面を蹴って歩きます。 |
|
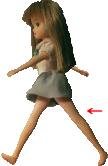 |
|
| 腓腹筋(■)の下にある他の筋肉たちは楽して動くことができ、収縮によって血流が促されます。 |
|
|
|
膝関節に障害があると、支えている下腿の筋肉も過緊張して硬直します。ふくらはぎの硬直を取りのぞくと、患部の痛みが楽になって、すいすい歩けるようになります。
ふくらはぎにはきっちり鍼を打って硬直をほぐしましょう。アスリートにはパルスをかけることもあります。取りきれない硬直にはお灸を追加することもあります。
患者さんの治療をするときは、外から眺めて、触って、押して、深部にある硬直をほぐすことができます。あまりにも簡単に治療できたので、自分の膝裏とふくらはぎにこんなにも苦労するとは・・・、想定外でした。
ふくらはぎの個々の筋肉治療の詳細は次ページで紹介します。(→ひざ痛・2) |
|
| *私の膝痛は・・・ |
自分のふくらはぎへは横向きになって鍼を打ちました。腓腹筋(■)だけでなく、深部の筋肉へも打てていたと思っていましたが、取り残しがあったのです。
もっと身体が柔らかければいいのですが、膝が曲がって患部が隠れてしまうのです。もちろん、透熱灸もできません。
膝裏の内側の硬直が残ってしまい、日に日に悪化して行きました。 |
|
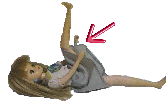 |
|
| 「素人臭い」からやらずに治そうと思ったのですが、カマヤミニの登場です。 |
 |
鏡を背にして立ったままでやりました。膝裏がほぐれてくれるのですが、しばらくたつとまた硬直がはじまってしまいます。
「時すでに遅し」でした。膝裏を引っぱっているふくらはぎに原因があったのです。
最初からもっとふくらはぎに注目していればよかったのですが、膝痛がなかなか治らないので、テニスを少な目にしたことが膝裏の悪化に拍車をかけました。
空いた時間、パソコンに向かってこのページを書いていたことが一番の原因だったのです。 |
|
|
|
|
|
膝の外側痛は治しやすい
|
|
2016年、Kさん(当時50歳、女性)が左膝の痛みでビッコを引いて来院しました。
新しく習ったコーチに「まともに歩けないんじゃ、レッスンは無理」と言われ、彼の紹介で仕方なしに、嫌々来たのは明らかでした。私を信用していなかったので、彼女の治療はほんとうに大変でした。
(患者さんとの相性は重要ファクターです) |
|
|
|
| ■ |
左膝=痛みは外側だが、全体に腫れ |
■ |
| ■ |
左内転筋=筋力低下 |
|
|
背骨がまっすぐ、筋肉は縮んでよじれ |
■ |
|
腰痛=左腰が外方に張り出している |
■ |
|
左志室は硬いコブ |
■ |
|
ふくらはぎ=筋力低下でゆるゆるに(アキレス腱あたりの皮膚が黒ずんでいた) |
■ |
|
|
5年前から左膝の故障をくり返していたそうです。外側の痛みで歩行も困難とのことでしたが、膝全体がパンパンに腫れていました。
膝の外側痛を治すのはわりと簡単で、腸脛靭帯(■)を中心に治療します。
腸脛靭帯は骨盤(腸骨稜)からはじまり、太ももの外側を垂直に下って、膝下(脛骨)につながる、帯状の強力な靭帯です。 |
|
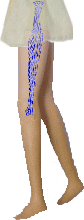 |
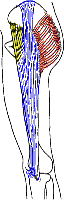 |
| 横 |
|
|
腸脛靭帯で終わる大腿筋膜張筋(■)と、後方から支える大殿筋(■)が収縮すると・・
→腸脛靭帯(■)が緊張
→膝関節が伸び、下肢は伸展位で固定
→体幹の直立が維持されます。
膝を伸ばして直立するのは、腸脛靭帯(■)の働きで、そのとき大腿四頭筋( )は脱力しています。(立っている人の後ろからグイッと膝を押すと、ガクンと膝が曲がるのはそのためです) )は脱力しています。(立っている人の後ろからグイッと膝を押すと、ガクンと膝が曲がるのはそのためです)
足と腰でん部にはパルス治療。左膝のまわりには透熱灸のあと、腫れが引くまでマッサージを念入りに行い、テーピングを6本貼りました。
治療のあとはビッコを引かずに、すいすい歩いて帰って行きました。 |
|
|
5年前の古傷、内側痛があらわれた
|
|
『もう来ないだろうな』と思っていたのですが、Kさんは2週間後に来院しました。試合で優勝した後、また膝の痛みがバクハツして、ビッコを引き引き歩いてきました。
外側(■)の痛みは1回で取れたのですが、内側(■)の痛みがバクハツしていました。
Kさんは週に6日以上テニスをし、月に3回以上試合に出ているという怒涛のテニス・ジャンキーです。
毎日筋トレをガンガンやって、毎日整骨院にマッサージに通い、病院ではときどき水を抜いてもらい、月に2回ヒアルロン酸の注射を受けているとのことです。 |
|
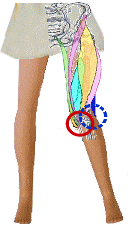 |
|
「せめて階段昇降が普通にできるまでは、テニスは休んだほうがいいよ」と言ったのですが、ぜんぜん聞いてくれません。たぶん、「治る」とは思っていないので、騙し騙し「つづける」ことを選択してきたのだと思います。
治療するとすいすい歩いて帰るのですが、練習と試合をガンガンやって、また歩行困難になって現れます。
それでもだんだん部位が狭まっていきました。
Kさんは、「5年前にはじめて膝が痛くなったのがここでした」と思い出しました。それでシングルスをあきらめたそうです。そのあとはダブルスの試合に出続けて、ときどき膝痛が大爆発を起こしたのだそうです。 |
|
| 初発 |
→ |
悪化の一途 |
→ |
治る過程で |
| 患部は内側 |
膝全体に波及 |
→ |
患部の痛みが眠る |
→ |
外側に痛み |
患部の内側痛を再発見 |
|
|
4回目、「病院でヒアルロン酸の注射を受けた」と言うので、「鍼灸かヒアルロン酸か、どちらかを選んでほしい」と言いました。
ヒアルロン酸の注射を受けた患者さんで、膝が曲がったまま伸びなくなった人、伸びたまま曲げられなくなった人などが、5人もいたのです。
鍼灸治療で痛みは取れて、普通に歩けるようにはなります。でも、どんなに治療をしても、どんなにストレッチをしても、可動域が1ミリも広げられませんでした。
私の推測では、どうやら「体内ギプス」が作られるようなのです。「薬」で起こった障害を治す「薬」はありません。
可動域が戻らないと「完治」は望めません。がんばって治療しても、併用して治らなかったら、「鍼では治らなかった」と思われてしまうのがイヤなのです。 |
|
|
|
|
ここで第1シードの大腿四頭筋( )の登場です。膝関節を支える最大の筋肉なので、関節のどこかに不具合があると必ず酷使され、膝の治療には必須の筋肉です。 )の登場です。膝関節を支える最大の筋肉なので、関節のどこかに不具合があると必ず酷使され、膝の治療には必須の筋肉です。
全体としては強力な下腿の伸筋で、直立歩行に必要です。「階段をのぼる」「座位から立ち上がる」「座位で下腿を持ち上げる」ときなどに強く収縮しますが、「太ももを上げてダッシュする」ときにも使います。
大きな負荷がかかって病んでしまうと、腫れてブワブワになり、膝関節の支持がゆるんでしまいます。硬直と痛みを取りながら筋肉を鍛えましょう。
| 大腿四頭筋 |
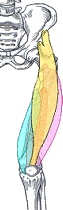 |
|
|
| 大腿直筋 |
前面の中央にあって、骨盤の下前腸骨棘と寛骨に付着。
大きな力を出すメインの筋肉。二関節筋で、股関節の屈曲と膝関節の伸展を行う。
(ボールなどを蹴るときに使うので「キックする筋」と言われている) |
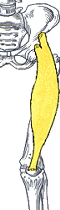 |
|
| 中間広筋 |
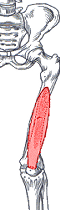 |
大腿直筋の下にあって、大腿骨に付着。
鍼はすぐ骨に当たるので透熱灸で治療する。 |
|
|
|
| 内側広筋 |
骨に付着
して、内に
ふくらむ |
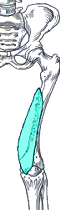 |
|
| 外側広筋 |
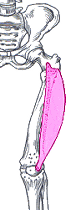 |
骨に付着
して、外に
ふくらむ |
|
|
|
| 膝蓋靭帯 |
 |
膝蓋骨(お皿)から
膝蓋靭帯を介して
脛骨結節へ |
|
|
大腿四頭筋( )は太ももの前面のふくらみをつくり、膝蓋骨(お皿)の下に入って、膝蓋靭帯(■)を介して脛骨結節にくっついています。 )は太ももの前面のふくらみをつくり、膝蓋骨(お皿)の下に入って、膝蓋靭帯(■)を介して脛骨結節にくっついています。
膝蓋骨の下にある索状の膝蓋靭帯は神経疾患の検査で使われます。足を下げて椅子に座って、ひざの下を強く叩かれると、足がピョンと持ち上がる=「膝蓋腱反射」で、みなさんも記憶にあるでしょう。
膝蓋靭帯がくっついている脛骨結節は、ひざの下にある骨のでっぱりで、大腿四頭筋を鍛えるほどに発達して大きくなります。 |
|
 大腿四頭筋のストレッチ 大腿四頭筋のストレッチ |
|
|
|
|
大腿四頭筋( )を上述した筋肉と重ねてみました。 )を上述した筋肉と重ねてみました。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大腿四頭筋 |
| ■内側広筋 |
| ■大腿直筋 |
| ■中間広筋 |
| ■外側広筋 |
| + |
■膝蓋靭帯 |
|
|
|
| *私の膝痛は・・・ |
テーピングをしながらテニスをつづけていたのですが、翌日の痛みがどんどん強くなっていきました。
『休んだほうがいいかな?』と思いつつ、ダブルスをやったら、テニスのときに痛みが出て、右膝をかばっている自分がいました。
そのあと大腿四頭筋に障害が波及しました。関節の支持がゆるんでブヨブヨに腫れ、正座や階段昇降でも痛むようになりました。
膝痛のすべての症状が出揃ってしまったのです。(自分を過信した報いですね・・・)
患者さんたちが自分でやっているお灸を試してみることにしました。
カマヤミニをお皿のまわりにするのですが、上にものっけてみました。ものすごく気持ちが良くて、熱さがジンジン浸透していく感じで、関節の奥まで温まっていきます。 |
|
 |
|
ワインを片手にテレビを見ながら、4つぐらいずつ火をつけて、消えたら別のポイントへのせて、えんえんとくり返しました。
翌朝には激しい痛みが消えていました。正座の痛みが激減し、階段昇降の痛みもなくなりました。まだ関節内部に寒風が吹くような「冷え」があって、「壊れて」いるという感じです。
2回目のカマヤミニの翌日には、冷えもなくなり、関節の安定感が戻りはじめました。お皿のカマヤミニの効果はすごいですね!
すぐにでも走り出せそうでしたが、「治りかけ」にこじらせるとまた長引いてしまうので、用心、用心です。ゆっくりスタートすることにしました。 |
|
|
|
|
(四頭筋の)内側広筋の神経障害
|
|
1ヶ月後(5回目)、Kさんは試合を2つやったそうで、少し腫れが出ましたが、膝の形はまあまあきれいになりました。透熱灸は卒業し、鍼(+パルス)治療だけにしました。
ふくらはぎの筋肉はまあまあでしたが、左内転筋は筋力低下したままです。可能性としては、①廃用性萎縮、②筋繊維が石灰化している、③神経が麻痺している、の3つが考えられます。
| ① |
廃用性萎縮は使われずにいたのが原因なので、筋トレですぐに戻ります。 |
| ② |
筋繊維が1本でも石灰化すると、伸び縮みができなくなります。筋力は戻りますが、そこから筋肉全体が硬直していきます。 |
| ③ |
圧迫が長引くと神経が変性してしまい。筋肉が神経性萎縮をおこします。パルス治療と筋トレでなんとか回復はしてくれるのですが、100%は望めません。
|
2ヵ月後(7回目)、へこんでいた内転筋が少し盛り上がってきて、手で触れるようになりました。Kさんの硬直している内転筋をグイ~ッと押しても、無反応です。普通の人は飛び上がるほど痛いのに、「ぜんぜん痛くありません」と言うのです。
鵞足をつくる内転筋ではなく、前方にある大腿四頭筋( )の内側広筋(■)が神経性萎縮をおこしているようでした。 )の内側広筋(■)が神経性萎縮をおこしているようでした。
パルスをかけて眠っている神経を「叩き起こす」感じです。
本人ががんばって鍛えると、「半年かかって5割、1年かかって7・8割」が限界ですが、なんとか「使える」筋肉になる可能性があります。
筋トレをやりすぎると余分な筋肉がついて身体が重くなります。軽量化はスピードアップの基本です。Kさんに「神経が変性を起こしている内側広筋(■)だけを鍛えるように」とアドバイスをしましたが、ピンと来なかったようです。
内側広筋(■)が虚弱なので、共同運動をしている他の筋肉たちに過負荷の連鎖反応がおこります。そのうえ全身の筋肉バランスにも悪影響を与えます。Kさんの腰は大きくゆがんでいました。 |
|
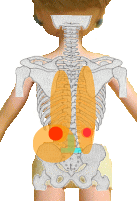 |
|
左志室(■)はコブのように盛り上り、左腰が外方に張り出していました。よくそこからぎっくり腰になったそうです。<→「腰の上方:志室の痛み」で紹介しました>
背中の筋肉はよじれるように硬直していました。
整骨院では「膝の痛みは腰から来ている」と言われ、「このコブは一生取れない」と言われたそうですが、私の考えは違います。
Kさんは両手バックハンドの強打が武器です。バックハンドは左足が軸足で、内転筋で踏ん張って打ちます。
内転筋が使えない状態でバックハンドの強打をつづけたために、左志室に過負荷がかかって、コブのように固まって外方に張り出してしまったのです。
年配のテニスプレーヤーは背中で強打する人が多いのです。足やでん部の故障をきっかけに下半身との運動連鎖が断たれてしまったこと。そして身体の柔軟性が失われた結果です。背筋だけで強打をつづけたために極度に硬直してしまったのです。
背中~腰でん部の硬直をほぐしつづけた結果、1年ぐらいでコブが取れ、腰椎もほぼ左右対称になりました。
1度ぎっくり腰を起こしたことがあるのですが、1回で治って、翌日の試合では問題なく戦うことができました。 |
|
|
1年でシングルスを再開、3年で全日本に
|
|
3ヶ月後(11回目)のときに「走れた」と報告してくれました。8ヵ月後(25回目)にはシングルスもできるようになり、11ヵ月後(36回目)にダッシュができるようになりました。太ももを持ち上げてダッシュをする、大腿四頭筋( )が使えるようになったのです。 )が使えるようになったのです。
内側広筋(■)の筋力は5割ぐらいなので、他の筋肉に過負荷がかかります。大腿直筋(■)の上方の付着部、鼡径靭帯(■)や股関節(■)の痛みがはじまり、腸腰筋などへの痛みの連鎖反応に悩まされるようになりました。
9ヵ月後(29回目)、「左内側の筋肉をたまに使ってみたら、かばいたい自分がいた」と報告してくれました。やっと内側広筋(■)の存在を認識してくれたようです。
膝の内側痛の治療をするときは、膝の下に枕をおいて足を外に広げます。 |
|
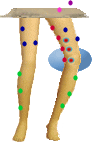 |
| ■ |
内側は2列以上 |
| ■ |
鼡径靭帯 |
| ■ |
股関節 |
| ■ |
太ももに数本 |
| ■ |
脛に3本 |
|
|
|
内ももから膝の内側へは2列以上、硬直している筋肉にズラリと鍼を並べて打ちます。それ以外は、太ももの内と外にそれぞれ1・2本、脛には3本が基本です。鼡径靭帯や股関節に痛みがあるときは、硬直部位に置鍼します。
Kさんには数本にパルスをかけました。
1年後、KさんはJOPのシングルスで全国にツアーに出るようになりました。
「治療のあとの試合は勝てる」「しばらくたつと負ける」ようになって、Kさんは「メンテナンスが必要」と思うようになりました。鍼灸をすると身体の切れが良くなって自在に動けるのですが、硬直がすすんで身体が固まると、動きが鈍くなってしまうのです。
1年半後(59回目)には、シングルスの試合で後脛骨筋の肉離れを起こしました。ふくらはぎの筋力はまだ発展途上でした。(→「ふくらはぎ(後脛骨筋)」
Kさんはシングルスに燃えて、毎日ハードなシングルスをやるようになりました。筋力がついていったとはいえ、内側広筋(■)は薄くて、7・8割ぐらいが限界でした。
膝痛はなくなったのですが、右肩や腰、背中など、次々にあちこちに痛みがおこりました。「ハードなテニスとゆるいテニスを組み合わせるように」とアドバイスしましたが、聞いてくれません。
激しい運動でたまった疲労物質をゆっくり動いて流す、そうしないと硬直がマックスになるので、鍼灸だけでほぐすのはほんとうに大変なのです。
3年後(108回目)、シングルスで全日本に出場することができました。
その2ヵ月後(117回目)が最後の来院になりましたが、Kさんはその後もテニス街道まっしぐらに突き進んでいるようです。 |
|
|
|
|
2016年の春、テニスクラブのベンチでNさん(当時65歳、女性)とバッタリ会いました。
私が「右腕を痛めて8日間もテニスを休んだんだよ」と言ったら、「たったの8日ならいいじゃない。私なんか3ヶ月よ。久しぶりに壁打ちに来たの」と言うのです。ミックスの試合で優勝したのですが、がんばって走りすぎて左膝を痛めたのだそうです。
2年半前にムチウチで1回、腰痛で1回治療に来たことがあるのですが、深い鍼が怖いと言うのです。
彼女の足を押しながら、「でも、ここに深い鍼を打たないと治らないよ」と言ったら、「じゃあ、そこは我慢する」となって、「膝以外は浅い鍼とお灸だけ」という話がまとまりました。
来院時は、「今は普通に歩けるようになったけど、左足1本で立つとき、膝を曲げるときに、内側と裏側が痛い」とのことでした。
右の膝裏にもひどい硬直がありました。筋肉が針金のようになって、膝裏を引っぱっていたのです。
Nさんには両膝の裏に鍼をびっしり置鍼したあとで、透熱灸も行いました。
ダブルスをやってみたら、ゲーム中の痛みはなくなったのですが、終わったあとで痛みが出たそうです。
テニスの再開は練習が中心で、ダブルスは1セットのみという慎重なスタートになりました。
1ヶ月後(7回目)、左膝裏のしこりが小さくなっていき、すこし走れるようになりました。
2ヵ月半後(14回目)、「自転車、階段昇降での痛みがなくなり、ゴルフも大丈夫」になりました。
テニスをするとちょっと悪化、治療してまたテニスのくり返しです。
「他は浅い鍼だけ」という約束でしたが、ある日いつものパターンで腰に深い鍼を打ちはじめ、「あ、ごめんね」と抜こうとしたのですが、「いいわよ」となりました。 |
|
|
|
| 左膝 |
| ■ |
全体に腫れ |
| ■ |
内側痛 |
| ■ |
裏側に痛みとしこり |
|
|
| 右膝 |
| ■ |
細くてか弱い |
| ■ |
裏側に痛み |
| ▲ |
内側半月板損傷 |
|
|
|
5ヵ月後(23回目)、左膝にはとくに「腫れ」がありません。
「もしかしたら、右膝に比べて左膝のほうが筋肉がある、ということじゃないの?」とききました。
ちんまり無言の右膝がずっと気になっていたのです。
Nさんは、「36歳のとき右膝の内側半月板を損傷したのよ」と教えてくれました。スキーの一級を持っているのですが、試験のときにインストラクターのジャンプを真似して跳んだら、着地で失敗して、担架で病院に運ばれたのだそうです。
膝関節の内部、大腿骨と脛骨の間には、外側と内側に半月板があってクッションの役割をしています。
Nさんは内側の半月板が欠けていて、かけらがときどき飛び出してくるのだそうです。「ロッキング」といって膝が動かせなくなって、ものすごく痛いのだそうです。
はじめてロッキングを経験したときに、そのままでは歩けないので、自分で押し込んで病院に行ったそうです。医師に「自分で押し込むとは何事だ!飛び出したまま来ないと診察できないじゃないか!」と怒られたのだそうです。
Nさんは、「押し込まないと歩けないから病院に行かれないんだもの。なんだ、医者はいらないのねと思って」と、自分で押し込んできたのだそうです。 |
|
|
|
|
右膝をかばってテニスをつづけてきたので、左膝の筋肉だけが発達したのです。右膝はか細くて、左に比べると大人と子どものような差がありました。
右膝の裏の筋肉の硬直が激しいのは、損傷部位を守るために筋肉が過緊張をつづけたせいだったのです。
壊れた半月板は治せないけど、引っぱっている筋肉の硬直をほぐせば、半月板への圧迫がゆるむはずと思いました。
(今のところ、1回もロッキングを起こしていません)
「右膝を使って筋肉を鍛えるように」とNさんにアドバイスしました。
左足だけに頼っていると、左足を壊したときに悲惨ですし、左右両方を使わないとテニスのパフォーマンスが低下する一方になってしまいます。
その5ヵ月後(35回目)には、右膝のほうが痛くなってしまいましたが、それは越えなければならないハードルです。
初診から1年後(37回目)に、練習のときはギプスをはずしてキネシオだけでテニスができたと報告してくれました。
ギプスのようなサポーターをつけていると、可動域が狭まってしまい、筋肉もつきません。Nさんは不安だからと両方を併用していたのです。
他にもいろいろな愁訴があったのですが、ここでは省略します。
Nさんはどんどん走れるようになって、手ごわい敵になりました。「テニスならごまかしがきく」けど、スキーは激しく膝に負担がかかるそうですが、スキーも大丈夫でした。用心深く膝の故障とつきあったおかげか、順調に回復してくれました。
Nさんは昔スキー仲間の鍼灸師にお灸を教わったそうで、自分でもちょこちょこお灸をしていました。ストレッチも真面目に取り組みましたし、「痛くても我慢してちゃんと歩く」努力もしてくれました。クラブには悪い見本がたくさんいるので反面教師になります。「ガニ股になるのは絶対にイヤ」とがんばったのです。
コロナで1年半ぶりの来院になったのですが、70歳になった現在、Nさんの膝は形がとてもきれいで、しかも両膝の太さがほとんど同じなっていました。 |
|
|
|
|
2017年に来院したYさん(当時62歳、男性)もテニスクラブの仲間です。1ヶ月前から膝が痛くて曲げられなくなったそうです。
コートでアドバイスを求められたので、「可動域が大事」と話して、ストレッチをすすめました。「正座」と「うんこ坐り」をがんばったのですが、自分では治しきれずにやって来ました。
かなりのテニスジャンキーでシングルスもやっています。足が速いのが自慢なので、膝の故障はこたえます。左膝は全体に腫れていました。
左膝をかばって強打をつづけたせいでしょう。左の背筋がガチガチに硬直していました。背中と腰にパルスをかけたらきれいにほぐれてくれました。足にもパルスをかけました。
治療のあと、しゃがんでもらったのですが、裏側でコックしてしまうそうです。ここから追加治療で、患部の硬直を徹底的にほぐします。
頑固な硬直は外側(■)と裏側(■)でした。もう一度うつ伏せに寝てもらい、硬直部位に鍼を打ったあと透熱灸をしました。 |
|
|
|
|
またしゃがんでもらったら、「さっきより曲げられる」とのこと。またうつ伏せになってもらい、残った硬直に鍼を打ちました。
これをくり返すたびに、ちょっとずつ曲げられるようになっていきました。
「これ以上は無理」というところまでやって、初回の治療を終了しました。
2回目の来院は2週間後でした。まだ痛みがあって、きっちり曲げることができないそうです。
左膝の腫れがあったので、大腿四頭筋( )のお皿のまわりに透熱灸をしました。 )のお皿のまわりに透熱灸をしました。
今回はふくらはぎ(■)の硬直が強く、びっしり鍼を打ってパルスをかけました。残った硬直にカマヤミニを4つ並べてお灸をしたら、きれいにほぐれてくれました。
Yさんは「正座もうんこ坐りも完璧だ」と言って、すっかり治ってガンガン走るテニスができるようになりまいた。
いろんなスポーツ愛好家を治療してきましたが、男性のほうが治しやすいという印象です。仕事をしているので、遊べるのはせいぜい週に2回ぐらいです。あまり悪化せずにすむのでしょう。
KさんやYさんのように、主婦だと毎日テニスができます。騙し騙しやっているうちにとことん壊してしまった女性がたくさんいます。男性でも、仕事よりもテニス中心、退職後にテニス三昧という人たちは根深い障害を抱えてしまうことがあります。 |
|
|
|
|
2015年に来院したMさん(当時52歳、男性)はテニスクラブの新入会員でした。先輩に言われて「お付き合い」でやって来たので、彼とはそれが初対面でした。
25歳からテニスをはじめ、仕事よりもテニス優先でやってきて、全日本にも出たことのある強者です。左膝痛で、「10年前にMRIでお皿の内側にギザギザができている」と言われたそうです。
平気なときもあるそうですが、筋肉が骨の棘にこすれて炎症を起こすと、「歩くのもつらい」「踏ん張れない」となり、何度も水を抜いたそうです。
医師に「骨のギザギザは手術で簡単に取れる」と言われたそうですが、しばらくテニスができなくなるので、騙し騙しやってきたそうです。
左大腿四頭筋は筋力がなくだらりと弛緩していました。骨棘にこすれて痛みが出ると、筋肉を緊張させることができなくなってしまうようです。
半年後(また先輩に言われて)今度は右膝痛で来院しました。右足だけで怒涛の走りをしていた癖が抜けず、過負荷がかかってしまったのです。
前回治療後に左膝の手術をしたそうです。内視鏡でちょいちょいっと棘を取り除くという簡単な手術で、翌日からテニスができたそうです。西洋医学を大絶賛していました。
Mさんはバイクも趣味なので、とても話があって、テニスを教えてもらったりしてすっかり仲良しになったのですが、「鍼灸」というものをまったく信用していませんでした。 |
 |
2014年に来院したHさん(当時49歳、女性)は、左膝痛が主訴で、1週間前から「階段昇り降りで痛む」「正座ができない」とのことでした。そのときの膝痛は4回の治療で治ったのですが、他にもいろいろと爆弾を抱えていました。
1年前に右耳の感音性難聴を患い、3回発症し、耳鳴りがあって「低音が聞こえにくい」そうです。
初回の治療の翌日から耳鳴りが悪化して、フラフラ感が1週間もつづいたそうです。これはメンケン反応です。
感音性難聴は私もなったことがあります。<→症例27「めまい・1改」>
私はすぐに治療をしたのできれいに治りましたが、1年もたっているので神経が変性をおこしている可能性があります。
元通りになるのは難しいと思いますが、Hさんは必死でした。コンピュータ-関係の会社で営業をしているので、システムのトラブルがあると苦情処理に追われます。
ストレスと聞こえの悪さにはあきらかな相関関係がありました。
背骨の形はまっすぐで、背中から腰までガチンガチンに硬直して板のようになっていました。若い頃に腰椎椎間板ヘルニアの手術をしたそうで、腰痛もとてつもなく難物でした。
Hさんの治療の中心は右耳と腰背部だったのですが、半年後(19回目)からまた左膝痛がはじまりました。
8ヵ月後(23回目)には階段昇降で痛むようになり、「体重移動のときにはずれそうな感じ」がするとのことでした。
主訴が左膝痛になっていきました。がんばって歩いてくれ、会社のトイレで立位のストレッチもはじめてくれたのですが、今回は一進一退です。 |
|
|
|
| ■ |
右耳=耳鳴りと感音性難聴(低音) |
■ |
| ■ |
右の首に硬直 |
|
| ■ |
右の鼡径靭帯と股関節に痛み |
|
| ■ |
左膝痛=1週間前から |
■ |
|
筋肉が縮んで板状になって硬直 |
■ |
|
腰痛(昔椎間板ヘルニア) |
■ |
|
ふくらはぎの硬直 |
■ |
|
|
10ヵ月後(31回目)、上述のMさんが来院したあと、Hさんの大腿四頭筋を眺めてみたら、筋肉が弛緩してゆるゆるになっています。
「どういうときに痛いの?」とあらためてきいてみたら、立ったままで体重移動をするとき、何かの拍子に「グキッと痛む」と言うのです。
Mさんの症状とそっくりなので、「もしかしたら、あなたもお皿の裏側に骨の棘があるんじゃないの?」と話しました。
Hさんは病院に行く気はないそうです。他の症状もあるので、鍼灸だけで治療をするとのことでした。
お皿の表面の骨棘は皮膚から近いので、お灸で簡単に治療できます。「膝をついた拍子にズキンと痛む」という症状ですが、血流が良くなると棘を吸収してくれるのです。
骨は原始的で可塑性が高く、出っ張ったところを吸収し、へこんでいるところに増殖して、継ぎ目も残さずにあるべき形に戻ろうとする力があるのです。
<踵骨の骨棘の治療例は→症例51「かかとの痛み」)
お皿の裏となると、お灸の熱がなかなか到達しません。お皿の下をめがけて鍼を打ち、お皿の上に多壮灸をすれば、骨の棘を吸収できるかもしれません。
治療後に痛みが増悪し、3日間ぐらいつづいたあとで薄らいだそうです。膝の痛みはマイルドにはなっていきましたが、なかなか完治してくれません。
私も毎回透熱灸での多壮灸をやりましたが、Hさんも毎日自分でカマヤミニをやってくれました。お灸をするととりあえず痛みが引いてくれるので本人も必死なのです。
お皿の上からまわりから、お灸の痕だらけになりました。
こげ茶色のシミが所狭しにびっしりと並んでいたので、妹さんに見られて絶句されたそうです。
(私のカマヤミニは彼女の真似です) |
|
 |
→ |
 |
|
|
その半年後(53回目)、こげ茶色だったお灸の痕が、いきなり薄茶色になっていました。「あ、治ったね~」とふたりで大喜びしました。膝が治った証拠なのです。
皮膚は内部を映す鏡です。私のする透熱灸とカマヤミニ(弱)であれば、内部が治れば皮膚のシミは薄くなり、数ヶ月後には消えてしまうはずです。
Hさんは着物が趣味です。着物で外出したり集まりに出席するととても目立って人目を引きます。良い姿勢を保持すると腰に負担がかかります。
その頃(50回目)には背中と腰の硬直がやわらいで形もきれいになりました。「板」から人間らしい凹凸があらわれ、長年の腰痛からやっと解放されました。
お皿への集中治療から半年もかかりましたが、膝の形もきれいになって、左右のバランスもよく、柔軟な筋肉で膝関節を支えられるようになりました。
入れ替るように顎関節症がおこりました。右耳の聞こえは悪いままでした。
初診から約3年後(62回目)が最後になりました。「膝OK、腰OK、両方の顎関節症で口が開かない、仕事のトラブルで耳の聞こえが悪い」とカルテに書いてあります。
そのあと、「治療のあとの聴覚検査で、耳の聞こえが良くなっていました。顎関節症の治療が効果があったようです」とメールをもらいました。
現在は年賀状のやり取りだけですが、そのまま持ちこたえてくれているようです。 |
|
| *私の膝痛は・・・ |
自己治療が難しいのは「裏側が見えない」ことだけでなく、「客観的に全体を見渡せない」ことです。
お皿を埋め尽くすほどのカマヤミニをを4日もつづけてやった翌朝、膝の裏に風船( )ような塊が出現しました。 )ような塊が出現しました。
触るだけでも痛いし、立っていることもできないほどの激痛でした。 |
|
|
|
|
「バランスを考えて治療する」ことがいかに大切かを思い知らされました。
ふくらはぎへの鍼も打っていたのですが、見落としがありました。解剖学の本を調べてあらゆる筋肉に鍼を打ちつづけ、風船( )の原因になった筋肉を見つけ出しました。 )の原因になった筋肉を見つけ出しました。
私の膝痛の話のつづきは、変形性膝関節症の症例と一緒に次ページで紹介してあります。<2022/4/17> |
|
|
|
 2ページ目へつづく 2ページ目へつづく |
| Updated: 2021/10/22 <初版 2006/10/18> |
|
|