|
症例33・ひざ痛 new 2 (2022)
|
|
|
<変形性膝関節症でも、筋肉をほぐして治す>
|
|
 まず酷使されるのが、膝を支える大腿四頭筋 まず酷使されるのが、膝を支える大腿四頭筋 |
|
故障してすぐに治療ができればスムーズに完治を目指せるのですが、こじらせてしまうと、膝関節を支える筋肉をすべて治療しなければなりません。
筋肉の硬直が長期間つづくと、硬直が硬直を呼んで「変形性膝関節症」になることもあります。軟骨や骨がすり減ったり癒着したりしていても、筋肉をほぐして鍛えつづけると、「使える身体」を維持できます。
硬直した筋肉は関節のほころびを悪化させますが、柔軟な筋肉は弾力あるクッションのようにほころびを守ってくれるのです。
前ページ(ひざ痛・1)で紹介した筋肉をおさらいしましょう。(イラストは右足。私が教科書をスキャンして作ったものなので、おおよその目安です)
膝関節を支える最大の筋肉は太ももの前面にある「大腿四頭筋」です。4つの筋肉が膝蓋骨の下にもぐりこんで、膝蓋靭帯になって脛骨にくっついています。
単独で痛むときは「階段を上るとき」ですが、膝関節を支える大黒柱なので、この治療は必須です。関節のどこかに不具合があると、必ず酷使されて痛みが出ます。腫れてブワブワになると血流が悪くなり、膝関節の支持がゆるんでしまいます。しっかり筋力をつけて、正座とストレッチで可動域を維持しましょう。
<詳細は→ひざ痛・1「大腿四頭筋」を参照してください>
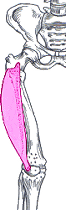 |
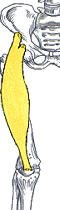 |
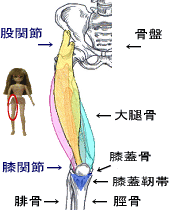 |
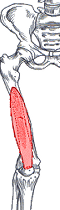 |
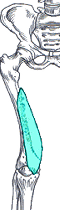 |
| 外側広筋 |
大腿直筋 |
< 大腿四頭筋> 大腿四頭筋> |
中間広筋 |
内側広筋 |
筋肉内部には血管が通っているので、鍼の効果が持続します。骨に付着している腱には血管がないので、透熱灸のほうが効果的です。お灸を重ねると深部まで温められます。
| *鍼を打つとき |
 |
| 複数の筋肉が重なっているポイントを狙う |
|
|
| *腱は骨に付着 |
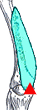 |
 |
| 透熱灸 |
|
| 急性期には透熱灸で深部の血流を促す |
|
|
*イラストの は骨に付着している は骨に付着している |
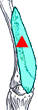 |
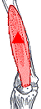 |
| 鍼は「点」になるが、透熱灸は「面」で治療できる |
|
|
自分で治療するときはカマヤミニが簡単で便利です。
膝蓋骨の上、周囲の付着部、筋肉の圧痛点を探して、押して痛いところに片っ端からお灸をしましょう。
痛みを感じたタイミングで、日に何回やっても大丈夫です。(4つぐらいずつ順番に。一度に火をつけると火傷します) |
|
|
|
 |
 こじらせやすい、内転筋の付着部(鵞足) こじらせやすい、内転筋の付着部(鵞足) |
|
太ももの内側にある内転筋、薄筋(■)、縫工筋(■)と半腱様筋(■)の三筋は、膝関節の下、脛骨で鵞足(○ガソク)となって癒合しています。
<詳細は→ひざ痛・1「内転筋」を参照してください>
腱が融合しているので、こじらせやすく治しにくく、みんなでそろって硬直します。初期症状では「階段を下りるとき」に膝の内側に痛みが出ます。
硬直がすすむと、裏側にくっついている筋肉と引っぱりあって、関節が変形してしまうことがあります。
 |
+ |
 |
|
■+■+■
鵞足(○)で
腱が融合している |
|
|
|
→ |
 |
| 大腿四頭筋 |
内転筋(太ももの内側) |
大腿前面の筋肉 |
|
大腿四頭筋と重ねてみました。
内転筋に連動して、すぐそばにある内側広筋(■)も一緒に硬直するので要注意です。
それぞれの筋肉に個別に鍼を打ちましょう。
痛みの激しいときは、骨に付着している腱に透熱灸。沈静化したあとは浅い鍼でOKです。 |
|
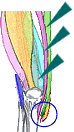 |
| 横から個別に鍼を打つ |
|
|
| *腱に透熱灸 |
 |
| 圧痛点を目安に、骨への付着部を個別に治療 |
|
|
|
|
|
 長引くと、ハムストリングスに波及する 長引くと、ハムストリングスに波及する
|
|
太ももの裏側にある筋肉は、骨盤の「坐骨結節」からはじまっています。
鵞足(○)を形成する半腱様筋(■)と、横に並ぶ半膜様筋(■)は膝裏の内側に向かって走行し、脛骨の内側にくっついています。大腿二頭筋(■)は膝裏の外側に向かって走行し、脛骨の外側にくっついています。
三筋をあわせてハムストリングスと呼ばれ、股関節と膝関節の2つの関節を飛び越えて伸びる二関節筋です。股関節を伸ばし、膝関節を屈曲させるのですが、両方同時に働かせることはできません。
膝関節を支えるためにハムストリングスが過緊張します。硬直して縮むと、上から膝関節を引っぱって悪化させます。膝関節の故障が長引くと、大腿後面やでん部に痛みが波及して、腰痛の引き金にもなります。
治療するときは、でん部や股関節につながる筋肉にもきっちり鍼を打ちましょう。丁寧に圧痛点を探します。複数の筋肉が重なっているポイントを選ぶのがコツです。
<ひざ痛・1「大腿後面」も参考にしてください>
| ハムストリングス |
 |
+ |
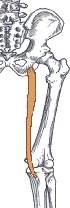 |
+ |
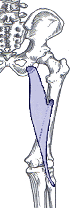 |
|
| ■半腱様筋 |
■半膜様筋 |
■大腿二頭筋 |
|
→ |
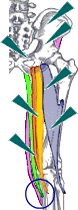 |
圧痛点を目安に
ツボを選ぶ |
|
|
|
|
|
|
|
|
2006年6月に来院したTさん(当時54歳、女性)は、でん部からハムストリングスへの痛みで、びっこを引き引き歩いていました。坐骨神経痛?と思って治療をはじめましたが、元凶は膝関節の故障でした。1年以上も膝をかばっていたせいで、裏側で支えている筋肉に痛みが波及してしまったのです。
<詳細は→症例34「バレエ;膝痛→お尻から太ももに波及」にあります>
膝関節の内部です。大腿骨と脛骨の間には半月板(■)があって、クッションの役割をしています。
内部には後十字靭帯(■)と前十字靭帯(■)が、両サイドには外側側副靭帯と内側側副靭帯があって、大腿骨と脛骨をつないでいます。
Tさんの初診の問診票に「7年前に右膝の靭帯切断」と書かれてあり、てっきり側副靭帯の断裂と思い込んでいました。
この間はじめて、実は前十字靭帯(■)の断裂だったことを知りました。スキー場のてっぺんからスノーモービルに引かれて担架で下ったそうです。ギプスを装着したまま仕事をこなしたそうです。
医師に「切れたものは元には戻らない。でも、筋力をつければなんとかなる」と言われ、「ただ筋トレするのはつまらない」とバレエをはじめた、という話もはじめて聞きました。
ときどき「右足に力が入らない」という不安を抱えながらも、バレエをやりたい一心で、筋トレをがんばってくれました。「靭帯がなくてもなんとかなる」という見本です。隔週で治療をつづけ、70歳になった現在も毎週バレエに通い、トゥでも踊れているそうです。
前ページで半月板(■)を損傷した人を紹介しました(→ひざ痛・1「半月板」)。
つながっている筋肉の硬直をほぐせば、半月板への圧を軽減できます。
器質的損傷があっても、弾力あるクッションのように柔軟な筋肉があれば、テニスもスキーもバレエもこなせる膝関節を維持できるのです。 |
|
 もっと長引くと、ふくらはぎをこじらせる もっと長引くと、ふくらはぎをこじらせる |
|
2004年、Nさん(当時67歳、女性)が11年ぶりに来院しました。脳幹出血で寝たきりだった旦那さんが5ヶ月前に亡くなったそうです。20年もの献身的な介護生活のせいで身体はボロボロでした。
11年前に治した腰痛がとことん悪化して、腰椎の4番と5番が癒着していると手術をすすめられたそうです。でも、「近所で、車椅子になった人がいるのよ」と、そのリスクは絶対に避けたいとのことでした。
「台所に10分と立っていられない」「歩くのは10mぐらいまで、それも杖をついてやっと」という状態でした。
初回の治療後、「腰の痛みは3割減」になりました。週に1回の治療で、2週間でだいぶ歩けるようになり、3ヶ月後(12回目)には足の指(三指と四指)の痺れも取れ、8ヵ月後(29回目)には30分ぐらい歩けるようになりました。
腰のほうは順調に良くなっていき、痛みの中心が膝に移動しました。両膝とも変形性膝関節症でぶわぶわに腫れていましたが、まず右膝から、そして左膝も、だんだんすっきりした形に戻っていきました。
10ヶ月後(32回目)からは、痛みの中心がふくらはぎに移動していきました。「ふくらはぎが痛だるい」「ふくらはぎがつる」と訴えるようになり、その後は、ふくらはぎに重点をおいての治療になりました。
|
|
|
骨盤からはじまる内転筋とハムストリングスは、膝関節の下にくっついています。
ふくらはぎを覆っている腓腹筋(■)は、内側は「内側頭」、外側は「外側頭」になって、膝関節の上にくっついています。
関節の上から下方に引っぱっているのです。
上下で交差している筋肉の硬直がすすむと、膝が曲がったまま伸びなくなります。
ついには、硬直した筋肉に引っぱられて、膝関節の変形を起こしてしまいます。
腓腹筋(■)の下にはたくさんの筋肉があって、共同運動をしています。
当時は駆け出しだったので、痛みや痺れやつりなど、本人の愁訴をもとに、硬直した部位を片っ端からほぐしていきました。 |
ふくらはぎ中心の治療から3ヶ月後(40回目)、「ふくらはぎが楽になったら、膝の痛みがなくなって、すいすい歩けるようになった」とのことで、いったん治療を終了しました。
半年後、あちこちの痛みがぶり返して来院しました。20年間の介護生活の無理がたたって、首から背中から腰から、カチンカチンにこり固まっていました。これをほぐすのは容易ではありません。
でも、Nさんは、とても働き者。ちょっと良くなると、買い物に、散歩にとでかけます。多摩川に桜が咲いたときには、日に何度も花見に行ったそうです。お料理が得意なので、お孫さんたちに、毎日おいしいお料理を作ってあげ、時々私にもおすそ分けが回ってきした。うちのぬか漬けの種はNさんからいただいたものなのです。
「ちょっと良くなると動き回る」ことが、治癒の秘訣です。「動く人は良く治る」「動かない人は治りにくい」ことを実感したのはこの頃でした。
実はNさんは開業第一号の患者さんです。1993年2月2日、まだ看板ができていいなかったときに、私のバイクを目印に来てくれました。
私が調布病院でリハビリをしていたときの知り合いで、2キロの道を車椅子を押して毎日リハビリに通っていました。旦那さんは脳幹出血から8年、マットの上での寝返りがやっとでした。フレッシュマンだった私が鍼などあれこれ試していたら、触発された(?)主任が、角度を調整できる電動ベッドの上に旦那さんを寝かせて、立位訓練をはじめてみました。
2か月後、車椅子の上でグラグラしていた旦那さんが、座位を保てるようになりました。「自分でコップを持って麦茶を飲めたのよ!」「サンドイッチを手にもって食べられたのよ!」など、どんどんレベルアップして、半年後には平行棒で歩行訓練ができるようになりました。
80キロの旦那さんを抱えて毎日お風呂に入れていたのですが、まったく立てずにグニャグニャするのと、一瞬でも自分で立てるのとでは、介護の負担が大きく違います。「あきらめない」ことが進化の秘訣で、維持の基本でもあります。 |
|
|
|
|
保育士のMさんは開業前からの患者さんです。首から腰まで背骨がまっすぐなので、首肩こりと腰痛はお友達。性格もまっすぐ真面目で、仕事も家事も趣味でも手を抜きません。生まれつき関節の強度が弱いらしく、膝痛、五十肩、腱鞘炎など、あちこちの痛みに悩まされながら、「私は痛みに弱いのよ」と、ずっとメンテナンスをつづけていました。(→「寝違え」と「ガングリオン」にも登場しています)
お孫さんが生まれて忙しくなり、8ヶ月間治療の空白があったあと、2005年(当時62歳)、右股関節の痛みで久しぶりに来院しました。しばらく前から痛かったそうです。歩くと痛い、朝起きるときも痛いと、けっこう重症でした。
1ヶ月後(4回目)には両でん部に痛みが移動し、5ヶ月後(10回目)には右膝の痛みがバクハツして、病院で「変形性膝関節症」と診断されました。1年前まできれいだった膝関節は、いつの間にかブワブワになっていました。
保育士の仕事はほんとうにハードです。園児を抱き上げるときに腰と膝に過負荷がかかります。立ったりしゃがんだりを頻繁にくり返します。園庭で遊ぶ園児を見守るときは立ちっぱなしです。お散歩に出かけるときは、長時間歩かなくてはならず、ときには子どもを追いかけてダッシュもしなければなりません。
園児用の小さな椅子に腰かけて、園児と一緒に食事をし、保育日誌や連絡帳を書き、こまごまとした手仕事をします。赤ちゃんを左手で抱っこして、右手で書き物をすることも普通にあります。
保育士は「背中にも目がある」んじゃないの?と思われるぐらい、常に子どもたちの様子を見守りながらの仕事なので、緊張感も半端じゃありません。
小さな椅子に膝を曲げて腰かけるので、Mさんは「膝の裏にモノがはさまっているみたい」という苦痛を訴えていました。
膝の内側が痛い、歩くときに痛い、階段を下りるときに痛い、立ち上がるときに痛い、などが典型的な変形性膝関節症の症状です。
本人の愁訴をもとに、あらゆる筋肉の圧痛点を片っ端から治療しました。Nさんが、ふくらはぎの治療で大きな改善が見られたので、今回は初めからふくらはぎにも重点をおきました。
膝の裏には太い神経があって、敏感なので自分としては避けたい部位ですが、Mさんの膝の裏には深い鍼を打ちました。水ぶくれになってもいいと言うので、透熱灸(多壮灸)も行いました。
下腿外側の硬直もあって、長腓骨筋(■)にも鍼を打っていました。
Mさんは自分で毎日カマヤミニをやって、腕前はセミプロでした。ときどき私にもお灸をしてくれました。 |
|
|
「少しいい」と「また痛い」をくり返しながら、右膝痛発症から3ヶ月後(13回目)、左膝の痛みも感じるようになりました。反対側に痛みが出るのは症状が落ち着いた証拠です。6ヶ月後(30回目)にやっと両膝痛が一段落しました。
1年後(48回目)、「自転車で転びそうになって、左足でふんばった」拍子に左膝を痛めてしまい、もう半年かかってしまいました。
あまり思いやりある職場とは言えなかったので、Mさんは歯を食いしばって仕事をしつづけ、完治したのは発症から1年半(72回目)でした。膝のブワブワもすっかり取れ、良い姿勢で颯爽と歩くことができるようになりました。
2012年(67歳)に退職するまで、25年以上も鍼灸治療をつづけていました。同年配がどんどん小さくなっていく中で、Mさんの身長は1ミリも縮まなかったそうです。筋肉のほぐすと、姿勢も身長も維持できるのです。
当時の私はストレッチには関心がありませんでした。経験を重ねて、「きれいに治った人は、全員ストレッチをしていた」ことに気づいたのです。
年金暮らしになってからは来院がありませんが、一緒に温泉に行ったときに様子をきいてみました。「走れるし、正座もできるし、なんの問題もないわよ」と嬉しそうに報告してくれました。ストレッチのことをきいたら、「ものすごい痛みをこらえて、毎日必死で正座をがんばったのよ~」と教えてくれました。
60代以上で立位の360度ストレッチができるほとんどいないのですが、74歳のMさんは難なくやってみせてくれました。
「仕事があってよかった。つらかったけど、やりつづけていたから、ここまで治ったんだと思う」と当時を振り返って、動ける自分に誇らしげでした。
鍼灸と運動とストレッチは、完治には欠かせない三種の神器です。60代を過ぎたら、「努力している人しか治らない」のが現実なのです。 |
|
 努力が嫌いでも、そこそこ治る 努力が嫌いでも、そこそこ治る |
|
PTAのバドミントン時代からの知り合いのKさんは、中高で熱中したバスケットボールのせいで膝の不具合を抱え、サポーターをぐるぐる巻きにしてバドミントンをやっていました。
たまに治療に訪れるぐらいだったのですが、2003年(53歳)に93歳のお姑さんを引き取ってからストレスで首肩がバリバリになって、毎週来院するようになりました。1年前に左膝の前十字靭帯を断裂したそうです。上述のTさんはそこからバレエをはじめたのですが、Kさんは15年つづけたバドミントンをあきらめて、コーラスをはじめていました。
変形性膝関節症のせいで、歩くときに痛い、階段昇降が難しい、ずっと立っていると痛いなど症状があったのですが、何よりつらかったのが「バスの座席」とのことでした。腰かけていると膝がどうしようもなく重だるくなって、長い時間曲げていることができなかったそうです。
Kさんのお母さんも変形性膝関節症のせいで、大好きなバス旅行に行かれなくなって何年もたつそうで、80歳から車椅子生活になってしまいました。
本人は「自分の膝は治らない」とあきらめていたのですが、旅行に行く楽しみもないのは悲しいなあと、膝を治す決心をしました。
左膝の方が悪いのですが、かばうせいで右膝も悪くなっていました。両膝ともブワブワに膨れ上がって、まるで象の足のようでした。左ふくらはぎには昔の肉離れのしこりが残っていたので、ふくらはぎにも重点をおきました。
Kさんが「深い鍼は怖いからいやだ」「お灸で痕が残るのはいやだ」と言うので、浅い鍼と糸状灸だけの簡単な治療しかできませんでした。
10ヶ月後(28回)に「膝が少しマシ」になり始め、11ヶ月後(32回)にバス旅行に出かけてみました。そのあと少し痛みが出たのですが、長時間座席に坐っていることができたそうです。翌月には、神戸と京都に行き、山道も歩きまわれるようになりました。
Kさんは腰回りも固まっていて、身体を揺らさないと足が前に出ません。「次は腰を治そうよ」と言ったのですが、Kさんの目標は「たまの旅行」だったので、それで満足でした。
治療に来るときは足が重くてつらい、帰るときにはスイスイ歩ける。そんな状態でおおむね隔週で鍼灸治療をつづけて来ました。
現在Kさんは72歳。趣味は「蓄財」と「楽をすること」なので、たまに自転車に乗る以外、まったく動きません。家事はすべて旦那さんがこなし、用事がなければ歩かないし、階段は上りません。週4の仕事でもずっと坐っています。いくら言っても、散歩もしないしストレッチもやりません。
私の生きがいは「もっと元気にすること」なのですが、本人の努力がないと加齢には対抗できません。身体のゆがみもちょっとずつ進行し、筋力もちょっとずつ落ちています。
それでもなんとか「年相応」を維持し、旅行にも行けているので、Kさんの目標は「達成」ということでしょうか。努力の嫌いなナマケモノでも、変形性膝関節症とそれなりに共存できるという見本です。 |
|
|
|
|
2006年、Sさん(当時77歳、女性)が松葉杖をついて来院しました。若い頃に左の股関節を手術したので、右足に頼って美容師の仕事をつづけたそうです。鍼灸師の弟さんにずっと治療をしてもらっていたのですが、7年前に亡くなってから、どんどん右膝が悪くなっていったそうです。
病院でヒアルロン酸の注射をつづけても、痛みが取れるどころか、だんだん膝が曲がっていきました。お医者さんに「どうして膝が曲がるんだろうね?」と首をかしげられたそうです。真面目に通っていましたが、「注射の痛みに耐えられなくなって、私のわがままで、注射をやめてしまったんです」とSさんは、ほぼ90度に曲がった右膝を眺めて言いました。
まだときどき昔馴染みのお客さんに頼まれて仕事をしていました。曲がった右膝で踏ん張っているうちに右腰が痛くなり、とうとうぎっくり腰で動けなくなっての来院でした。松葉杖にすがるようにして歩いていたので、両肩が痛み出し、両腕も痺れが出て力が入りにくくなり、物を持ってもいつのまにか落としてしまうようになってしまったそうです。
70歳まで鍼灸治療を受けていたので、Sさんの治療はスムーズでした。週1回の治療で、2ヶ月後には足が軽くなって、だいぶ楽に歩けるようになったのですが・・・
筋肉の硬直をほぐしたために身体がぐにゃぐにゃになってしまい、怖くて歩けなくなってしまいました。腕にも力が入らないので、松葉杖にも頼れません。
硬直した筋肉が「杖」のように身体を支えていたのでした。がんばって動いて自前の筋肉をつけなければならないのですが、思うように行きませんでした。
Sさんは優しい妹さんと暮らしています。家事一切をやってくれ、Sさんが目覚めるとすぐに飛んできて、着替えから何から手伝ってくれるそうです。みんなでよってたかって面倒を見てくれ、それに甘えているうちに、とことん筋肉が落ちてしまったのです。
うちの母もそうでしたが、動けなくなったお年寄りの陰には、必ず「優しい働き者」たちがいます。みなさんも気をつけましょう。
Sさんのあと、ヒアルロン酸の注射をつづけて「膝が曲がったままになった」、あるいは「伸びたまま曲げられなくなった」という患者さんが何人も来院しました。「FAQ11:筋肉の石灰化の原因は?」で、筋肉の疲労物質である「乳酸」は酸性なので、そこに血中のカルシウム(アルカリ性)が引き寄せられていくのではないか?という「仮説」を立てました。
ヒアルロン酸も酸性なので、カルシウムが引き寄せられて沈着し、一種の「体内ギプス」を作るのではないか?という可能性が考えられます。関節の支持力は高まるのだけど、膝関節が固まってしまう、ということなのかもしれません。
でも、「完治」を目指すためには「可動域」が必須の条件です。
2010年に、Eさん(58歳、女性)が「膝の関節が曲げられない」と来院しました。5年前から右膝にヒアルロン酸の注射を受けていたそうです。医師には「安静にするように」と言われ、じっとしていたので痛みはないそうです。
私の主義は「安静はご法度」です。動いて動いて動きまくって、自分のやりたいことができる「使える身体」を手に入れるのです。
Eさんは「動いていいのね!」と大喜びしました。動けば痛みが出ます。治療して痛みを取って、また動いて筋肉をつけるのです。週に1回の治療で、歩きも自転車もすいすいこなせるようになりました。
Eさんは宗教をやっていたので、「一生に一度でいいから、もう一度正座でお経をあげてみたい」というのが望みでした。でも2年半、どんなに鍼灸でがんばっても、可動域は1ミリも広げられませんでした。ストレッチも不可能でした。悲鳴を上げるほどの激しい痛みで、ある角度以上はどうしても曲げられないのです。
活動的な日常生活は送れるようになりましたが、Eさんの一番の望みはかなえてあげられませんでした。
(Eさんは症例46「手根管症候群」にも登場しています) |
|
 私の膝痛: パソコン仕事が悪化に拍車をかけた 私の膝痛: パソコン仕事が悪化に拍車をかけた |
|
前ページ(ひざ痛・1)は、私の膝痛からはじまっています。「すぐに治せるはず」「治したところで終わりにしよう」と思ったのですが、長引いてしまいました。
去年の6月にシングルスで古傷痛がバクハツしたあと、7月にテニスを再開しました。用心にテニスを少なめにしたのですが、浮いた時間はずっとパソコンに向かっていました。前ページで紹介した私の膝の状態です。
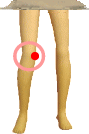 |
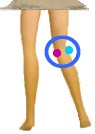 |
| ■ |
古傷=内転筋の付着部(鵞足) |
| ■ |
大腿四頭筋が腫れて、全体に脆い感じで、膝関節の支持力が低下 |
| ■ |
膝の裏側は渋い感じの不快感 |
| ■ |
ベッドへの前傾姿勢で圧がかかる |
| ■ |
パソコンの前で長時間坐ると固まる |
|
パソコン仕事が膝に悪いことには気づいていたのですが、どうしても止められずに夜中までやっていました。(テニスをすると身体がほぐれてくれます)
全身治療は週に2回。腰とかの不具合を見逃さないための用心です。大脳にはフォーカスの機能があるので、自分では一番痛い部位だけしか感知できないのです。気になる部位には順番に、毎日治療をしつづけました。
8月には筋力も躍動感も取り戻すことができました。歩行も階段昇降も問題なしで、テニスのときは痛みもなく、ガンガン走れました。
テニスは全力でやりました。目指すテニスに見合う身体を維持するためです。右膝をかばって中途半端なテニスをするとパフォーマンスが低下して、取り戻すためにかえって時間がかかってしまうからです。
でも翌朝になると膝の痛みが出るのです。不具合を抱えて全力疾走するせいで大腿四頭筋に過負荷がかかり、膝まわりがブワつきはじめました。
膝の裏側の硬直がますますひどくなっていきました。裏側とふくらはぎには手が届きにくく、おざなりの治療しかできませんでした。
9月に入って膝痛はどんどん悪化していき、テニスのときのテーピングが次第に増えていきました。ある日、ついにダブルスで膝に痛みが出てしまいました。
すぐに治療したのですが、翌朝の痛みと冷えが激しく、関節がもろくなってしまった感じで、階段の昇り降りで痛みが出たのです。「これこそが膝痛」という症状がすべて出揃い、絶望のどん底に陥りました。
患者さんが自分でやっていたカマヤミニのことを思い出し、私も試してみることにしました。膝のお皿のてっぺんと周辺に4つぐらいやってみたら、想像以上の気持ち良さです。ワインを飲みながらえんえんとくり返すうちに、膝全体がポカポカに温まって、痛みも冷えも消えてしまいました。
翌日には階段昇降の痛みもなくなり、「リョコちゃんストレッチ」での痛みも激減していました。(私のブログ→2021/9/20)
2日、3日とつづけてやって膝関節の安定感を取り戻し、ガンガン走っても大丈夫になりました。4日目の夜は『もう、いらないな』と感じたのに、欲を出してやってしまいました。。。 |
|
 膝の裏に「風船」が出現 膝の裏に「風船」が出現 |
|
膝の皿へのカマヤミニを4日つづけてやった翌朝でした。いつものようにティラのお散歩をたっぷり1時間。歩きも階段もなんの問題もありません。テニスに行こうと着替えてテーピングをして、出かける前にトイレに入りました。
WOWOWの番組表に見入って、立ち上がったとたん、膝の裏に激痛が走りました。立っていることすらできません。膝の裏に手をやってみると風船( )のような塊ができていて、触るだけでも痛むのです。 )のような塊ができていて、触るだけでも痛むのです。
びっこを引き引き歩いていくうちに痛みがやわらぎ、バイクに乗ったあとがまた激痛で、歩きはじめると消えていきます。
全体のバランスを無視した治療の怖さをまざまざと思い知りました。
はじめに壊した「①内転筋」は、ちゃんと治療できたのでまあまあです。過負荷がかかった「②大腿四頭筋」は、お皿のカマヤミニで症状が激減しました。
|
|
→ |
 だけ消えた だけ消えた |
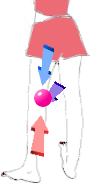 |
|
前面からの圧迫がなくなったために、裏側の「③ハムストリングス」と「④ふくらはぎ」の硬直だけが残って、上下で引っぱって風船( )ができてしまったのです。 )ができてしまったのです。
自己治療の限界を感じましたが、症状が現れたときが治療のチャンスです。
膝の裏への鍼は無理です。ふくらはぎに紐のような硬直のスジを見つけ、引っぱっている紐をほぐせば、風船が消えてくれるかもしれない・・・と思いました。
横向きに寝て、ふくらはぎの中央ラインにズラリと鍼を打ちました。ズシンズシンと響き、直後は歩けないほどの痛みに襲われ、長靴を脱ぐこともできなくなりました。患者さんの治療なら、寝た子を起こしたら、また寝かしつけて終わりにしますが、時間がほぐしてくれるのを待つしかありません。
翌朝には激痛が消えて、風船が少し小さくなりました。(ブログ→2021/9/30)
ハムストリングスは「下腿の深筋膜」にくっついています。 膨れたのは筋膜かな?と、ハムストリングスを徹底的にほぐしました。
少し小さくなったのですが、膝を曲げて坐るだけでも痛みが出るようになりました。 |
|
|
治療するたびにちょっとずつ風船( )が縮んでいき、動作と痛みの関連が明確になっていきました。 )が縮んでいき、動作と痛みの関連が明確になっていきました。
|
|
|
トイレでゆったり坐っているときには問題なしです。WOWOW の番組表に見入ったあとに痛みが出ます。
パソコン作業に没頭したあとや、バイクで「突っ走った」あとにも出ます。
「夢中」になって「前のめり(→)」になると風船( )がふくれるのです。 )がふくれるのです。 |
|
|
|
ちょっとだけシングルスをやったときのこと。相手がドロップショットを多発するのを、ことごとく追いついて返していたら、風船( )がふくれはじめました。 )がふくれはじめました。
爪先立ち(○)になって、地面を蹴って走る動作が、膝の裏を引っぱるのです。
「膝関節の屈曲」が直接の原因ではなさそうです。 |
|
|
|
ベッドに向かって前傾姿勢をつづけると、風船( )がふくらみはじめます。台所でずっと料理を作ったあとにもふくらみはじめます。 )がふくらみはじめます。台所でずっと料理を作ったあとにもふくらみはじめます。
短時間ならすぐに消えますが、長時間つづけると、どんどん悪化し、歩けないほどの痛みになってしまいます。
爪先立ち(○)と前のめり(←)に関係があることが明らかになっていきました。(→2021/10/11) |
|
|
 地面を握りしめる筋肉 地面を握りしめる筋肉 |
|
猿は足の指で木の枝につかまることができます。人間の足はそこまで器用ではないけど、猿と同じ筋肉が指先までつながっています。
なにかに「集中」したり、「夢中」になったり、「緊張」したりするとき、無意識に足の指で地面をつかみ、握りしめるのです。(→2021/10/20)
足関節の底屈をするふくらはぎの筋肉は7つです。協力して、「踵を上げる」「爪先立ちになる」「地面を蹴る」などの運動をしています。
| 全体 |
⇔ |
腓腹筋 |
ヒラメ筋 |
後脛骨筋 |
長母指
屈筋 |
長指
屈筋 |
足底筋 |
膝窩筋 |
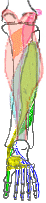 |
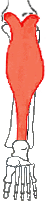 |
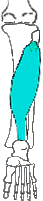 |
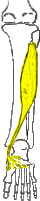 |
 |
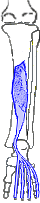 |
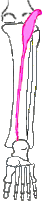 |
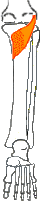 |
長母指屈筋(■)は腓骨からはじまって、内果の後を通って、母指の裏の付け根にくっついています。母指を屈曲する(親指を曲げる)筋肉ですが、「この屈曲動作をつづけると足関節底屈の補助をする」という働きもしていたのです。
膝痛の当初から、爪先立ちで地面を蹴るときに、足の母指から内果の下を通って、膝関節に違和感が伝わることに気づいていました。ストレッチのときに母指につながる足底がつりそうになりました。
なるほど・・・と、この筋肉をほぐしたら、風船( )は出なくなりました。 )は出なくなりました。
翌朝、脛骨に沿って、内くるぶしから膝まで、ズシ~ンと重だるい不快な「冷え」で目が覚めました。ひとつほぐすと、次は別のが悲鳴を上げるのです。
長指屈筋(■)は脛骨からはじまって、内果の後を通って、2指~5指までの4本の指の裏の付け根にくっついています。
当初から、「脛骨が痛む」症状があったのですが、脛骨の裏側で骨を引っぱっていたことに気がつきました。脛骨の上にズラリとカマヤミニを並べてお灸をしたら、とりあえず不快な冷えと鈍痛は消えてくれました。
足指の外側4本を屈曲する筋肉ですが、「この屈曲動作をつづけるときは足関節底屈が起こる」という働きもしていたのです。
何度も言及した腓腹筋(■)はふくらはぎを全体を覆っています。上から押して硬直を探せばすべての筋肉を治療できます。ヒラメ筋(■)は一緒にアキレス腱を形成しています。(→症例52:「ふくらはぎ(腓腹筋とヒラメ筋)」)
後脛骨筋(■)は脛骨と腓骨+いろいろな筋膜からはじまって、足底のあちこちにくっついています。(→症例54:「ふくらはぎ(後脛骨筋)」)
膝窩筋(■)の治療は無理と思ってあきらめました。 足底筋(■)はか弱くて、ない人もいるそうです。
長母指屈筋(■)の治療前の状態です。膝の内側の風船( )がしつこく残りました。自分の鍼が届きにくいので、硬直を取るのにとても苦労しました。 )がしつこく残りました。自分の鍼が届きにくいので、硬直を取るのにとても苦労しました。
|
|
|
「前のめり」で「夢中」になって作業するときは、無意識に足の指で床を何度も握りしめるのでしょう。 ダッシュで地面を蹴るときは、足の指で地面をつかみます。
長母指屈筋(■)と長指屈筋(■)が酷使され、骨に張り付いて固まってしまいます。
共同運動をしている他の筋肉たちに過負荷がかかって、一緒に硬直します。
みんなで固まって癒着し、団子になって動くせいでふくらはぎ全体が硬直していくのです。 |
上からの内転筋が鵞足(○)になって脛骨に張りついています。大腿骨にくっついている腓腹筋(■)の内側頭と上下で交差しているので、このラインが激しく硬直するのです。
関節の内側で変形が起こりやすい理由が納得できます。 |
|
|
|
|
風船( )は消えたのですが、膝を曲げて坐ったあとや、しゃがみこんで作業をしたあとに、膝裏にときどき「枕」のようなもの出現するようになりました。痛みもなくすぐに消えるのですが、「はばったい」感じです。(→2021/10/31) )は消えたのですが、膝を曲げて坐ったあとや、しゃがみこんで作業をしたあとに、膝裏にときどき「枕」のようなもの出現するようになりました。痛みもなくすぐに消えるのですが、「はばったい」感じです。(→2021/10/31)
位置的にやっぱり膝窩筋(■)です。骨にべったりと付着している筋肉なので、透熱灸が有効なのですが、自分ではできません。当てずっぽうでも毎日1本鍼を打って気長に治療することにしました。
上述のMさんも「枕」の不快を訴えていたのですが、彼女の愁訴には「下腿外側の硬直」もありました。
「踵を上げる(=足関節底屈)」ための筋肉はふくらはぎ以外にも存在します。下腿の外側をまっすぐに走る長腓骨筋(■)です。
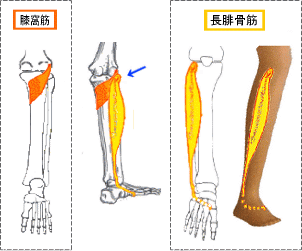 |
|
膝窩筋(■)は骨に張りついて膝裏で膝関節を支えています。
長腓骨筋(■)は外側から膝関節を支えています。
2本は脛骨の外側(←)で交差していています。
仲良く並んで硬直したようです。 |
その後、これらの筋肉のストレッチを思いつきました。筋肉の収縮方向と逆の方向に伸ばすのがコツです。(→2021/11/27)
|
|
|
膝窩筋(■)は「①膝関節の屈曲」、「②屈曲のしはじめに脛骨を内旋する」働きをしています。
太ももの付け根から踵までビシーッと足を伸ばし、足をしっかり固定。
足先を思いっきり外に倒すと、「外旋」=膝関節を外方に回旋させることができます。 |
|
|
|
|
|
長腓骨筋(■)は下腿の外側、腓骨に沿って外果を下り、足の裏で母指の下にくっついています。
「①足関節の底屈(爪先を下げる)」、「②足関節の外反(小指側に曲げる)」働きをします。
太ももの付け根から踵まで、ビシーッと足を伸ばし、膝を固定して、足先を思いっきり内側に寄せてストレッチします。 |
|
|
最後に残ったのが膝窩筋(■)と長腓骨筋(■)の硬直でした。ほぐしたあとは「枕」が出なくなりました。 |
|
 シングルスの試合前日に完治 シングルスの試合前日に完治 |
|
10月はふくらはぎの筋肉をほぐすことに集中しました。でもなかなか「完治」に持っていけません。調布市民大会シングルスの試合の予定でしたが、無理をして「壊して逆戻り」するかもしれないと出場を断念しました。
「1日おき」のテニスがやっとでした。テニスのときは、ガンガン走りまくっても、ガンガン打ちまくっても、痛みはぜんぜん出ません。翌朝に痛みが出て、仕事をしているうちにだんだん引いていって、夜にはすっかり楽になる・・・というパターンがつづきました。
自分でも不思議だったのは左膝の頑丈さでした。治療もしていましたし、右を「かばわないように」気をつけてもいたのですが、それにしても、どんなに打っても走ってもびくともしないのです。
11月に入っても「あとちょっと」から先へ進みません。市民大会が雨で3週間延びのですが、試合直前に3日もつづけてテニスをしてしまいました。3日目は朝から膝が痛かったのに、です。「リョコちゃんウォーク」でなんとかしのいで、ハードなダブルスを3セットもやってしまいました。
そのまま治療室に直行して全身に鍼を打ちまくりました。治療直後はあらゆる筋肉がほぐれたのですが、翌朝には両方の大腿四頭筋がパンパンに腫れて、しゃがむのも大変になりました。
翌日の試合のために2日分の患者さんがいました。痛みをこらえて、ゆっくりしゃがんでストレッチして、立ち上がるときにもやっとの思いです。仕事に支障がでるなんて、右膝痛はじまって以来の最悪の危機的状況でした。
仕事をしているうちに、あれあれ?痛みがちょっとずつ引いていき、夜には太ももの硬直が取れ、両足ともどんどん軽くなっていきました。
どうやら「メンケン反応」だったようです。反対側に痛みが出るのは「治る直前」というサインでもあります。試合当日の朝、ふいにしゃがんでも平気になっていたので、恐る恐るコートに向かいました。
シングルスは4ヶ月ぶりでした。若い女性相手に2試合もガンガンやったのに、翌日になっても右膝の痛みは戻りませんでした。右膝痛とはそれっきり、すっかり縁が切れたのです。
(→2021/11/10)
右膝痛が治ったあとは、全身のあちこちに「痛いよ!」の輪唱がはじまりました。不具合をかかえて動きまくったために、今まで我慢していた筋肉たちが「ボクも」「私も」と次々にアピールをはじめたのです。1ヶ月後のシングルスのラウンドロビンでは、途中で右股関節に痛みが出ました。
(→2021/12/5)
手が届くのですぐに治せましたが、そのあと、右の坐骨結節とハムストリングスに痛みが移動し、いまだに完治していません。
自分で自分を治療をしたせいで長引いてしまいましたが、おかげで膝関節を支える筋肉の詳細な地図ができあがりました。ほとんどの患者さんがどうして簡単に治ったのか?という疑問の答えも出ました。
「治療をしました」「治りました」よりも信憑性がありますよね。「終わりよければ、すべて良し」です。(笑)
シングルスを封印してずっとダブルスをやっていたので、ダブルスはかなり上達しました。シングルスはこれからまだまだ挑戦です。
テニス歴数十年のベテランに対し、私は鍼灸師歴30年です。現在66歳でテニスにハマってまだ10年ですが、やるたびに経験を積んでいます。年を取っていっても、身体さえ大丈夫ならこの先いつまでも挑戦できるはずという「挑戦」でもあるのです。 |
|
 |
| Updated: 2022/4/17 <初版 2006/10/18> |
|

