| 2021/10/20(水) |
 「風船」と「紐」の正体が分かった! 「風船」と「紐」の正体が分かった! |
|
前回、「爪先立ち」&「前のめり」を同時にやるとき、風船( )がふくらむ・・・と報告した。 )がふくらむ・・・と報告した。
太ももの裏、半腱様筋(■)と大腿二頭筋(■)の硬直が、「下腿の深筋膜」を引っぱって、筋膜がふくらむのでは・・・?
そう仮定して、両方の筋肉の硬直をを徹底的にほぐした。
風船( )は少し縮んだけど、膝を曲げて坐るだけで痛みが出た! )は少し縮んだけど、膝を曲げて坐るだけで痛みが出た!
まるで悪化したみたい??? |
|
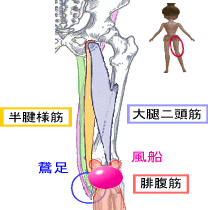 |
仮説のやり直しである。
ここで「膝裏の痛み」についてネットで検索したら、「ベーカー嚢腫」というものがあった。関節包に溜まった水が後方に流れて溜まってしまう。弁があるので逆流することができずに、貯留してふくらんでしまうとのこと。「走り過ぎが原因」と書いてあるサイトもあった。。。
・・・ゾ~ッとした。走れなくなったら私のテニス人生は「お終い」である。
「水を抜いてもまた再発するので、安静にして自然治癒を待つ」と書いてある。関節包に溜まった水は鍼とお灸で流れてくれる。自然に抜けるものなら、地道に治療をつづければ、いつかは治るはず・・・と気を取り直した。
それに、私の風船( )はふくらんだり縮んだりするんだから、「ベーカー嚢腫」とは違うはず、と思った。 )はふくらんだり縮んだりするんだから、「ベーカー嚢腫」とは違うはず、と思った。
膝の裏とふくらはぎに徹底的に鍼を打つことにした。
足を上げてみたり、右に向いてみたり、左に向いてみたりして、いろんな角度から打ったので、ものすご~く大変だったんだよ。
前々回のブログで、<「紐」の硬直をほぐせば、「風船」の炎症が引いてくれるかもしれない>と思って、「足底筋」を目がけて鍼を打った話をしたよね。
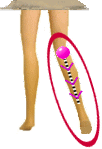 |
|
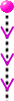 |
|
最後の最後に、膝の裏からふくらはぎへと、細くて硬い「糸」のような筋肉の塊が手に触れた。
風船( )を引っぱっている紐(―)が、確かに存在していたのである。 )を引っぱっている紐(―)が、確かに存在していたのである。
膝裏の中央からふくらはぎの中央の、そのライン上にズラリと鍼を打った。ズシン、ズシンと鍼が響いた。 |
『この紐(―)の正体は何だろう?』と、筋肉の図をつぶさに調べて、長母指屈筋(■)を見つけた。母指球で地面を蹴って踵を上げる(=足関節底屈)ときに使われる筋肉である。
膝痛がはじまった頃から、爪先立ちで地面を蹴るときに、足の母指から下腿の骨を通って、違和感が膝関節に伝わることに気づいていた。ストレッチのときに母指がつりそうになったし。。。
先月やっと母指からつながる足底には鍼を打った。足底はほぐしたんだけど、ふくらはぎの下方、中央の深部での硬直が残っていたのだ。
| 長母指屈筋 |
| 腓骨の後面の下2/3、骨間膜、隣接する筋間膜中隔と筋膜 |
| ↓ |
| (アキレス腱の下にもぐり、内果の後を通って) |
| ↓ |
| 母指の裏の付け根 |
|
|
長母指屈筋(■)は母指を屈曲する(親指を曲げる)筋肉だけど、「この屈曲動作をつづけると足関節底屈の補助をする」と本に書いてあった。
鍼でほぐしたあと、とりあえず、風船( )は出なくなった。 )は出なくなった。
翌朝、脛骨に沿って、内くるぶしから膝まで、ズシ~ンと重だるい不快な「冷え」で目が覚めた。以前から、「脛骨が痛む」症状があったのだけど、筋肉がないのに何で?と不思議に思っていたのである。
長指屈筋(■)が、脛骨の裏側で骨を引っぱっていたのである。
足の外側4本を屈曲する筋肉だけど、「この屈曲動作をつづけるときは足関節底屈が起こる」と書いてあった。
| 長指屈筋 |
| 脛骨中部3/5の後面、後脛骨筋(■)をおおう筋膜 |
| ↓ |
| (アキレス腱の下にもぐり、内果の後を通って) |
| ↓ |
| 4本の指の裏の付け根 |
|
|
脛骨の上にズラリとカマヤミニを並べてお灸をしたら、とりあえず不快な冷えと鈍痛は消えてくれた。
なんと、長指屈筋(■)は後脛骨筋(■)にもくっついていた!
| 後脛骨筋 |
| 脛骨後面の外側、腓骨の内側面の上部、深横筋膜、隣接する筋間膜中隔、骨間膜の後面 |
| ↓ |
| (アキレス腱の下にもぐり、内果の後を通って) |
| ↓ |
| 足底のあちこち |
|
|
ふくらはぎの筋肉を並べてみた。みんなで協力して「踵を上げて」「爪先立ちになる」運動(=足関節の底屈)をしているのである。(他にもあるけどここでは省略した)
| 腓腹筋 |
ヒラメ筋 |
後脛骨筋 |
長母指
屈筋 |
長指
屈筋 |
足底筋 |
膝窩筋 |
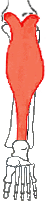 |
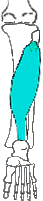 |
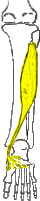 |
 |
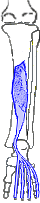 |
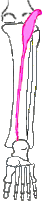 |
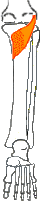 |
重ねてみると、ほとんどすべてが巨大で強力な腓腹筋(■)におおわれている。
|
|
|
歩行に問題がなかったのは「リョコちゃんウォーク」で歩いたからだろう。 |
膝を伸ばして地面を蹴るときには、二関節筋である腓腹筋(■)が活躍する。
他の筋肉たちは楽して動け、血流が促される。
『爪先立ちで痛みが出るのでは?』と不安に駆られながら歩いたんだけど、治療効果があった! |
|
次々に筋肉の硬直をほぐしつづけて、風船( )が少しずつ縮んでいったんだけど、最後に残ったのが、鵞足(○)につながる内側だった。 )が少しずつ縮んでいったんだけど、最後に残ったのが、鵞足(○)につながる内側だった。
ハムストリングス
治療の前 |
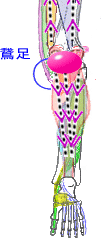 |
|
→ |
ハムストリングス
治療のあと |
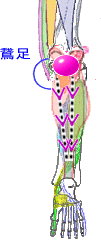 |
|
→ |
長母指屈筋(■)
の治療の前 |
 |
|
太ももの内転筋、半腱様筋(■)と薄筋(■)と縫工筋(■)は膝の内側の下で、腱が融合して鵞足(○)となって脛骨に張り付いている。三筋が融合しているので、とても治しにくい。
腓腹筋(■)の内側頭がそこで交差している。ふくらはぎの内側の筋肉の硬直が激しく、そして治しにくい理由が分かった。上から下から引っぱられるので、この部位での関節の変形が起こりやすい理由も納得できる。
|
|
膝を曲げて「夢中」になって作業をするときは、無意識に足の指で床を何度も握りしめるのだろう。 |
長母指屈筋(■)と長指屈筋(■)が酷使され、骨に張り付いて固まってしまう。
腓腹筋(■)とも固まって、鵞足(○)を引っぱる。
筋肉たちが固まって、団子になって動くせいで、このラインが激しく硬直するのだろう。 |
|
長母指屈筋(■)、長指屈筋(■)、後脛骨筋(■)など、骨や筋膜に付着している部分の多い筋肉は、鍼を打っても治しにくい。骨に垂直に当たってしまい、「点」で治療することになってしまうからである。私は透熱灸で治療するけど、自分のふくらはぎにはそれは無理。
ついでに言うと、膝窩筋(■)も骨に付着している部分が多い。自分では治療できないうえに、触ることすらできなかった。
私がもうひとりいて、私の膝の治療をしてくれたら、とっくの昔に治っていただろう。膝の裏もふくらはぎも、上から触ってツボを取り、硬直をほぐせるのだから。
苦労したおかげで、硬直しやすい筋肉に名前がついて、筋肉と動作の関係が明確になった。気分は超スッキリ、爽快である。このまま「完治」してくれれば、「終わりよければ、すべて良し」になるんだけど。。。
私の膝は治る寸前で、あとちょっと・・・である。
でも、歩行で痛みが出たのはほんの一瞬だったし、階段昇降で痛かったのはたったの1日、テニスで痛かったのもたったの1日。
まあまあだった・・・ということかもしれないね~(笑) |
|
|
|
|
|
| 2021/10/11(月) |
 「ひざ痛」が、膝痛悪化の最大要因だった 「ひざ痛」が、膝痛悪化の最大要因だった |
|
ブログの更新に手間取ったのは、自分の膝痛の解析で紆余曲折したからである。
『これだ!』と思ってイラストを作り、文章を書く。でもまた別の発見があって、イラストを手直しして文章を書きはじめる。するとまた別の発見が・・・、という具合に状況がどんどん変化していったからなのだ。
前回のブログで「足底筋は二関節筋だから、膝と足首を同時に屈曲させるときに緊張する」と書いたんだけど、それは間違いである。なのでその部分を消去させてもらった。あまりの痛みにパニック状態になってしまったのである。
「足底筋に鍼を打った」つもりだったけど、狙った筋肉も違っていた。
 |
私が鍼を打ったのは足底筋(■)じゃなくて、腓腹筋(■)の中央ラインだった。ふっくら太った大きな筋肉だから、奥の足底筋までは届かない。
どちらも二関節筋だから、「膝を曲げた」状態では収縮できない。
そのうえ、教科書によれば、足底筋はとてもか弱く、ない人もいるとのこと・・・ |
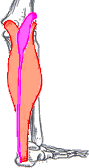 |
激しく硬直した腓腹筋(■)が、膝裏を引っぱっていた。幅が広くて、膝上から踵へと縦方向に筋繊維がたくさん並んでいるので、硬直ラインに片っ端から鍼を打った。
腓腹筋は大腿骨だけでなく「関節包」にも付着しているので、風船( )は関節包かもしれない?・・・そう思ってがんばったんだけど、それでもときどきふくれてしまうのである。 )は関節包かもしれない?・・・そう思ってがんばったんだけど、それでもときどきふくれてしまうのである。
最初に風船( )がふくれたのは、膝を曲げて腰掛ける姿勢のあとだった。 )がふくれたのは、膝を曲げて腰掛ける姿勢のあとだった。
 |
→ |
 |
|
|
トイレでゆったり坐っているときには問題がないが、
WOWOW の番組表に見入ったあとに痛みが出る。
パソコン作業に没頭したあと、バイクで「突っ走った」あともそう。
「夢中」になって「前のめり(→)」になると風船( )がふくれるのである。 )がふくれるのである。 |
必死の治療が功を奏して、腓腹筋(■)もふくめて、ふくらはぎの硬直はすっかり取れた。それなのにその後も風船( )がときどき出現した。 )がときどき出現した。
仕事場に行けばパソコンに直行して作業に没頭してしまう。夢中になって前のめりになって緊張するので、それが一番の悪化の原因だったのだ。
|
|
|
先週土曜日、男とえんえんとラリーをしたあと、ちょっとだけシングルスをやった。
彼はドロップショットを多発。ことごとく追いついて返したのであるが、走りすぎたらしく、風船( )がふくれはじめたのを感じた。 )がふくれはじめたのを感じた。
爪先立ち(○)になって、地面を蹴って走る動作が、膝の裏を引っぱるらしい。
膝関節の屈曲が原因ではなかったのだ。 |
膝が多少痛くても、テニスに出かけたほうが、筋肉の硬直が取れて膝が楽になる。壁打ちだけしているより、コートに立って動いたほうがいい。途中でパキッと音を立てて、内転筋の癒着がほぐてくれる。
シングルスは止めたほうがいいみたいだけど、ダブルスのときはそこまで走らなくてすむ。壁打ちのときに痛くても、ゲームをしている間に軽くなるのである。
<*断っておくが、歩行も階段昇降も正座も問題なしが前提条件だよ>
テニスが原因で発症した膝痛だったけど、テニスを休んで「ひざ痛」の症例に没頭したことが、悪化に拍車をかけたのである。
|
|
|
ベッドに向かって前傾姿勢をつづけると、風船( )がふくらみはじめる。 )がふくらみはじめる。
2時間ぐらいなら、それほど悪化しないうちに縮んでくれるんだけど、長時間つづくと、どんどん痛くなっていく。
昨日の日曜日、台所でずっと家事をしたあとで、風船( )が出現した。そのまま仕事に突入したら、どんどん悪化し、歩けないほどの痛みになった。 )が出現した。そのまま仕事に突入したら、どんどん悪化し、歩けないほどの痛みになった。
爪先立ち(○)と前のめり(←)に関係があることがはっきりした。 |
パソコン仕事だけじゃなく、治療するときの姿勢も悪化の原因だった。患者さん2人に置鍼している間に、途中でこっそりテーピング( )をした。 )をした。
 |
→ |
 |
|
|
痛みの激しい中央に1本貼ったら、かえって痛みが悪化し、立っていられないほどになった。
両サイドに1本ずつ、テープを貼り変えたら痛みが薄れた。
そのままどんどん軽くなっていき、風船( )が消えた。 )が消えた。 |
風船( )の正体は何なのだろう・・・? )の正体は何なのだろう・・・?
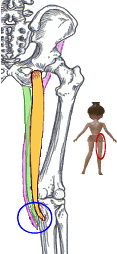 |
これは「ひざ痛」のページに挿入したイラスト。
鵞足を形成する内転筋のひとつ半腱様筋(■)は膝の下、内側にくっついている。
太ももの裏の巨大な筋肉、大腿二頭筋(■)は、膝の下、外側にくっついている。
どちらの筋肉も膝の下で「下腿の深筋膜」にもくっついている。 |
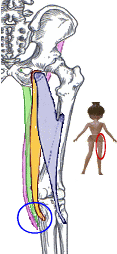 |
私の持っている本では、これ以上の詳細な説明は書かれていない。
これは想像なのだけど、爪先立ち(○)になって、前のめり(←)になると、ハムストリングスを構成している半腱様筋(■)と大腿二頭筋(■)が緊張するらしい。筋肉の硬直が「下腿の深筋膜」を引っぱるせいで、風船( )のようにふくらんでしまうのかもしれない。 )のようにふくらんでしまうのかもしれない。
保育士だった患者さんが「膝の裏にモノがはさまっているみたい」と訴えていたんだけど、自分が体験してしまった。(保育士は園児の椅子で仕事をする)
自分で自分を治療するときは、ツボを取るために、どうしても解剖学の詳細な知識が必要だ。地図を見ながら歩くようなものである。
患者さんの治療をするときは、大雑把な知識があればいい。外から全体を診て、圧痛点を探してツボを取ればいいのだもの。
私が今まで何気なく普通にしていた治療が、それで「十分」で、足すことも引くこともないという・・・大きな発見をしたのである。
あとは、自分で手の届きにくい裏側を、どうやって「完治」に導くか・・・だよね。
今日は朝起きてすぐに膝の裏にテーピングをした。欲を出して長めに貼ったら、かえって痛みが出た。やっぱり12センチぐらいがちょうどよかった。ティラの散歩に出かけたあと、ストレッチでもほとんど痛みが出なかった。
そのままテニスに出かけた。表側の大腿四頭筋はもう治ったかのようにスッキリしていたんだけど、1ゲーム終わったあとで不安に駆られてテーピングを追加した。
ガンガンやってもテニスはOKだったけど、シャワーのあとで膝裏の内側だけ、風船( )がちょっとふくらんだ。だんだんターゲットが絞られてきたようである。 )がちょっとふくらんだ。だんだんターゲットが絞られてきたようである。 |
|
|
|
|
|
| 2021/9/30(木) |
 15年ぶりに「ひざ膝」を改訂 15年ぶりに「ひざ膝」を改訂 |
|
15年ぶりに「ひざ痛」を改訂した。ずいぶん前から書き直したくてたまらなかったんだけど、どういう組み立てにするか、ビジョンがぜんぜん浮かばなかった。
自分の膝を痛めたことがきっかけになって、鵞足を構成する内転筋のイラスト作りからはじめたのである。
解剖学の教科書と「図説 筋の機能解剖」の本から、骨格や筋肉の図をスキャンして、色をつけて重ね合わせた。だいぶ上達して素早くなったんだけど、凝り性なので、何度も何度も作り直しをしてしまう。
イラスト作りの手間は楽しめたけど、患者さんのカルテを見ながら要点を整理するのも大変だったので、2ヶ月もかかってしまった。
自分の膝が一進一退だったので、おかげで考察が深まった。これですっきり治ってくれれば「怪我の巧妙」と喜べるんだけど・・・
前回、膝のお皿へのカマヤミニで症状が劇的に改善された話をしたよね。
 |
膝のお皿の上とまわりにカマヤミニをたくさんした。終わってから眺めると、お灸のあとがほとんどすき間なくびっしりと、まるで碁盤にのせた碁石のように並んでいる。
(一度にぜんぶ燃やしたら大やけどをしてしまうから、4つとか5つとか、少しずつやってね~~)
1回目のあと、階段昇降の痛みがなくなり、正座での痛みが激減した。2回目のあとは、膝関節の「冷え」がなくなり、関節の不安定感が薄らいだ。 |
翌日からテニスを再開。壁打ちとミニラリーだけにして、(今度こそ)用心深くスロースタートではじめたのである。
「翌朝の痛み」を目安にしたんだけど、順調に回復してくれたので、4日目も壁打ちとミニラリーと、サーブ練習もした。
4日目の夜、『もうカマヤミニはいらないな』と思った。お皿全体がポカポカ温まっていたから、やる必要はないと思ったんだよね。
・・・でも欲を出して、またやってしまった。
翌朝、いつものようにティラのお散歩をたっぷり1時間。歩きも階段もなんの問題もないし、ストレッチでの痛みも激減していた。
着替えてテーピングをして、出かける前にトイレに入った。WOWOWの雑誌に見入って、立ち上がったとたん、膝の裏に激痛が走った。
 |
歩くどころか、立っていることすらできない。膝の裏には風船のような塊があって、どうやら強い炎症があるらしい。触っただけで激しく痛むのである。
カマヤミニをしてみたけど効果がない。テニスはあきらめて、仕事に出かけることにした。
ビッコを引き引き歩く羽目になった。激痛はだんだん薄らぐんだけど、バイクから降りたらまた激痛になった。
膝を曲げて坐っていると炎症が悪化するらしい。 |
全体のバランスを無視した治療の怖さをまざまざと思い知った。
表側のカマヤミニをやり過ぎたために、裏側の不具合がバクハツしたのである。
ハムストリングスやふくらはぎにも鍼を打てるようになったんだけど、「見えない」部位への手探りだから、やっぱり「当てずっぽう」である。用心に患者さんの2倍以上もの鍼を打っていたんだけど、「取り残し」があったのだ。
「図説 筋の機能解剖」の本を見ると、膝の裏にはもう2つ筋肉があった。
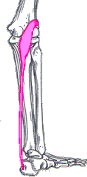 |
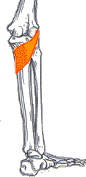 |
| 足底筋 |
膝窩筋 |
|
|
膝の裏の炎症(■)の範囲は広いので、当てずっぽうの治療は無理。
足底筋(■)を狙ってみることにした。「紐」の硬直をほぐせば、「風船」の炎症が引いてくれるかもしれない。
ベッドに横たわって、ふくらはぎの中央のラインにびっしり鍼を打った。
硬直がはげしくて、打つ鍼打つ鍼、ズシンズシンと響く。
なんか、効きそうだぞ~~ |
鍼のあとは痛みが悪化して、立つことすら難しくなった。患者さんなら、激痛を取り除いて帰すのだけど、自分ではどうしようもない。ビッコを引き引きやっとの思いで家に帰った。
玄関で長靴を脱ごうとしたら激痛が走って、自分ではどうしても脱げない。踵を押し付けて足を引き出そうとするときに激しく痛むのである。
ポプラに頼んで脱がせてもらったのだけど、ブリブリ文句を言われた。。。
ハードな鍼でいったん悪化したとしても、狙いが当たっているなら、一晩寝れば炎症が引いてくれるはず・・・と期待したのである。
翌朝、膝の裏の炎症(■)は消えてくれていた。
坐ったあとの痛みも出ないし、靴を脱ぐのも平気になった。
患者さんの足底筋(■)を治療したことは一度もない(と思う)。たぶん他の筋肉の硬直をほぐすだけでOKの小さな筋肉なのだろう。
「ひざ痛」を書くために、長時間パソコンの前に坐っていた。坐ると裏側が硬直することに気づいていたけど、どうしてもやめられなかった。膝裏の治療を自分ではできなかったので、とことんまで行っちゃったのである。
翌々日の月曜日には、壁打ちとサーブ練習のあと、ダブルスを1つやった。ときどき右膝をかばってしまうし、ゲーム勘もなくなっていた。私にせいで負けたけど、それでも「ゲームって、楽しいね~」と言ったら、みなさんが「だよね~」と口々に同意してくれた。「壁打ちだけじゃ、人間が暗くなるよね」と男が笑った。
翌日の痛みも出なかったので、水曜日に壁打ちを1時間ぐらいやった。
今朝は半腱様筋の付着部あたりだけ、ズシンと圧迫感があったけど、動いているうちに消えてくれた。膝関節の支持力が少しずつ増している。
テーピングを1本減らし、壁打ちのあと、ダブルスを2セットやった。おっかなびっくりはじめたけど、ちゃんと右足で踏ん張ることができたんだよ。
このまま治ってくれるといいんだけどね~~ |
|
|
|
|
|
| 2021/9/20(月) |
 右膝をこじらせ、大腿四頭筋まで痛めた 右膝をこじらせ、大腿四頭筋まで痛めた |
|
結局右膝をこじらせてしまった。日常生活で痛みがなくなって7月にテニスを再開し、8月には筋力を取り戻し、そのまま治るかと思ったんだけど、それは甘い期待だった。
テーピングをすれば練習もダブルスもガンガンできた。テニスのときは平気なのに、翌日に痛みが出てしまう。治療をするとまた痛みがなくなるけど、テニスの翌日にまた痛みが出る。
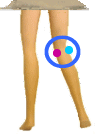 |
膝裏の内側(■)がどんどん硬直していった。
自分ではどうしても鍼を打てない。
もっと身体が柔らかければいいんだけど、膝が曲がって隠れてしまうのだもの。
もちろん、透熱灸もできない。 |
 |
カマヤミニは素人臭いからと除外していたんだけど、鏡を背にして、立ったままでカマヤミニをはじめた。でも、「時すでに遅し」だった。
翌日に出る痛みの程度がどんどん激しくなっていった。ここでテニスを減らせばよかったんだけど、やっているときには大丈夫なんだもの。
正座では痛みがなかったのに、だんだん冷や汗が出るほどの痛みが出るようになった。ダブルスをやめればよかったんだけど、大腿四頭筋のテーピングを加えて、ガンガンやっちゃったのである。
|
|
|
立位のこのストレッチは、太ももの付け根や股関節の腰まわりの筋肉をほぐすために考え出したもの。
ところが、膝を曲げて身体を押し付けると、膝から太ももに強い痛みが出るようになった。
具合が悪くないときは、どのストレッチがどの筋肉を伸ばすのか分からない。悪くなってはじめて、筋肉の存在を認識するのである。
←これと正座で引き伸ばされるのは、大腿四頭筋の大腿直筋(■)なのだ。
(なので「リョコちゃんストレッチ」のここを手直しした) |
膝関節の支持が不安になって、関節がもろくなってしまった感じで、正座がつらくなっただけでなく、階段の昇り降りでも痛みが出るようになった。
まさに膝痛の王道ともいえる症状がすべて出揃ってしまったのである。
このところずっと「ひざ痛」の症例を書き直している。解剖学の本を読みながらイラストを作ったりしているので、ものすごく時間がかかっている。
「とことん壊した」のは、神様が「もっとちゃんと書くように」とメッセージを送っているのかもしれない・・・ね!
下の図が大腿四頭筋である。
| 大腿直筋 |
前面の中央にあって、骨盤(下前腸骨棘)と脛骨に付着。
大きな力を出すメインの筋肉。二関節筋で、股関節の屈曲と膝関節の伸展を行う。
(ボールなどを蹴るときに使うので「キックする筋」と言われている) |
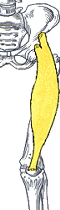 |
|
⇔ |
| 中間広筋 |
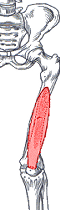 |
大腿直筋の下にあって、大腿骨に付着。
鍼はすぐ骨に当たるので透熱灸で治療する。 |
|
| ↑ |
| 内側広筋 |
骨に付着して、
内にふくらむ |
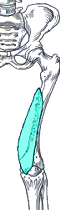 |
|
← |
| 大腿四頭筋 |
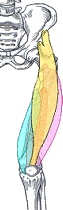 |
|
→ |
| 外側広筋 |
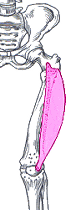 |
骨に付着して、
外にふくらむ |
|
| ↓ |
| 膝蓋靭帯 |
 |
膝蓋骨(お皿)から
膝蓋靭帯を介して
脛骨結節へ |
|
|
|
大腿四頭筋は「筋肉の上にお皿をのっけて」というイメージだったんだけど、実際にはお皿の下にめり込んで、膝蓋靭帯を介して膝下の骨にくっついているという、とても複雑な構造だったのである。
膝関節を支える最大の筋肉なので、関節のどこを壊しても、必ず過負荷がかかってしまう。あなどれない存在なのだ。
鍼を打つだけでなく、(患者さんが自分でやっているみたいに)お皿のまわりにカマヤミニをやってみた。ついでにお皿の上にものっけてみた。
4つぐらいずつ、何度もくり返すと、そのうちお皿まわりがどんどん温まっていって、ものすごく気持ちがいい。
ワインを片手にテレビを見ながらやりまくったら、翌朝の痛みが軽くなってた。膝まわりのブヨブヨも取れていく。階段昇降も大丈夫になった。
「素人臭い」とバカにせず、最初からやってればよかったね~~
今日は痛みはほとんど取れているんだけど、関節内部に寒風が吹いているような「冷え」を感じるし、支持がもろいような不安感もある。
なので、こんないいお天気なのに、テニスに行かずに仕事場に来てこれを書いている・・・という淋しい休日になったんだよ。(泣) |
|
|
|
|
|
| 2021/9/8(水) |
 またまたサーブのフォームを改造中 またまたサーブのフォームを改造中 |
|
7月にテニスを再開して以来、サーブの不調がつづいた。雨の日が多かったし、「やりすぎ」は禁物とセーブしていたので、練習もろくろくできなかった。
ダブルスでまた苦労するようになった。バシンと打とうとするとフォルトする。不安に駆られて「入れ」にいってダブルフォルトをする。・・・という始末だった。
久しぶりにサーブ練習をしてみたら、「バイエル100番」サーブのフォームをすっかり忘れてしまっていた。
バイエルを忘れたついでに、自分の身体に見合った自然なフォームを見つけてみよう・・・と思い立った。
ちょうどカナダで、ドイツのズベレフ対ロシアのルブレフの試合をやっていた。ふたりは親友なのだそうだ。(比べると小さな)ルブレフのサーブが気に入ったので、真似してみようとじっくり観察した。
ジュニアから一度も勝てなかったズベレフに、ルブレフが躍動感ありありで、初の1勝を勝ち取った。終わったあとのふたりの表情がとても爽やかで、すっかりファンになってしまったんだよ~~
翌日のサーブ練習では、バイエルにこだわらずに、ルブレフを思い描きながらバッシンバッシンと打ちまくった。
リターンに入った人が、いちいち「ナイスサーブ」と言ってくれるほどのスピードサーブだったんだけど、アドサイドからはすべて「イン」で、ジュースサイドからはすべて「ジャストオーバー」になってしまう。
根本的に何かが間違っているに違いない・・・
フォームと回転、フォームとコースの関係を明確に把握したいと思って、昔買った本に書いてあった確認法を試してみることにした。
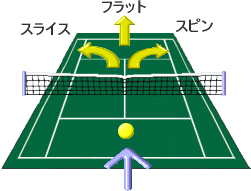 |
コートの中央からセンターライン上にサーブを打つ。
弾んだあとのボールの軌道で、フォームを確認できる。 |
| 左に曲がる |
スライス |
| まっすぐ飛ぶ |
フラット |
| 右に曲がる |
スピン |
|
|
センターラインでサーブを打ってみたら、なんと、ボールがぜんぜんまっすぐに飛ばない。あっちやこっち、とんでもないところに飛んでいくのである。
・・・これじゃあ、ノーコンなのも無理はない。
自分を観察すると、トスに合わせて無意識に足を動かしていた。ダブルスのときは「入れなくちゃ」というプレッシャーがあるから、「とりあえず打っている」うちにフォームが崩れてしまったのだろう。
|
|
左足軸足を固定して打とうと思った。Wさんが教えてくれたように、左足の上にラケットを置いてみたら・・・
ラケットが邪魔で打てない!
左足を横に向けて構えるんだけど、打つ瞬間に爪先が前を向くのである。(■→■)
「スライスは横向きのままで、フラットは早めに正面を向く」と聞いたことがあるので、速いサーブを打とうとすると、爪先が前を向くのだ。 |
|
 |
だったら、最初から爪先を前向きにしたらどうだろう?と考えた。
足が妙な形で固定されるのでとっても不自由なんだけど、爪先の向きにサーブが飛んで行く。
「フォーム=型」なので、型にはめたほうが安定する。
『これがコントロールするコツかな?』と思って、2日間は練習もダブルスも、これでやってみた。
サーブに安定感が出たんだけど・・・ |
でも、決める前にプロの足を見ることにした。
ちょうど全米オープンが開催中なので、試合を早送りして、次から次へとサーブのときの足だけを観察したのである。
そしたら、爪先前向きはひとりもいない。もしかしたら、回転がかけられなくなってしまうのかもしれない?残念ながら「却下」である。
 |
ほとんどの男子と大坂なおみは、爪先横向きで構えていた。なんだ、今までと同じか・・・と思ったけど、そこからが違う。
そのまま右足を寄せてサーブを打つ。左足の角度はそのままで、微動だにしない。
フラットもスライスも足の形は同じなのである。
必要不可欠なのは「軸の安定」らしい。 |
 |
女子はほとんどの選手がが左足の爪先を斜めに構えていた。男子に比べて非力な女子には「斜め」が楽なのだろうか?
でも身長198センチのズベレフは、この構えで時速210キロ以上のサーブを打っている。
「爪先斜め」を試してみたい!とうずうずしていたけど、毎日雨でぜんぜんテニスに行かれなかった。 |
今日は9日ぶりのテニスである。コートが埋まっていたので、練習なしですぐに女ダブをやることになった。
ルブレフ・サーブの練習で上半身と腕の振りはおおよそできている・・・と信じることにして、軸の安定だけに集中してゆっくり打った。
爪先斜めの構えからだと、上半身の動きがよく分からなくなってしまうんだけど、最後までやり通したのである。
勝つ直前にダブルフォルトでゲームを落とした。ペアに「ごめんね。今サーブのスタンスを変えているので、そのまま打っちゃったの」とあやまったら、「いいのよ、いいのよ。試合じゃないんだから、どんどん試してちょうだい!」と、にっこり笑顔で励ましてくれた。
「入れる」ために軸を崩したら元も子もない。爪先を横にするか斜めにするかはまだ決めていないけど、「軸を維持する」ことは貫きとおす。
それが自分のモノになったら、上半身と下半身はそのあとで組み合わせればいいもの。
スピードサーブで相手を押して、トップスピンで相手を押す。。。
勝ち上がるためにはシングルスの試合を短く終わらせなくちゃならない。とりあえず自分の得意を磨こうというのが今の作戦である。 |
|
|
|
|
|
日記  TOP TOP |
|
|
|
|
前の日付へさかのぼる |
|

