|
症例18・首こり&肩こり new 1 (2023)
|
|
|
<目標は首と肩があるのを忘れること>
|
|
 こりが居座って、苦痛を与えつづける こりが居座って、苦痛を与えつづける |
|
私がはじめて首のこりを感じたのは26歳のときです。その日から一瞬たりと首の存在を忘れることができなくなりました。いつもいつも、縮んで固まった首が鉛のように重くのしかかっていて、苦しくて苦しくて、誰かに「首を切り落としてもらいたい」と思ったほどでした。
何度も寝違えをくり返し、身体ごとでないと振り向けないのが普通の状態。首の可動域がどんどん狭まっていきました。当時は見るも哀れなほどの猫背でした。
33歳で鍼灸学校に入ってから、自分の首こりを治すための必死のツボ探しがはじまりました。治療のあとで軽くなっても、しばらくするとまたこりはじめます。治っていくにつれてメインの患部が移動していき、あらゆる部位を治療することになりました。
下の図は首・肩こりで悩まされる部位です。
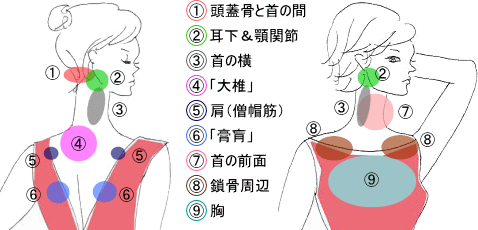
| ■ |
① |
頭蓋骨と首の間 (後頭神経痛を起こすこともある) |
| ■ |
② |
耳の下&顎関節 (めまいや顎関節症の原因にもなる) |
| ■ |
③ |
首の横 (ソーセージ状に固っていく) |
| ■ |
④ |
「大椎」=頸椎と胸椎の境目にあるツボ |
| ■ |
⑤ |
肩こりの部位 (頭蓋骨からつながる僧帽筋が肩甲骨を引っぱる) |
| ■ |
⑥ |
「膏肓」=肩甲骨の内縁にあるツボ |
病は「陽から入って陰に留まる」ので、慢性化すると身体の前面のこりにも悩まされるようになります。
| ■ |
⑦ |
首の前面 (胸鎖乳突筋や喉の筋肉が硬直する) |
| ■ |
⑧ |
鎖骨周辺 (鎖骨下方の「中府」「雲門」など) |
| ■ |
⑨ |
胸 (胸式呼吸が難しくなり、息が吸いにくくなる) |
硬直部位が少なければ簡単に治療できますが、根深いコリを抱えた患者さんたちは私と同様の経過をたどりました。部位が多ければ多いほど大変で、きれいに治るまで何年もかかることがあります。
すべて治ってしまえば、自分に「首」があることを忘れてしまいます。「首がある」ことを意識させられたら「こっている」ということなのです。 |
|
|
|
|
 頭痛、眼精疲労、めまい、高血圧を起こす 頭痛、眼精疲労、めまい、高血圧を起こす |
|
頭部へ行く血管はすべて首を通っています。首の筋肉が硬直すると、血管を圧迫して頭部への血流が悪くなります。なんとかして脳に血液を送ろうとして心臓ががんばるので、高血圧の原因にもなります。
目に行く血管が圧迫されると「眼精疲労」の原因になり、目がかすんだり見えにくくなったりします。
首の硬直が頭部の筋肉に波及すると、頭重感や頭痛の原因になります。偏頭痛をくり返したり、後頭神経痛をおこしたりします。
耳の下の筋肉が硬直すると、めまいや顎関節症、耳の聞こえが悪くなるなどの症状を誘発します。 |
|
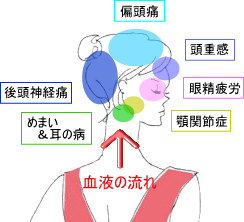 |
|
|
 呼吸困難、不眠、気力と体力の低下も 呼吸困難、不眠、気力と体力の低下も |
|
女の人は胸式呼吸をする人が多いので、呼吸に影響を及ぼしして「息が吸いにくい」「息苦しくなる」などの症状がおこります。(ちなみに胸式呼吸は鎖骨を引き上げて行い、腹式呼吸は横隔膜を引き下げて行います)
不眠の原因にもなります。首こりが悪化すると、「眠りが浅くなる」「熟睡できない」「明け方に目が覚めてしまう」ことになって、「寝ても疲れが取れない」状況になります。睡眠中につらさを感じると枕のせいにしたくなるのですが、たいていは無実の罪です。
首こりが学業や仕事に悪影響を及ぼして、休みがちになったり、うつになったり、引きこもりになったりした患者さんも少なくありません。
首・肩こりはほんとうにあなどれないのです。 |
|
 筋肉の硬直が、硬直を呼ぶ 筋肉の硬直が、硬直を呼ぶ |
|
首にはここでは紹介しきれないほどのたくさんの筋肉があります。重い頭部を支えるだけでなく、複雑にからみあって、前屈、後屈、側屈、回旋など、微妙で多彩な動作を行っています。中には頭蓋骨から骨盤までつながっている長い筋肉(=脊柱起立筋など)もあるのです。
筋肉の主な働きは収縮で、縮むことで関節や表情筋などを動かしています。多方向に張り巡らされた筋肉が、それぞれ別方向に収縮することで、多彩で伸びやかな動きを可能にしているのです。
筋肉の内部には血管が通っています。自由に動ければ「筋ポンプ作用」で内部の血流が促されますが、動けなくなると血流が滞り、疲労物質の代謝がそこなわれ、ますます硬直する、という悪循環がおこってしまいます。
筋肉たちはみんなで共同運動をしています。ひとつの筋肉の硬直が、かばって動く他の筋肉に連鎖していきます。
硬直が硬直を呼び、骨に張りついたり、筋肉同士が癒着したりしてガチンガチンに固まっていくことにもなります。硬直した筋肉は次第に縮んでいくので、年齢とともに身長が縮まる原因にもなります。
首の可動域が制限されていき、ロボットのような動きしかできなくなると、多彩な愁訴に悩まされることになるのです。 |
|
 生まれつきの骨格と関係がある 生まれつきの骨格と関係がある
|
|
「西洋人に肩こりはなく、日本人特有の病気」と言われていますが、背骨の形はまず「遺伝」で決まります。うちの父はいつも「首がこる」と嘆いていましたが、母と弟は無縁でした。患者さんの家族を治療して、母と娘と孫息子、父と息子など、背骨の形状を受け継ぐ人たちがいることに気がつきました。
背骨の形と首・肩こりには密接な関係があります。骨格のきれいな人の首・肩こりは一過性で、すぐに治ってほとんど再発しません。
メンテナンスに通ってくる患者さんたちは背骨の形が悪い人が多く、ほぐしてもほぐしてもまた硬直してしまいます。
正しい脊柱は横から見ると、前後にスラロームして頭部の重みを分散しています。日本人に多いのは「ストレートネック」で、頸椎がまっすぐだと不具合を起こしやすくなります。逆に「前弯増強」、つまり曲がりが強すぎるのが原因と医師に言われた患者さんもいました。
左右にスラロームするのが脊柱側弯症で、首・肩こりや腰痛などに悩まされることになります。<→腰痛2「鍼灸で背骨の矯正」>
小さな椎骨たちが脊柱を構成しています。椎骨を支えているのは筋肉と靭帯です。先天的な骨格が歪んでいると筋肉が過緊張を強いられ、そこに生活習慣や仕事などによる過緊張が加算されます。
筋肉が過緊張すると硬直し、硬直すると骨格の変形を促します。筋肉の硬直をほぐすと骨格の歪みも矯正されていきます。
日本人に特有の「まっすぐな背骨」は着物文化からきていると思います。着物姿は背筋がまっすぐだと美しく、そのうえ清く正しく立派に見えます。「まっすぐな背骨」を持つ人が好まれて、たくさんの子孫を残したのでは?と推測しています。
中国から伝来した鍼灸が庶民にまで浸透し、温泉療法が日常的に愛されているのも、日本人の背骨の形状と関係があるのです。 |
|
 神経障害を引き起こすこともある 神経障害を引き起こすこともある |
|
脳細胞からはじまる神経線維は脊髄となって脊柱内部を下り、椎骨の間を通って、それぞれの支配領域に向かっていきます。
脊柱を支える筋肉が硬くなって縮むと、上下の椎骨を引っ張って、間を通り抜けている神経を侵害することがあります。このタイプの神経障害は、支えている筋肉の硬直をほぐすことで治療ができます。
頸椎からは主に腕につながる神経が走っています。頸椎周辺で侵害されると、首~肩~肩甲骨~腕へと放散する激しい痛みと痺れがおこり、耐えがたいほどの苦痛に悩まされます。
頚椎症なら鍼灸で改善していきます。<→症例12「頚椎症・1」>
椎骨と椎骨の間にある椎間板が圧迫され、内部にある髄核が突び出して神経を侵害するのがヘルニアです。器質的疾患なのですぐには治らず、しばらくすると元通りの痛みが戻ってしまいます。<→症例1「(腰椎)椎間板ヘルニア」>
血流が悪くなると、筋肉や靭帯にカルシウムが沈着することがあります。後縦靭帯が石灰化するのが後縦靭帯骨化症です。中枢神経障害を伴うのですが、鍼灸で改善が見られました。<→症例30「後縦靭帯骨化症」>
鍼灸は物理的な圧をかけずに治療ができます。悪化するリスクを避けることができるので、試してみて損はありません。 |
|
 首はあっさり、圧をかけずに取穴する 首はあっさり、圧をかけずに取穴する |
|
首の特徴は細くて狭い通路にたくさんの筋肉がひしめきあっていることです。あっちもこっちも硬直しているからといって、数多くの鍼を打っても「苦しさ」は消えません。かえって増悪してしまうこともあります。
10年以上も隔週で私を治療してくれたSさんは腰の治療がとても上手だったのですが、首には無関心でした。何年かたって首の硬直を単刺で取り除く治療をお願いするようになりました。私の何十倍もの鍼をとても丁寧に打ってくれたのですが、「苦しさ」を取る治療は自分でやっていました。
ある日のこと、治療のあとで『なるほど、これがムチウチか!』と思うほどの苦痛に襲われて、息も絶え絶えになってしまったのです。
腰でん部の治療をするときは、Sさんのようにグイグイ押して、深いところにある硬直を探り出さないと治ってくれません。でも同じ調子で首をグイグイ押して取穴したため、物理的な圧力がかかってムチウチ症状をおこしてしまったのです。
掲示板があった頃、全国の人から相談メールが舞い込んできたのですが、多くが「首に鍼を打ってもらえない」というものでした。うちに来院して「他ではやってもらえなかった」と言った患者さんもたくさんいました。首の治療に失敗して怖くなった鍼灸師がたくさんいるのでしょう。
首を「壊さない」ように軽く触って取穴しましょう。「腰はグイグイ、首はあっさり」です。自分の首に苦労したせいか、私は一度も失敗したことがありません。やられたおかげで理論化できた極意です。 |
|
 手足の治療で「苦しさ」を取る 手足の治療で「苦しさ」を取る |
|
首の「苦しさ」を取るためには手足の治療が必須です。
気の流れる道筋を「経絡」というのですが、ほとんどが首を通過しています。手足にある「要穴」を使って経絡のバランスを調整します。微妙なバランスを取ることで、首の歪みを矯正し、苦痛を取り除くことができます。
慢性的な病には陰経の鍼が効果的です。積み重なったこりや疲労を取るために、20歳を過ぎた患者さんには全身治療をしていますす。
患部の硬直をほぐすことは大切ですが、患部だけを治療するのは、ドブの詰まりだけをつつくようなものです。手足への治療で「気」の流れる道筋をつくります。部屋に風を入れるとき、入口の窓だけ開けても風は通ってくれません。出口の窓を開けたとたんに、風がサーッと吹き抜けていってくれるのです。
手足はストーブの煙突、車やバイクのマフラーのようなもので、詰まっていると首の邪気が流れていってくれません。吹けが良くなると、身体の中を風が通るように、新鮮な「気」が滞った邪気を吹き流してくれるのです。 |
|
 一番悪いところをちょっとだけひいきする 一番悪いところをちょっとだけひいきする |
|
「左側が苦しい」と訴える患者さんの中には、治療師に「あなたが悪いのは右側です」と言われてきたという人がいます。たしかに客観的に見ると、右側のほうが硬直が激しく盛り上がっています。でも人間の左右の感覚は確かなことなので、患者さんの訴えを重んじましょう。
左側の硬直が深いところにあって体表から触れない場合もあります。左をかばったために右側に過負荷がかかった結果、ということもあります。
左側が苦しいときに、両側を同じようにほぐしたり、右側をよりほぐしたりすると、左側の苦しさが残ってしまいます。
病の深い左側には深部まで熱を通す透熱灸を施し、右側には軽く糸状灸で表面の硬直をほぐす、というやり方もあります。最後の仕上げで右側から先にはじめ、左側をきれいにほぐしたところで終わらせる、という方法もあります。
一番つらいところをちょっとだけ「ひいき」するのが、「苦しさ」を取り除いて楽にしてあげるコツなのです。 |
|
|
|
|
 「気」を動かす経絡治療を組み合わせる 「気」を動かす経絡治療を組み合わせる |
|
経絡治療学会に3年通って終了証をいただいたのですが、脈診では落ちこぼれでした。私の経絡治療は自己流で、「あらゆる経絡の両側に1本は置鍼をする」というものです。安全で一定の効果を得られます。
患者さんの状態に応じて、「気」を動かす浅い鍼と、筋肉の硬直を直にほぐす深い鍼を組み合わせます。
鍼灸治療は「どうやったら治るか」を身体に教えるのが仕事です。浅い鍼でも、切皮の瞬間から「気」が動きはじめます。その効果が全身に及ぶまで少し時間がかかるので、しばらく置鍼をします。
置鍼の間に鍼たちの連携プレーがおこり、あらかたの不具合を調整してくれます。ゆるんでいるいるところに力を与え、冷えているところを温め、硬直をほぐし、邪気を押し流して、新鮮な「気」を全身に巡らすことができるのです。
首への置鍼は浅い鍼を数本だけです。深い鍼を打った状態で患者さんが動くと、鍼も動く可能性があるので、刺激量のコントロールができません。つながる筋肉たちがほぐれると、首のこりが激減します。
手で「気」を流して全体をほぐしながら、残った硬直部位を探します。仕上げは単刺で、首から腰までの脊柱側を中心に、ひとつひとつほぐしていきます。
それでも硬直が残ったら、お灸を追加したり、金粒・銀粒や磁石を用いるバランス療法を行います。
脊柱の歪みを磁石を貼って矯正する治療法は→症例14「ぎっくり腰」の「磁石を使って背骨の矯正」で紹介しています。
鍼灸の基本は背骨の矯正です。数年前に治療法を変えました。FT(フィンガー・テスト)を使って、脊柱の中央ラインの歪みのポイントを探し、数か所に深い鍼を置鍼するものです。広範囲の筋肉をほぐすことができます。 |
|
 古いムチウチと骨格のコラボ 古いムチウチと骨格のコラボ |
|
問診のときに「昔のムチウチ」を訴える患者さんはたくさんいます。直後なら簡単に治せるのですが、時間の経過とともに硬直の連鎖反応がおこってしまいます。こじらせてしまうととても厄介なことになるのです。
1993年3月に来院したAさん(当時42歳、女性)は20年前に交通事故で1カ月入院したあと、ムチウチと左顔面神経麻痺になったそうです。それ以来「左肩と左背中が苦しい。首はかろうじて回る。左腕が痺れる」などの症状に苦しむようになったとのことでした。
それでもAさんはスーパーウーマン。仕事や趣味や家族の世話など、信じられないほどの活躍ぶりをつづけていました。愁訴の数は私以上で、上述のあらゆる部位の症状がすべて出そろっていました。
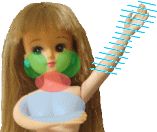 |
|
| ● |
首全体 |
| ●● |
メインの患部 |
| ● |
肩と肩甲骨 |
| ● |
顔面パンパン |
| ● |
息が吸いにくい |
 |
左腕に痺れ |
|
|
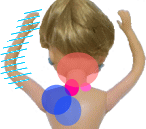 |
開業したての患者さんです。まだ鍼の技術が未熟だったので、お灸とあん摩を組み合わせ、ふたりで話し合いながらいろんな治療法を試しました。メインターゲットは一番つらい左首です。「苦しい左側をちょっとだけひいきする」極意は、Aさんの治療で学んだことです。
治療のあとは「軽くなった~」と喜んでくれるのですが、1週間ぐらいするとまた戻ってくるので、ほとんど毎週の治療になりました。坐骨神経痛など他にもいろいろあったのですが、ここでは省略します。
1998年4月にAさんはアメリカに移住し、1年後に頚椎症を発症しました。医師には「ストレート・ネックで、日本人特有の病気」と言われたそうです。6月のグアテマラ旅行中に治療をして、1週間で激痛から解放されました。
Aさんが頚椎症を発症したのは右側でした。何十年も悩まされた左側ではなかったことが不思議です。経過を診ていないので理由は分かりませんが、たぶん、元気な右だけを使い過ぎたため、がんばり過ぎた右の硬直が進んでしまったのだと推測します。 |
|
 歯の治療から顔面と首の苦痛がはじまった 歯の治療から顔面と首の苦痛がはじまった
|
|
2008年に来院したMさん(当時45歳、男性)は、4年前に左下の親知らずを抜いた直後から、絶え間ない苦痛に悩まされるようになったそうです。
左首~肩~肩甲骨(■)は硬直してパンパンに腫れ、痛みと痺れがありました。いつも「モヤモヤ」して、奥のほうに「何かがある」感じがして、常時苦しいのだそうです。
左顔面( )には引きつりと「イライラ」があって、耳の下(■)と顎関節(■)に違和感があり、左目(■)がよく見えないとのことでした。 )には引きつりと「イライラ」があって、耳の下(■)と顎関節(■)に違和感があり、左目(■)がよく見えないとのことでした。
ときどき喉(■)が詰まって息苦しくなるそうです。左手に痺れ( )がありました。 )がありました。
右首(■)はずっと昔にムチウチになったそうで、痛みとつっぱりがありました。
ずいぶん前から首を回せなくなっていたそうで、見事にあらゆる症状が出そろっていました。 |
|
|
初回には単刺、糸状灸、透熱灸、磁石治療もやりました。2回目には仰向けでも首に単刺をし、井穴から邪気を抜き、経筋への糸状灸も行いました。
Mさんの首は腫れて太くなっていて、しかも凝りが深いので、首への単刺は2寸(3番)の鍼でないと患部に届きませんでした。いろんな治療を試しましたが、軽快するにつれてメインの愁訴が変化していきました。
2ヶ月後(9回目)には「ギクギクがキクキクぐらい」になったそうです。3ヶ月後(12回目)には左が軽くなって、右のギックリ首(寝違え)を起こしました。4ヶ月後(15回目)からは左顔面のドヨ~ンが気になりはじめ、消えるまで半年以上かかりました。首が回せない、腕が上げられないなど、いろんな不具合をくり返しながら、つらさが一段落したのはだいたい1年後(54回目)でした。
太かった首がスッキリ細くなりました。
一番つらい症状が落ち着くと、それまで隠れていた愁訴が現れます。
職業が映画監督だったので、撮影がはじまるとほとんど不眠不休です。緊張感が半端ではないらしく、全身が鉱物のように硬直してしまいます。
踏ん張って左足首が腫れたり、左坐骨神経痛が再発したり、右の脛が腫れたりと、あちこちの硬直に悩まされ、治療でリセットしては猛ダッシュという生活がつづきました。引っ越しを契機に治療を終了したのは2013年4月でした。
余談ですが、はじめてやって来たMさんが玄関で一瞬立ちすくみました。後悔しているのかなと思って、『治療しないで帰ります?』と言うところでした。ホームページを見て来院したにしては珍しい光景でした。
後日聞いてみたら、「バレてました?」と笑っていました。「玄関があまりに狭いし、しかも先生はアニメ声だし。ものすごくいい加減なのか、それともよっぽど自信があるのか、どっちなんだろう?」と思ったそうなのです。
4年間もいろんな所に通って、それでもどんどん悪くなっていったMさんでした。初回の治療でだいぶ「楽」になったので、私を信頼してくれたのです。
首の「苦しさ」を取るのには、ほんとうにちょっとした「コツ」があるのです。 |
|
 筋肉の硬直を「骨」だと思った人もいる 筋肉の硬直を「骨」だと思った人もいる |
|
2006年に来院し、症例34「バレエ;膝痛→お尻から太ももに波及」で紹介したTさん(当時54歳、女性)には、首の横にウインナーソーセージのような形の硬直した「こり」が張りついていました。メインは下半身の強化でしたが、首・肩こりの治療にも重点をおきました。
首のこりが激しいので、仰向けでも首に単刺をし、横の硬直(■)には透熱灸をしました。
数年かかりましたが、「固まり」がきれいに取れてくれました。Tさんは「骨だと思い込んでいたのよね~」と、ときどき思い出して笑っています。
背中が板(■)なのは相変わらずですが、71歳の現在も元気にバレエをつづけています。
<→症例33「ひざ痛・2」の「前十字靭帯断裂して、バレエをはじめた人」にも登場しています> |
|
| 首の横に「骨」 |
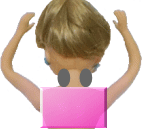 |
| 背中は「板」 |
|
2008年に来院し、症例9「アトピー性皮膚炎・1改」で紹介したSさん(当時28歳、女性)は、「プロトピック」のリバウンドでおこる顔面のアトピーがメインでしたが、首のこりも相当なものでした。
首の筋肉が癒着して、骨に張りついて固まっていました。筋肉がまるで「骨」のように硬くなっていて、はじめの頃は鍼が入っていきませんでした。
透熱灸をくり返して、1年近くかかって、やっと筋肉に単刺ができるようになりました。
小学生の頃からアトピーに悩まされていたそうですが、アトピーの人はみなさん首や背中のこりが激しいのです。関連があるのかもしれませんね。 |
|
| 首全体が「骨」 |
 |
|
2000年に頚椎症で来院したUさん(当時62歳、男性)も、首や背中に半分に割ったフランクフルトソーセージのような「固まり」がいくつも乗っかっていました。
「骨」のように硬くて、ほぐすのに4年近くかかりました。フランクフルトが消えた後は「頚椎症が再発しそうな気配」を感じることがなくなったとのことです。 |
|
 首が治ると活動的になる 首が治ると活動的になる |
|
1993年に来院したKさん(当時26歳、女性)は遊園地の乗り物でムチウチになって以来、6年間もずっと家に引きこもっていたそうです。「うつ病かしら?」と家族みんなで心配していました。
Kさんは首全体が硬直して、背中(■)にも痛みがありました。右目(■)が疲れると頭痛(■)がおこり、手に痺れが出る、とのことでした。
若いのでみるみるほぐれていきました。2か月半後(9回目)には首の硬直が取れて、眼の疲れも頭痛も起こらなくなりました。
すぐに仕事をはじめ、友人も恋人もでき、活動的な生活ができるようになったのです。
腰痛など他にもいろいろな愁訴があったのですが、→症例14「ぎっくり腰」の「根深い腰痛でも、20代ならきれいに治せる」で紹介してあります。 |
|
| 首の硬直から・・・ |
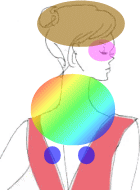 |
|
2000年に首・肩こりで来院したYさん(当時35歳、女性)は、腰痛もあり、喘息や花粉症などのアレルギー性疾患もありました。激しいメンケン反応をくり返しながらでしたが、どんどん元気になっていき、3人目のお子さんを保育園に預けて仕事に出るようになりました。
「大学生の頃から、やる気がない、体力がないとバカにされつづけてきたのですが、原因は体調不良だったんですね!」と嬉しいメールをいただきました。
<症例27「めまい・1改」、症例34「ねんざ・2」の「ヒビよりもひどい腫れ」にも登場しています> |
|
 職場のストレスは「首」を直撃する 職場のストレスは「首」を直撃する
|
|
2008年に来院したCさん(当時46歳、女性)は美人で独身のキャリアウーマンで、首・肩こり(■)の他にもいろんな愁訴を抱えていました。
胸(■)が苦しくなると、気分まで落ち込んでしまうそうです。
喉(■)が詰まってくると、息が吸いにくくなったり、食べ物が飲み込みにくくなってしまうとのこと。
1年前にひどいめまい(■)を起こして以来、ときどき再発することにも不安を抱いていました。
子宮筋腫(■)には毎回透熱灸を行いましたが、大きくなったり小さくなったりをくり返しました。
ヘルニア(■)の既往がありましたが、詳細は訊き損ないました。 |
|
|
Cさんの首の硬直が激しいので、仰向けでも首に単刺を行い、状態に応じて糸状灸や透熱灸を組み合わせました。
プライベートでも悩みを抱えていたとはいえ、上司のストレスが悪化に直結する引き金であることが明らかになっていきました。その上司は社長の身内で、経理の素人が仕事をしないで威張りまくるという最悪のパターンでした。職場のストレスがCさんの首こりの源だったのです。
4ヶ月後(12回目)に首の左側のこりが増悪したのですが、なんと上司が左隣の机に引っ越してきた日からはじまりました。それ以来、左側の凝りに悩まされるようになりました。
1年後(47回目)、今度は首の右側の硬直が強くなったので、「上司の席はどこ?」ときいてみました。右斜め前方に引っ越したタイミングでした。Cさんは机に資料を積み上げて上司が見えないようする、などの工夫をしてストレスを乗り切っていきました。
ガングリオンで紹介したEさんが、「うちのダンナも肩こりがすごいんです」と心配していました。「後姿を見たら、身体が歪んでいて、左肩がせり上がっていたんです」と言うので、「もしかしたら、イヤな上司が左側に坐っているんじゃないの?」と、Cさんの例を話しました。
指摘された彼は「みづ先生は霊能者なのか!」とびっくり仰天したそうです。
職場の人間関係がいかに首こりを増悪させるか、 横山正輝の漫画「三国志」を読んだときに実感しました。とにかく、あちこちに首がごろごろ転がっているのです。戦いで負けたり任務に失敗すると、首を落とされます。「首になる」は「首だけになっちゃう=死んでしまう」ことなのです。
「仕事を首になる」「首を切られる」のは生きる糧を奪われることですし、「借金で首が回らない」という言葉もあります。
生存の危機と首こりには大きな相関性がありそうです。 |
|
 対人緊張がこりを悪化させる 対人緊張がこりを悪化させる |
|
私は子どもの頃からの対人恐怖症だったのですが、20代の頃にはまったく自分に自信がなくて、自己嫌悪に悩まされていました。生まれつきの骨格にプラスして、対人緊張が自分の首・肩こりの悪化に拍車をかけました。
みんなが「すばらしい!」と拍手しているときに、『あれ、なんで?』などと思ってしまう。みんなが「これはダメだね」と納得しているときに、『え?別に、いいじゃない?』などと思ってしまう。。。
周りの人たちと異なるものの見方、感じ方をする。反対意見を述べてその場がシーンと静まり返る。ときには総スカンを食らう。心のうちがバレないように身を縮め、疎外感を味わって身を縮める。。。
「高所恐怖症」「閉所恐怖症」など、恐怖症にはいろいろな種類がありますが、「対人恐怖症」は、英語では social phobia(社会恐怖症)と分類されていて、日本人特有の恐怖症とされているのだそうです。
コロナ禍で話題になった「同調圧力」がひとりひとりの個性をつぶすのです。
調布病院で働いていた頃、ブラジルの日系二世が大勢「付き添いさん」として働いていました。昔の日本人のように職務に忠実で、ブラジル人らしく誰に対しても率直にものを言う、両方の長所を兼ね備えていました。
ある女性に「日本人て、人間関係で仕事をやめるんですってね」と言われて、えらく驚きました。「ブラジルでは違うの?」ときいたら、「職種できめるのよ。この仕事は自分に向いているとか、向いていないとか、それで職場を選ぶのよ」と言われたのです。
ブラジルの病院では、日本と違って医者が威張っていないそうです。掃除婦にも普通に挨拶するし、みんなで飲み会に行くときは、職種に関係なく、お互いにファーストネームで呼び合って和気藹々に楽しむのだそうです。
家族の病気でいろんな病院に通いましたが、たしかに、素晴らしい治療をしてくれる病院では、院長先生がぜんぜん威張っていませんでした。看護師も事務員もみなさんが胸を張って仕事をしていたことを思い出します。 |
|
 男性の肩には<七人の敵・灸>が有効 男性の肩には<七人の敵・灸>が有効
|
|
男性の「いかり肩」が気になることがあります。首が肩を引っぱって持ち上げている感じで、首と肩の距離が縮んでしまっています。気になったときは最後の仕上げにお灸をします。
背中を向けて椅子にすわってもらい、首と肩の硬直のつながりをみて、だいたい3ヶ所に透熱灸を行います。1壮ごとに肩が下がっていくのですが、たいてい2壮で終了です。硬直がほぐれて肩がストンと落ちます。
右のイラストは単なる例です。
毎回異なるツボを選んでいます。
首から肩へ、左右それぞれ3ヶ所づつ、硬直のつながりを見ながらツボを選びます。 |
|
|
|
|
女性にはほとんど効果がないので、男性だけにやっている治療です。
昔からのことわざに「男は敷居を跨げば七人の敵あり」とか「男子家を出ずれば七人の敵あり」などがあります。「男はいったん外に出ると七人の敵がある」と言われていたのです。
たぶん男性は外に出るとき、「敵がいないか?」を警戒する習性があって、あたりを見まわしながら無意識に肩をいからせて歩くのでしょう。 |
|
 首こりは私にとって「一病息災」の利があった 首こりは私にとって「一病息災」の利があった |
|
20代の後半にはひどい猫背に悩んでいました。ブティックの試着室の鏡の中の自分を見てびっくり仰天、どうがんばっても背筋を伸ばせないのです。よく人違いされたのですが、『こんなにも!』と驚くほどの猫背の人ばかりでした。バドミントンの試合の録画を見たら、猫背のクマがコートの中をノソノソ・・・で、あまりにもみっともないのです。
鍼灸治療に出会ってしばらくたった頃から、久しぶりに会う人に「ずいぶん若返ったね」と言われるようになりました。もとから若く見られていたのになんで?と不思議だったのですが、姿勢が良くなっていったおかげだったのです。
ちょっとずつ猫背が治っていき、55歳でストレッチをはじめてからは一気に加速して、60歳の頃には猫背とはすっかり縁が切れました。昔を知っている人たちには、「あんなに猫背だったのに!」と驚かれています。
首こりの「苦しさ」がなくなってからは、腰痛のほうが重大問題になりました。背骨の形状で、頸椎が悪い人はたいてい腰椎にも問題を抱えています。腰痛やぎっくり腰、坐骨神経痛などを起こしやすくなるのです。
腰椎だけが悪い人が首・肩こりで悩むときはたいてい一過性です。
何十年も格闘した首こりでしたが、そのおかげでずっと鍼灸治療をつづけてきた私です。まさに「一病息災」だったなあと感謝しています。 |
|
 |
| Updated: 2023/4/4 <初版 2003/7/18> |
|

