|
症例1・椎間板ヘルニア・改
|
|
|
<硬くなって縮んだ筋肉が椎骨を圧迫する>
|
|
 坐骨神経痛の症状で来院 坐骨神経痛の症状で来院 |
|
一番最初の症例を英語版にあわせて書き直しました。2001年のお正月早々、大工のYさん(当時31歳、男性)が、「左のお尻から足にかけて、ものすごい痛みで・・・」と電話をかけてきました。
1987年に一緒にバスケのチームを作って以来の友人です。開業のときに間仕切りを作ってくれた大工さんですし、いそいで治療室に向かいました。
|
左のでん部と足には、激痛だけでなく痺れもありました。坐骨神経痛の症状です。
Yさんは10代の頃からぎっくり腰をくり返した腰痛持ちです。長年やっていたバスケをやめて2ヶ月後のことでした。
「楽してるはずなのに、なんで?と思ったけど、運動を急にやめると、よくある話なんだってね」とYさんが言いました。
激しいスポーツはいろいろな筋肉障害の原因になることもありますが、人間の身体は動くように作られています。
動くことで、筋肉内部の血流が促進され、疲労物質などの代謝ができます。 |
 |
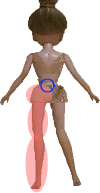 |
| ■ 症状 / ■ 原因 |
|
坐骨神経痛なら簡単に治せるはずと、自信たっぷりで治療をしました。痛みも痺れもほとんど消えて、「あ、楽になったみたい」とYさんは喜びましたが、「坐っていると、だんだん痛くなってくる感じ・・・」があったそうです。
次の日に電話がかかってきて、朝起きたら、元通りの痛みが戻っていたと言うのです。その日も必死になってありとあらゆる治療を試してみました。痛みはいったんは消えるのですが、やはり3時間ぐらいたつと、同じ痛みがまた戻ってきてしまいます。
それは器質的疾患である証拠です。 |
 |
 4週間後、ヘルニアは自然に消えた 4週間後、ヘルニアは自然に消えた |
|
Yさんは病院でMRIを撮ってもらいました。4番と5番の間にある椎間板が飛び出しているのが見つかり、「椎間板ヘルニア」という診断をされました。
「お尻から足の痛みだけで、腰には何の違和感もなかったんだよね」とYさん。自分の痛みの原因が腰椎にあると知って、たいそう驚きました。
医師に「手術をしなくてもたぶん治るだろう」と言われたので、家で安静にすることに決めました。はじめの頃は、寝てても痛い、立っても痛い、坐っても痛いと、激痛に悩まされたのですが、2週間、3週間とたつうちに、痛みが少しずつ薄らいでいったそうです。その頃になってやっと、自分の腰に問題があると気づいたそうです。
4週間後、痛みも痺れもすっかり消えてなくなりました。MRIでヘルニアがきれいに消失していることがわかりました。
Yさんの話では、ちょうどテレビでヘルニアのことを放映していたそうで、「リンパ球とか白血球とかがヘルニアを食べちゃうんだってね!」と教えてくれました。
うちの患者さんたちを見ていると、手術をしなかった人のほうが予後がいいようです。
17歳のときに受けたヘルニアの手術のあと、「ずっと左足に痺れがつづいている」と言う人もいます。脛の筋肉麻痺が残ってしまった患者さんもいます。
| 侵害部位 |
麻痺した神経 |
麻痺した脛の筋肉 |
坐骨神経
 |
深腓骨神経 |
前脛骨筋 |
足首を曲げる |
| 長母指伸筋 |
足の母指を持ち上げる |
| 長指伸筋 |
残りの四指を持ち上がる |
脛の筋肉は足先を持ち上げる働きをします。
神経麻痺で筋肉が萎縮してしまった場合でも、筋肉にパルスをかけて治療をすると、また動かせるようになります。自分で筋トレをやるなど、本人のそうとうな努力が不可欠ですが、半年かかって5割、1年かかって7・8割ぐらいの回復が望めます。
詳しく知りたい方は、症例56「足先が上がりにくい(脛の神経麻痺)」を参照してください。 |
|
|
|
|
脊柱は1本の「柱」ではありません。
首(頚椎)は7個、背中(胸椎)は12個、腰(腰椎)は5個、合計24個の小さな椎骨と仙骨(骨盤)が、靭帯と筋肉でつながれて、柱を形成しています。
右(→)は脊柱を後から見た図で、脊柱起立筋を例にしてあります。
他にもたくさんの筋肉が脊柱を支えています。
様々な形状で、様々の場所に位置し、それぞれが別方向に収縮します。
小さな椎骨たちで連結され、多様な筋肉たちで支えられている・・・
そのおかげで脊柱は、柔軟に動くことができるのです。
極端に言えば、脊柱は「器の中の水」のようなものなのです。
支えている筋肉たちの形状で、脊柱の形状が決まります。 |
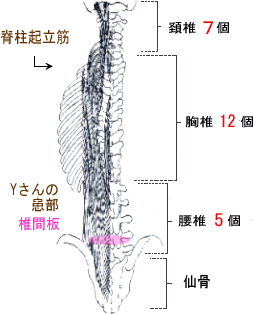 |
|
|
 日本人には脊柱の形が悪い人が多い 日本人には脊柱の形が悪い人が多い |
|
脊柱を横から見てみましょう。
正しい脊柱の形状は、頭部の重みを分散するために、前後にスラロームしています。
頚椎は前弯し、胸椎は後弯し、腰椎は前弯しています。
残念ながら、日本人は脊柱の形状が悪い人が多いのだそうです。
頚椎症などは「日本人特有の病気」と言われ、ストレート・ネックが原因とのことです。
日本人に首・肩こりが多いのは、そのせいです。
Yさんもそうですが、ヘルニアや脊柱管狭窄症を患う患者さんは、みなさん腰がまっすぐです。
(私自身も首から腰までまっすぐなので、若い頃からずっと鍼灸のお世話になっています・・・) |
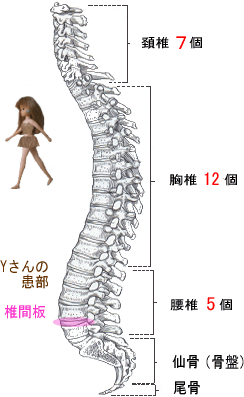 |
何故、日本人は背骨の形が悪いのでしょう?
近年、「着物文化」が原因と思うようになりました。着物姿は背筋がまっすぐなほど美しいですし、しかも正しく立派な人物に見えます。背骨がまっすぐな人間が選択的に好まれて、多くの子孫を残したのでは?と思っています。
頚椎由来の神経症状は、男性にも女性にも平等に起こります。でもうちの治療室では、腰部の椎間板ヘルニアの患者さんは全員が男性でした。
「男は背骨から老化がはじまり、女は骨盤から老化がはじまる」というのが、最近の私の感想です。 |
|
 背骨を圧迫するのは重力ではない 背骨を圧迫するのは重力ではない |
|
「ヘルニア」は「狭いすき間から何かが出る」という意味で、脱腸でも使われます。
Yさんのヘルニアの患部は上図の椎間板(■)でした。上の椎骨(4番)と下の椎骨(5番)が強い力で引っぱられ、間にある椎間板が出っぱってしまいました。椎間板の中には「髄核」というゼリー状の物質があって、クッションの役割をしています。押されてピョコンと髄核が飛び出して神経を侵し、痛みや麻痺、知覚障害など様々な神経症状が起こります。
鍼灸学校では、「人類が直立して二足歩行をするようになったおかげで、重力に対して頭の重さを支えられなくなったのが原因である」と教わりました。
でも、私の考えでは、椎骨を圧迫するのは「重力」ではないと思います。
筋肉は収縮することで働きます。筋疲労が重なると疲労物質がたまり筋肉が硬くなります。疲労回復されないまま働きつづけると、筋肉はそのまま硬くなって縮んでしまいます。どんどん縮んでいって、上下の椎骨を引っぱりつづけます。
硬くなった筋肉の中を走ってる血管も圧迫されるので血の巡りが悪くなり、ますます疲労の回復ができにくくなり、ますます筋肉が硬くなり、それによってますます圧力が高まる、という悪循環に陥ってしまいます。
Yさんは腰がまっすぐで10代からの腰痛持ちですが、治療に来るのはぎっくり腰で動けなくなったときだけでした。小さな腰痛を無視している間に、筋肉がどんどん縮んでいきました。そのせいで椎骨が圧迫され、ついには昼夜を問わない神経痛を起こしてしまったのです。 |
|
 鍼灸はヘルニアに物理的圧力をかけない 鍼灸はヘルニアに物理的圧力をかけない |
|
Yさんのように、身体のどこかに痛くなったら、まず鍼灸治療を受けにくる患者さんは少なくありません。治療をしてみての治り具合で、ダメそうだったら病院で調べてもらうという選択肢もあります。
ヘルニアの場合は、物理的な圧力はタブーです。頚椎ヘルニアのときに指圧を受けて、悪化してしまった友人がいました。壊れた部位に圧力をかけると、もっと壊れてしまうという危険があるのです。
鍼灸は物理的な圧力をかけません。身体に鍼を刺したり、お灸をしたりするのは、身体にどうやったら治るのかを教えてあげて、自然治癒力を高めるためです。ツボを取るために過度に押すのはリスクが高いので要注意です。
Yさんは、自分の腰に問題があるとは夢にも思っていませんでしたが、もちろん私は知っていました。原因となる部位と、症状の出ている部位を両方とも治療しました。
うちの治療室ではつねに全身を治療します。
生命エネルギーである「気」は、全身を巡っています。手足にある「要穴」を使って、気の流れる経路である「経絡」のバランスを調整します。手足はバイクのマフラーや煙突の役割もしています。詰まっていると気が流れません。末端を治療することで、体幹に溜まった邪気を外に流すことができます。
ひと通りの治療がおわると、小さな不具合はほとんど消えてしまいます。そのあと残ったこりをひとつずつ鍼で取りのぞきます。お灸を追加することもあります。 |
|
 鍼灸の「痛み止め」効果 鍼灸の「痛み止め」効果 |
|
身体のどこかに不具合があると、渋滞している道路のように血液の流れが悪くなります。うっ滞した古い血は、どうやら「痛み」のサインを出すようです。新しい血液が流れてくると、痛みが薄らいでいくのです。筋肉もほぐれて温まります。
人体に鍼を刺すと、エンドルフィンという体内麻薬(モルヒネ様物質)が分泌されるという研究報告もあります。治療中に眠くなるのはエンドルフィンの作用かもしれません。
エンドルフィンは「ランナーズ・ハイ」でも有名です。マラソンで限界を越えて走りつづけると、ある瞬間から、至福の快感が訪れてくる・・・という現象です。それでマラソンにはまり込んでしまうのだそうですが、実は私もバスケやテニスでランナーズ・ハイを経験しています。
Yさんは、お風呂に入っているときだけは激痛から解放されたそうです。お風呂から出た瞬間に、激痛が戻ってしまうと不思議がっていました。
感覚神経は、痛覚、触覚、圧覚、温覚、冷覚と、それぞれ別々に分かれています。温かいお風呂に浸かると、全身から「温」の情報がやってきます。その瞬間は「痛」の情報を脳がキャッチできないのだろうと思います。
ヘルニアや骨折のような器質的疾患の場合、痛みを作り出している原因を、すぐには取りのぞくことができません。どんなにがんばっても壊れた組織が修復されるまで症状がつづきます。
痛みが消えるのはたったの3時間ですが、その間は神経の圧迫がゆるめられています。ちょっとの間でも楽になれるのは身体にとっては有益なのでは?と思います。 |
|
 鍼灸は「奇跡」ではなく、伝承の医療技術 鍼灸は「奇跡」ではなく、伝承の医療技術 |
|
1995年に来院したSさん(当時36歳、男性)は、トラック運転手だった頃からつづく根深い腰痛を抱えていました。当時は無職で「ヒモ」暮らし。どうしようもなくなると治療を受けに来るというパターンをつづけていました。1997年7月(38歳)、「痛みで動けなくなった」と連絡をもらい、出張治療に行きました。
湯呑みを持ちあげた拍子にギクリとなって、そのまま痛みで動けなくなったそうです。鍼とお灸でなんとか動けるようにはなったのですが、状況はあまり改善されません。
Sさんは4年前に胆のう癌になって、胆のうの摘出手術を受けたという既往がありました。「もしも、3時間後に元通りの痛みが舞い戻ったら、救急車を呼んだほうがいいかも・・・、良くてヘルニア。最悪の場合は、癌の再発も考えられるから、ヘルニアだったらラッキーと思うしかないね」と伝えました。
夜中に痛みが増悪したので、救急外来に行ったそうです。大きなヘルニアが見つかって、そのまま入院。錘をぶら下げてベッドで安静にしていたそうです。
1ヶ月半後に退院したSさんと道でばったり会いました。「鍼じゃあ治らなかったね」とSさんに言われ、ちょっとムッとしました。病院ではただ安静にして寝ていただけです。鍼なら、1回で治らなかったら「治せない」となり、病院なら、1ヶ月入院して「治った」となるのは、不公平な感じです。
Sさんも手術はしないで、ヘルニアが自然に消失するのを待ちました。退院から2ヶ月後、坐骨神経痛の症状で来院しました。来院のパターンは変わらずで、その後も腰痛とは縁が切れないまま引っ越していきました。 |
|
 前兆が現れたときに治療するのがベター 前兆が現れたときに治療するのがベター |
|
神経には「閾値」があって、一定レベル以下の刺激は受けつけないという性質があります。長い間痛みがつづくと、「閾値」が上がっていきます。つまり、神経が鈍感になって、小さな痛みを感じなくなっていくのです。なので「絶好調」は、ときに大きな危険をはらんでいる場合があります。
「ぎっくり腰で動けない」ことが患者さんとの最初の出会いだった、ということがよくあります。筋肉性の腰痛なら、たいてい1回、長くても3回ぐらいで治ってしまいます。そのうちに、「早く来たほうがすぐに治って楽だ」と気づきます。
みなさんそれぞれ、不具合の予兆を知るサインを持っています。「腰のあたりがモヤモヤする」とか、「腰がなんか言っている」とか、「足がピリピリする」とか、そのタイミングで治療に来てくれると、本人も治療師も楽チンです。
腰痛にはいろいろな種類がありますが、椎間板ヘルニアになる前の段階を潜在性ヘルニア(椎間板膨隆)といいます。髄核が出っ張ってはいるが、まだ神経根を侵していない段階です。
Yさんによれば、「あれ!?おかしいな?から1週間で激痛。あれ?楽になってきた?まで4週間かな?」とのことでしたので、最初の「おかしいな?」のときに治療に来てくれれば、ヘルニアにならずにすんだかもしれません。
せめて「腰痛」のうちに治療をしておくこと。鍼灸を続けることで、骨の変形などの器質的な変形も、徐々にではありますが改善されていきます。 |
|
 ベストは日ごろのメンテナンス ベストは日ごろのメンテナンス |
|
ヘルニアが消失しても、原因となった筋肉の硬直はそのまま残されています。放っておいたら、またぶり返してしまう可能性があります。
外部から圧力を加えて形を変えようとしても、支えてる筋肉・靭帯の状態がそのままなら、楽になるのは一時的で、どんどん元の状態に戻っていきます。
硬くなった筋肉をほぐし、緩い所に力を与えてあげれば、背骨は筋肉という「器」に合わせて徐々に形を変えていきます。これは理論で、実際は、その人の年齢、生まれつきの骨格、癖や仕事の性質によっては、そんなに簡単には曲がった背骨の形までは変えられません。これ以上悪くしないようにするのが精一杯ということもありますが・・・<→ 症例17「腰痛・2改 鍼灸で背骨の矯正」を参照してください>
鍼灸治療は急性の病を即効で治療する技をたくさん持っていますが、真の醍醐味はメンテナンスにあります。1年、3年、5年と、治療を積み重ねていくと、いろんな不具合がリセットされ、身体がだんだん若返っていきます。
鍼灸治療だけでは、「完治」が望めない場合もあります。とくに60歳を過ぎたら、努力している人しか元気に暮らせない・・・というのが実感です。
日ごろのメンテナンスはとても大切です。よく動く人、運動をしている人は、暦年齢より若いですし、ストレッチをつづけている人もそうです。
自分でできるメンテナンスとして、「360度リョコちゃんストレッチ」と「リョコちゃんウォーク」を紹介してあります。みなさんもチャレンジしてみてください。 |
|
|
|
|
 |
| Updated: 2020/6/12 <初版 2002/12/18> |
|

