|
症例56・足先が上げにくい(脛の神経麻痺)
|
|
|
<前脛骨筋、長母指伸筋などの深腓骨神経の障害>
|
|
 1人目:左腰と足の激痛→感覚がなくなった 1人目:左腰と足の激痛→感覚がなくなった |
|
深腓骨神経麻痺の患者さんは4人いて全員男性です。順に紹介します。
2000年にぎっくり腰で来院したTさん(当時53歳、男性)は、2010年から隔週でメンテナンスをするようになりました。
2013年5月(65歳)、京都のお母さんに腫瘍が見つかって入院中とのことで、心労もあって、左半身がバリバリにこっていました。左足~足首~母指に痺れを訴えたので、腰から足までかなりハードな治療をしました。
その夜、Tさんは車を運転して山梨の別荘に出かけました。翌朝、左腰から足に激しい痛みが起こり、歩けないほどになったそうです。痛み止めの座薬を入れて、5時間後、痛みは嘘のように消えたのですが、左足全体が痺れて、感覚がなくなったそうです。
翌日、運動麻痺と知覚異常が、左足母指、足底、足背、脛とふくらはぎに残り、びっこを引きながら仕事に出かけたそうです。
病院では「何だろう?」と首をかしげられ、MRIの所見から、17歳のときに受けたヘルニアの手術の残骸(=小さな破片)が残っているので、それが神経を圧迫しているのかもしれない・・・と言われたそうです。 |
 |
 腰から足先まで、あらゆる部位を治療 腰から足先まで、あらゆる部位を治療 |
|
発症から10日たっての来院でした。
隔週でメンテナンスをしていた患者さんです。腰痛とはすっかり無縁になって、どんどん若返っていったはずなのに・・・と、すごい責任を感じました。
足の爪先を上げる筋肉が麻痺していました。足を引きずって歩くしかなく、つまづいて転びそうになったり、自転車のペダルから足が落ちてしまったりするそうです。
神経の病気は最初が肝心なので、はじめは週2で治療をしました。神経は長い間圧迫がつづくと変性を起こし、もう二度ともとには戻りません。麻痺した筋肉へはパルス(電気治療)が有効です。適宜、お灸を追加しました。
腰やでん部には痛みも痺れもありませんが、重点的に治療し、透熱灸や灸頭鍼もしました。経絡治療を中心に全身のバランスも整えなければなりません。
2回目の治療時に、足の指だけ上げられるようになりました。日を追うにつれ、痺れの部位がだんだん少なくなっていきました。
6回目(2週間後)を過ぎて、残ったところが下の図です。「母指を中心に、全体にスポンジをかぶったように感覚が遠い」とのことでした。
| ○ |
Tさんのヘルニアの手術痕 |
|
● |
運動麻痺、知覚異常、痺れ |
 |
|
| ふくらはぎ~アキレス腱 |
|
 |
|
| 脛、足背、母指 |
|
 |
|
母指の裏、母指球、
足底内側 |
|
| ・・ここの痺れは現在も残っています・・ |
|
|
|
 坐骨神経は仙骨神経叢から分岐している 坐骨神経は仙骨神経叢から分岐している |
|
Tさんの運動麻痺と知覚異常は、坐骨神経の支配領域にあります。どこで神経が圧迫されたのでしょうか。脳から脊髄なら中枢神経障害なのでお手上げですが、末梢神経の障害なら鍼灸で治療ができます。
脊髄から分岐する仙骨神経叢の、5番目が坐骨神経です。シャープペンシルぐらいの太さで、運動神経と感覚神経が束になっています。束の中から障害のある神経を選り分けることは(鍼灸では)できません。
腰椎4番~仙骨2番から、末端の麻痺と感覚異常のある部位まで、神経を圧迫している可能性のあるところを、片っ端から治療しました。ポイントを絞るために、解剖学の助けをかりました。
| 仙骨神経叢から分岐する神経の支配する筋肉 (皮枝は省略) |
|
|
|
| 2)上殿神経(L4~S2) |
⑥中殿筋、⑦小殿筋、⑧大腿筋膜張筋 |
|
|
|
|
|
| 5)坐骨神経(L4~S2) |
大腿二頭筋、半腱様筋、半膜様筋 |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
 |
| 外側腓腹皮神経 |
|
| 浅腓骨神経 |
長腓骨筋、短腓骨筋 |
| ◎深腓骨神経 |
①前脛骨筋、②長母指伸筋、③長指伸筋、 ④第三腓骨筋、短母指伸筋、短指伸筋 |
|
|
|
|
 |
| 5-2)脛骨神経 |
腓腹筋、ヒラメ筋、足底筋、膝下筋、⑤後脛骨筋、長指屈筋、長母指屈筋 |
|
|
|
 |
| 内側腓腹皮神経 |
|
| 内側足底神経 |
短母指屈筋、母指球筋 |
| 外側足底神経 |
母指内転筋 |
|
|
|
|
 前脛骨筋を中心、手探りの治療をつづけた 前脛骨筋を中心、手探りの治療をつづけた |
|
7回目の治療時にやっと、「朝起きたときは母指球の痺れだけ。歩いているうちに脛の上まで広がっていく」ようになりました。足関節の背屈と内反ができなかったので、①前脛骨筋に重点をおきました。治療後は、痺れの範囲が「朝と同じレベル」になりました。筋肉の使い方を思い出せるように、前脛骨筋にテーピングをしました。
8回目には、⑤後脛骨筋(ふくらはぎの後方、足屈と内反)麻痺の可能性を考えて、ふくらはぎから足裏の母指球までのパルスを追加しました。<→症例54「ふくらはぎ(後脛骨筋)」に詳細とイラスト>
12回目(6週後)、足先も少し持ち上げられるようになり、内反もできるようになり、「筋力が7割ぐらい戻った」とのことでした。痺れは変わらずでしたが、少しずつ筋力が回復していき、ビッコを引かずに歩けるようになりました。ここから週1の治療になりました。
19回目(3ヵ月後)、MRIで「ヘルニアのかけらが消失した」と報告してくれました。筋力も8割ぐらいもどったそうで、歩行時につまづく心配がなくなったとのことでした。
30回目(半年後)、私自身が④第三腓骨筋の肉離れを起こしたあと、Tさんも足首の外反が難しいことに気がついて、そこへのパルスも追加しました。<→症例47「ねんざ(足首)・第三腓骨筋」に詳細とイラスト>
33回目には、前脛骨筋のパルスに反応して足先が元気に持ち上がるようになりました。ここから従来どおり、隔週での治療になりました。 |
|
 ぎっくり腰のあと、前脛骨筋が痩せた ぎっくり腰のあと、前脛骨筋が痩せた |
|
発症から2年4ヵ月後のことです。2015年7月(67歳)、Tさんは20キロのカメを持ち上げて、ぎっくり腰になってしまいました。それは1回で治ったのですが、次の来院時(2週間後)に、Tさんの脛の筋肉が痩せているのを発見しました。
内側から眺めると、脛骨の尾根のむこうに筋肉の盛り上がりがなく、筋肉がえぐれているように見えました。その筋肉の落ち方の激しさにとてもショックを受けました。発症してすぐに治療をはじめたのに、神経の変性が起こっていたことを知りました。
ちょうど大学は夏休みでした。通勤もなくなり、校舎の中を歩き回ることもなくなったので、それが原因と思いました。
来院のたびに毎回「歩け」「動け」としつこいぐらいにくり返しました。「そうだな、歩こう!」と口では答えるのですが、Tさんは本を読んでいれば幸せという学者肌の人です。必要に迫られなければ歩くこともせず、運動もいっさいやりません。
大学がはじまって、歩く機会が増えたら、筋肉もすこし戻っていきました。
神経が変性しているので、いったん萎縮してしまうと、もとに戻すのは至難の業です。でも、どれだけ動いたかと、筋肉の痩せ具合にはあきらかな相関性がありました。
73歳になった今でも前脛骨筋は痩せてしまっていますが、日常生活には問題のない状態をなんとか維持しています。
ぎっくり腰のとき数日間「安静」にしていたことが、「えぐれ」のきっかけだったことを知ったのは、他の患者さんの治療をしてからです。 |
|
|
|
|
脛にあって、足先を上げる筋肉はおもに3つです。
①前脛骨筋は、脛の前面にある大きな筋肉です。前脛骨筋麻痺では、足先を持ち上げられなくなって、爪先がだらりと下がってしまう「下垂足」になるそうです。
その下にある、②長母指伸筋は足の母指を持ち上げ、③長指伸筋は残りの四指(2指~5指)を同時に持ち上げます。
これらの3つの筋肉は重なっているので、同時に治療できます。鍼をずらりと(10本ぐらい)並べて打ち、パルスをかけます。電気刺激で眠っている神経をたたき起こすのです。強制的に筋肉を動かすことで筋トレにもなります。
| ① |
② |
③ |
⇒ |
3つの筋肉を重ねる |
(骨) |
| 前脛骨筋 |
長母指伸筋 |
長指伸筋 |
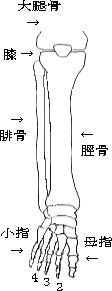 |
 |
 |
 |
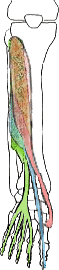 |
| 足首を曲げる |
母指を上げる |
2~5指を上げる |
爪先を上げる |
|
|
 2人目:長母指伸筋の神経麻痺 2人目:長母指伸筋の神経麻痺 |
|
2018年9月に腰痛で来院したSさん(当時60歳、男性)も、左の脛の筋肉が萎縮して、すでに「えぐれ」ていました。
まず左脛の痛みに苦しんだそうです。そのあと腰痛が激しくなって、3年前の8月、ヘルニアの手術(腰椎4番)をやったときには、足の爪先が上げられなくなっていました。神経を調べた医師に「反応ゼロだな。でも0.1はあるかな・・・」と言われたそうです。
足の母指を上げる②長母指伸筋がピクとも動きませんでした。私はいつもの通り、「動くようになるよ。パルスをかけて、筋トレがんばれば、半年かかって5割、1年かかって7.8割が限界だけど」という話をしました。
Sさんは筋肉ムキムキのアスリートで、ロードバイクが趣味でした。脛の筋肉が麻痺すると、自転車のペダルから足が落っこちてしまうそうです。トライアスロンにも挑戦したいけど、走ろうとすると、左足の爪先が上がらずに転びそうになるとのことです。
か弱い左脛をかばって動くので、左の股関節と鼡径靭帯、そこからつながる太ももの筋肉がパンパンに張って、痛みがありました。首から腰までゆがんで縮まっていて、背中もバリバリにこっていました。
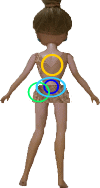 |
| ■ |
ヘルニアの手術痕 |
| ■ |
腰痛 |
| ■ |
運動麻痺と知覚異常 |
<脛をかばったせいで>
|
 |
 |
|
| 母指はまったく動かなかった |
|
|
|
 ちょっとでも動かせれば筋トレができる ちょっとでも動かせれば筋トレができる |
|
Sさんの治療は毎週行いましたが、他の部位は省略します。
仰向けでパルスをかける前に、「足首すべて」「母指だけ」「四指だけ」と順番に上げてもらいます。上のイラストでわかるように、3つの筋肉は重なっていて、前脛骨筋と長指伸筋も弱っていました。
長母指伸筋はピクとも動かないので、場所を特定するのに苦労しました。硬くなっている筋肉を探すのは簡単ですが、力なく弛緩しているので触診で見つけられません。本を見ながら大体の当たりをつけて、長母指伸筋を中心に、脛全体にびっしりと鍼を並べ、すべてにパルスをかけました。
神経が麻痺していると、はじめはパルスに反応しません。筋肉に電気刺激が伝わらないからです。でも本人によると「モヤモヤする」ようになって、3回目ぐらいからちょっとずつ動くようになりました。
ちょっとでも動けば、自分で筋トレも可能です。Sさんの努力も大変なものでした。プールで歩いて泳いで、自転車で走って、ジョギングもやりました。
運動するときは、長母指伸筋にテーピングをしてもらいました。テーピングがあると「そこを使え」と注意を向けられますし、筋肉を補強できます。
9回目(2ヵ月後)、5%ぐらい。12回目には10%ぐらい。13回目(3ヵ月後)には「大分力が入れられるようになって、自転車で50キロ走る間、1回も足がペダルから落ちなかった」と報告してくれました。 |
|
 痛み止めのロキソニンを飲んでいた! 痛み止めのロキソニンを飲んでいた! |
|
母指を動かせるようになってからは、長母指伸筋を見つけるのが楽になりました。か弱いので、何回か上げるとすぐに疲れてしまいます。
治療開始から5ヶ月(21回目)、2019年3月に腰痛のために、痛み止めのロキソニンを飲んでいることを知りました。腰痛が起こった8月に医師に処方され、休日以外は毎日服用しているとのことでした。
鎮痛剤など、神経に作用する薬を飲んでいると、鍼の効きが悪くなるのです。薬をやめようとがんばったのですが、金曜日だけは、会議で長時間坐っていると腰が痛くなって耐えられないとのことでした。
ちょうど同時期に、長年治療している患者さん(53歳、男性)が腰痛を訴えるようになりました。彼も坐っているときに痛みが起こるそうです。腰つきが同じなので、毎回アプローチする部位をちょっと変えて、2人を同時進行で、いろんな治療を試してみました。
FT(フィンガーテスト)で脊柱中央にツボを取るのですが、そこを中心に深い鍼を打ってしばらく置鍼、残ったこりを単刺で取るやり方が一番効果があることがわかりました。長年愛用してきたIPコードは引き出しにしまいました。
3ヶ月たって、2人とも腰痛の心配から解放され、Sさんはロキソニンを飲まなくても大丈夫になりました。開業して26年もたって、治療法の開拓ができました。 |
|
 1年半で筋力が5割以上回復 1年半で筋力が5割以上回復 |
|
鎮痛剤をやめたおかげで、Sさんの脛の筋肉はぐんぐん育っていきました。7月には、ロードバイクで90回転まで上げられるようになりました。筋力は5割ぐらい戻ったそうです。
「2時間半走った」とか、「80キロ走った」とか報告してくれるようになりましたが、左脛はか弱いので途中で疲れてしまうとのことでした。
はじめの頃は、脛から母指へはお灸をしていました。この頃から、筋肉がカチンカチンになってしまうので、パルスのあとは単刺でこりを取りのぞくようにしました。
ハードな筋トレで、治療前にはかなり筋肉が太くなったように見えるのですが、それは「腫れ」です。治療をすると腫れが引いて、「あ、やっぱり痩せているね」となるのが、神経麻痺の悲しいところです。
1ヶ月ぐらい前に、足首の硬さが気になるようになりました。長い間動かさずにいたので、筋肉の癒着がおこっていたようです。癒着を取るために鍼と透熱灸をし、Sさんにもストレッチをお願いしました。足首がスッキリしたら、ときどき力が抜けそうになるそうです。
現在、治療開始から1年半たちました。横たわっているときは、可動域もほぼ100%になり、右足と同じように動かせるようになりました。でも、パワーは足りません。他の筋肉がムキムキでパワフルなので、彼らについていけないのです。左脛だけ特別扱いで筋トレをするようにお願いしました。 |
|
|
|
 3人目:原因は脊柱管狭窄症 3人目:原因は脊柱管狭窄症 |
|
3人目の症例は1995年からの患者さんのNさん(当時49歳、男性)です。運動神経バツグンで筋肉ムキムキ。テニスで走り、道でも走るスポーツマンです。腰痛持ちだったのでずっとメンテナンスをしていたのですが、60代になってからは、来院するのはぎっくり腰をおこしたときだけになりました。
「不思議なことに、腰痛はすっかり治ったよ」とNさんは言うのですが、感じなくなっただけなのです。60代になると身体が鈍感になって、小さな不具合を感じなくなる・・・という、よくある落とし穴です。不具合を固めて治す=筋肉のギブス化がおこって、腰も背中もどんどん縮んで行きました。
2014年(68歳)の夏の終わりに、右ひざから下が「冷たい」感じがするようになりました。血管には異常なしでした。またぎっくり腰を起こしたあと、11月、2回目のMRIで脊柱管狭窄症が見つかりました。
長年の間、左の腰痛に悩まされてきたのですが、脊柱管狭窄症が起こったのは右側でした。右のでん部と足に軽い痺れがあり、知覚異常もありました。 |
|
 上殿神経と坐骨神経に異常があった 上殿神経と坐骨神経に異常があった |
|
脊柱管狭窄症と診断される前から、Nさんは右のでん部(■)の硬さと痛みを訴えていて、ずっと治療をしていました。
現在も、⑥中殿筋と⑦小殿筋が硬くなって痛みがでます。
太ももの外側、⑧大腿筋膜張筋(■)も張って、ときどき痛みが出ました。
どちらも上殿神経支配です。
<↑神経の表>
冷たさを感じた部位(///)は坐骨神経の支配領域です。
股関節と鼡径靭帯(■)は、かばって動くせいで、ときどき痛みが出ました。 |
|
|
女性は骨盤から老化がはじまるので、女性のでん部はつねに治療の必須ポイントです。でも、男性のでん部は故障しにくい。男性は背骨から老化がはじまるのです。
男性がでん部の痛みを訴えるときは、ほとんどが脊柱が原因です。
本人はあまり気にしていませんでしたが、背中(■)と腰(■)が縮んでいくので、必死になって治療をしました。 |
|
|
 走る筋肉と「ゆっくり」動く筋肉は異なる 走る筋肉と「ゆっくり」動く筋肉は異なる |
|
Nさんの治療はほとんど毎週行いました。ときどき一緒にテニスをするのですが、若者のように走れます。でも、立っている姿は「おじいさん体形」です。60代後半になると、鍼灸と運動だけでは老化に対抗できないのです。
「ストレッチをやってください」としつこいぐらいにお願いしたのですが、「俺はストレッチなんかやらないよ」と、あくまでも頑固です。うちの母もそうでした。自分の身体に自信があって、誰よりも若さを誇ってきた人にありがちなのです。
他の人たちが身体に不安を抱き、歩いたり、体操をしたりするようになるのを横目で見て、『自分はそんな努力をしなくても、誰よりも若くて元気でいられる』という自負心があるのでしょう。
Nさんは、走ったり、山登りをしたりのハードな運動には熱心ですが、スローな運動には無関心です。健康のための努力は「弱者」のすることと思い、自分が「負け犬」になったように感じてしまうのかもしれません。
激しい運動は大きな筋肉を鍛えられます。でも、それは特急電車に乗っているようなもので、小さな筋肉たちを見過ごすことになるのです。各駅停車に乗る=「ゆっくり動く」と、急いでいるときにはスルーしてしまういろんな筋肉を鍛えられます。
激しい運動をすると、筋肉に疲労物質の乳酸がたまり、筋肉がどんどん硬くなっていきます。ゆっくり動けば、筋肉たちに新しい血液を送り込んで疲労物質を代謝できます。
ストレッチと合わせれば、柔軟性を維持することが可能になるのです。 |
|
|
|
|
 ぎっくり腰のあと、一気に筋肉が萎縮 ぎっくり腰のあと、一気に筋肉が萎縮 |
|
Nさんの神経症状は日に日に改善されて、なんとか維持をしていたのですが、発症から4年後、2018年6月(72歳)頃から、ときどき右足が上がらずに駅や階段で転んでしまうようになりました。(反射神経がいいので、事故にはつながりませんでしたが)
右脛をよく見ると、なんとなく筋肉が薄い感じです。それまで、痺れがあるのは右でん部~ふくらはぎだったので、うつ伏せのときしかパルスをかけていませんでした。あわてて右脛へのパルスを追加しました。
2019年4月(73歳)、スピンサーブの練習をしてぎっくり腰になりました。Nさんはすっかり意気消沈して、しばらく引きこもり状態になってしまいました。
最愛の奥さんを亡くして12年、ボランティア活動にいそしんで喪失感を紛らわしていたのですが、何かあると一気にどん底に落ちてしまいます。うちの母もそうだったのですが、夫婦仲が良くてあまりにも幸せが大きいと、失ったあとの不幸はそれだけ大きくなってしまうようですね。
それまで、右脛の筋肉は「よ~く見ればちょっと薄いね」という程度だったのですが、脛の筋肉が一気に痩せてしまいました。
11月にインフルエンザにかかり、直後に寝違えになりました。どちらも生まれてはじめてのことだったので、またNさんはすっかり意気消沈して、2週間も身動きもせずに寝込んでしまいました。右脛の筋肉は「えぐれ」て見えるほど萎縮してしまいました。
現在は痺れはなくなり、テニスで走ってはいますが、ちょっと気をゆるめると脛の筋肉はすぐに痩せてしまいます。本人の努力に期待したいところです。。。 |
|
 「安静」はご法度=動いて治す 「安静」はご法度=動いて治す |
|
Nさんの筋肉が一気に萎縮したことで、1人目のTさんの筋肉が萎縮したのは、ぎっくり腰で数日「安静」にしていたのが原因ということがはっきりしました。
私自身は、ぎっくり腰でも他の怪我でも、仕事も家事もいっさい休みません。「動いて治す」主義なのです。安静にして「治った」と思っても、筋肉が落ちてしまうので、新たな負荷がかかるとまたぶり返します。筋肉を維持したまま、可動域を維持したままなら、「治った」ときは、そのまま復帰できます。
「動いて、動いて、動きまくる」、それが元気に動きつづける唯一の方策なのです。
でも、テニスだけは休みます。不具合を抱えたまま激しいスポーツをすると、こじらせてもっと長引く可能性があります。痛みが他に波及する可能性もあります。フォームが崩れると、元に戻すのにも時間がかかります。
「イタタ、イタタ」とつぶやきながら、家事と仕事をこなす。テニスなどのスポーツは、日常生活が問題なくこなせるようになってから再開しましょう。
神経が麻痺しているので、いったん筋肉が萎縮してしまうと、もとに戻すのは至難の業です。走っても、歩いても、どうしても麻痺した筋肉を使うことを忘れてしまう。身体の中に「弱者」がいたら、そこだけ特別扱いしてあげる必要があるのです。 |
|
 4人目:13年前にヘルニアの手術 4人目:13年前にヘルニアの手術 |
|
4人目の患者さんはKさん(57歳、男性)です。2019年8月、13年ぶりの来院でした。右腰のぎっくり腰になって、痛みに耐えられずに来たそうです。
Kさんの初診は2006年12月(45歳)、ぎっくり腰が主訴でした。20歳頃から何度もぎっくり腰をくり返してきたそうです。
彼が剣道を教えていた小中学生が次から次へと1回で治ったので来院したのですが、長年の無理がたたった腰痛はそう簡単ではありませんでした。
3回治療をしたあと、「ヘルニアが見つかったので手術をする」と連絡をくれました。
当時のカルテを見たら、右のでん部からふくらはぎまで「筋力低下」がありました。
坐骨神経の圧迫が原因ですね。 |
初診時のKさん
|
 |
|
|
|
|
|
|
Kさんの右脛の筋肉は痩せて薄くなっていました。右脛をかばって動くので、上述の3人と同じように、右の股関節周辺にも痛みがありました。
Kさんはすっかり意気消沈していました。右脛に力が入らないので、大好きな剣道も思うように行かず、夢も希望もやる気もなくなったそうです。
Tさんからはじまった深腓骨神経麻痺は、手探りの治療をつづけてすでに4人目です。私もかなり熟練しました。「あきらめたら終わり」で、可能性はゼロです。あきらめずにがんばれば、きっと取り戻せると励ましました。
2回目には、腰痛が日に日に和らいでいるとのことで、プールで筋トレをはじめ、毎日たくさん歩くようになったそうです。Kさんの筋肉は一気に盛り上がりはじめました。
ハードな運動をしたあとは右脛がつるそうです。筋肉痛になるほどがんばった結果です。6回治療して、腰痛はほぼ改善。今もがんばってくれていることと思います。 |
|
|
|
|
無意識に運動をすると、神経が麻痺している筋肉だけ忘れられてしまいます。右脛の筋肉は、足の爪先を上げる働きをします。歩くときには、「正しく」歩きましょう。踏み出す足は踵からついて、爪先立ちになり、膝を伸ばしたまま地面を蹴りましょう。歩幅を大きくすれば、股関節のストレッチもできます。
< FAQ24:「正しい」歩き方とは?リョコちゃんウォーク を参照してください> FAQ24:「正しい」歩き方とは?リョコちゃんウォーク を参照してください>
歩くときに「爪先を上げる」、立っているときにも「爪先を上げる」、坐っているときも「爪先を上げる」ことを意識して、ちょこちょこ運動をしましょう。
下の図は、①前脛骨筋、②長母指伸筋、③長指伸筋を別々に持ち上げる筋トレです。同時にストレッチになります。つりそうな筋肉を見つけたら、カマヤミニでお灸をしてください。足指の柔軟性があると、転びにくくなりますよ。
<*FAQ22:「リョコちゃんストレッチ」からの抜粋です>
- #26: 足指のストレッチと筋トレ -
| ① |
 |
| 足背を上げる |
|
| ② |
 |
| 親指を上げる |
|
| ③ |
 |
| 四指を上げる |
|
|
 |
⇔
交互に |
 |
| 上げ⇔下げ |
|
⇒ |
 |
⇔
交互に |
 |
| 曲げる⇔伸ばす |
|
| 次に、足指を広げたり、縮めたり、伸ばしたり、曲げたり・・・ |
足首を曲げて脛を、伸ばしてふくらはぎを、同時にストレッチ |
|
- #27: 足首とつながる筋肉のストレッチ -
 |
 |
| 寄せる⇔広げる |
|
| 太ももの付け根~踵まで、ピシーッと伸ばして、いろんな筋肉をストレッチ |
|
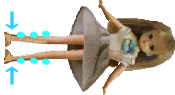 |
| 長腓骨筋(脛外側)、etc. |
|
⇔
交互に |
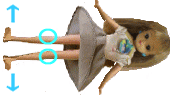 |
| 膝窩筋(膝裏)、etc. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|

