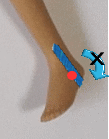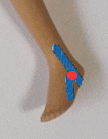|
|
みづ鍼灸室 by 未津良子(症例集) |
|
| 症例47・ねんざ(足首) 1
|
|
|
|
|
|
| 症例47・ねんざ(足首) 1 |
|
|
|
|
| 腫れさせないことが重要 |
|
| 関節のあるところ、ねんざあり |
ねんざは、「動き」とともにおこります。「グキッ」とか「ペリペリ」とか、音がすることもあります。
関節を支持している靭帯が、過負荷、過伸展によって、損傷された状態を「捻挫(ねんざ)」といいます。
(患者さんのなかには、靭帯でなく、筋肉を痛めた症例もありました。
 「#3短腓骨筋の障害」 「#3短腓骨筋の障害」
 「#4第三腓骨筋の肉離れを併発」) 「#4第三腓骨筋の肉離れを併発」)
関節のあるところ、ねんざはどこでも起こります。「ムチ打ち」「ひざ痛」「手首痛」など、別の病名がついていることもあります。
ここでは、足関節の捻挫について書きます。 |
|
|
| 炎症とは? |
ねんざの4大特徴は、発赤、腫脹、発熱、疼痛です。靭帯の損傷の程度によって、重傷度はさまざまです。
組織が損傷を受けると、炎症が起こります。傷ついた細胞からは浸出液がでますし、大量の血液(白血球やリンパ球など)が集まってきます。
痛みは「ここが悪いぞ」のサイン。患部の発熱も治療のためです。
炎症は自然治癒力の一環ですが、早く治すためには、そのサイクルを小さくする必要があります。すぐに冷やすこと。氷嚢を作って患部にあて、足を高く上げて、しばらくは安静にしましょう。
冷やすのはせいぜい10分以内。いつまでも冷やしつづけると血流が悪くなり、治りが遅くなります。
足を動かさないようにして、テーピングなどで固定をし、なるべく早く来院してください。 |
|
|
| 腫れを引かせる |
発症直後は、急性の炎症をおこしています。患部にいきなり深いハリを打つと、炎症が増悪する可能性があります。
まず、炎症を沈静化させ、腫れを引かせるところからはじめます。患部とその周囲に、浅いハリをたくさん置鍼して、ざっと気血を動かします。
お灸は「温めるもの」と思いがちですが、細くて長い糸状灸で「冷やす」ことができます。「腫れ」を囲んで糸状灸を並べ、寸止めで火を消します。何回かくり返すこともあります。腫れが引いていき、痛みもやわらいでいきます。
小さな患部に水分が集中すると、渋滞をおこします。行きたくても行かれない、出たくても出られない、ということになります。
まず、「腫れ」を引かせる。腫れていない状態を維持する。
それが、ねんざ治療のコツです。 |
|
|
| 患部に集中治療 |
あらかたの熱と腫れが引いたところで、患部に深いハリを刺し、置鍼します。これも何回かくり返す必要があるかもしれません。
次に、温めるお灸です。灸点紙を敷いて、もぐさをのせ、透熱灸をします。深部までツーンと熱さがとおるまでやりましょう。
マッサージは西洋医学の一部で、静脈血を心臓に送る方向(求心性)に手技を行います。
いったん腫れが引いたとしても、すぐに元通りになります。
経絡治療では、遠心性が基本です。
気の流れを促すために、末端へ、足指の方向へ指を動かしていきます。
そのほうが、長持ちをする、というか、腫れを引かせる効果が翌日まで持続します。
患部に金粒を貼り、反体側治療で、腕に銀粒を貼ります。
井穴から邪気を抜くと、痛みと腫れが引くのが早いです。 |
|
|
| ねんざのテーピング |
足首の外くるぶしの捻挫を例にテーピングを紹介します。FAQ20「キネシオ・テーピングのやり方」を参考にしてください。
| ① |
伸ばされた靭帯を保護する方向にテーピングをします。軽い捻挫には1本で充分ですが、痛みが出るときはもう1本貼ります。
可動域を制限して、患部を守ることが目的です。 |
| ② |
捻挫の部位をかばって動く筋肉にテーピングをします。可動域を維持しながら、より楽に動けるようにするのが目的です。 |
捻挫も動いて治します。そのほうが、筋ポンプ作用で患部の血行が良くなるので、早くきれいに治ります。足首の内側など、他の部位の捻挫の場合も同様です。
何本か貼ってみて、歩いてもらって、動きが楽になるテーピングを見つけましょう。患者さんが自分で貼れるように、写真にとります。
長時間テーピングをつづけるとかぶれてしまいます。貼っている時間をできるだけ短くするために、運動の前に貼って、終わったらすぐにはがすようにしています。
でも捻挫の場合は、眠っている時間も貼りましょう。睡眠中に足を動かしてしまい、朝になると悪化しているという危険性があるからです。①の「可動域を制限するテーピング」は睡眠中にも必要です。
私はお風呂の前にテーピングを剥がして捻挫の治療をし、しばらく皮膚を休ませてから、寝る前にまた貼ることにしています。 |
|
|
| ②患部(●)を守るためにかばって動く筋肉を補強するテーピング |
| 筋力と可動域の維持が重要。動いて治すために酷使する筋肉を補強します。 |
| 前脛骨筋と長母指伸筋 |
 |
足の母指 脛 脛 |
|
|
|
|
|
|
| 全身治療も必要 |
高校生ぐらいまでは患部だけを治療しますが、大人の場合は全身治療もします。
疲労がたまっていると、自然治癒力が低下し、治りが遅くなるからです。
最初の1回、もしくは週に1回はフルコースの治療をし、間に患部だけの治療に通ってもらうパターンにしています。
経絡治療で疲労を取り、全身の経絡のバランスを整えます。
かばって歩くために、ひざや腰に痛みが出たり、反対側の足に負担がかかったり、つかまり立ちで腕や肩が疲れたりと、あちこちに不具合が出ている場合がほとんどです。
身体のどこかに滞りがあると、気の流れが悪くなります。
この機会に大掃除をしましょう。 |
|
|
| 慢性のねんざ |
骨と違って、筋肉や靭帯は治る速度が遅いので、傷跡がのこってしまう場合があります。
肉離れなどで、同じ筋肉を何度も切る人がいるのは、この「瘢痕治癒」のせいです。
ねんざをそのまま放っておくと、完全に治りきらないまま、慢性になってしまうことがあります。
患部の腫れがそのまま残って、ブワブワした感じになっている人もいます。
いったん靭帯が伸びきってしまったあとなので、ちょっとしたことでねんざをしてしまいます。
たいていは軽症で、簡単に治ります。
最初のねんざのときに、きちんと治療しておくことをオススメします。 |
|
|
| 2ページ目へつづく |
|
 |
|
| Updated: 2013/12/30 |
|