| 3/1(日) |
「鉄平流」特訓で私にもガングリオンが |
年末に、足が痛くて歩けないという患者さんが来た。
4ヶ月前に足の裏に出来たガングリオンが元凶だったので、あちこちに広がった痛みもあわせて簡単に治療ができた。
ガングリオンがあった患者さんは他にもたくさんいて、自分でカマヤミニで治すこともできる。
新しい更新は、症例55「ガングリオン」だよ~~
最近イラストにこっているので、時間をかけて書いていたら、完成直前に、自分にも(また!)ガングリオンができちゃった。
6週間もテニスを休んだので、はじめはリハビリと軽めにやっていた。
でも壁打ちで久しぶりに「鉄平流」特訓をやったあと、足の裏にまたできちゃったのである。
「おれは鉄平」はちばてつやの剣道漫画である。
主人公の鉄平は、ちっちゃくて運動神経バツグンで、勝ちにこだわる策略家で、何をしでかすかわからない破天荒な少年である。 |
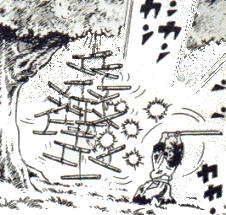 |
彼が人知れずやった特訓は、木の枝からたくさん竹刀をぶら下げ、その中に入り込んで、次から次へと竹刀を打つもの。
ブランブラン揺れるので、避けそこなうと絡まってしまう。
鉄平はそうやって反射神経を鍛えたのである。
私の「鉄平流」特訓とは、壁とやるボレー&ボレー。
至近距離で壁に向かってバッシンバッシンボールを強打し、壁から返ってくるボールを打つ。
壁の手前、まずサービスラインのちょっと内側からはじめて、だんだんに壁に近づいていく。
バシバシ返ってくるボールをバシバシ打って、反射神経を鍛える。
ラケット面を合わせるだけだと、鋭いショットを打てない。テニスは「フォーム」で打つのである。
「まず足を出す」という練習も兼ねて、打ったらすぐにスプリットと、足はずっとステップを踏みつづける。
かなりハードな特訓である。
筋力の落ちているところで、「鉄平」をやったので、足裏に過負荷がかかってガングリオンができてしまったらしい。
治療をしてすぐに消えたと思っていたら、数日後、10年前と同じところに、新たなガングリオンができていた。
< =ガングリオン・マークだよ。これにもかなり苦労した。(笑)> =ガングリオン・マークだよ。これにもかなり苦労した。(笑)> |
| <今回> |
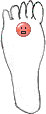 |
中足肢節関節 |
| 中足骨寄り |
| >床を踏むと感じる |
| スプリットステップのせい? |
|
|
| <10年前> |
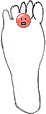 |
中足肢節関節 |
| 指寄り |
| 爪先立ちで感じる |
| 走ると出来る? |
|
|
詳細は「ガングリオン」のページに書いたので、ここでは省略するけど・・・
左足に鍼やお灸をしようとしたら、あちこちがつりそうになった。
右足はまだマシで、指を広げて地面を掴むことができるけど、左足はグーで地面につく感じである。足が固まっていたのである。
胸骨と大胸筋を痛めたせいで、この2ヶ月は上半身の治療に専念していた。腰の心配もしていたので、足は盲点だったのである。
脛の筋肉の神経麻痺を治療している患者さんが3人いる。彼らにすすめている筋トレを自分でもやらなくちゃ・・・と慌てふためいた。
予防のためにはストレッチが有効だけど、「踵でぐりぐり、足裏マッサージ」だけでは足りなかった。
それで、リカちゃんストレッチのムーブメント#7に、新しいバージョン=足指のストレッチを加えたのである。
(リカちゃんの足の指はくっついているので、イラストを作るのにえらく苦労をした)
足の指を動かすための大きな筋肉は、脛からつながっている。
それぞれ使われる筋肉が違う。 |
| ① |
 |
| 足背を上げる |
|
| ② |
 |
| 親指を上げる |
|
| ③ |
 |
| 四指を上げる |
|
| ↓ |
 |
⇔
交互に |
 |
| 上げ⇔下げ |
|
| 次に、足指を広げたり、縮めたり、伸ばしたり、曲げたり・・・ |
|
| ↓ |
 |
⇔
交互に |
 |
| 曲げる⇔伸ばす |
|
| 足首を曲げて脛を、伸ばしてふくらはぎを、同時にストレッチ |
|
|
| ついでに・・・ |
 |
 |
| 寄せる⇔広げる |
|
| 太ももの付け根~踵まで、ピシーッと伸ばして、いろんな筋肉をストレッチ |
| ↓ |
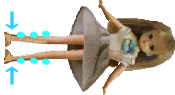 |
| 長腓骨筋(脛外側)、etc. |
|
| 交互に |
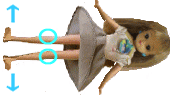 |
| 膝窩筋(膝裏)、etc. |
|
|
筋力も大切だけど、足と足指の筋肉に柔軟性があったら、ガングリオンはできなかったかもしれない。
足の指の器用さは、脳年齢にも関係しているとも言われている。
小さくなったとはいえ、私の足の裏にはまだ、プニュッと が2つあるのを感じる。 が2つあるのを感じる。
痛くもなんともないから、ついメンテナンスを忘れてしまうけど・・・やらなくちゃね~~
足の指を動かそうとして、指やら足底やらの筋肉がつりそうになったら、そこをカマヤミニで治療する。
自分でできるので、みなさんもやってみてね。 |