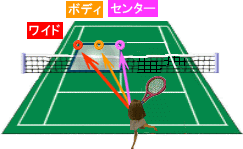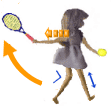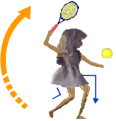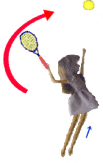みづ鍼灸室 by 未津良子(リョーコのブログ) みづ鍼灸室 by 未津良子(リョーコのブログ) |
|
|
|
|
| リョーコの手作りブログへようこそ! |
|
| 2024/9/7(土) |
|
|
迷走台風10号のせいで雨の日がつづき、先週木曜~日曜までテニスを休んだ。ポプラがいたので、ティラのお散歩もしなかった。草取りもやらず、通勤以外は外に出なかった。
エアコンの室内で仕事と家事の4日間を過ごしたのだけど、それって、ものすごく身体に悪いことだったのである。
月曜日にテニスに行ったら、身体が固まっていた。壁打ちだけではほぐれそうもないので、ダブルスで動いてほぐすことにした。
雨台風の置き土産、風速8mの強風が舞っていたので、風に乗ってボールが飛んだり、曲がったり、止まったりと予測不可能。思うように動けないので、最初は0行進がつづいた。
1セット目の後半からやっと動けるようになったのである。
年寄りの身体ってほんとに怖い。筋肉が縮もう、縮もうとしているみたいで、動かさずにいるとみるみる固まっていくんだね!
ティラのお散歩1時間は必須だね~~
その4日間にラストスパートをかけて、ふろく8<補聴器は早めがお得、「聞こえにくい」がつづくと脳機能が低下する>を更新した。
20年ぐらい前、オリヴァー・サックス博士の「火星の人類学者」(→本のコーナーで紹介)を読んだ。
その中の<「見えて」いても「見えない」>には、白内障の手術のあとで視力を回復したあと、うつ状態になってしまった男性のことが書かれてあった。
網膜も視神経も正常で、視覚検査では「見える」のに、見えているものが何なのかが分からない。「触る」ほうが理解できるのだ。
晴眼者の暮らしに適応するのは困難を極めた。家族に「盲人のような振る舞いは止めてほしい」と言われることもプレッシャーだった。。。
彼は混沌と混乱に追い込まれた。
盲人だった時代にはYMCAで働き、完璧に自立した人間だった。
「見える」ようになったあと、普通に仕事をこなすことができなくなって、退職せざるを得なくなった。
ついに身体にも変調をきたして、本物の「障害者」になってしまった。。。
大脳皮質の2分の1が視覚情報の処理に関連しているそうだ。盲人になると、脳細胞が改変されて、別の働きを担うようになる。
視覚は触覚に置き換えられ、指先で点字が読めるようになる。聴覚機能が向上し、ノートを取らずに記憶できるようになる。。。
晴眼者は目の前の光景を(奥行まで含めて)一瞬で認識できる。
盲人は触って認識する。しばらく歩くとスイッチが現れ、しばらく歩くと階段が現れる。「空間認知」が「時間」に置き換えられるのではないか?という推測もしている。。。
脳細胞の機能はフレキシブルで、損傷した細胞をカバーするのだ。
もしかしたら、聴覚も視覚と同じような現象が起こるのではないだろうか?
あまりに長い間「聞こえない」状態がつづくと、聴覚野の能力が衰退するのではないだろうか?という仮説を立てたのである。
ある患者さんのお姑さんがものすごく耳が遠くて、会話が難しくて困っていた。
より悪いほうの耳に高額な補聴器を買ってあげたけど、「ガーガーうるさいだけ」と使わなかったのだそうだ。
「聴覚能力がマシなほうに補聴器を使ってみたら?」とアドバイスしたんだけど、家族はさじを投げていた。
・・・そんな話が巷にはゴロゴロしているのである。
耳の遠い患者さんたちに、「聞こえるうちに補聴器を買った方がいい」とすすめたんだけど、みなさんに聞き流された。
耳の遠い人の多くはそもそも、「話をちゃんと聞こう」とか「相手を理解しよう」とか、そういうスタンスがないんじゃないか?と、そんな疑いを持ちはじめた。
もしかしたら、「話を聞かない」人間は、「聞かず」にいるうちに「聞く」機能が落ちていき、廃用性萎縮を起こすのではないだろうか?という仮説も立てたのである。
数年前に補聴器を買おうとした女性が、医師に「聴覚野の機能低下」について説明を受けたという話を聞いた。やっぱり!である。
脳の機能は局在している。分野に分かれて、それぞれが別の働きをしている。
聴覚野は聞こえてきた音を解析するが、聞こえた言葉を記憶する働きもしている。
しかも「音」を聞く能力と「言葉」を聞き取る能力は別物なのだそうだ。
「年寄り臭い」とか「値段が高い」とか、補聴器が敬遠される理由はいろいろあるけど、会話ができないと孤独になるし、認知症が進むという説もある。
まだ「聞こえている」うちに補聴器をつけた方が、「費用対効果」を考えると絶対にお得なのである。 |
|
|
|
|
|
| 2024/8/27(火) |
|
|
先週金曜日はシングルスのラウンドロビンだった。
試合前の2週間はシングルスをやる機会がなかったけど、ダブルスでの「マイ・サーブ」に取り組んだ。
結果はまあまあ。打てなくなるゲームもあったけど、ちゃんと打てるゲームもあった。
男性陣に励まされたおかげで、女ダブでも大丈夫になり、ちょっと精神力がついてきた感じである。
今回のテーマの一つ目は「マイ・サーブを打ちつづける」だった。
二つ目のテーマは「uno→dos→tres」である。
一発で決めようとしてミスする悪い癖を修正するために、スペイン語の「1、2、3」を合言葉にしようと思いついたのである。
1本目は「uno」と唱えて、まあまあ厳しいボールをコーナーに打つ。返ってくるボールを「dos」で打ち、次のボールを「tres」で打つ。1本で決めようと焦らずに、3本目のボールで仕留めるという作戦である。
真昼間にクラブに行ったとき、他に人がいなかったので、男性にシングルスラリーをしてもらった。フラットで打つ練習をして以来、ストロークのスピードと威力が向上していた。
短めのボールが来たら、「uno」でコーナーに打つ。やはり返ってくるが、厳しいボールの返球なので、1本目より易しいボールになる。「dos」でほとんど決められた。
「これなら勝てるよ!」とにこにこ、おおいに励ましてもらった。
シングルスでは前に出るのは「賭け」である。ベースラインでステイバックしていればほとんどのボールに対応できるけど、前に出るとオープンスペースが広がってしまう。
『返ってくるボールを取れなかったらどうしよう』という不安感から、慌てて打ってミスをしてしまう・・・というパターンだったのだ。
返球に対応できることが分かったので、試合で試してみようと楽しみにしていたんだけど・・・
今回のラウンドロビンは(暑いので)参加者は19人と少なく、4人ブロックが1つに、3人ブロックが3つだった。私は3人ブロックで、いつもなら8ゲーム先取だけど、熱中症対策で6ゲーム先取で行われた。
1戦目の相手はセオリー通りの戦い方をしていた。上手すぎて、「uno→dos→tres で決める」を試す機会がなく、あっという間に0-6で負けた。
2戦目の相手はミスを多発。すぐに自滅してくれるので、やっぱり試す機会がなく、6-0で勝った。
本部に報告に行って、コーチに「6先が2試合で物足りない」と言ったら、「そんなこと言うのみづさんだけですよ。みなさん暑さに参ってて、6先で良かったってホッとしてますよ」と言われた。
・・・たしかにリタイアする人が多かった。
ちょうど見学にやってきたクラブの男性に、「どうだった?」ときかれ、「6-0で勝ったけど、でも相手のミスだから」とボソボソ答えた。
「勝ったんだからすごいよ。2位になって賞品ももらえるし。今伸び盛りなんだからがんばって!」と、おおいに励ましてくれた。
まあいつも連敗よりも、人聞きがいいな・・・と思い直した。(笑)
2位トーナメントの初戦は強敵だった。出はじめた頃から知っている常連さんで、対戦のたびにいろいろアドバイスをしてくれる。
私の深いストロークを打ちにくそうにしていたけど、短くなったとたんに前進して来て、スパ~ンとコーナーに決められてしまう。途中のジュースをなんとか取って、1-4で負けた。
コートを出るときに「みづさん、すごいね!」と声をかけてくれた。
「ちょっとずつマシになってるでしょ」と言ったら、「ちょっとどころか、すごいよ。足も速いし」と言ってくれ、「気を抜くとやられそうだから、必死でやったんだよ~」と、思いっきり褒めてくれた。
クラブの人が出ていたので、彼女とあれこれお喋りして、一緒に決勝戦を見学することになった。
私の1戦目の相手のプレーを見て、彼女が「あの人省エネだね」と言う。なるほど突っ立ったままで適当に打っている感じなのだ。それでちゃんとコントロールしている。
彼女のほうが「見る力」がある。
自分の試合中は対戦相手のことを見ることもなく、ボールだけを見て翻弄された私だった。
「読みが速いよね」と彼女。たしかに2人とも、ボールの落下地点に入るのが速い。「自分の打ったボールを相手がどう返球してくるかを予測して、待ち構えているんでしょうね」と言う。なるほど。。。
1戦目の相手が準優勝で、優勝者は50歳ぐらいのジョッパー、全日本クラスの人だった。優勝者のほうがストロークに威力があった。
みなさんに褒められたので、やる気が出た。9月と10月と、2回分の申し込みをして帰ったんだよ。
対戦相手はどんなコーチよりもたくさんのことを教えてくれる。「やられて覚える」主義なのである。
次回は「押したと思ったら前に出る」にトライしてみたい。返球に備えてのスマッシュ練習をしなくちゃならない。
短いボールを走って追いかけてコーナーに打ち込む練習もしなくちゃならない。
やればやるほど課題が具体的になっていくのが嬉しいね。
「マイ・サーブ」をがんばったけど、セカンドになると当たり前のように打ち込まれるので、そのあとプレッシャーでダブルフォルトしてしまう。手がラケットに貼り付いてしまい、自由に振れなくなるのだ。
サーブの前に「力み」を抜く方法を発見し、ファーストが入れば「まあまあ」でも何とかなるという発見もした。
昨日サーブ練習をしたら、ジャンプを忘れていたことに気がついた。試合になると「入れなくちゃ」のプレッシャーで、突っ立ったままで打っていたのだ。
「低く構える」低さが足りなかったのも原因だ。
崩れたフォームを修正したあと、治療室で自分の治療をした。
鍼を打つと、テニスで酷使した筋肉が判明する。動作と筋肉の関連が分かるので、テニスは仕事にも役に立つんだよ~~ |
|
|
|
|
|
| 2024/8/21(水) |
|
|
数カ月前から、私の夜のワインのお供は警察犬、シェパードのレックスが大活躍するドラマである。ケーブルテレビの予告を見て、片っ端から録画予約をしておいたのだ。
最初に見たのは、1994年のオーストリアの「レックス~ウィーン警察 シェパード犬刑事」だ。
これが大ブレイクし、カナダ、イタリアでもリメイク版が作られたのだそうだ。
レックスのパートナーだった警察官が事件の捜査中に殉死した。
レックスは他の誰にも心を開かず、ご飯も食べず、水も飲まず、意気消沈したままだった。そのままだと殺処分されることになるという。
ところが殺人課の刑事モーザー(トビアス・モレッティ)には心を開き、久しぶりに生きる気力を取り戻したのだった。
モーザーがレックスを引き取ることになり、家に連れて帰り、一緒に出勤した。
警察内の反対を乗り越えて、レックスの活躍で様々な事件を解決することになったのである。
2019年、カナダでリメイクされたのが「ハドソン&レックス~セントジョン警察 シェパード犬刑事」である。
殺人課の刑事チャーリー・ハドソン(ジョン・リアドン)がレックスを引き取ることになったところからはじまる。
カナダの大自然が背景にあって、いろんな社会問題を題材にしながら、レックスが大活躍をする。
テンポが速くて、いろんな容疑者が次々現れ、最後にどんでん返しというパターンなので、酔っぱらって見終わったあと、「あれ、犯人は誰だっけ?」となったりする。(笑)
今見ているのは2008年にリメイクされたイタリアの「マルコ&レックス ローマ警察シェパード犬刑事」である。
殺人課の刑事マルコ・テルツァーニ(フランチェスコ・アルカ)がレックスのパートナーである。
筋肉ムキムキで型破りな刑事で、仲間もまた型破り。危ない目にあいまくりで、ハラハラドキドキのストーリー展開なのだ。
物語の中の警察犬レックスのあまりの利口さもすごいけど、演じているシェパードがすごいよね!
どのレックスもめちゃかわいくて、ニタニタ笑ったりハラハラしたり。テレビのレックスがワンワン吠えても、やっぱりティラはぜんぜん吠えない。いつも通りである。
自分の犬を撫でながら、テレビの中のレックスにも惚れ込んでいる私・・・なのだ。
超でっかいシェパードの活躍を見たあとは、ティラが小さすぎて頼りない感じがしてしまう。大人になっても赤ちゃんみたいなチワワが好きなんだけど、大型犬を好む人の気持ちがよく分かった。
ところで、すでに梅干しは出来上がっている。今年は紫蘇も入れたので、鮮やかな色になった。 |
|
 |
|
 |
|
紫蘇は干したあと、
ミキサーにかけて
「ゆかり」を作った。 |
|
|
1日目は炎天下、夜干しをして、2日目の午後にカメに戻した。
ベランダの手すりが陰になるので、もうちょっと干したかったけど、お天気不安定なのだもの。
小梅なので、それで充分と思う。
毎日が突然の雷雨なので、早めに干してよかったと胸を撫でおろしているところである。 |
|
|
|
|
|
| 2024/8/9(金) |
|
|
最近、5月のJOPの試合で知り合った男性(→2024/5/31)とシングルスをやるようになった。
シングルスらしいストロークをきっちり打ってくるし、足も速い。学生時代にやっていた人なので、引き出しが多い。ちょこちょこアドバイスをしてくれて、それがとても役に立つ。
ほとんど毎回やっているおかげで、だんだんシングルスに慣れてきた。
彼がミスで自滅してくれる以外、自分で取れるのは1ゲームぐらいなので、見放されないようにがんばっているんだよ~(笑)
サーブのフォームもだんだん安定してきた。
今年のサーブ「サーシャ」はアレクサンダー・ズベレフの愛称なので、名前を変えなくちゃならない。とりあえず「マイ・サーシャ」にしようかなとか思っていたとき、突然「マイ・サーブ」という言葉が浮かんだ。
そうだ、これこそ「マイ・サーブ」だ。練習を重ねて苦節10年。イントロからフォームを固めたら、バラツキがあった腕の振りが安定した。自分なりのフォームがやっと出来上がったのである。
インパクトに集中できるようになったので、「コースを狙う」課題に取り組むことにした。
①「マ」でラケットを回しはじめ、②「イ」でトスアップし、③「サー(ブ)」でインパクト、というパターンを考えたんだけど、インパクトのときに合言葉でコースを打ち分けたらどうだろう?と思いついた。
最近はずっと「ボディ」を狙って練習してきた。身体の正面は打ちにくいので、リターンエースされにくい。
「ワイド」は相手をコートの外に追い出せる。たまの「センター」はエースが取れることもある。 |
|
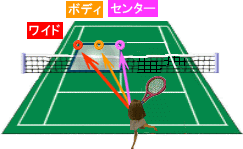 |
|
ときどきボールに黄色い「点」が見えることがあって、きっちりボディに飛んでいくことを発見していた。
フォームも変えず、トスも変えずに、コースを打ち分けるコツは、「点」を見つけることかもしれない?と思う。 |
|
| マイ・サーブ |
| コースをイメージ |
 |
| 低く構えてボールを突く |
|
| ↓ |
| マ |
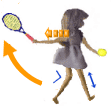 |
| 先にラケットを回す(弓を引く) |
|
→ |
| イ |
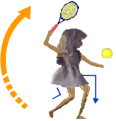 |
| 右足でステップインして、トスを上げる |
|
|
| ↓ |
| ボールの中の「点」を狙う |
 |
| さらに深く沈み込み、ラケットを振り上げる |
|
| ↓ |
| ボー or ワー or セー |
|
|
合言葉でコースを狙う
ボー=ボディ、ワー=ワイド、セー=センター |
|
|
|
|
水曜日はミックスダブルスを2つ。サーブはまあまあで(威力はともかく)ほとんど練習通りのフォームで打てた。
「ダブルスで崩れないフォーム」を目指していたので、気分は爽快だったんだけど・・・
木曜日はまず女ダブを2セット。ダブルフォルトは1回だけだったけど、終わったときにはフォームが崩れていた。そのあとのシングルスでは、まともなサーブが打てなくなってた。
しかも、1年ぶりにバックサイドに入れてもらったあと、ストロークが崩れていた。まともなラリーもできなくなっていたのである。
去年のシングルスでの失敗(→2023/7/15)から、ダブルスではフォアに入って、ベースラインからのクロス打ちに励んできた。
ペアが決めてくれる人だと勝てるけど、ストロークを打っているだけでは決定打がなく、「ノープラン」なのだ。
バックサイドに入れば別人格になってプレーができて、女ダブの勝率を上げられるかもしれないと思ったのである。
それは正解だったけど、シングルスで何もできず、ボロ負けしてしまった。
あたりはすっかり薄暗くなり、疲れ果てていたけれど、サーブ練習はしなくちゃならない。
「マ」と「イ」のタイミングが崩れていたことを発見。50球ぐらい打って、やっと「マイ・サーブ」を取り戻した。ホッ。。。
「シングルスとダブルスは全く別のスポーツと思った方がいい」と先輩に言われたことがあるんだけど、こんなにも違うのか!とあらためてびっくり仰天である。
2週間後にはラウンドロビンの試合があるので、「ダブルス適応」作戦はしばらくお蔵入りにするしかないね~~ |
|
|
|
|
|
| 2024/7/30(火) |
|
|
バイデンが大統領戦を撤退して、副大統領のカマラ・ハリスが民主党の大統領候補に指名された。
もしかしたら女性初の大統領が?と思った瞬間、ふいに心の底から高揚感が沸き起こってきた。
ちょうど当時の最高裁判事、ルース・ベイダー・ギンズバーグの伝記的映画を見ているときだったので、女性差別の歴史、自分が味わった屈辱の数々を思い起こしていたからだと思う。
(最近、WOWOWオンデマンドの映画を観ながら鍼を磨いている。
すでにストーリーを知っているものを選ぶと、画面に集中しなくてもいい。1本の映画を数日に分けて見ても、場面がつながってくれる。
もぐさを詰めるなど、退屈な単純作業のお供にちょうどいいのである)
ルース・ベイダー・ギンズバーグ(Ruth Bader Ginsburg=RBG)は1933年生まれで、うちの母と同年代。娘のジェーンは私と同じ1955年生まれだ。
戦勝国アメリカと敗戦国の日本が共に男性優位の社会で、女性の立場が似通っていたことに驚かされる。
映画「ビリーブ 未来への大逆転」の監督はミミ・レイダーで、1956年、ルース(フェリシティ・ジョーンズ)がハーバード大学の法科に入学したところからはじまる。
夫マーティン(アーミー・ハマー)は法科の2年生。2人で協力して家事と育児を分担し、生まれたばかりの娘を育てながら学業に励んだ。
男子学生500人中、女子はたったの9人だったそうだ。教授の質問にルースが高々と手を上げるんだけど、女性なので指名してもらえない。
(映画「ハリーポッター」で、授業中にハーマイオニーが高々と手を上げるシーンと重なって、ほんとうに感慨深い)
マーティンが精巣癌で闘病中のときは、ルースが彼の講義にも出席してノートを取った。2人分の授業を受けるという離れ業をこなしたのだ。
マーティンは病を克服して無事に卒業し、大手の法律事務所で税務関係の弁護士として働くようになった。
でも大学を首席で卒業したにもかかわらず、女性だからという理由で、ルースを雇ってくれる法律事務所は皆無だった。
大学で教えるようになったルースは、弁護士として仕事をしたいという夢を捨てきれないでいた。
そんなとき、母親の介護費用の控除を認められず、租税裁判所に訴えて敗訴した男性の案件に出会った。
控除の対象は女性と寡夫だけで、独身男性は対象外という法律だったのだ。
憲法では「平等」が明記されていたけど、様々の法律が「男は仕事、女は家庭」を前提に作られていた。
性差別の撤廃を願うルースは彼を訪ねて、無料で弁護を買って出た。
税法に卓越したマーティンが協力してくれ、共同弁護士として国税庁を訴えたのである。
国税庁側の弁護士は自信満々である。性差別はあって当然の「自然の法則」で、100年間も勝訴をつづけてきたのだ。
司法省から送られてきた膨大な趣意書には、性によって異なる法律が178も列挙されていた。
法廷は先例を重視する。しかも判事はマーティンにだけ話しかけて、ルースの意見を聴こうともしないのである。
敗訴は濃厚で絶体絶命と思われたとき、最後の最後、ルースが立ち上がり、時代の変化を訴えた。
これからを生きる子どもたちの将来への希望の芽を摘まないで欲しい。世の中はすでに変化している。法律が時代遅れになる前に、新しい先例を作ってほしい・・・
そしてまさかの大逆転を果たし、この勝訴が性差別撤廃への道を開いたのである。
ルースは1993年にクリントン大統領によって連邦最高裁判事に指名され、2020年に亡くなるまで27年間、リベラル派の法律家として性差別撤廃に取り組んだのだそうだ。
彼女の死後、トランプが保守派の判事を3人も任命し、中絶禁止など時代をさかのぼる裁定が相次いで、日本でも話題になったよね。
以前にマイケル・ムーア監督のドキュメンタリー映画「華氏119」を紹介したとき、言及しなかったシーンがある。 <ブログ→2022/1/8>
ヒラリー・クリントンが女性初の大統領になるはずと信じていた女性たちの集会で、期待を裏切られた大勢の女性たちが泣き崩れていた。
あのときは妙な違和感を感じ、不思議?と思ってスルーしてしまったのである。
子どもの頃から「女だからという理由で差別されない」ことを希求してきたけれど、挫折をくり返しているうちに、いつの間にか「あきらめ」とともに心の奥底に沈められていたのだろう。
年を重ねるにつれ、世の中の事について視野が広がっていく。あらゆることが複雑化していき、一刀両断に結論づけることが難しくなっていくことが起こるのだ。
「女」であるメリットもある。「可愛い女」を演じながら、男社会の中でそれなりに折り合いをつけてきたのがたいていの日本女性と思う。
キリスト教の影響下、アメリカは日本の数倍も保守的な国なのだ。だからこそ、ああやってひとつひとつ闘って、「女性の権利」を勝ち取らなければならないんだなあ。。。
今になってあのシーンを感慨深く思い出したのである。 |
|
|
|
|
|