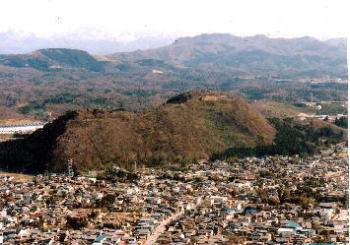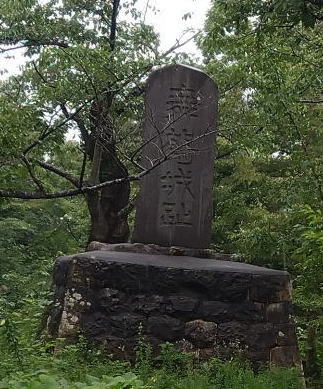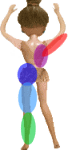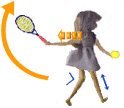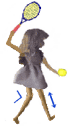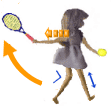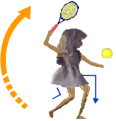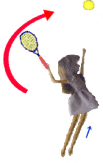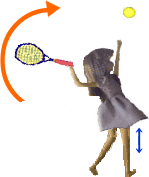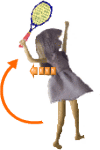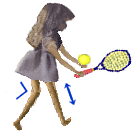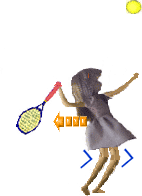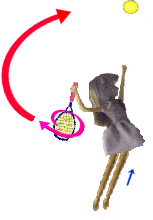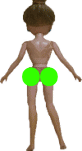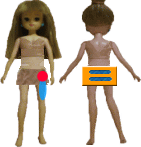|
去年の暮れぐらいから久しぶりの患者さんの来院が相次いだ。そのうちの何人かを紹介しよう。
ずっと苦手としていた年寄りの治療だけど、この頃はコツが分かってだいぶ上達したのである。
その過程で新しい発見をした。太ももの硬直は腰でん部の縮みと関連があるらしいのだ。 |
|
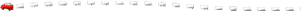 |
|
「ひざ痛2」で紹介した保育士さんのMさんは、年金暮らしになって来院を中止したあと、12年ぶり、80歳でやって来た。
腰でん部(●)は縮んで固まって、岩盤のようだった。
膝痛(●●)も悪化していて、とっくに正座ができなくなっていたとのこと。
右の坐骨神経痛(●)と診断されたそうだが、症状が軽い。でん部の深層の筋肉が硬直して神経を圧迫する「梨状筋症候群」と思った。たいてい1~3回で治る。 |
|
 |
| 80歳 |
|
|
でも年齢はあなどれない。軽減していったものの、「まったく痛みが出ない」日がつづくまで、週に1回の治療で2カ月かかった。
腰でん部(●)の盛り上がりがちょっとずつ薄くなっていったところで治療を終了した。
数年前から足が前に出にくくなって、歩くのが遅くなってしまったそうだ。
腰椎が縮むと仙骨が後方に突き出し、骨盤の筋肉が固まる。股関節の可動域が狭まって、足が前に出にくくなるのだ。 |
|
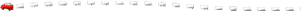 |
|
10年前に数回治療したことのあるKさん(78歳、女性)が「ダブルスで動けなくなった」と来院した。
うちの患者さんが走れているのを見て来たのだけど、「その年だと難しい。週に1回の治療で3カ月はかかる」と覚悟してもらった。
本人が感じる痛みは鼠径部(●)のみで、すぐに消えた。
全身が縮まっていて、とくに背中から骨盤(●)にかけて、盛り上がった硬直が岩盤のように固まっていた。 |
|
 |
| 78歳 |
|
|
トシなので「定量」の治療しかできない。それでも治療の翌日はでん部とハムストリングス( )が痛くて走れなくなる。翌々日には痛みが消えて動けるようになる。 )が痛くて走れなくなる。翌々日には痛みが消えて動けるようになる。
身体のどこかに不具合があると、筋肉が「ギプス化」する。患部を固めて痛みを眠らせるのだ。
硬直をほぐして痛みを掘り起こさないと深部まで治せない。Kさんに「どうする?」と尋ねた。
「動けるようになりたい」が目標だと、「痛みが出る」のは必須の過程なのだ。
Kさんは「なるほど」と納得してくれた。
Kさんが「仰向けの鍼が痛いのよね」と言うので驚いた。筋肉が硬直していると、鍼が細胞の間を分け入っていくときにズシンと響くのだ。
太もも(●)と脛の筋肉に深い鍼を打つのと打たないのでは治療効果に大きく差が出るので、飴をなめて耐えてもらった。
うつ伏せのほうがたくさん打っているのに、「そっちは痛くない」そうなので、不思議でならなかった。
めでたく3カ月後には「横に」動けるようになったそうだが、「後に動けないのよね」と言う。 |
|
|
|
|
後に動くためには左右のでん部(●)を別々に使えなければならない。
骨盤が一枚岩のように固まっているので、年齢的にそれは不可能に近いと思う。
同世代のテニス仲間とのダブルスでは、充分な動きができるようになって、「動けるとテニスが楽しい!」と、Kさんは大喜びしてくれた。 |
|
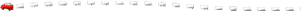 |
|
そのあと、「太もも(●)の鍼が痛いですね~」と、Kさんと同じことを言った患者さんがいた。
脊柱管狭窄症・2の「40代で発症、50代直前に再発して悪化」で紹介した男性である。
彼は現在60歳で、テニスや水泳を愛するスポーツマンである。
隔週でメンテナンスをしているけど、腰椎下方の硬直はまだ取り切れていない。 |
|
|
|
|
股関節の可動域が狭まって、それでも走ろうとすると、太ももの筋肉に過負荷がかかるのではないだろうか?
もしかしたら、太ももの硬直は、腰椎や骨盤が固まっているのが原因なのかもしれない?
腰痛持ちの患者さんには太ももが硬い人が多いのだけど、その理由が判明したのである。 |
|
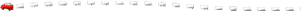 |
|
テニスクラブのNさん(現在73歳)はKさんの来院のきっかけになった女性である。
2013年にひざ痛の治療をしたあと、現在も支障なく走っている。(→「左膝痛で来院、右膝には昔の半月板損傷」で紹介)
コロナでしばらく中断したあと、背中から腰まで甲羅のようになっていて、ほぐすのに苦労している。
「草取りをすると腰が痛くなる」と言い、年中腰痛と格闘しているそうなのだ。
1年前から、左鼠径部(●)と太もも(●)の痛みに悩まされるようになった。
「テニスをすると悪化する」「ダッシュのあとで悪化する」とのことで、一進一退に手こずっているのである。
前回の治療時に、テニスのときは腰にテーピング( )をして、そのうえコルセット(●)もしているという話を聞いた。 )をして、そのうえコルセット(●)もしているという話を聞いた。 |
|
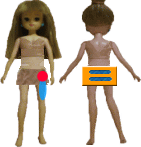 |
| 73歳 |
|
|
え~!と驚いた。
腰痛に効果のあるテーピングがないことは私が経験済みである。骨盤の筋肉は縦横に張り巡らされているからだ。
コルセットもご法度である。コルセットに支えられていると筋力が落ちてしまう。それぞれの筋肉の可動域が制限され、団子でしか働けなくなる。
「腰痛」があるだけマシなのだ。MさんもKさんも腰痛をまったく感じていなかった。
甲羅が薄れてきているのに、コルセットをしてテニスをするのはもったいない。それでは「完治」は望めない。
「テニスで動く」ことが治癒の秘訣なのである。
自分で自分の腰を後ろ手で治療するようになって、えらい苦労を重ねてきた。
壁打ちで快方に向かい、ラリーで快方に向かう。深部にある細かい筋肉までひとつひとつに鍼を打つことはできないので、「動く」ことが完治への道なのである。
ダブルスをやってまた快方に向かい、シングルスのあとで「治った」という経験もした。
走れるようになったからこそ、遠くのボールも取りに行く。
腰でん部を固めた状態でダッシュをするせいで、左鼠径部(●)と太もも(●)に過負荷がかかってしまうのである。
Nさんはぎっくり腰を恐れているけど、壊れたときが深部の硬直を治療するチャンスで、そのあとグーンと可動域が広がるのだ。
・・・というわけで、Nさんに新たな挑戦をお願いしたところである。 |
|