| 5/18(水) |
今年の「魔物」は右腕に取り憑いた |
毎年この時期、どこかしらの故障でテニスができなくなっていたので、早め早めに用心をしていたはずだった。
今シーズン2回目の温泉は箱根である。どうしても硫黄の温泉に行ってみたくて、るるぶで調べた。
調布駅まで来てくれたあんずを乗せて、中央道~圏央道~東名~箱根新道と、ひたすら高速道路を走った。便利になったね~。
家を出てすぐに調布インターにのれるので、それが一番楽なのである。
みんなに「箱根は混んでいた?」とか、あれこれ聞かれるのであるが、何も答えられない。
平日でしかも雨で、温泉に直行し、2時間入って、即、帰ってきたからである。
(夜は、あんずの友だちと3人で調布で飲んだので
...^-^)
箱根湯の花プリンスホテルは広大なゴルフコースの中にあって、露天風呂は、箱根で一番標高が高いんだって。
硫黄の匂いがプンプンして、白濁していて、景色が広々としていて、けっこう開放感がある。
内風呂は澄んでいたが、そっちのほうが比重が高そうだった。小雨のせいだったかもしれないね。
あんずも私も露天じゃないと息がつまるので、内湯には1分といられない。
う~ん、どうなんだろう?
硫黄の効果があった気もするし、いつも行っている相模湖の温泉と大差はなかった気もする。
リラックス効果が長距離運転で相殺されたかもしれない。
往復で約240キロ。道路はすいていて、片道1時間半だったけど、ガソリン代と高速代、プラス、入浴料は1700円とかなり高い。
ホテルのフロントで貴重品を預け、えんえんと通路を歩く。レストランもないし、落ち着けるスペースもない。
お泊りなら快適なんだろうけど。
でも、すでに「魔物」に取り憑かれていた私・・・
温泉の前日、どうも右腕全体が重いかんじで、患者さんの治療の合間に、自分で自分の腕にハリを打った。
あっちに打つと、次はこっち。はじめたら止まらなくなった。
腕が軽くなったかなあと思ったとたん、肘の内側(肘窩)の痛みが蘇った。
1ヶ月前のことである。
右肘をギュッと曲げたら、肘窩の奥にギクッと激しい痛みが走った。勢いよく折りたたむときに、ギクッと、いや~な痛みが走るのだ。
患部と思われる肘窩の奥にハリを打ってみたけど、いまいち手ごたえがない。
その痛みは2・3日で消えたんだけど、眠っていただけだった。。。
サーブのフォームを変えたのが原因だと思う。
結局は、フラット・サーブも却下。ファーストを気持ちよく打てても、セカンドの安定に苦労する。
やっぱり、「一気に完成形」を目指すしかない。
トスは少し前方に。ラケットはゆるく握って、野球のピッチャーの投球フォームをイメージして、ゆっくり腕を振って、ラケットをシュッと走らせて回転をかける。
今まで使っていなかった筋肉を使うことになって、腕のあちこちに、かなりの無理がかかっていたんだね。
ほとんど支障なくテニスができたつもりだったけど、不安感は日に日に増大し、テーピングの数がどんどん増えていった。
1~7の順で、青い○が「肘窩」である。 |
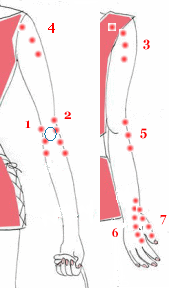 |
| テーピングが増えていく・・・ |
| 1 |
野球肘になりそう?肘の尺側に |
| 2 |
肘の内側の橈側。肘窩をはさんで、両側にテーピングをしたことになる |
| 3 |
肩の外側(上腕三頭筋) |
| 4 |
肩の内側(上腕二頭筋) |
| 5 |
テニス肘の古傷(短橈側手根伸筋)が心配 |
| 故障明けの練習でプラスしたのは・・・ |
| 6 |
人差し指の裏から前腕 |
| 7 |
母指の裏から前腕 |
|
結局、テニスは休むしかなくなり、とにかくハリを打ちつづけた。
どこかの筋肉にハリを打つと、『あ、楽になった?』と思う。でも、5分ぐらいで、肘窩のギクッが舞い戻る。
別の筋肉が気になる。いったんは楽になっても、また5分ぐらいで肘窩のギクッが舞い戻る。
首、肩、上腕、肘、前腕、手の甲から手の平にも。上から下まで、表も裏も、あらゆる筋肉に打つことになった。
肘をギュッと折り曲げる動作には、上腕と前腕のあらゆる筋肉が使われるということがわかった。
肘窩のギクッは、最後の警鐘だった。
応急処置とテーピングで、なんとか乗り切れちゃったことがアダになって、右肩から指を動かす筋肉まで、右腕全体がダメになってしまったのである。
とにかく、腕を使わない時間は1分もない。
仕事も、パソコンも、家事もする。使わないのは寝ているときだけ。
治療して腕が軽くなっても、腕を使うとすぐにズシンと重くなる。
テニス肘と同じく、女性の腕は治りにくいのである。
8日間テニスを休んで、その間は、まさにハリ・オタク。
故障明けで練習をしたときは、とりあえず、テーピングなしではじめてみた。
途中で、気になる筋肉に次々にテーピングをした。①~⑤はそれまでと同じところ。⑥と⑦は、新たな部位である。
(テーピングだけ見ると、まるでプロの選手の腕である)
2時間ぐらい練習したあと、ゲームを3セットやった。おっかなびっくりはじめたけど、動かしたことが功を奏して、終わったあとは、逆にかえって楽になった。
1日おいて、今日の午前中はいつもの練習会。
用心にしたテーピングは3本(①、②、④)だけ。でも、楽しく快適にテニスができたよ~!
とりあえず、右腕に取り憑いた「魔物」は、退散したみたいである。(笑) |
|
|
|
|
|
| 5/6(金) |
ストレッチに真向法を追加した |
症例集の更新をはじめたら止まらなくなった。
臨床医学というものは、治療をしながら「仮説」をたて、経験を積み重ねながら「定説」を導き出す作業でもある。
開業したての頃は、「自分を実験台にして」と言ってくれる患者さんがたくさんいた。今日の治療は、明日より良い治療をするための礎でもある。
患者さんたちは教師でもあって、よってたかって私を育ててくれた。
「疑問」や「仮説」や治療の「成果」をペンディングの箱に入れ、一定の再現性を発見したら、ラベルをつけて頭の中の棚に並べる。
新しい発見があると、棚から本を取り出して、新たなページを書き加える。
そうやって常に進化していくので、昔に書いたものは、どうしても未熟で言葉の足りないものになる。
時代とともに世の中も変化するしね。
そんなこんなで、気になっていたものを順次書き直している。
症例5:「いぼ・改」と、症例16:「水虫・改」の改訂版を更新した。読んでね~。
パソコンに向かう時間が長くなると、身体がロボット化していく・・・?
壁打ちなどで調整する時間がないときは、いきなりコートに立って、ゲームをはじめることもある。
そしたら・・・
腰のあたりがギシギシしている。股関節や肩関節など、あちこちが硬直している。
この間のぎっくり腰は、行っていきなりハードに打ったのが原因だったから、今はとても用心するようになった。
ストロークもゆっくりと。全力疾走は控え、無理なボールは取りに行かない。準備運動状態からスタートしないと、身体が壊れそう・・・
体操も準備運動も大嫌いだった私だけど、年齢とともに、そうは言っていられなくなった。
毎朝ストレッチをするようになって、丸6年が過ぎた。
80代の患者さんに触発されてストレッチを始めたのは、2009年の春ごろだった。
彼の体操は「真向法」といい、FAQ21:「ストレッチの効果は?」に、そのへんのいきさつが書かれてある。
犬の散歩中しか時間が取れなかったので、野川の河川敷のハシゴ段に足をかけ、立ったままでやれるストレッチを考え出した。
それが私の「360度ストレッチ」なのである。
ヴェルがいなくなってからは、食卓の上に座布団を重ねて、その上に片足をのせてやっている。
「朝ごはんの前」というのが決まりで、「ストレッチが終らないと、ご飯が食べられない」と、自分に縛りをかけている。
嫌いなことはそうでもしないと、なかなかやる気になれないものである。
この間のぎっくり腰のとき、360度はできたのに、両足をそろえての前傾姿勢での痛みがつづき、かなり苦戦をした。
片足ずつでのストレッチでは盲点があった、と思った。
それで、先週から、真向法をストレッチのメニューに加えている。すべて、床の上に坐っておこなう体操である。
| ① |
両足をまっすぐ投げ出して坐り、前屈して、おでこをくっつける。 |
| ② |
両足を広げて、床におでこをつける。 |
| ③ |
両足の裏をくっつけて、あぐらをかいた状態で、床におでこをつける。 |
| ④ |
正座(下腿を少し横にずらした状態)をして、仰向けに倒れる。 |
ゆっくり息を吐きながら、ゆっくり曲げていくんだって。④は気をつけないと危ないかも。私はそお~っと寝そべっている。
詳しくはネットで調べてね。
6年前に試したときと比べると、かなり柔らかくなっていた。おでこをつけられるようになるには、かなりの日にちがかかりそうだけど。
毎朝、ストレッチに30分ぐらいかける。時間をかけてやらないと、ほぐれなくなってきている。
去年までは、時間のない日は5分ぐらいではしょったりもしたんだけど、そうは行かなくなった。
(老化現象は確実にやってくる・・・)
患者さんの中には、年齢に見合わない柔らかい身体だな・・・と驚かされる人がたまにいる。
聞いてみると、何十年も毎日30分以上のストレッチを欠かさないでいる、と言う人ばかり。
ほんとうに治りが早いんだよ。
みなさんもトライしてみましょう! |
|
|
|
|
|
| 4/27(水) |
大好きなフラット・サーブで |
本年第2弾、症例50:「肋軟骨の障害」を更新した。2013年の今頃、自分が患った肋軟骨痛の話である。
毎年、この季節、なにかしら故障をしていた私。今年は無事に乗り切れるだろうか?「未病を治す」じゃないけれど、用心、用心。
そして第3弾、症例32:「傷、おでき、ヒョウ疸、褥痩、しもやけ・改」も更新。2005年に書いたものの改訂版である。
先々週の、症例49:「ぎっくり肋間筋(胸郭)」とあわせて読んでね~。
これからもしばらくは昔書いた症例集の手直しと、新しい症例の更新に取り組んでいくつもり。やっと「モノ書き」モードに突入できたみたい。
結局、Cさんにまたサーブを教わることになった。
改造は「自分なりに」と固く決心したはずではあったが、幼稚園から教わっているようなものだから、とても逆らえない。
自分のフォームを自分で把握できないのだから、できる人に見てもらうしかない。
教えてくれる人がいるのは、本当にありがたいことである。
一番の問題は、腕の振りの軌道が、毎回違ってしまうことである。
まるで、方向音痴の人が、毎回道に迷ってしまう現象と同じ?
人の顔は覚えられないけど、道は1回走ったら忘れない・・・というのが自慢だった私だけど、どうしてもたどり着けない友達の家がある。
八王子の小さな山の住宅街。2回目に行ったとき、入り口の信号の名称は「分からない」と言われ、さんざん道に迷って、そこら中を走り回った。
そのあと、もうお手上げになった。どの道もどの景色も、見覚えがあるのである。
方向音痴の友人が、「そうなの。どの道も見覚えがあるから、本当の道がどれなのか分からなくなっちゃうのよね」と話してくれた。
じゃ、私はサーブの方向音痴?
腕の軌道だけでなく、手首の角度もマチマチになってしまう。
言われたとおりに打てるときもあるのだけど、すぐに当たりがバラバラになる。
ジーッと見ていたCさんは、「できるようになりそうな『気配』もないな・・・」とつぶやいた。
「じゃ、フラットで打ってみて」と言われた。
フラットサーブは、私の大好きなサーブである。バッコ~ンと思いっきり打ち込むので、とても気持ちがいい。
野球の直球のようなもので、スピードがあるのだが、直線的に飛ぶので確率が低くなる。
はじめの半年はフラットの練習をした。まず「当たり」を覚え、次に「回転」を覚えるんだって。
(そのスライス回転で、2年半も苦戦している)
「フラットを打とう」と思うと、テイクバックのラケットの位置が、自動的に変わる。細かい注意事項を忘れて、勝手に腕が振られていく。
もしかしたら、それが私の身体に合ったサーブなのかもしれない?
人はそれぞれ骨格や筋力が違う。誰かと同じフォームで打とうと思っても、自分なりにしか打てないのかもしれない?
まだ仮説の段階ではあるが、その「フラット」が私にとっての自然な動きだとしたら、もう腕の振りに悩む必要はない。
軽くスライスがかかっているので、コートの中に落ちてくれるし。
軸足の安定はクリアーできた。肘も上がっているし、膝の屈伸も使えるし、腰の捻りも加えられる。
(注意事項が激減する・・・)
Cさんは、「手首のコックを気をつけないと、そのうち入らなくなるよ。スマッシュにも影響するし」と、まだまだ心配そうである。
「ピッチャーの投球フォームの練習をして、シャープにラケットを振れるように励め」と、あらたな課題もつきつけられた。
変えたばかりのフォームで、今日、いきなりのゲームデビュー。
優しいおばさまたちが、「上から打たないと練習にならないから」と、ダブルフォルトをおおらかに受け止めてくれた。
途中、アンダーに日和りたくなったこともあったけど、フォルトはしても、ぐちゃぐちゃにはならなかった。
しばらく、これでやってみよう。ファーストもセカンドも、とりあえず目指すのは「フラットスライス」サーブである。
実は、確実に入るセカンドをモノにしたら、ゆくゆくは大好きなフラットサーブをファーストにしようと、内心ず~っと考えていたんだ(笑) |
|
|
|
|
|
| 4/17(日) |
クラシック・バレエにヒントを得て |
サーブの改造に取り組んでから、もう3年である。
注意事項があまりに多いので、すべてを一度にやろうとすると、ぐちゃぐちゃになってしまう。
フォームを分解して、ひとつずつモノにしていこうと決めた私であった。
| ① |
腕の振りだけ覚える(上半身だけのサーブ) |
手首をコックしたまま、一定の軌道でラケットを振る。
腕だけでは力が足りないので、後ろ(右足)から前(左足)への体重移動でボールを飛ばす。力むと形が崩れるので、あえてポッコンに甘んじる。 |
ポッコンでも、かるく回転のかかったサーブが、ゲームでも安定して入るようになった。次の課題は、下から上への体重移動でサーブを飛ばすことである。
練習をはじめた私のコートへWさんがやってきた。2月頃、グッドタイミングでグッドアイデアをもたらしてくれた人である。
トスと同時に左の爪先を上げる癖を直そうと苦労していた私を見て、にっこり笑って、左足の上に自分のラケットを置いてくれたのだ。
「こうやると、左足を固定するしかなくなるでしょう。軸足が安定するんですよ」と教えてくれ、とても役に立ったのである。
私の試行錯誤を見ていたWさんは、
「スタンスを広くすると、後ろから前への動きになって。スタンスを狭くすると、ほら、下から上への動きになるんですよ」と、実演してみせてくれた。
質問したわけじゃないんだよ。見ていると課題が分かるのかなあ?驚きのグッドタイミング、アゲインである。
(テニスクラブは名コーチの宝庫なのだ)
練習の途中、「肘が下がっている」と、隣のコートからCさんに注意をされた。
自分では上げているつもりだったけど、いつの間にか悪いクセが戻っていたらしい。腕の振りもまだまだ修正が必要だった。
| ② |
体重移動は下から上へ(下半身のバネを使う) |
腕の振りは変えずに、左足軸足に体重をのせ、ちょっとひざを曲げる。
下から上への体重移動と同時に、下から上にラケットを振りあげる。 |
フォームの変更は、マイナーチェンジでも難しい。一度に2つも変更点を加えたので、またゲーム中にぐちゃぐちゃになった。
クラシック・バレエをやっている患者さんに、あれこれ聞いてもらった。
64歳の今も、週一のレッスンで、トゥ(=爪先立ち)で踊っているんだよ。バレエは片足1本で、立ったり、回ったりするんだもんね。もっと大変である。
「軸足の上に身体を乗せる、という感じなのよね」と、彼女は言う。
バレエは、肩を上げずに、腕を上げなきゃいけないんだって。やはり、つい肘が下がってしまって、とても難しいらしい。
「小指から上げるように意識すると、肘が上がるらしいのよ」と教えてくれた。
49歳でバレエをはじめた彼女は、54歳のときに、1年間足を引きずっていた状態で治療に来た。それ以来のおつきあいで、もう10年になる。
(→症例34:「坐骨神経痛に似た症状・2」に出演した女性である)
バレリーナになったつもりで、コートに立ってみた。WOWOWでロシアのマリインスキー・バレエを見たばかりなので、その気になっちゃって。。。
足も背筋もピンと伸ばす。美しいポーズをイメージする。
トスを上げたあと、左足軸足の上に身体を乗せて・・・あれ?左足の裏で地面のざらざらを感じる。コートに撒かれた砂を、足指を広げてつかむような感じ。
根っこが生えたような安定感がある。
軸足の上に乗ってサーブを打ってみたら、ぜんぜんグラグラしない。スピードがのっていい感じ?
しばらく、これでやっていこう。②をマスターしたら、次の段階に行こう。
| ③ |
腰の回転を使う(右半身のひねりを加える) |
| 左足に右足を寄せたとき、右腰を後方に少しひねって、「捻り戻し」を利用して、ボールによりパワーを与える。 |
「這えば立て、立てば歩めの親心」というか、Cさんは、「一気に完成形に」と言うけれど、今回は言うこと聞かないぞ~。
ゲームのときはサーブを入れなくちゃならないし、いったんぐちゃぐちゃになると、またしばらく大変なんだもの~~(笑) |
|
|
|
|
|
| 4/13(水) |
久しぶりの症例更新「ぎっくり肋間筋」 |
先週、仕事が早く終ったので、「じゃあ、ライトアップでも見るか」と、バイクで家に向かった。
今年は大橋も細田橋も通行止め。迂回させられた道は大渋滞で、かなり苦労して帰宅した。
遊歩道は見物人で大渋滞。それを自宅のベランダから見物できる私。
絶好の観客席をひとり占めで、ライトアップを上から見れる・・・のであるが、かなり淋しい。
こんなことなら誰か呼べばよかったなと毎年思うんだけど、そのためには家の掃除とか、準備が大変なのである。
ベランダでの見物はかなり寒いので、ジャケットやオーバーパンツを着込んだまま、部屋の中でストーブの横に坐って、とりあえずビールを飲んだ。 |
 |
野川の桜を見ると、どうしてもヴェルを思い出してしまう。
今となっては、犬のために毎日お散歩をする自分なんて想像もできない。考えるだけでも面倒である。他にやりたいことが山とあるんだもの。
でも、ヴェルのためなら、やったんだよね。7年間、毎日野川を歩いて、桜を見物した。
あ、ポロポロと涙が・・・
他の犬を飼う気にはなれない。いつまでたっても、I miss Vel... なのである。 |
 |
桜見物の翌日、またまたぎっくり腰になってしまった。
午前中の練習会に遅刻して行き、いきなりビシビシストロークを打ちはじめ、たったの20球打ったところで、ビシッ~と腰に稲妻が走った。
理由は・・・?
・・・腕の振りをマスターするために、何ヶ月も上半身だけのサーブを打っていた私だけど、さあ、次の段階に。下半身の使い方を教わって、サーブを打ちつづけていたら、腰を回転させる筋肉がキシキシ音を立てた。やばいな・・・と思った。
・・・私を治療してくれる友人がドタキャンのくり返しだった。
・・・ライトアップのとき、寒い中、変な格好でずっと坐っていた。
・・・そうとう疲れがたまっていたみたいである。だから遅刻したんだけど。最初から参加していれば、ミニラリーから、ミニボレストと、準備運動をかねてゆっくりスタートできたのに、いきなりフルスイングではじめたこと。。。
ぎっくり腰になって、すぐに仕事場に直行し、自分で治療をはじめたけど、恐れていたことが起こった。
腰とでん部の筋肉が、無数の筋繊維で編まれているカゴのようなものだと想像してちょうだい。
過負荷に耐えて、ぎしぎしにこり固まっていた「カゴ」。1本がピキッと壊れると、それまで持ちこたえていた他の筋肉にまで負荷がかかって、全体が崩れていく。
ぎっくり来たのは腰を回旋させる筋肉なのだけど、この間からときどき不具合をおこしていた腰の蝶番のほうに痛みが移っていった。
前傾姿勢がつらい。重いものを持ちあげられない。ずっと坐っていると、腰がずんずん重くなって、立ち上がったあとも痛みがつづく。
友人はやっぱり来てくれない・・・
それで、4日間も不安をかかえる羽目になった。
パソコンの前に坐っていると腰が悪化するのはわかっていたけど、時間があったので、久しぶりに症例集を更新した。
症例49:「ぎっくり肋間筋(胸郭)」である。
2015/10/4のブログ、「コンピューター・ハザード」のときから構想はあったんだけど、お喋りしていることを文章にするのはほんとうにしんどい。
考察が深まるのでいいんだけどね~
結局自分で治療して、月曜日からはテニスも仕事も家事も、普段どおりにできた。
よかった~~ (^0^)~~ |
|