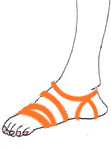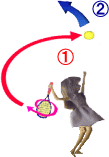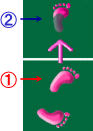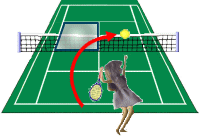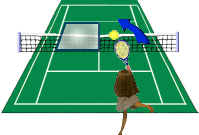みづ鍼灸室 by 未津良子(リョーコのブログ) みづ鍼灸室 by 未津良子(リョーコのブログ) |
|
|
|
|
| リョーコの手作りブログへようこそ! |
|
| 2022/12/29(木) |
|
|
本年最後の更新は症例58「虫刺され」だよ。蚊の話からはじまって、ダニ、プランクトン(チンクイ虫)、ブヨ、スズメバチ、ノミとつづき、ノミに刺されて「とびひ」になったときの治療法を紹介してある。
6月にティラのトリミングをしたときにノミを見つけた。(ティラのブログ→2022/5/29)
いつまでたっても刺される・・・と思っていたら、掻きむしったために「とびひ」という皮膚の感染症になっていたのである。 |
|
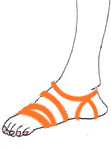 |
|
サンダルの紐のライン上に水泡やかさぶたができていて、痛くて歩けなくなってやっと気づいた。
必死でお灸をして、1ヶ月も格闘したんだよ。
先週ついにスマホに買い換えた。
前のガラケーは10年9ヶ月も使っていたとのこと。電池パックが劣化してきたので、いきなりクラッシュしたらパニックになる・・・と思い、やっと決心がついたのである。
買い物が苦手で大嫌いな私である。いつもあんずに付き合ってもらっていたんだけど、なかなか日程が合わない。
ちょうど「はじめてスマホプラン」のチラシが届いたので、それに決めれば迷わなくてすむと、自力でドコモに出かけていったのである。
機種を選んで、説明を聞いて、スマホケースを選び、保護シールを貼ってもらい、データーをコピー・・・と、3時間もかかって、頭がくらくらした。
何より恐ろしかったのが、電話番号の登録件数が693件もあったこと。「あ」からはじまる大昔の患者さんや、すでに亡くなった人の名前がずらりと並んでいたのである。
まるで過去帳をのぞき込んだみたいに、いろんなことが頭の中をぐるぐる回って、卒倒しそうになった。
とりあえず、使いやすいように電話帳の整理をした。新しいフォルダーをいくつか作って、最近おつきあいしている人をまとめたのである。いちいち過去帳をめくる必要がなくなって、ホッとした。
スマホの苦労話をはじめると、「そうなのよね~」と患者さんが共感してくれる。同じ苦労に同じドツボで、誰もが通る道なんだね~。
年末はとっても忙しい。去年の年末もパソコンが壊れて大変な思いをしたというのに、なんでまたこんな時にスマホに変えちゃったんだろう・・・
おおいに後悔したけど、毎日ちょこちょこいじったおかげで、ちょっとずつ慣れてきている。
自分のスマホサイトを自分で見れるようになったことはよかった。(笑)
残りは来年に持ち越して、ゆっくり取り組むことにした。
この頃は寒暖差が激しいので、寒さが身に応える。ブログには書かなかったけど、ゴルバチョフが「寒暖差がつらい。とくに磁気嵐がつらい」と言っていたんだよ。彼の言葉をちょくちょく思い出してしまう。
毎年のように、年末年始にぎっくり腰になった私。今年こそは無事に乗り越えたいものである。
みなさんも元気で、良いお年を! |
|
|
|
|
|
| 2022/12/20(火) |
|
|
日本中がワールドカップに熱中していたね。関心のない私はうんざりする思いだった。
日本が負けたあと興味を失った人もいたけど、ポプラはそのあとの試合も観戦していた。時間が重なるとチャンネル権を譲って、私は「モンテクリスト伯」を読みはじめる。サッカーは、バックグラウンドミュージックでしかなかったのである。
日曜日の夜中、決勝戦がはじまったら、本を取りに行くのも忘れて、そのままサッカーに熱中してしまった。
アルゼンチンの猛攻に魅入られてしまったのだ。メッシを本気で見たのははじめてだったけど、人の身体や足が林立するすき間に分け入って、人の何十倍も関節があるかのように、しなやかにすり抜けていく。
ここにもメッシ、あそこにもメッシと、そこら中に出没し、緩急つけたコントロールでゴールするのだもの。
フランスのエムバペも超人だね。
世界一の選手たちの中で、メッシとエムバペはまるで宇宙人のようにずば抜けていた。PKのレベルの高さにも驚いてしまった。
それに、メッシにはちょっとした思い入れがあった。2010年の秋にバルセロナのカンプノウでバルサVSマジョルカの試合を見たのである。
一緒に行った先輩が大のサッカーファンで、物見高い私は「おつきあい」だったんだけど、98000人の熱気に感動してしまった。(翌年5月にブログに書いた→2011/5/11)
その話をした友人に「メッシのゴールを見れたなんてすごい!」とめっちゃ羨ましがられたんだよ。
些細なことで羨ましがられるのって、気分がいいよね。
あんまり大きなことを自慢すると、相手が不快になったり妬みをかったりして、人間関係にヒビが入ることもあるから、ご用心を。。。
先週シングルスをやった相手はテニスやサッカーの観戦が大好きで、その話を興奮してしゃべりまくるおじさん。けっこうな自慢屋なので、たまには羨ましがらせてやろう・・・と思い、「バルセロナのカンプノウでメッシのゴールを見たんだよ」と自慢してみた。
彼は「え~!」と驚き、「どうせ昔の話なんでしょ」と言うのである。
「たしかに昔、10年ぐらい前のことだから」と答えたら、「10年前なんて昔じゃない。昨日と同じ」とかブツブツ言いながらウロウロして、ものすごく悔しがっていた。
自慢返し大成功、やったね!(笑)
日本人はみなさんアルゼンチンに味方していたみたい。
私もスペイン語圏の国には肩入れしている。テニスでもデルポトロ、ナルバンディアンとか大好きな選手がたくさんいた。
心臓ドキドキで、手に汗握ってアルゼンチンを応援した。途中で眠くなって死にかかったけど、最後まで観戦して、終わったあとも感動が冷めやらなかった。
元サッカー少年だったおじさんと話したんだけど、あんなすごい試合はめったに見られないとのことだった。
初観戦にして初感動とは、ほんとにラッキーだったね~~ |
|
|
|
|
|
| 2022/12/10(土) |
|
|
ホームページを自分で作るようになってから20年。治療をしながら発見したことを随時書いてきたんだけど、経験を積むにつれてどんどん考察が深まっていく。
治療をしては発見し、また治療をしてはまた発見しと、進化していくのが鍼灸治療なのである。
年齢と治り方には相関性があるらしい?ということに気づいたのは、開業して何年もたってからである。「負け」を認めたくないけれど、年齢に合わせた治療をしなければならなくなっていった。
以前にFAQ4「治り易い人と治りにくい人」を更新し、FAQ5「鍼灸を続けると身長が縮まらない?」を更新し、FAQ8「年を取ると効き目が遅く出る」を更新し、それらを2015年に補足事項を加えて改訂した。
重複する内容があるので、まとめて書き直そうかと思っていたんだけど、結局新しいページを作ることにした。
FAQ27「50代からの鍼灸治療」は、いつも治療室で患者さんに話していることをまとめたものである。
昔のページを書き直したい、新しい症例を加えたいと、頭の中にいろんな言葉がポンポン浮かんでくる。でも文書化するのは大変で、ものすご~く時間がかかるから、このペースがやっとである。
来年の2月2日に開業30周年を迎えるんだけど、その頃からの患者さんもいる。「形あるものは必ず壊れる」の諺どおり、患者さんたちが次第に老化していくのを見ることになった。
37歳だった私も67歳になり、自分自身の老化をひしひしと感じている。それでもあきらめたくないと悪戦苦闘しているのである。
「老化」に抵抗するアクティブライフを目指すのなら、ぜひ読んで参考にしてちょうだいね~~
マスコミが中国の「ゼロコロナ」政策のことを笑っていた。習近平の独裁体制が確立し、反対意見を言える人がいない。汚職撲滅キャンペーンで政敵をすべて牢屋にぶち込んだのだそうだ。自分の頭で考える人間をすべて排除してきた結果、自分の「意見」を持っている人は政府内にはひとりもいなくなったのだろう。
医療制度が脆弱で、患者の受け入れ態勢がないことも理由のひとつ、とも言って、中国を「後進国」と笑いものにしていた。
でも日本にだって「日本式ゼロコロナ政策」が存在している。
効果のないワクチンを宣伝することには熱心だけど、いまだにマスクも外せない。
人が集うときには感染対策を万全にして、消毒を徹底し、密にならないように少人数で・・・がつづいている。
医療制度も脆弱で中国を笑えない。発熱してもすぐに病院に行けず、「自分で判断」しなくちゃならない。
昔は赤ちゃんが鼻水を垂らしただけで心配になって病院に連れて行った。医者に「どうしました?」ときかれ、「風邪を引いたんです」と答えたら、「風邪かどうかは医師が判断することです」と怒られた。
それがなんだか、古き良き時代のように感じられてしまう。。。
コロナの直前、友人のだんなさんが死にかかって救急車を呼んだとき、受け入れ先の病院が見つかったのはなんと21軒目で、何時間も救急車の中で待機させられたそうだ。
コロナの前から日本の救急医療は絶滅危惧種になりはじめていたのだ。
7月からコロナを2類から5類に落としたほうがいい・・・という話が始まっているのに、いまだに実行されないのは、中国と同じく、自分の頭で考えて「意見」を言える人間がすでに一掃されているせいかもしれないね。
「日本式ゼロコロナ政策」の一番の被害者は子どもである。
教育現場ではいまだに子どもたちがワイワイ騒ぐことも規制され、体育や音楽や遊びにも制限がかかったままらしい。
子どもたちがかわいそうでたまらない。。。
病院や施設にいる高齢者たちも一番の被害者だ。
家族の面会も外出もままならず、集団リハビリも停止され、個室に隔離されているらしい。
うちの母は月に1回外食に連れ出したんだけど、どうやらそこでマイコプラズマに感染したらしく、一気にレベルダウンした。誤嚥性肺炎と誤診されたこともあって、半年ぐらいで亡くなってしまった。
でも私は後悔していない。身体という牢獄に6年半も閉じ込められ、辛い思いに耐えた母だけど、最後まで家族に会えて「希望」と「幸せ」を感じることができたのだもの。
物体のように生きながらえても、本人に取ってそれが幸せだろうか?家族に会えないまま死んでいくことのほうが、よっぽど辛いに違いない。
うちの母は私がリハビリをつづけなければ、あっという間に植物人間になっていたのである。
コロナの前に亡くなって本当に良かった・・・とつくづく思う毎日である。 |
|
|
|
|
|
| 2022/12/1(木) |
|
|
1991年に「ソビエト連邦」を解体したミハイル・ゴルバチョフは、2022年8月30日に91歳で死去した。ウクライナ侵攻の真っ只中である。
ドキュメンタリー映画「ゴルバチョフ 老政治家の”遺言”」は、2020年にラトビアとチェコの合作でつくられた。亡くなる2年前の姿を見ることのできる最後の貴重な作品となった。
映画は「ミハイル・ゴルバチョフは言った」からはじまる。「私でなければ誰が?今でなければいつ?」という彼の言葉が響いてきた。
どうやらソ連崩壊時のテレビ番組らしい。
・・・彼は祖国を改革し、世界をより良い場所へと変えました。グラスノチとペレストロイカ。政府を解散し、国に自由を招き入れました。「この人は歴史を永遠に変えた」と私が心から言える人物は・・・
そして、テレビの前でゴルバチョフが(老人らしく)うたたねをはじめた。
でもゴルバチョフは90歳にして頭脳明晰で、ユーモアのセンスのある愉快な人だった。
インタビューがはじまると、ゴルバチョフは「変人との対話、というタイトルにしたらどうかね」と笑っている。(野心を持たず、蓄財に興味を持たない人間は、この世界では「変人」扱いされるのだろう)
巨大な帝国ソビエトの大統領を退いたとき、ゴルバチョフの持っていた資産は、モスクワの小さなアパートだけだった。
1991年、ゴルバチョフがソビエト連邦の大統領を自ら退いたことで、連邦を形成していた各国に独立国家となるチャンスが与えられた。
その支配者たちが(死ぬまでという期限付きで)プレゼントしてくれたモスクワ郊外の大邸宅で、彼は使用人に見守られてひとりで暮らしていた。世界各国で行う講演や執筆で生活費を稼いでいた。
重病を患い、立ち上がるのも一苦労、歩行器を使ってヨタヨタと歩いていたけれど、ウォッカやビールを愛する、なかなかの美食家らしい。
家の中には20年前に亡くした妻、ライサ夫人の肖像画や写真がたくさん飾られてある。
| <奥様が亡くなったとき、言われましたね。「生きている意味がなくなった」と?> |
| そうだ。私たちは離れたことがない。いつも一緒だった。どうしてそんなことができたんだろう。尻に敷かれているとも言われたが、否定したことは一度もない。むしろそうありたかった。彼女への誉め言葉だから。 |
|
| <人生とはもっと高尚なものでは?> |
|
ひとりの女性を愛すること、愛されていると感じること、そして子どもを持つこと、それより高尚なものがあるかね?・・・「大勢の美しい女性たち、愛らしい名前」「ただ1人が私の眠りを妨げる」・・・もうすっかり忘れてしまったが、以前はたくさんの詩を覚えていた。 |
彼女を車に乗せてあちこちに出かけたそうだ。ゴルバチョフの語る詩とともに、ロシアの風景が映し出される。見渡す限りに広がる厳しい自然、そして春を待ち焦がれる心。ウクライナ民謡を唄うゴルバチョフの楽しそうな笑顔。・・・若き日は二度と戻らない・・・
ライサ夫人の母親はおそらくロシア人で、母方の祖父は処刑されている。父親のチタレンコはウクライナ人だった。
ゴルバチョフの父親はロシア人で母親はウクライナ人。母方の祖父は自分が創設したコルホーズの責任者だったそうだが、裁判にかけられて銃殺刑を宣告された。
あとから調べた地方検事補が「罪状に該当する違反は見当たらない」として釈放になった。1年2ヶ月の収監の間に祖父はさまざまな拷問をうけて、出てきたときには両手の骨を折られていた。
「原因は祖父のトロキズムだろうけど、なんであんなものを信じていたのか・・・」と笑った。いつも「スターリンは悪くない」と言っていたそうだ。
ゴルバチョフは10年生で共産党員になった。モスクワ国立大学の法学部に入学が決まり、家族に見送られて電車で出発するとき(銃殺刑を宣告された)祖父は泣いていたそうだ。
冒頭のインタビューに戻ろう。
| <ご自分を自由な人間だと?> |
|
何故なら、はっきりと自分の意見を言えるし、たくさん書き物もして、私の見方を率直に伝えている。 |
| <しかし、ロシア国内であなたの意見が誰の耳に届くのですか?> |
|
聞きたいと思えば誰でも聞ける。でもある新聞が私の寄稿文を拒否してきた。衝突したのはつい最近のことだが。
「ゴルバチョフの時代は終わった」のだそうだ。誰がそんなことを言ったのかね?まだ始まったばかりだ。すべての国家に機会と自由、そしてゆとりが与えられるべきだ。 |
| <自由はロシアに内在するものなのですか?民主主義は暴力なのでしょうか?> |
|
その質問の答えはどちらも同じだ。その通り。だがいつの時代も社会を変えようとする者はいた。 |
| <しかし、追放されたり絞首刑になったり国を追われたりしましたね。ロシアは自由ではない社会に当然のように戻っていきましたね?> |
|
その答えを出したのは私ではなく、この国の真の民主主義者だ。
心のうちに自由の火が燃え、誇りの声に導かれる限り、・・・「同志よ、ロシアに捧げよう。若く美しい我らの魂を」・・・そう考えてみなさい。
・・・「シベリアの鉱山の奥底でも、我らの誇りを守りなさい」「君たちの苦しみに満ちた労働と高い志は滅びはしない」「ロシアは長い眠りから覚め、専制政治の瓦礫の上に、我らの名前が刻まれる」・・・ |
| <民主主義はどこに?> |
|
何故私に聞く?
私は自分を社会主義者だと思っている。率直に言えば、今でもレーニンは神だと思っている。 |
|
| ウラジミール・レーニンは共産主義の世界的勝利を目指し、10月革命を敢行、ソビエト国家を確立した。 |
|
|
私が社会主義を破壊したと言う人もいるが、いいかね、社会主義はゆるぎない視点だ。人々が人生の新たな高みを見出し、自分自身を極めようとすればするほど、社会主義の必要性が高まる。これが当時の私の考えだ。 |
| <スターリンは社会主義者か?> |
|
私の高校の卒業論文のテーマは「スターリンは我らの闘いの栄光、青春と飛翔」で、最高の評価をもらった。私は優れた教育を受け、責任感をそなえていた。
だがその後、書記長になったとき、秘密にされていた資料の内容を詳しく調べ上げた。ひどいものだった。何十年にわたる処刑のリスト、100人、200人の単位だ。ぞっとするような記録だった。 |
|
| ヨシフ・スターリンは1000万人をこえる人々を銃殺、労働収容所送りにした。 |
|
|
人としても党としても、スターリンは社会主義者というより、独裁主義者だったのだろう。しかし今でも多くの人がスターリンを支持している。 |
| <この国に社会主義の指導者はいますか?> |
|
「私だ」と答え、「他には?」ときかれ、「いない」と答えた。「あれは傑作だった!」と書きなさい。(・・・と言いながら笑う)
一番大事なのが命だ。さらに大事なことは、その命がどのように扱い、扱われるのか、だ。 |
|
| <プーチンとの関係は?> |
|
あの日、「ロシアの日」は6月12日だったね?間違いないな?
赤の広場にテントが設営され、料理のテーブルが並んでいた。そこで2つのグループが会う。プーチンと私だ。プーチンに「ご無沙汰だったね」と言うと、「そんなことはない」と答えた。
「いや、君は私を避けている。君は3回私との会合をセッティングし、3回とも姿を現わさなかった」と言うと、プーチンは、人生は複雑なものだという説明をはじめた。
そのまま私たちはクレムリンへ。プーチンは料理のテーブルへ。私たちがすでに袂を分かっていたとわかるエピソードだ。
泣きはしないが・・・、私の気持ちを想像したまえ(と言いながら、こめかみに銃を当てるしぐさをくり返した) |
新年のお祝いは友人(?)の家に行った。小さなキッチンで乾杯して食事をする。テレビではプーチンが演説をしている。「愛」「プレゼント」「優しさ」「思いやり」「幸せ」「家庭」と、次から次へと美しい言葉がちりばめられ、「自由な祖国」を語るプーチン。
ゴルバチョフは「自由な祖国か・・・誰がその自由をもたらしたんだ?」とつぶやいていた。
映画の最後はライサ夫人のお墓参りである。「ここは予約済みだ」と隣のスペースを指さす。
たぶんそこにゴルバチョフは眠っているのだろう。
ゴルバチョフは西欧社会で高く評価され、ノーベル平和賞を送られた。かつてソ連邦だった独立国にとっても救い主だっただろう。
「オリバー・ストーンが語る、もうひとつのアメリカ史」では、自国の大統領の悪行を次から次へと暴き立て、こき下ろしていった監督が、ただひとりゴルバチョフだけを「偉大な政治家」と賞賛していた。
(以前にブログで紹介している→2016/7/24)
でもロシア人にとっては、ソ連邦の帝王から一国家へと貶めた張本人となる。プーチンはさぞかしゴルバチョフを憎んだことだろう。
「あの夢をもう一度」とばかりに、まず取り戻そうとしたのがウクライナである。ウクライナの悲惨さは言うまでもないが、プーチンの野望は世界中の人々を困難に陥れた。ロシア人は加害者であり、同時に被害者でもある。
ロシア人に疎まれたゴルバチョフはそれでもロシアを愛し、心の奥底に内在する変革の力を信じていたようだ。
ダライ・ラマのことも思い出した。彼はマルクスレーニン主義の本をたくさん読んで、宗教を否定することを除いて、かなりの部分に共感を覚えたそうだ。だが中国の毛沢東に会って失望した。彼のことを「マルクスレーニン主義の皮をかぶった中国大国主義者だ」と評していた。
私のロシアの知識といえばドストエフスキーやトルストイぐらい。社会主義も民主主義もよくわからないし、現代史にも疎い。何の力も持たないし、ずっと変人扱いされてきたけど、これだけは分かる。
小さな世界で愛し愛され、ゴルバチョフは幸せな人だった。その愛と幸せを世界中の人々にもたらしたいと願った。
野望のために殺人を行うプーチンのような輩とその協力者たちは、きっと孤独で不幸な淋しい人間なのだろう。。。 |
|
|
|
|
|
| 2022/11/23(水) |
|
|
テニスクラブの先輩、Cさんが教えてくれたサーブは、ボールの上方で回転をかける「トップスライス」である。同じトス、同じフォームでフラット、スライス、スピンを打ち分けられるそうだ。
私なりに分解して組み立てたのが「ラ、ディ」サーブ(→2021/11/16)で、ネットに対して横向きで構えるけれど、サーブを打つ方向は正面なのだ。 |
|
|
|
|
横向きのまま、左足を固定して打つと、左半身が邪魔になる。地面にくっつけたまま、左足先を正面に向けると、軸がぶれてしまう。
①→② インパクトの直前に身体の向きを変えるためにはジャンプが必須なのである。
左足でジャンプすると、空中で身体の向きを変えることができる。つまり「ラディ」は、「膝を曲げて、ジャンプ」がセットなのである。 |
|
| ① 構え |
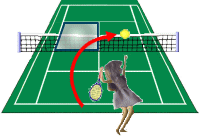 |
| 斜め横でラケットを振り上げる |
|
|
| ② インパクト |
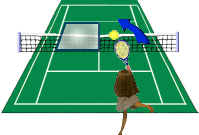 |
| 最後は正面を向いて終わる |
|
|
ダブルスではフォルトが怖くてずっと上半身だけでサーブを打っていた。
全身の運動連鎖で行うサーブは、微妙な狂いですべてバラバラになる。ジャンプを加えることは、清水の舞台から飛び降りるような勇気がいるのである。
でも「ジャンプ」を抜くなら「ラ、ディ」をあきらめるしかない。ここまでがんばってきて、別物のサーブに日和るなんてとんでもない。
ダブルスでも練習と同じサーブを打つしかない。打つことが筋トレになるし、精神力も鍛えられるかもしれない。。。
「ダブルスでラディ」と決心はしたものの、ゲームだけだとだんだん崩れていってしまう。やっぱり練習で修正する必要がある。
薄暗い中でひとりでサーブ練習をしていたら、4年前にトスのアドバイスをしてくれたHさんがコートでランニングをはじめた。(→2019/1/9)
彼はコロナで休会していたし、私もずっと練習をしなかったので、昔懐かしいシチュエーションだった。
「Cさんとかに教えてもらっているの?」ときかれたので、「注意事項がたくさんあると混乱するから、サーブに関してはそっとしておいてと、みなさんに言ってるの」と答えた。
細部を意識すると、各駅停車の電車みたいになって、インパクトのときには集中力が尽きている。。。
インパクト重視で力んでしまうと、ロボットみたいに硬くなって、バネをつかった伸びのあるサーブが打てなくなる。。。
インパクトの瞬間までは力を抜いてなくちゃならない。もう「ラ、ディ」で打つ気になれなくなっていた。新しい合言葉は?とずっと考えていたんだけど・・・
そうだ!カエルだ!と思いついた。
柳の下で身をかがめ、ジャンプして枝に飛びつく「カエル」をイメージしたらどうだろう?「カエル」ならぜんぜん力が入らないし、細部を忘れて「ジャンプ」だけに集中できる。
カエルをイメージしてサーブを打ったら、力が抜けてスムーズにラケットが振れるのである!
ランニングしているHさんが「遠目で見るとカッコいいよ」と声をかけてくれた。
スポーツに関する誉め言葉は(自信がないので)どうしても自分の中を素通りしていくんだけど、彼の言葉を信じることにした。
サーブの前にボールをつくとき、『カエル、カエル、カエル』と唱えつづけ、カエルのイメージをしっかり心に焼き付けてから打つ。。。
大発見だったね!合言葉が「カエル」では力みようがない。
男に混じってるときは気楽に打てる。男は狙ってミスもするしダブルフォルトもするから、私のミスに寛容でおおいに励ましてくれる。
女ダブではどうしてもペアの思惑が気になってしまう。だんだん緊張が高まると、途中で手の平が上を向いたままで打ってしまう。
ボールを下からこすり上げるサーブである。まあまあのスピードだし、球種が変わるので、たまだと有利に働くこともあるけど・・・目指すサーブとは違うし、つづけるとフォームが崩れてしまう。
『なんでこうなるんだろう?』と分析して、「手の平上向き」は「力んでいる」というサインだと気がついた。
スムーズに振れなくなって、落ちてくるトスに間に合わず、手首を返すプロネーションの時間がなくなった結果だったのだ。
「手の平上向き」が出たら、トスを上げて沈み込むときに「カ~エ~」と唱えることにした。気が抜けて、力が抜ける。
苦節十年でついにサーブへの不安が消えた。シングルスの試合ではペアがいないので伸び伸び打てる。今までもシングルスでサーブがレベルアップしてきたのである。
試合がものすごく楽しみになった。
先週金曜日のシングルスのラウンドロビンは19人が参加して、5つのブロックに分かれてリーグ戦をした。6ゲームマッチ(6-6タイブレーク)のノンアドで、私は4人ブロックだった。
初戦の相手(リーグ2位)は長身でフレンドリーな常連さんで、数年前に負けたことがある。
「攻め」ようとしてミスをしたので、初心者なんだから欲を出すのはやめようと思った。やっぱりシコラーになるしかない。
だんだんシングルスに慣れていった。2-6で負けたけど、若いベテラン相手に2ゲーム取れたから、上々の滑り出しと思った。
2戦目は相手(リーグ1位)に前に出られて打ち込まれ、1ポイントも取れないまま3ゲーム目に突入した。
なるほど、ストロークで「押せた」と思ったら、前に出て決めるという定石を、当たり前にできる相手なのである。(私も真似しようとしたけど、やっぱりまだまだ無理だった)
相手にとって打ちにくいボールを打ちつづけるしかない。だんだんポイントが取れるようになっていった。後半はまあまあになったけど、1-6で負けた。若いベテラン相手に1ゲーム取れたのだから良しとしよう。
3戦目はミスしてくれる相手(リーグ4位)だった。順当にポイントを重ねたんだけど、プレッシャ-との戦いになった。
勝ちを意識するとどうしても安全に行きたくなる。身体が縮もう、縮もうとしはじめた。こっちのボールの威力が減じると、相手を勢いづかせてしまうかもしれない。
いったんフォームが縮こまってしまうと、取り戻すのが大変になることはすでに経験済みである。ここで勝てても、次の試合でまともに戦えなくなる。
縮もうとする身体をこじ開けるようにして、なんとか振り抜いてがんばって、6-1で勝てた。
リーグ3位になった。3位トーナメントは4ゲーム先取である。
最初の相手が1-2になったところでリタイアした。右のでん部が痛いとのこと。「明日はミックスの試合だし、このあと練習会なんですよ~」と言うので、思わず「若いね~!」と叫んでしまった。
決勝の相手はストローク力はまあまあだけど、安定していて、ものすごく足が速かった。私のたまの決めボールにも楽々と追いついて返してくるので、えんえんとラリーがつづいた。
3-2でマッチポイントが来たんだけど、それを逃して、3-4で負けた。
とにかくシングルスが楽しくて楽しくてたまらなかった。
前衛がいないのでどこへでも自由に打てる。ミスしても「ごめんなさい」とあやまる必要もない。
コート中を駆け回ることが楽しくて、まだまだ「走れる」自分を再発見できたから超ハッピーである。
途中でコーチが「ジュニアみたいなフォームで打ってますね」と話している声がきこえてきて、ちゃんと打てていることを知って調子づいた。
走って追いついて、膝を曲げて地面を蹴って、思いっきり振り抜いて打つ。それを最後までやり通したんだよ。
2年前にできなかったことは、相変わらずできないままだった。
ダブルスでは相手コートが見え始めてきたんだけど、シングルスでは相手を見るどころじゃない。ひたすら打つだけで精一杯だった。
今度こそシングルスの練習をするぞ!とあらためて心に誓った。
2年前にできていたことはレベルアップしていた。ストローク力はアップしていたし、試合運びに頭を使うこともできた。
何よりサーブに自信が持てたのが快挙である。ちゃんと打てている自分に驚きながら、「不安がない」が、だんだん「自信」に変わっていった。
ファーストをフォルトしても、『これはもともとセカンドサーブなんだから』と自分に言い聞かせて、ずっと「カエル」を打ちつづけられた。ダブルフォルトはトータルで2回ぐらいだったと思う。
ラウンドロビンのあと、クラブの女子に混じってダブルスを1つやった。
ダブルス→シングルスはすぐに慣れるんだけど、シングルス→ダブルスにはぜんぜん対応できない。(サーブもボロボロになった)
終わったあと太ももの筋肉痛がはじまったので、そのまま温泉に直行した。マッサージをしながら45分間もがんばった。その日の疲れをリセットしたあと、残った不具合を治療しようという作戦なのだ。
翌朝になってもどこも壊れていなかった。4時間以上も走りまくり、打ちまくり、全身全霊でシングルスをしたのに、どこも壊さずにすんだのである。
まだまだこれからも挑戦できる身体ということがわかって、最高の気分なんだよ~~ |
|
|
|
|
|