|
症例57・ふくらはぎ4(地面をつかまえる筋肉)
|
|
|
前のめりになって足指で地面を握りしめる
|
|
|
|
|
|
ひざ痛のおかげで認知した筋肉
|
|
患者さんのふくらはぎなら、上から眺めて形を見て、指で押して圧痛点を探して、隅々まで治療ができます。去年6月に自分の右膝を故障したときは自分で自分の治療をしました。
大脳にはフォーカスの機能があるので、自分では一番痛い部位しか感知できません。その日気になる部位を治療すると、翌日には別の部位が悲鳴を上げる・・・という「追っかけっこ」の毎日でした。
テニスを控えめにして、パソコン仕事に熱中したのが運の尽きでした。この機会にと、「ひざ痛」のページを改訂する作業をはじめたのです。パソコンがふくらはぎにいかに悪影響を及ぼすかをまざまざと実体験しました。
足の裏側に手が届きにくく、はじめはおざなりの治療をしていました。ふくらはぎの硬直がだんだん悪化していき、どうしても膝痛が完治しません。
解剖学の筋肉の図を見ながら、仰向けになったり横向きになったりと工夫を重ね、ふくらはぎのあらゆる筋肉をひとつひとつ治療して、やっとひざ痛を治すことができました。<→その顛末は「ひざ痛2(変形性膝関節症)」にあります>
ふくらはぎを構成するすべての筋肉を紹介します。 |
|
|
ふくらはぎは7つの筋肉で構成されている
|
|
| 足関節の底屈(踵を上げる)をするふくらはぎの筋肉は7つです。みんなで協力して、「踵を上げる」「爪先立ちになる」「身体を支える」「地面を蹴る」「床を踏みしめる」などの運動をしています。 |
|
|
|
|
|
|
|
腓腹筋(■)はふくらはぎの大黒柱。膝の上から始まって、アキレス腱となって踵骨にくっついて、足関節の底屈をします。この筋肉だけは二関節筋なので、膝を曲げていると使えず、膝を伸ばした状態でのみ働きます。
ヒラメ筋(■)は膝の下から始まって、腓腹筋(■)と共にアキレス腱を形成して踵骨にくっつき、足関節の底屈をします。
両方を合わせて下腿三頭筋といいます。
→ 症例52:「ふくらはぎ(腓腹筋とヒラメ筋)」に詳細があります |
|
|
前傾になって、足指で地面をつかまえる
|
|
パソコン仕事でふくらはぎが硬直するのは、前のめりになってパソコンに熱中することが原因です。夢中になると自然に前傾姿勢になります。身体を支えるために、足の指まで緊張して地面をつかまえます。
猿は足の指で木の枝につかまることができます。人間の足はそこまで器用ではないけど、猿と同じ筋肉が指先までつながっています。
なにかに「集中」したり、「夢中」になったり、「緊張」したりするとき、無意識に足の指で地面をつかみ、握りしめるのです。(→2021/10/20) |
|
| パソコンに夢中になる |
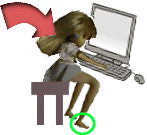 |
|
|
「夢中」になると、前のめり( )になって、無意識に足の指( )になって、無意識に足の指( )で地面を握りしめます。 )で地面を握りしめます。
足の指につながる長母指屈筋(■)と長指屈筋(■)を酷使します。
これが長時間つづくと、これらの筋肉が硬直し、他の筋肉に硬直が連鎖していきます。
長母指屈筋(■)と長指屈筋(■)が使われる動作は他にもあります。 |
|
| バイクで「突っ走る」 |
 |
|
|
バイクでスピードを上げるときは、自然に前傾になります。スクーターはタンクがないのでニーグリップ(両膝でタンクを抱え込む)ができません。
足の指でステップを握りしめ、身体のバランスを保つのです。 |
|
| ベッドでの治療 |
 |
|
|
| ベッドの上の患者さんを治療するときは、前傾姿勢です。足指で床を握りしめ、無意識にバランスを取っています。台所で料理をするときも同じです。 |
|
| シングルスで走る |
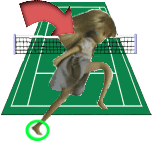 |
|
|
| シングルスではコートの全面をひとりで守らなければなりません。ダッシュをするときは前傾して、足指で地面をつかんで蹴るという連続運動をします。 |
|
|
長母指屈筋(母指の下へ)
|
|
長母指屈筋(■)は母指を屈曲する(親指を曲げる)筋肉ですが、「この屈曲動作をつづけると足関節底屈の補助をする」という働きもしています。
母指球で地面を蹴って踵を上げる(=足関節底屈)ときにも使われます。
腓骨からはじまって、内果の後を通って、母指の裏の付け根にくっついています。
膝痛の当初から、爪先立ちで地面を蹴るときに、足の母指から内果の下を通って、膝関節に違和感が伝わることに気づいていました。ストレッチで母指から足底の筋肉がつりそうになるのがサインでした。 |
|
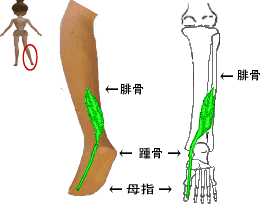 |
|
| 長母指屈筋 |
| 腓骨の後面の下2/3、骨間膜、隣接する筋間膜中隔と筋膜 |
| ↓ |
| (アキレス腱の下にもぐり、内果の後を通って) |
| ↓ |
| 母指の裏の付け根 |
|
|
| ふくらはぎの下方~足の母指~足底につながる長母指屈筋(■)を治療したら、硬直が消えてくれたのですが・・・ |
|
|
長指屈筋(4指の下へ)
|
|
やれやれと一安心したのも束の間で、翌朝、脛骨に沿って、内くるぶしから膝まで、ズシ~ンと重だるい不快な「冷え」で目が覚めました。膝痛の当初から「脛骨が痛む」症状がありました。
長指屈筋(■)は足の外側4本を屈曲する筋肉ですが、「この屈曲動作をつづけるときは足関節底屈が起こる」という働きもしています。
脛骨からはじまって、内果の後を通って、2指~5指までの4本の指の裏の付け根にくっついています。
長指屈筋(■)が硬直して、脛骨を裏側から引っぱっていたのです。 |
|
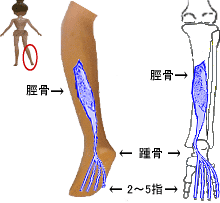 |
|
| 長指屈筋 |
| 脛骨中部3/5の後面、後脛骨筋(■)をおおう筋膜 |
| ↓ |
| (アキレス腱の下にもぐり、内果の後を通って) |
| ↓ |
| 4本の指の裏の付け根 |
|
|
| 脛骨の上にズラリとカマヤミニを並べてお灸をしたら、とりあえず不快な冷えと鈍痛は消えてくれました。 |
|
|
後脛骨筋(踵の下へ)
|
|
長指屈筋(■)は後脛骨筋(■)にもくっついています。症例54:「ふくらはぎ(後脛骨筋)」で、「テニスの試合でつる筋肉?」と紹介しています
後脛骨筋(■)は膝の下(脛骨と腓骨+いろいろな筋膜)からはじまって、足底と足指につながる骨のあちこちにくっついています。底屈(踵を上げる)だけでなく内反(足首を内側に曲げる)働きをしています。 |
|
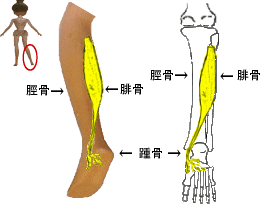 |
|
| 後脛骨筋 |
| 脛骨後面の外側、腓骨の内側面の上部、深横筋膜、隣接する筋間膜中隔、骨間膜の後面 |
| ↓ |
| (アキレス腱の下にもぐり、内果の後を通って) |
| ↓ |
| 舟状骨粗面、全楔状骨の底面、第2・3・4中足骨底の底面、立方骨、載距突起 |
|
|
|
足底筋、膝窩筋
|
|
足底筋(■)と膝窩筋(■)は大腿骨の外側上顆からはじまっています。どちらも足関節の底屈(踵を上げる)動作にはあまり関係がないようです。
足底筋(■)は下腿三頭筋(=腓腹筋(■)+ ヒラメ筋(■))の働きを助けるということですが、か弱い筋肉で、ない人もいるそうです。 |
|
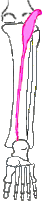 |
足底筋 |
|
|
| 下腿三頭筋の働きを助ける |
|
|
| 膝窩筋(■)は膝関節の屈曲と、屈曲のしはじめに脛骨を内旋する筋肉です。骨にべったりと付着しているので、鍼で効果があがらないときは透熱灸が有効です。 |
|
| 膝窩筋 |
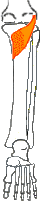 |
|
|
| 膝関節の屈曲、脛骨の内旋 |
|
|
|
(ふくらはぎの外側)長腓骨筋
|
|
| 「踵を上げる(=足関節底屈)」ための筋肉はふくらはぎ以外にも存在します。下腿の外側をまっすぐに走る長腓骨筋(■)です。下腿を外反すると同時に、足関節の屈曲を行います。 |
|
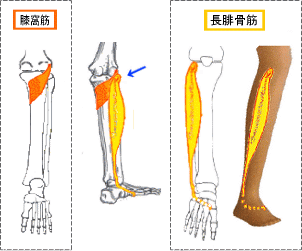 |
|
膝窩筋(■)は骨に張りついて膝裏で膝関節を支えています。長腓骨筋(■)は外側から膝関節を支えています。
2本は脛骨の外側(←)で交差していているので、仲良く並んで硬直するようです。
2年前、コロナ自粛で日本中が外出禁止になったとき、空いた時間にパソコン仕事に熱中したときは、この部位(←)から硬直がはじまりました。
<→膝窩筋(■)と長腓骨筋(■)のストレッチは、リョコちゃんストレッチ #27を参照してください> |
|
| ふくらはぎの治療は・・・ |
|
ふくらはぎの治療は腓腹筋(■)を中心に行います。全体をおおっているので、上から押して硬直部位を探せば、深部にある筋肉を同時に治療することができます。
筋肉は共同運動をしています。どこかの筋肉が硬直すると、連鎖反応がおこって、関連する筋肉に硬直が波及していきます。ついには筋肉同士が癒着して、骨に張りついて固まってしまいます。
硬直が激しいときは深部の筋肉は沈黙していますが、上をおおう筋肉がひとつひとつほぐれていくにつれ、深部の筋肉に手が届くようになります。
古くて頑固な硬直のときは、一枚ずつはがしていくような根気が必要です。
足の後面の筋肉は、おもに骨盤から始まって、膝関節にくっついています。 |
|
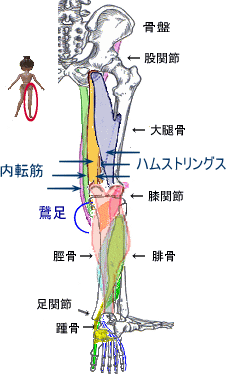 |
|
太ももの内側には「内転筋」があります。
薄筋(■)、縫工筋(■)と半腱様筋(■)の三筋が、膝関節の下、脛骨の内側で鵞足(○ガソク)となって癒合しています。
後面にある「ハムストリングス」のうち、半腱様筋(■)と半膜様筋(■)は、内側の脛骨にくっついています。
大腿二頭筋(■)だけが脛骨の外側にくっついています。
つまり、膝の内側には太ももの筋肉のほとんどが密集しているのです。
ここに腓腹筋(■)の内側頭がくっついて、太ももの筋肉と上下で交差しています。 |
|
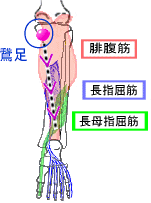 |
|
長母指屈筋(■)と長指屈筋(■)を酷使すると、硬直がすすんで、骨に張り付いて固まってしまいます。
共同運動をしている他の筋肉たちに過負荷がかかって、一緒に硬直し、みんなで固まって癒着してしまいます。
太ももの筋肉と腓腹筋(■)の内側頭に硬直の連鎖反応がおこり、硬くなって縮んで上下で膝関節を引っぱります。
それが変形性膝関節症を引き起こすのです。
腓腹筋(■)は大腿骨の上から始まって踵骨にくっつく二関節筋です。膝を曲げていると働くことができないので、しっかりと膝を伸ばして動きましょう。
歩いたり走ったりジャンプしたりと、腓腹筋(■)が収縮をくり返すと、下にある他の筋肉たちが、楽をして動くことができます。収縮すると「筋ポンプ作用」で、筋肉内部の血流が促進され、ほぐれてくれるのです。 |
| <→歩くときは「リョコちゃんウォーク」がおすすめです> |
|
 ふくらはぎの筋肉(表) ふくらはぎの筋肉(表) |
|
| 上述した筋肉を表にしました。 |
|
|
|
|
|
筋肉 |
起始 |
停止 |
支配神経 |
作用 |
| 下腿三頭筋 |
| ■ |
腓腹筋 |
内側頭 |
大腿骨内側上顆 |
両頭は合わせてアキレス腱をつくり、踵骨隆起へ |
脛骨神経 |
足の底屈 |
| 外側頭 |
大腿骨外側上顆 |
| ■ |
ヒラメ筋 |
|
腓骨頭、ヒラメ筋線(脛骨) |
|
|
|
|
|
|
|
筋肉 |
起始 |
停止 |
支配神経 |
作用 |
| ■ |
後脛骨筋 |
下腿骨間膜の後面 |
舟状骨、内側楔状骨 |
脛骨神経 |
足を底屈し、かつ内反する |
| ■ |
長母指屈筋 |
腓骨体下部後面 |
第2~5指末節骨底 |
母指の屈曲、足の底屈 |
| ■ |
長指屈筋 |
脛骨中央後面 |
母指末節骨底 |
足指の屈曲、足指の底屈 |
| ■ |
足底筋 |
大腿骨外側上顆 |
踵骨腱の内側縁に融合 |
下腿三頭筋の働きを助ける |
| ■ |
膝窩筋 |
大腿骨外側上顆 |
脛骨上部後面 |
膝関節の屈曲、脛骨の内旋 |
| <下腿外側の筋肉> |
| ■ |
長腓骨筋 |
腓骨頭、腓骨体上部外側面 |
第1楔状骨の外側、第1中足骨底 |
浅腓骨神経 |
足を外反し、かつ底屈する |
|
短腓骨筋 |
腓骨体下部外側面 |
第5中足骨底の外側 |
|
|
|
| Updated: 2022/10/23 |