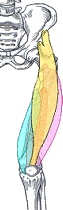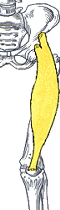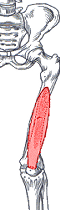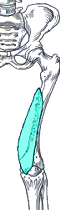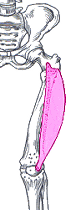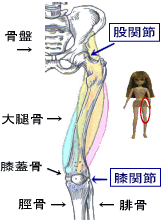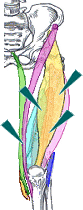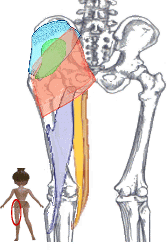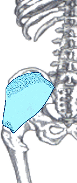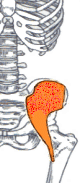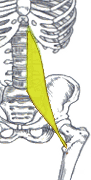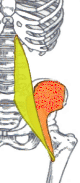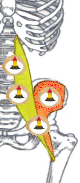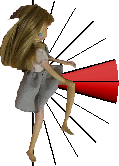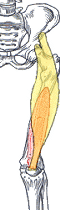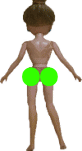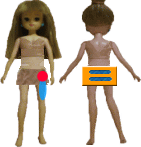| みづ鍼灸室 by 未津良子(症例集) | ||
| 症例64・太ももと鼠径部(股関節)の痛み |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
症例64・太ももと鼠径部(股関節)の痛み
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
大腿四頭筋と腸腰筋、でん部、ハムストリングス
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ダッシュをくり返して右太ももを痛めたとき
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 週に1回のスクール生時代をのぞくと、私が毎日のようにテニスクラブに通うようになったのは2011年の夏頃で、56歳のときでした。 筋力がほぼない状態で全力疾走をくり返すようになって、まず最初に苦労したのは右太ももの痛みでした。 太ももを持ち上げてダッシュすると、大腿直筋(■)を酷使します。 テニスのあとは右太ももが痛くて、パンパンになっています。家に帰ったらまずお灸、それからビールという日々がつづきました。 痛みのある部位は筋肉が硬直しているので、指で押して圧痛点を探します。直後ににカマヤミニでお灸をすると、腫れと痛みが引いてくれました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 隔週で友人に全身治療をしてもらっていたおかげもあったかもしれませんが、応急処置のカマヤミニでも絶大な効果がありました。 温めると血流が促されるので、ちょっとした不具合は「血」が治してくれるのです。 ときには自分で鍼も打ちましたが、全力でのダッシュをつづけることができました。 数か月後には古傷が癒えて、太ももはかなり頑丈になりました。 「壊す→治療する→再生する」をくり返して筋力がアップしていくのです。 右の大腿直筋(■)には肉離れの古傷がありました。 高校時代にバスケの合宿で肉離れを起こし、32歳のときにバレーとバドミントンとバスケに励んで同じ部位にまた肉離れを起こしました。 鍼灸治療と縁のない時代だったので、筋肉に傷跡(=瘢痕治癒)が残っていたのです。「ほころび」があると周囲の筋繊維に過負荷がかかります。 肉離れを経験した患者さんを何人も治療しましたが、みなさん筋肉に「しこり」が残っていました。放っておくと同じところを壊してしまいます。 時間はかかりますが、鍼灸で古傷の治療をすることができます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
太もも前面をおおう大腿四頭筋
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 私のテニス街道の最初のハードルだった大腿直筋(■)は、他の3つの筋肉と一緒に大腿四頭筋( 下肢における最大の筋で、太ももの前面で大きくふくらんでいる、直立歩行に必要な筋肉です。「坐位から立ち上がる」「階段をのぼる」「ダッシュする」「ボールを蹴る」ときに強く収縮します。 全体としては強力な下腿の伸筋で、椅子に坐って「下腿を持ち上げる」(=膝関節伸展)」ときにも使います。(鍛えると膝痛の予防になります) イラストは私が教科書からスキャンして組み合わせたものなので、おおよその位置です。 <左半身を例に。濃い( |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 太ももの前面中央の大腿直筋(■)だけは骨盤からはじまる二関節筋で、股関節の屈曲と膝関節の伸展を行います。 おおいに頼りになる筋ですが、酷使されるので痛めやすく、アスリートにとってはもろ刃の剣になります。 4本の筋肉は膝蓋骨(お皿)の下にもぐり込み、膝蓋靭帯(■)を介して脛骨にくっついています。付着部である脛骨結節は、ひざの下にある骨のでっぱりで、大腿四頭筋を鍛えるほどに発達して大きくなります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
太もものメンテナンスは
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 太ももには前面にある大腿四頭筋の他、大腿と膝関節を両サイドで支えている筋肉があります。 太ももの内側の内転筋は骨盤から始まっています。 薄筋(■)、縫工筋(■)と半腱様筋(■)の三筋は、膝関節の内側を通り、腱が融合して鵞足(○ガソク)を形成して脛骨にくっついています。 ひとつの筋肉を痛めただけでも、みんなでそろって硬直します。こじらせると治しにくいので、要注意です。 <→症例33「ひざ痛1」「ひざ痛2」に詳細があります> |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大腿をおおう大腿筋膜が外側面でとくに肥厚して腸脛靭帯(■)となっています。 骨盤の腸骨稜から下に向かって垂直に走り、脛骨の外側顆にくっついている帯状の強力な靭帯です。 骨盤からはじまる大殿筋(■)と大腿筋膜張筋(■)が腸脛靭帯(■)を緊張させます。 膝関節が伸び、下肢は伸展位で固定、体幹の直立位が維持されます。このとき大腿四頭筋( |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 太ももを治療するときは、すべての筋肉に注意を払いましょう。 メンテナンスの鍼は複数の筋肉が重なっている部位が効率的ですが、基本的には硬直部位と圧痛点を探します。 筋肉に深い鍼( |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ハムストリングス付着部、坐骨結節でバキッ!
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017年2月に長年私の治療をしてくれたSさんがリタイアしました。他の鍼灸師を見つけるまで・・・と、ストレッチをしながら、自分で自分の治療をするようになりました。 6年後にはかなり上達しましたが、はじめは後に手が届かずに苦闘の日々がつづきました。 ストレッチに真向法を加えたのが2016年5月、開脚では頭が床まで10センチでした。 苦節3年、2019年2月には床にキスできるまで可動域が広がったのです。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可動域が広がるにつれ筋肉バランスが変化します。 それまで使っていなかった筋肉が使えるようになるので、筋力がつくまでは要注意なのです。 2019年5月31日、シングルスのラウンドロビンの朝、時間に追われてやったのが失敗の元でした。 開脚でいきなり前屈をしたとたん、左の「坐骨結節」の外側がバキッとなりました。 とくに痛みもないので試合に出かけ、シングルスを6試合、5時間走っても問題なしでした。 でも日に日に違和感が増していきました。 2週間後、開脚の前屈で、前回と左右対称の同じ部位、右の「坐骨結節」の外側がバキッとなりました。 坐骨結節から出ている筋肉の腱の癒着が剥がれた音だったらしく、開脚の前屈で苦労するようになりました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 骨盤の「坐骨結節」は腰かけるときに椅子に当たる骨のでっぱりです。 ハムストリングスと呼ばれる3本の筋肉がくっついて、大腿骨を後に上げる働きをしているので、走るときに酷使されます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1週間後:でん部に痛みが移動した
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 坐骨結節の「ほころび」を抱えたまま全力疾走をつづけていたら、でん部の筋肉が痛みはじめました。 骨盤から股関節につながる筋肉は他にもたくさんあるのですが、走るときにとくに酷使される筋肉を紹介します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上述の大殿筋(■)は一番外にあって、でん部をおおう大きな筋肉です。 地面を蹴って走る(=大腿骨を伸展する)ときの主力筋で、立ち上がるときや階段を昇るときにも働きます。 その下にある中殿筋(■)と、その下にある小殿筋(■)は、反対の足を上げるときに骨盤を傾けて固定します。 おかげでスムーズに左右交互に足を運ぶことができます。 大殿筋(■)は表面にあるせいか、治療で手こずった記憶はありませんが、骨への付着部分が多い中殿筋(■)の治療は大変です。 ちなみにマラソンはハムストリングスとでん部の筋肉だけで走るので、ここを痛めるマラソンランナーが多いのです。 骨盤内部には共同運動をしている他の筋肉があります。 連動して硬直するので、こじらせたときは深部の細かい筋肉の治療もしなくてはなりません。 <症例41「マラソン;坐骨結節~ハムの痛み」> |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
鼠径部(股関節前方)と太ももに痛みが移動
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必死で治療をし、ストレッチとリョコちゃんウォークをがんばって、2週間ほどででん部の痛みがやわらいだのですが、今度は股関節の前方に痛みが波及してしまいました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| でん部にある中殿筋(■)は、骨盤の外側に貼り付いています。骨盤の内側には腸骨筋(■)が貼り付いています。 裏表で骨盤を支えているので、硬直の連鎖反応が起こりやすいのです。 ここのぎっくり腰にはほんとうに苦労させられました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 骨盤の内側からはじまる腸骨筋(■)と、背骨の内側からはじまる大腰筋(■)は、鼠径靭帯の下を通って、共通の腱をつくって大腿骨にくっついていいます。 合わせて腸腰筋となって一緒に働きます。 「疲労しやすく、治りにくい」筋肉だそうです。後方は背骨と骨盤、前方は内臓ではさまれているので、体表から触れることはできません。 歩きはじめに腸腰筋(■+■)が大腿骨を持ち上げたあと、大腿直筋(■)が主役になってさらに高く持ち上げます。 連動して働くので、硬直の連鎖がおこりやすいのです。 犬の散歩では、はじめは痛みで左足が出にくく、痛みをこらえて(正しく)歩いているうちに、だんだん痛みが引いていきました。 立ったままで靴下をはくときに、左足が上げにくくなりました。 それでもダッシュをくり返していたら、大腿直筋(■)に不具合が波及しました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
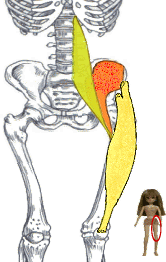 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 腸腰筋(■+■)は、後方は背骨と骨盤、前方は内臓ではさまれているので、鍼を打てる場所は限られています。 ① お腹の上から透熱灸をすると、深部まで熱を伝えることができます。女性特有の「冷え」からくる腰痛にも効果的です。 ② 鼠径部の痛みを伴います。深部にある股関節に向けて、筋肉の通り道を狙います。大腿直筋と合わせて深い鍼を打ちます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
太もも痛は中間広筋への透熱灸で完治
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 坐骨結節のバキッから1カ月後、7月5日はシングルスのラウンドロビンがありました。 6試合やったのですが、途中から左太ももの筋肉痛がはじまり、激しい痛みでついに走れなくなりました。 <ブログ→2019/7/10> 左足を持ち上げるとき、途中までは問題がないのですが、90度前後の角度( 大腿四頭筋( |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 靴下を履くときに足を持ち上げると痛む、バイクのステップに左足をのせるときに痛むという状態で、足を組むときは、太ももを手で持ち上げていました。 日常生活では痛まなくなって、「治った」と思っても、テニスをするとまた痛みがぶり返します。必死で鍼を打ったのですが、どうしても全力疾走に耐えられないのです。 もしかしたら壊れたのは、奥にある中間広筋(■)かもしれないと思いました。 大腿直筋(■)の奥に隠れている筋肉です。 大腿骨に付着しているので、鍼がすぐ骨に当たってしまいます。 骨との付着部を治療するのは、「点」で打つ鍼よりも透熱灸が効果的です。 「面」で治療できますし、深部に熱を伝えることもできます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テニスの試合を見ながら、えんえんと透熱灸をしたら、痛みがやわらいで、筋肉に弾力が戻った感じでした。 太ももにはお灸の痕が点々と残りましたが、中身が治れば痕はきれいに消えます。 数日後には太ももを持ち上げても痛みが出なくなりました。そろそろ「動いて治す」時期です。 ストレッチだけでは、いくら念入りにやっても、身体のあちこちがなんとなくギシギシするのです。 太ももにテーピングをしてテニスを再開し、1週間後には完治してくれました。 <ブログ→2019/7/20)> 腰でん部への鍼は後ろ手で打つので「当てずっぽう」になります。脳にはフォーカスの機能があって、自分では一番痛いところしか治療できません。 「治った」と思い込み、でん部の硬直を残したままで全力疾走をくり返したせいで、太ももの筋肉を痛めてしまったのでした。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
腰でん部が縮むと太ももが硬直する
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ここから先は今年のブログ<→2024/6/12>を転載したものです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||