|
| 2025/2/24(月) |
 左膝の不具合はシングルスの試合で完治 左膝の不具合はシングルスの試合で完治 |
|
冬場は横と裏側の植込みの草取りをしているんだよ。
横のはサービスコートぐらいの広さの三角形。木がたくさん植えてあるんだけど、葉っぱが落ちて日当たり良好である。
そこから裏側に幅2メートルぐらいの植込みが数十メートルもつながっていて、太陽さんさん、草がニョキニョキ生えている。
去年の春に草取りをはじめたとき、管轄外と放っておいたら、ものすごい密林になってしまった。秋に都の業者があらかた刈ってくれたんだけど、草刈り機では根っこのほうが残ってしまう。
あまりにも草ぼうぼうだと、草むらに入る勇気も出ない。伸びる前に根っこを刈れば、密林にならずにすむかもしれない?と思ったのである。
深く張った根っこから刈るとなると、100本は無理。鎌100回を目安に、毎回5分ぐらい、ちょっとずつ取り組んだ。
裏側の植込みの草はとくに根深くて、ものすごい力がいる。左足をかけて踏ん張って、両手で引っこ抜くしかない。その頃から左膝の違和感がはじまった。 |
|
 |
大腿四頭筋の硬直が原因らしく、膝はきれいで何の問題もない。お散歩の歩きはじめに、足をつくとき力が抜ける感じで、かすかに痛む。でも歩きつづけていると平気になるのだ。
テニスのときもそう。はじめは左膝が不安定な感じで軽い痛みが出るんだけど、走っているうちに平気になる。
シングルスの試合の前日、女ダブに誘われた。迷ったんだけど、女子のボールに慣れておくのもいいかも、と思った。
左膝(■)にテーピングをしてやったら、左の股関節(■)が痛くなった。大腿四頭筋の大腿直筋は股関節にくっついているので、そっちに過負荷がかかったのである。
夜は治療室で全身治療。股関節(■)の痛みは消えたけど、左膝(■)上部はまだ工事中な感じ。「1日休んだら完治」という状態だったけど、試合なのでやるしかない。
(ちなみに試合のあと、左坐骨結節周辺(■)がパンパンに張った。①→②→③で、新しいのが治って、古い不具合が露出した) |
|
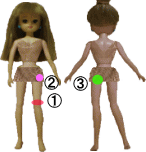 |
金曜日のラウンドロビンは19人がエントリーして、4人ブロックが4つで、私は3人ブロックの3番手だった。
2試合しかできないので物足りないな・・・と思ったけど、左膝が不調なのでちょうどいいかも・・・と思い直した。
待ち時間に左膝にテーピングをした。
たいていの相手はバックにボールを集めてくる。バックハンドは左足で踏ん張らなくちゃならないし、サーブの軸足も左足なのだ。
バックハンドが不調だったのは無意識に左足をかばっていたせいらしい。しっかり左足軸足で踏ん張って打つことにした。 |
|
 |
あんちょこもしっかり読んだ。今回のテーマは「自分の一番いいショットの練習をする」ことだった。確率が悪くても「決めボールをきっちり打つ」ことを目標にしたのだ。
そして「基本を忘れない」こと。相手が打つときに「1」と数え、「2」で軸足を出す。「自分のボールを見送らない」ことも私には重要だ。
1戦目の相手(リーグ1位)は、スパン、スパンと打ち込んで来る展開の速い女性。なんとかラリーに持ち込んでも、最後は私のミスで終わる。あっという間に0-6で負けた。
2戦目の相手(リーグ2位)は9月<ブログ→2024/9/23>の対戦で、短いボールに苦労させられた女性である。
去年から練習していたので、「短いボールは回り込んで近づく」とつぶやきながらボールを迎えに行った。ちゃんと打てていたらしく、相手は違う戦術を試しはじめた。
1ゲーム目を相手の凡ミスで取ったあと、どうしてもゲームが取れない。相手コートで試合ができたし、内容的には競っていたんだけど、やっぱり「決め手」に欠けるのだ。1-6で負けた。
3位トーナメントまで1時間以上も待たされた。始まったときはすっかり集中力を欠いていて、サーブはグチャグチャだし、まともなテニスができずに、あっという間に0-4で負けた。
勝ち上がるためには、試合に臨む緊張感を持続させなくちゃならないんだな・・・、とつくづく実感した。
ラウンドロビンのあとは治療室で全身治療をした。すでに左大腿四頭筋の硬直は消えていた。動いたおかげで、血流が完治をもたらしてくれたのだ。左坐骨結節周辺(■)の不具合が舞い戻ったけど、日に日にやわらいでくれている。
3連敗でえらく気落ちはしてる。でもサーブはかなり安定した。練習の成果があって、短いボールの処理も上手になった。決めボールはイマイチだったけど・・・、トライした自分を褒めることにした。
若い女性相手の試合はもうやめたい・・・という気持ちもあるけど、ちょっとずつ進歩しているから・・・と気を取り直した。
「走ることが楽しい」だけで始めたシングルス。あれこれ考えてできるようになった今は、勝てないことが重くのしかかるようになった。
ジョッパーの先輩が、「今は楽しくても、そこからが苦しくなるのよ」と言っていたんだけど、ほんとうにその通りかもしれない。
まだまだ先は長いのである。 |
|
|
|
|
|
| 2025/2/11(火) |
 32周年記念日は映画「リフト」で乾杯 32周年記念日は映画「リフト」で乾杯 |
|
先週日曜、2月2日はみづ鍼灸室の開業32周年記念日だったけど、相変わらず何の予定も立てていなかった。ポプラと外食・・・とも思ったけど、あまりの寒さに気力が萎えた。
患者さんが帰ったあと、いつものように鍼を磨きながらWOWOWオンデマンドで「リフト」を見始め、これぞ記念日のプレゼント!と思った。
自宅で鑑賞し直すことにして、パスタにフランスパン、ビールとワインをお供に、ティラとお祝いをしたのである。
「リフト」はホームレスシェルターやスラム街で暮らす子どもたちにクラシックバレエを教えるプロジェクトのこと。ニューヨーク・シアター・バレエ団の創立者、ダイアナ・バイヤーが立ち上げて、30年もつづけているのだそうだ。
この映画は監督ダビド・ピーターセンとクルーたちが10年間に渡って彼らを撮影したドキュメンタリーなのである。
黒人の青年スティーブン・メレンディスがシェルターを訪れ、少年少女たちにパンフレットを配っている。はにかむ子どもたちに「クラシックバレエって知ってる?」ときく。
「ぼくはスティーブン、バレエダンサーです。3年ここにいたけど、バレエを始めて出られた」と語りかける。「ぼくの所属する学校では週に4・5日、1時間半、熱心な指導が受けられます。生活や宿題の助言もするけど、軸はバレエです」
親たちもニコニコ笑って、興味津々である。
スティーブンがシェルターに来たのは20年ぶりだった。1989年、7歳のときに「リフト」の奨学生になり、14歳でプロデビューし、一流のバレエダンサーとして世界中で公演をしていた。
アキレス腱の炎症を抱えて、引退を考えはじめたときに、自分が教える側になるというのは自然な選択だった、と彼は言う。
幼い少女たちがシアターにやって来た。自分の身体に合わせてと、レッスン着からタイツ、靴下まで貸してくれる。
レッスンが始まると、パッセとかフランス語のバレエ用語に合わせて、子どもたちが一生懸命に踊る。みんなニコニコと楽しそうなのだ。
10歳で「リフト」の奨学生になったビクター・アブレウは、公営住宅で暮らす黒人の少年だ。ダイアナは「最も有望な生徒」と誇らしげだ。スティーブンも「彼は技巧派で潜在能力があって、スター性があって、自分を越えるダンサーになるだろう」と期待している。
貧困の中で家族も余裕がない。劣悪な環境の中で、横道にそれそうな子どもたちもいる。
バレエを教えるだけでなく、生活の規律を教え、レッスンへの熱意を支え、希望を与えて励ますことも仕事のうちなのだ。
シェルターの子どもたちと関わるようになって、スティーブンは自分の中のトラウマに気づかされることになった。当時は自分の住居を秘密にしていたのだった。
子どもたちも自分の境遇を恥じている。スティーブンはシェルターで暮らした過去から得たもの、失われたものを整理し、自分のトラウマを直視するようになった。
スティーブンは新作バレエに取り組みはじめた。
子どもたちそれぞれに自分の心から沸き起こる動きを表現してもらう。それらのモチーフを組み合わせ、ひとりひとりの心、互いの関わり合いをバレエで表現するというもの。
主役はビクターである。彼は16歳でスクールオブアメリカンバレエの入試に合格した。そこでも才能を認められ、ニューヨーク・シアター・バレエ団の団員になったのだ。
ビクターの力強く甘やかな踊りを中心に、「リフト」の子どもたちが生き生きと踊り、大絶賛されたとのことである。
貧しさの中で必死に生きる家族の笑顔。熱意をもって見守る人々の笑顔。希望を与えられた子どもたちの笑顔。。。
あふれるような笑顔に思わず微笑んでしまう。見ているだけで幸せを感じさせてくれる、とっても楽しい映画なんだよ。 |
|
|
|
|
|
| 2025/1/31(金) |
 9回目のJOPのシングルスも初戦敗退 9回目のJOPのシングルスも初戦敗退 |
|
公式戦の1週間前に、男性2人にシングルスをちょこっとやってもらったけど、サーブもフォアも思うように打てなかった。
あまりにもマズいと、飲み仲間のNさんに勇気を出してメールをした。実力差がありすぎるので遠慮していたのだけど、自分の殻を破らないとどうしようもない。ついに切羽詰まったのである。
先週木曜日、シングルスをはじめたら、ボールが全部当たりそこないだった。「最近、フォアが変なんだよね」と言ったら、「ラケットを引くのが遅すぎるんだよ。ボールが弾んでから引いてるでしょ。相手が打った瞬間にフォアかバックか分かるから、すぐにラケットを引いて、それから走るんだよ」と言われた。
・・・そうだった。それを忘れていた・・・
次には「ボールに近づきすぎる。それじゃあラケット振れないでしょ」と、指摘された。
・・・そうだった。そのことも忘れていた。スランプというものは初歩の初歩、基本の「キ」を忘れるのが原因のひとつかもしれないね。
サーブも狂ってしまっていて、ダブルフォルトを連発した。ラケットがまともにボールに当たらないのである。
Nさんが「トスの位置が後ろすぎるんじゃない?のけぞるように打ってるよ」と言った。『え、そうなの?』と驚いて、トスの位置を前にしたら、とりあえずボールに当たるようになった。
ボールが近すぎて、腕を振るスペースがなくなったのだ。ときどき同じ症状に悩まされていたんだけど、これが修正ポイントだったのだ。
彼は初心者の頃からの仲間なので、私がサーブに苦労していたことを知っている。「細かいフォームを考えるとダメなんだよ。サーブはリズムで打つんだよ」と言う。
「俺なんかさ、サーブがダメなときはトスがダメなときなんだよ。トスはどうやって上げているの?」と聞かれた。
昔スクールのコーチに教わったように、ボールを手の平の上のせた。
指を使うとボールがあちゃこちゃ行くから、手の平の上にのせて、エレベーターが昇るようにスーッと上げる。
そう教わったのだった。 |
|
| ①今まで |
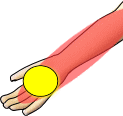 |
|
「俺のコーチはね・・・
人差し指と中指にボールをのせて、こっち側の筋肉で上げると教えてくれた。
親指で上からボールを押さえるようにすると安定するんだよ」と言う。
なるほど、トスは橈側の筋肉で上げるのか! |
|
| ②橈側の筋肉で上げる |
 |
→ |
 |
|
|
<①手の平の上>だと、前腕の筋肉のあちこちが微妙に動いてしまう。それでトスがバラついてしまったのか!と納得した。
<②人差し指の上>だと、橈側の筋肉しか使えない。トスが格段に安定した。まさに目鱗のアドバイスだった。
1年前まで膝を使ってトスを上げていた。腕を「棒」で使っていたので、なんとか安定していたらしい。手だけで上げるようになって、不具合が露見したのだ。
トスがどうしても安定しなくて、『誰かに聞かなくちゃ』と思いつつもチャンスがなかったのである。思わぬ大転換になった。
Nさんは1歳上で、中高軟式のあと硬式をはじめ、いまだにスクールでコーチに教わっているテニキチなのだ。
さすが「テニス歴57年」である。「試合の前だから」と、最低限必要なことだけ教えてくれた。
0-4で負け、0-4で負け、そのあとサーブ練習とラリーを少しして、最後のゲーム練習も0-4で負けたけど、やっとフォアの打ち方を思い出した。
3時間も走りつづけられたので、自分の体力に自信が持てた。
翌日の壁打ちでは久しぶりに壁相手に安定したラリーができた。サーブ練習では、「リズムで打つ」を唱えながらやったら、いつものマイサーブが普通に打てた。
「これしか打てない」というフォームを身につけつつあるのだった。
そして本番。月曜日がJOPの試合だった。1時半以降試合開始なので、12時ごろにクラブに着いたら、そこにCさんがいた。
体力はあるから、動きまくった方がいいと思って、1時間ぐらいラリーとシングルス練習をやった。
フォアは良かったんだけど、バックハンドが不調だった。
初戦は私と同じくポイント「0」が相手だった。私のサーブで彼女がミスをしまくり、ラブゲームキープになった。
『ミスの多い人なのかな?』と相手を侮ったのが失敗の元。そこからどんどん調子を上げていったのである。途中からムーンボールを多用したけど、そこからの決め手がない。2-4で1セット目を取られた。
2セット目に入って、相手のパフォーマンスがいきなり向上した。相手に攻められ、追いかけてなんとか返しても、最後は決められてしまう。
木曜日にNさんが、「相手のコートでテニスをするんだよ。こっちが優位なときは、相手を走らせて相手コートで試合ができる。押されているときは走らされて、自分のコートで試合をすることになる」と言ったんだけど、本当にその通りなのだ。
別の飲み仲間、Iさんが見学していた。「ナイスラリー」と声をかけてくれたんだけど、単なる励ましだ・・・と思った。
「自分のコート」で走らされるという惨めな状態だったんだもの。
Iさんも中高軟式からテニスに邁進しているテニキチで、初心者の頃から励ましてくれてる(年下の)先輩なのだ。2回目のJOPの試合のあとの、彼に尋ねた質問の答えを思い出した。<ブログ→2020/10/18>
「勝つために自分ができるショットだけを打ったほうがいいのか、負けてもいいから難しいことを試すのか、どっちがいいのかなあ?」
という私の質問に、「練習でできても試合でできなければ意味がないですよ。試合で打たないと、本当には自分のものになりませんからね~」と教えてくれたのだった
そう思ってもなかなかできることじゃないんだけど、0-1になったあと、『自分の一番いいショットを試合で使う練習をしよう』と決心した。当然ミスが増え、たったの20分で0-4で負けてしまった。
9回目だから初戦に勝たなくちゃ・・・とか思っていたけど、それはおこがましい考えだった。みなさん年に10回も20回も試合をし、それを何十年もやってきた強者なのだもの。
相手はテニスを知っているし、試合も知っている。初めはミスを恐れず自分のショットの調整をしながら、相手の弱点を見抜く。対策のための引き出しをたくさん持っているのだ。
今回の試合では、ダブルフォルトは1回で、ほぼ練習に近いサーブが打てた。フォアがまあまあ安定して打てたけど、バックハンドはしょぼいまま修正できなかった。
原因を考えているんだけど、左足軸足のふんばりが足りなかったのかもしれない。。。
そんなに疲れていなかったので、試合のあと女ダブに入れてもらった。今までならシングルスのあとはダブルスに適応できなかったんだけど、何の問題もなかった。ダブルス女子のボールがスローモーションに感じて、上手なペアに6-1で勝てたのである。
試合と同じようなサーブも打てたんだよ。
好奇心に駆られてエントリーした私。試合中はぜんぜん楽しくなかったけど、新しい発見がたくさんあった。あれこれ考えながらシングルスができたことは進歩である。
おまけに身体のどこも壊れていない。1時間練習したあと、1時間も試合をやって、そのあと女ダブをやっても大丈夫だった。
そうとう筋肉がついたらしい。これならまだまだ挑戦できるね~~ |
|
|
|
|
|
| 2025/1/22(水) |
 長引く風邪が大流行している 長引く風邪が大流行している |
|
去年年末から「風邪を引いた」という患者さんが増えはじめ、今年になって予約のキャンセルが相次いだ。来院した患者さんの中にも、お正月に家族全員で寝込んだという人が複数いるのである。
今までなら風邪を引く患者さんは「たま」だった。あっても年に数回、1人か2人というパターンだったのに、前代未聞である。
患者さん以外でも多発している。
「咳が抜けない」という人、「お腹がゆるゆる」という人がいるので、たぶん異なるウィルスに罹患していそうである。
どっちにしても、みなさんが長引いている。
前回のブログのとおり、5日までは元気いっぱいだった。その夜、家に帰ってすぐに、冷え切った部屋で、(背中にストーブを置いて)裸で髪の毛を切った。冷え切ったお風呂場でまず排水口の掃除をし、その途中で皮膚の内側に「冷気」が入り込んだことに気がついた。
翌朝にはしっかりと風邪を引いていたのである。
症例10「風邪 new1(2020)」で治療マニュアルを紹介した。その中のいくつかを順に試していった。
早く治すためには体力のあるうちに勝負するのがコツである。熱々の野菜スープ、お風呂でガンガン温まって、湯たんぽを入れたお布団にくるまる。発熱してウィルスと戦い、発汗で毒素を排泄するのが私の風邪の治療法なのである。
初期に効果的なのは、商陽(大腸経)から邪気を抜く治療である。喉には金粒( )を貼った。 )を貼った。
1日休養することにしたけど、元気いっぱいで、家の中で働きまくった。
夜には37.8度の熱が出たけど、思うように発汗してくれない。 |
|
商陽から
邪気を抜く |
 |
|
|
| 喉の金粒 ① |
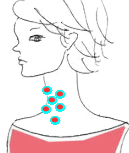 |
|
翌日には「まるで治ったかのよう」になった。元気いっぱいだったので、「仕事と家事だけの生活って、なんて楽なんだろう・・・」と、パンを焼き、ピザにもんじゃと、いろんな料理を作っては、ビールを片手に全豪オープンを観戦したり。風邪生活を楽しんでいたのである。
4日目の夜中、冷えて冷えて、目が覚めた。そういえば年末ぐらいから、そんな夜が何度もあった。「冷え」が芯までもぐり込んでいるらしい。
自律神経が乱れて風邪を引いたのか、ウィルスが脳下垂体に憑りついて自律神経を乱すのか、どっちなんだろう?
映画「レナードの朝」みたいに、風邪が原因で嗜眠性脳炎になったらどうしよう・・・と恐れおののいた。
身体のどこかに潜んでいるウィルスを引っぱり出して、なんとかして発熱して、スッキリ素早く治したいと思った。
鼻は通っていたんだけど、鼻の奥に鼻汁が溜まっているのを感じた。後鼻漏である。
鼻の奥に溜まっている鼻汁をウィルスごと引っぱり出そうと思った。
鼻づまりの特効穴、飛陽に銀粒( )を貼ったら、鼻水がジャージャー流れはじめた。 )を貼ったら、鼻水がジャージャー流れはじめた。 |
|
|
喉の上のほうを探ると、あちこちにゴロゴロと塊があった。リンパ節が腫れていたのだ。
『こんなところに逃げたのか!』と、金粒( )を貼った。 )を貼った。
狙い通りに(?)ウィルスが「出て」きて、風邪症状が現れた。
まだまだ元気いっぱいで、午後はテニスに出かけ、夜は治療室で全身治療をした。 |
|
| 喉の金粒 ② |
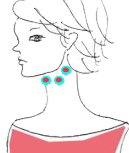 |
|
温まりつづけたおかげで「冷え」は消えたけど、発熱して発汗したくても、あっても微熱程度なのだ。何百回も風邪を引いたので、こういうスローウィルス的タイプが長引くことは経験済みである。
7日目、頻繁に咳が出るようになった。今回のウィルスは喉に憑りつくタイプだった。無意味な「空咳」は苦しいし体力も消耗する。
空咳を抑えて痰の排泄を促すことができるツボがある。
喉の天突に金粒( )、郄門(心包経)に銀粒( )、郄門(心包経)に銀粒( )を、セットで貼った。 )を、セットで貼った。
ずいぶん昔に発見した治療法だけど、久しぶりにやったら、自分でも驚くほどの劇的な効果があった。
咳の回数が激減した。 |
|
|
2週目に入って、「元気」がどっかへ行ってしまい、体力の低下を感じるようになった。ウィルスが気管支に移動したのである。
違和感のある気管支の上にカマヤミニ( )を置いて、ゆっくり煙を吸い込んだ。お灸の煙は喉や鼻の粘膜に効果があるのだ。 )を置いて、ゆっくり煙を吸い込んだ。お灸の煙は喉や鼻の粘膜に効果があるのだ。
気管も広がるらしく、しばらくは楽になる。2日ぐらいつづけたら、ウィルスが気管支から撤退した。
(昔は閉め切った部屋で、もぐさをぼうぼう燃やして、煙を吸わせて喘息の治療したとのこと) |
|
|
10日目、シングルスのラウンドロビンだったけど、何試合も走り回る自信がなくてキャンセルした。午後にクラブに出かけてダブルスをやった。
「病み上がり」と言いつつも、まだときどき咳が出たので、両腕の「冷え」にカマヤミニをしてみようと思い立った。
|
|
|
昔はよく腕から風邪を引いたものだったけど、今回も初めから腕の冷えが気になっていた。
皮膚の下にスースーすき間風が吹いている感じなのだ。
両腕にカマヤミニをして、ついでに煙もゆっくり吸い込んだ。
なんと翌日、咳がピタリと止まり、鼻水も出なくなった。 |
|
|
来週はJOPの公式戦、京王オープンのシングルスにエントリーしている。ラウンドロビンで練習しようと思っていたのに。。。
今年は1回もシングルスをやっていないのである。公式戦にぶっつけ本番はあまりにもヤバイ。焦りまくっていたら、試合に出ることを知ったおじさんたちがシングルスの相手をしてくれた。
ウィルスとの戦いは体力を消耗する。体力を取り戻すには動くのが一番なのだ。
スローウィルスタイプは厄介である。今度は声帯あたりに逃げ込んだらしく、声が割れてしまった。
完治まではもうしばらくかかりそうである。 |
|
|
|
|
|
| 2025/1/5(日) |
 「浦島太郎」から脱出 「浦島太郎」から脱出 |
|
30日は団地の掃除、買い物、ティラのお風呂、31日はまたまた買い物に行き、自宅の大掃除をして大量の料理を作った。
元日はファミリー7人が大集合。今年はあんずが紙の麻雀セットを持ってきたので、初詣に行きそこなった。食べに食べて、飲みに飲んで、おしゃべりに花が咲き、久しぶりに「家族がいる」と実感できた。。。
いつもは年末年始にダウンするんだけど、今年はそれほど疲れを感じず動けたのはやっぱり草取りのおかげかもしれない?
2日、3日、4日と連続でテニスクラブに出かけた。2日からテニスクラブに出かけられたのは、なんと6年ぶりだった。
平日会員がいないので相手を見つけるのが難しい。正会員の女子は3人しかいないので、土日祝日にダブルスをするには男性に入れてもらうしかない。
いつもやっている仲間とはいえ、『女は邪魔かな・・・』という遠慮もある。みなさん快く「どうぞ」と言ってくれるけど、『本心はイヤかもしれない・・・』とか、気にしてしまう。
でも勇気を出してコートに入ったのである。
2日は男性6人のところに混ぜてもらってダブルスをやった。
1週間ぶりのテニスだったし、いきなりのゲーム。チャンスボレーを2本ミスして、気弱病に襲われてしまった。みなさん上手で、よく走るし、何でも返って来る。3-4、2-4、2-4と負けつづけた。
3日はとても寒かったせいか、知り合いがひとりもいなかった。壁打ちとサーブ練習だけやって、仕事場の大掃除のつづきをした。
4日は男性5人のところに混ぜてもらった。1戦目は3-4で負け、気弱病がどんどん悪化していった。動体視力も玉勘も落ちている。
2戦目もボロで、あっという間に0-3になった。そのまま「0」で負けそうと思ったけど、『気弱病を克服するには動いて動いて打ちまくるしかない』と自分に言い聞かせてがんばった。
途中からなんとか金縛り状態を脱することができ、2-5から5-5に追いついた。結局は5-6で負けたけど、女と組んだペアが負けるのは普通のことなので、気にしないことにした。
ゲーム中に気弱病から立ち直れたのは快挙だった。
おととし「とびひ→低温火傷」で4カ月もテニスを休み、去年から再スタートしたあと、「浦島太郎」のように心もとない状態だった。
誰が「仲間」なのか分からなくなった。「友だち」だったはずの女性がはっきりと私を無視している。気後れと遠慮で気軽に声をかけにくくなってしまい、ダブルスをやる機会が激減した。
これは「シングルスに集中しろ」という神様の思し召しと思うことにして、練習中心でいいやと居直った私だったけど・・・
仕事が忙しくなって、どうしても早く起きれない。夏ならば7時過ぎまでテニスができるけど、年末は4時にはもう暗くなってしまう。ダブルスの機会がますます減少した。
そして12月のラウンドロビンで、ゲームの中で動き回らないと「腰が固まる」ことを発見したのだった。
「積極的にダブルスに入れてもらおう」と決心したとたん・・・、不思議なことに、毎回ダブルスに誘われるようになったのである。
人からは心の中まで見透かせない。自分の心の逡巡が、人を寄せ付けないオーラを醸し出していたのだ。
「浦島太郎」は私の心の問題だったのである。
80歳までテニスをするための大切な仲間だから、これからも教わりながら仲良くやっていこう・・・というのが新年の抱負である。
今日は本業の仕事始めである。本年もどうぞよろしく! |
|
|
|
|
|
日記  TOP TOP |
|
|
|
|
前の日付へさかのぼる |
|

