|
症例63・とびひ(+あせも)・改2
|
|
|
<搔きむしると飛び火する皮膚の常在菌の感染症>
|
|
 2度目の改訂のお知らせ 2度目の改訂のお知らせ |
|
4年前(2022年7月)にノミに刺されてとびひを発症しました。<↓初発>
水泡をつくる黄色ブドウ球菌の感染症でした。すでに大発生していたので、追いかけるのが大変でしたが、お灸で痒みが消え、数日で水泡が消失しました。
たった1回だけ左足にステロイドを試して、とびひが巨大化。<↓ステロイド>
えらい苦労しましたが、なんとか1カ月で治癒しました。
最初の更新のあと、翌年にステロイドを塗った左足に出来たとびひが一気に巨大化しました。<↓再発>
直径2センチもあって縮む気配もなく、何百壮もお灸をやった結果、低温火傷になりました。<↓低温火傷>
その報告をしなくちゃ、と改訂をしました。
3年目にもとびひが再発したのですが、お灸で簡単に退治できました。
4年目(2025年6月)、虫刺されをきっかけにとびひが再発したのですが、今回はお灸が効きませんでした。あちこちに広がったあとで、やっとカサブタを作る連鎖球菌とコラボしていたことを発見。<ブログ→2025/9/7>
その報告をするため、またまた改訂をすることになりました。 |
|
| *関連ページ: 細菌やウィルスによる皮膚の感染症 |
 |
症例5 |
いぼ ウィルス性のいぼはお灸でポロリ |
| 症例16 |
水虫 お灸の熱で細菌が死ぬ |
| 症例32 |
傷、おでき、ヒョウ疸、褥痩、しもやけ 退治と感染予防 |
| 症例36 |
帯状疱疹 鍼で血行促進、お灸でコロニーを撲滅 |
| 症例58 |
虫刺され 蚊、ダニ、ブヨ、チンクイ虫、スズメバチ、ノミ他 |
| 症例60 |
外耳炎 耳まわりの鍼で血行を促進 |
| 症例63 |
とびひ 黄色ブドウ球菌と連鎖球菌の違い |
|
|
 黄色ブドウ球菌は水泡をつくる「とびひ」 黄色ブドウ球菌は水泡をつくる「とびひ」 |
|
とびひ(伝染性膿痂疹)は皮膚の常在菌による感染症です。掻きむしった皮膚の傷を栄養源にして繁殖し、指にくっついた細菌があちこちに飛び火して、コロニーを増やしていきます。
水泡をつくるのは黄色ブドウ球菌で、「水泡性膿痂疹」と呼ばれます。子どもが罹ったときにほんとうに苦労しました。掻きむしってしまうので、次々に全身に広がります。薬の効果がなく、海水浴で治しました。
黄色ブドウ球菌のイメージは蝶です。軽やかにひらりひらりと飛んで、あちこちに水泡をつくります。水泡が薄いので、すぐに潰れて広がっていくのです。 |
|
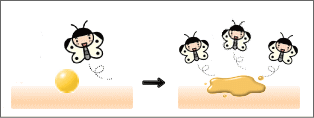 |
|
感染力が強いのですが、水泡が薄いおかげでお灸の熱が透ります。壊さないようにして、出来立ての水泡にお灸をします。すぐに痒みが消えて半日ぐらい持続し、朝晩のお灸で、1日2日で水泡が消えてくれます。
テニスもつづけ、散歩もつづけたので、靴下にこすれて広がって大変なことになりましたが、なんとか1カ月ぐらいで完治してくれました。 |
|
 連鎖球菌(溶連菌)はカサブタをつくる 連鎖球菌(溶連菌)はカサブタをつくる |
|
4年目、靴でこすれた左足にとびひが出来て、一気に直径1センチ大に成長しました。お灸をしても縮む気配もなく、硬くなって居座りつづけました。ジワリジワリと巨大化していき、あちこちに飛び火していったのです。
大きくなると厄介なので、水泡をつぶして抗生物質を併用することにしました。
効果があるらしく、塗布すると水泡が薄くなります。
でも破れて漏れ出た汁が、また新たなとびひを生み出すのでした。<ブログ→2025/9/7> |
|
 |
ここでやっとネットで調べ、「黄色ブドウ球菌と連鎖球菌が同時に感染する場合がある」という記述を見つけました。今年のとびひは連鎖球菌(溶血性連鎖球菌=溶連菌)が主役だったのです。
連鎖球菌のとびひは「痂皮性膿痂疹」でカサブタを形成します。イメージはモグラです。何週間もジーッと皮膚の下に潜み、ジワリジワリと広がって、小さな赤い丘疹を作ります。増殖すると天井にカサブタを作って隠れ潜みます。
皮膚の下に潜んでいるのでお灸の熱が届きません。中途半端に温まる結果になって、細菌がどんどん増殖していくのでした。 |
|
 |
|
「石けんで洗い流すのが一番効果的」と書かれたサイトがありました。シンクに足を上げて石けんで洗うと、とびひがあきらかに意気消沈するのです。もしかしたら連鎖球菌はアルカリ性に弱いのだろうか?と思いました。
「痒い」ときにキンカンを塗りたくっていたのですが、コロニーが出来にくい感じだったのです。キンカンの主成分はアンモニア水でアルカリ性です。
広範囲に塗りたくるとスーッとして気持ちが良く、しばらく痒みが消えます。また痒くなったらまた塗ってと、えんえんとくり返しました。 |
|
 石けんでゴシゴシ、巣を削り取る 石けんでゴシゴシ、巣を削り取る |
|
私の足を見た友人が、「子どもの頃に全身に出来たことがあった。とびひだったのね!」と言いました。おばあちゃんと1カ月湯治場に行って治したそうです。
とびひを追いかけては薬を塗って、痒みが出たらキンカンを塗りたくって・・・の追いかけっこに疲れて、温泉を試してみることにしました。
いつもの温泉が弱アルカリ性でした。古いとびひがみるみる沈静化しました。あらたなとびひが出来にくい感じです。
「温泉で治るかな?」と喜んでいたら、「敵もさるもの」です。
 |
|
6月に長い雑草を引っこ抜いたときに、いろんな虫が飛んできて腕を刺されました。それがとびひに発展したのですが、そのときの卵のように白くて硬い水泡がまた出現しました。
大きくならないように水泡をつぶして抗生物質を擦り込みました。 |
でもほとんどのとびひは赤い丘疹から始まります。
「痒い!」と思ってキンカンを塗りたくると、数日後に小さな赤い丘疹が出現します。それが数週間とどまって、薄くなっても、見えなくなっても、まだまだ飛び火しようと機を見計らっている気配がつづきました。 |
|
|
|
|
『コロニーを物理的に削ってみたら?』と思いつきました。石けんを泡立てた洗い布でゴシゴシこすると、とびひが小さくなります。汗や垢、コロニーの残骸が連鎖球菌の栄養源になるのかもしれません。
石けんゴシゴシの効果は抜群でした。バッグの紐や衣服でこすれたところに丘疹が出来ることもありますが、ゴマ粒以下の大きさでした。小さいと退治は簡単で、カサブタになることもなく、長くても1週間ぐらいで消えてくれます。
抗生物質の塗布は3週間ぐらいつづけましたが、効果があまり感じられなくなりました。もしかしたら耐性菌が?と思って止めました。来年もとびひができるかもしれないので、耐性菌とのいたちごっこを避ける目的もあります。
痒いと思ったらキンカンで、とりあえず増殖が防げるのです。 |
|
 温泉で治した・・・とも言える 温泉で治した・・・とも言える |
|
温泉には週に3回ぐらい通いました。暑いとあちこち痒くなるので、「助けて~」という感じで、とびひに追われるようにバイクを走らせました。石けんゴシゴシのあと温泉に入ると、はじめは猛然と痒みが襲ってきます。30分ぐらいで痒みがおさまり、出たときにはとびひが縮小しています。
とびひ大発生の足はずっと湯につけていられますが、上半身はそうもいきません。逃げ場を求めた飛び火の退治はキンカンです。
私は弱アルカリ性の温泉を選んだのですが、硫黄の温泉(酸性)で治療したという話も聞きました。白い膿がとろりと出て治るそうです
現代は朝でも夜中でもシャワーができますが、昔はそうもいきません。湯治場で治したという話におおいに納得しました。
コロナの前は毎年夏に海で泳いでいました。うちの母が「とびひは海に行くと治る」と言っていたのですが、海水も弱アルカリ性なのです。海水浴が夏のお肌の健康に役立っていたのかもしれません。
去年まではシングルスの試合のあとで温泉に行き、その日の疲れを取っていたのですが、今年は1回も温泉に行きませんでした。
来年はとびひ予防のために海水浴と温泉通いをしようと硬く決心しています。 |
|
 夏になると、また蠢(うごめ)く 夏になると、また蠢(うごめ)く |
|
「暑いととびひが痒くなる」「涼しいと沈静化する」、気温と細菌の活動にはあきらかに関連がありました。
「うごめいてる」の漢字は「蠢いてる」で、なんと「春」の下に「虫」が2つ並んでいるのです!春になると虫たちが活動しはじめる。気温が上がるにつれどんどん活発になって、夏には大暴れ。漢字の表現力はすごいですね。
人間の目からはすべすべに見える皮膚も、細菌たちにとってはうっそうたるジャングルのようなものなのでしょう。大発生したあと、生き残りが隠れ棲むところはいくらでもあるようなのです。
ずいぶん昔の話ですが、喉に「あせも」が出来たことがありました。汗で皮膚が刺激されたのでしょう。うっかり掻くと、傷口に皮膚の常在菌が繁殖して「あせものより」(=多発性汗腺膿瘍)になってしまいます。「あせものより」の原因菌も黄色ブドウ球菌だそうです。
発疹が出る前の状態だったので、鍼灸治療の狙いどころが分かりません。薬を使おうか迷ったのですが、刺激物である「汗」を取りのぞくために、ちょこちょこ喉を水洗いしてしのぎました。しばらくしたら痒みは消えてくれました。
翌年の夏にも、今にもあせもができそうな、チリチリするような不快感がはじまりました。ちょこちょこ喉に水をかけて洗いながら、『これが毎年つづくのか』とうんざりしたのですが、3年ぐらい過ぎたら「あせも」の気配は出なくなりました。
ネットでは「とびひにステロイドを塗ると悪化する」と書かれたサイトがありました。免疫力を低下させるそうなのです。
開業間もない頃、アトピー性皮膚炎で来院した女性の肌を思い出します。全身のあちこちに直径1センチぐらいの黒いものがへばりついていました。治せずに終わったのですが、あれは「とびひ」だったのだと今になって分かりました。
私の肌が(幼い子ども並みに)極端に弱いのも、小児ストロフルスのときにステロイドで治療したのかもしれず、その後遺症かもしれません。 |
|
|
|
|
2022年の春、ティラのトリミング中に生まれてはじめてノミを見ました。お腹の毛を抱っこで刈っていたときに、黒っぽい小さな虫が2匹、サササ~ッと毛の密林の中に滑るように逃げていったのです。(ティラのブログ→2022/5/29)
ティラが足で耳を掻くときは「そろそろシャワー」のサインと決めてはいたのですが、先延ばししていたのです。耳どころか、立ち止まって坐り込んでは、足であちこち掻いていたのはノミのせいだったのです。
シャワーをすれば逃げるだろうと思ったのですが、逃げついでに私の足をあちこち刺していきました。
ティラの背中に「フロントラインプラス」を垂らしたのですが、ダニのときほど効果がなく、いつまでたっても刺されつづけた・・・と思いました。ある患者さんに「ノミのジャンプ力はせいぜい足首から上ぐらい。場所からしても完全にノミですよ」と言われたのですが、すでにノミは駆除されていたのです。
ノミを見かけてから1か月後のことでした。
サンダルをはいて散歩に出かけたのですが、紐に当たる皮膚が痛くて歩けません。
サンダルの紐がかかる部位に小さな赤い発疹、水泡とかさぶたがびっしりとできていました。
ノミに食われた部位を掻きまくったせいで皮膚に傷がつき、「とびひ」という感染症になっていたことにやっと気がついたのです。 |
|
 |
|
|
 水泡の「とびひ」は「水疱瘡」とそっくり 水泡の「とびひ」は「水疱瘡」とそっくり |
|
人間の皮膚にはいろいろな細菌が常在しています。皮膚に傷ができるとそこに巣をつくって繁殖をはじめます。「とびひ」の原因になるのは黄色ブドウ球菌と溶血性連鎖球菌(溶連菌)で、水泡をつくるのはブドウ球菌だそうです。
「とびひ」になると保育園を休まなければなりません。小さな子どもに多いのは掻きむしってしまうせいでしょう。
娘が2歳ぐらいの夏、「とびひ」になって新潟に帰省しました。保育園で流行っていたのです。「皮膚病は海で泳ぐと治る」と昔から言われているので、毎日海に連れていきました。
2週間ぐらいたって、微熱があることに気がつきました。もしかしたらいつの間にか「とびひ」が「水疱瘡」になり替わっていたのではないだろうかと思いました。保育園では水疱瘡も流行っていたのです。
「水疱瘡のときは風に当ててはいけない」と昔から言われていて、大事にしないと後遺症を起こしてしまうそうです。対処法はまったく逆なので、真夏の盛りにかわいそうに娘は家でお留守番になりました。
通っていた皮膚科の医師も驚いていました。「とびひ」と「水疱瘡」は誰にも見分けがつかないほどそっくりなのです。
はじめは赤いプツプツで、それが水泡に変化し、最後はかさぶたになります。それらが皮膚の上に混在するのが特徴です。(帯状疱疹も同じです)
でも水疱瘡は時が来れば治りますが、「とびひ」はそうもいきません。水泡ができるタイプはとても治りにくいのです。 |
|
 水泡との戦い 水泡との戦い
|
|
掻くと皮膚に傷がつきます。菌にとっては傷は栄養源です。指先にくっついた菌が他の場所に運ばれて、そこでまた新たな巣をつくります。
痒くても「絶対に掻かない」のが信条の私ですが、ノミがいると思い込んでいたので、またか!と、ときどき足を上げて掻いていました。
ホームページのリニューアルと仕事で忙しくて、自分の足を見ることさえしていませんでした。裸足でパソコンに何時間も夢中になっていたので、足が冷えていたのも悪化の要因と思います。
毎日1時間以上もサンダルでティラのお散歩をしていたので、紐でこすれた皮膚に傷がつき、そのライン上に菌が大団地を作ってしまいました。スニーカーを履くことにして、紐をゆるめてゆるゆるの靴下をはいて歩いたのですが、ちょっとした刺激にも耐えられない皮膚になっていました。すでに菌の勢いが攻勢を増していたので、お灸はまるでゲリラ戦でした。
細菌は生き物なのでお灸の熱で死んでくれます。ターゲットの一番は水泡で、大きさに合わせてもぐさをのせました。中に棲む菌が流れ出さないように、水泡が破けないように用心しました。大きい水泡ほど頑丈で、中には1週間ぐらい持ちこたえたものもありました。
小さな赤いプツには小さな糸状灸です。一見滑らかでも痒みを感じるところが出発点なので、皮膚を軽く触ってみて寸止めで糸状灸をしました。かさぶたは末期症状ですが、用心に数日は追い打ちをかけました。 |
|
 ステロイドが水泡を巨大なビルにした ステロイドが水泡を巨大なビルにした |
|
夜な夜なお灸をしたのですが、お散歩はやめられません。移築されては撃退するという「いたちごっこ」になりました。
ある晩ステロイドを試してみようと思いつきました。左足だけにステロイド軟こうを塗ってみたら、目覚ましい効果がありました。痒みが消えたどころか、曇り空から一気に晴天になったように、足全体に爽やかな風が吹いているようでした。
右足にはいつもの糸状灸です。ステロイドを塗りたくなる自分をぐっとこらえて眠りにつきました。1時間後、左足の痒みで目が覚めました。今まで味わったことがないほどの猛烈な痒みに襲われたのです。右足にはまったく痒みがありません。お灸の痒み止め効果は半日以上つづくのです。
この先どうなるかを見たかったので、お灸をしたい気持ちをぐっとこらえて、キンカンを塗ってしのぎました。
翌朝自分の足を見比べて仰天しました。右足は小さな水泡が点々としていたのに比べて、左足の水泡は直径1センチぐらいの大きさに膨れ上がっていたのです。細菌やウィルスの作る巣は、大きいほど陥落が難しくなります。小さな家だと簡単に壊せるのですが、ビルとなると破壊するのは大変です。
でっかい水泡にはでっかいもぐさをのせました。1回では熱が透らず、何回もくり返す羽目になりました。(熱さを感じて痒みが消えるのが透熱のサインです)
いぼと同じく、水泡は菌が作った家なので、焼き尽くしても菌の家が壊れるだけで、皮膚にお灸の痕は残りません。残るシミは「ここは不健康」という目印です。
(薬は怖い!肩に抗ヒスタミン軟膏を塗ってみたことがあります。そのときのリバウンドの話はブログに書いてあります→2008/12/14) |
|
 皮膚のシミが消えるまで数か月 皮膚のシミが消えるまで数か月 |
|
「とびひ」が消えるまで1ヶ月ぐらいかかりました。再発が怖いのでとりあえずサンダルは来年までお預けにしました。
治ったあと皮膚にシミが残りました。いつか消えることは分かっているので、定例の鍼灸治療以外、とくにシミ目がけての治療はしませんでした。
1994年に来院したMさん(当時23歳、女性)の主訴は皮膚でした。むくみやすいこと、血行が悪いことなど他にも症状があったのですが、「肌をきれいにしてほしい」というのが一番の望みでした。
数年前にアルバイト先の喫茶店でネズミのノミが大量発生して、太ももから足首までそこら中を刺されたそうです。親同士も友達、娘同士も友達という古い知り合いです。「刺されあとのシミは鍼灸で治るよ」と言ったのですが、「こんな汚い足、誰にも見られたくない」と恥ずかしがっていたのでした。
全身治療の他に、シミの上には簡単な浅い鍼と糸状灸をやりました。だんだんシミが薄くなっていき、4か月後(13回)にはすっかりきれいになりました。
足を出さないように縮こまって暮らした数年間を振り返って、「こんなことならあのとき治療してもらえばよかった・・・」と悔やんでいました。
皮膚は内部を映す鏡です。こりのせいで背中や腰の皮膚が薄汚くなってしまった患者さんがときどきいますが、若ければ数ヶ月(若くなければ年単位)で皮膚のシミがきれいに消えます。それは深部まで治ったというサインでもあります。
私の足のシミも3カ月後には、よ~く見ると数か所にうっすらという状態になり、半年後にはすっかりきれいに消えてなくなりなりました。 |
|
 再発:免疫力の低下、そしてステロイドも原因? 再発:免疫力の低下、そしてステロイドも原因? |
|
翌年2023年はものすごい猛暑でした。恐る恐るサンダルに足を突っ込んでみたら、紐に当たる皮膚に渋いようなザワザワ感が起こり、あっちでチリチリ、こっちでゾワゾワと、まるで不快感のオーケストラです。
サンダルに黄色ブドウ球菌が付着したとしても、栄養源がないのだからとっくに死滅しているはずと思い、がんばってサンダルでお散歩をしました。
再発の可能性を考えて、毎日たんねんに足の皮膚をチェックしました。出来た瞬間の「とびひ」の芽を叩く作戦です。あちこちに飛び火すると厄介ですし、小さな発疹なら小さいお灸ですぐに退治できます。
6月からはじまった猛暑とともに患者さんが押し寄せて、治療室は大繁盛でした。テニスクラブに行けるのも週に2回+αでしたが、シングルスの試合も何回かこなしました。家事もあるしで疲れ果ていました。
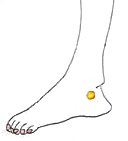 |
| 2023年7月 |
|
|
7月、(ステロイドを試した)左足の、サンダルの紐のライン上に小さな水泡を見つけました。
1回では消えず、2回目のお灸は水泡に合わせてもぐさを大きくして、3壮でムズムズ感が消えました。
3日後、茶色く縮んだ水泡のわきから、小水泡が2つニョキッと顔を出していました。そこにお灸をしたら、そのまま縮んでくれました。
作戦は大成功、これで完治、と大喜びしました。
<ブログ→2023/7/24> |
1週間ぐらいしたら、サンダルで歩くときの皮膚の不快感もなくなりました。どうやら皮膚が頑丈になって、健康を取り戻してくれた・・・と思いました。
今年は小水疱のうちに叩いたので、細菌の「家」は1個で終わり、「とびひ」に発展せずにすんだ・・・と思い込んだのですが、これがとんだ落とし穴でした。 |
|
 お灸のやり過ぎで低温火傷になった お灸のやり過ぎで低温火傷になった |
|
8月も仕事+シングルス+家事の生活がつづき、猛暑の終わりかけの9月に(ステロイドをを試した)左足に「とびひ」が再発しました。
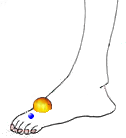 |
| 2023年9月 |
|
|
最初に小さなとびひ(●)ができましたが、すぐに縮んだので、気が緩んでしまいました。
数日後、テニスのあとだったと思います。仕事場で左足の甲に直径1センチ以上の水泡(●)を発見し、びっくり仰天しました。
スリッパをはいて仕事をしたあと、1.5倍の大きさに膨れ上がってしまいました。
皮が硬くてプヨプヨと弾力があって、半透明でぬらぬら輝く巨大ドームを建設されてしまったのです。 |
今回の水泡(●)はサンダルの紐から外れていました。テニスシューズで擦れて、いつの間にか巨大化していたのでしょう。
裸足なら歩けるので仕事には支障がありませんが、靴が履けないのでテニスは無理です。 こんなに大きいと、お灸をしても熱が届かず、消失までにかなりの日数がかかることはすでに経験済みです。
シングルスの試合を欠場して二連休になりました。ポワロなんかを見ながら、水泡の上にえんえんとお灸をしました。ぜんぜん熱くないのです。水泡に触るとポカポカと温かいので、『これでは細菌が喜んでしまう』と焦りました。
テレビの前に寝そべって、思い出してはお灸をしと、何百壮もやってしまいました。『細菌を焼き殺したれ!』と躍起になってしまったのです。そして3日後に低温火傷になってしまったことに気がつきました。
『そうだった、とびひを治すのは自然治癒力だった!』と反省、「お灸の熱で菌を焼き殺す」ことにこだわって大失敗をしたのです。<ブログ→2023/9/26>
最初のとびひのときはテニスも仕事もやれていました。お灸ができるのは朝晩だけだったので、やりすぎて火傷になることもなく、痕も残さずにきれいに治ってくれました。それで充分な効果があったのです。
巨大ドームを発見した数日後、お灸のあとで、爽快な「スッキリ感」を感じたことがありました。『やったー!細菌に勝った!』と感じたのですが、それが「治っていくぞ」のサインだったのです。
朗報を期待した翌朝、巨大ドームがそのままだったのを見てがっかり。そこからますます躍起になってしまいました。あのまま地道に「朝晩」でやっていれば、長くとも数週間で消えてくれたことと思います。
ステロイドがこんなにも免疫力を低下させることも驚きです。巨大ドームで繁殖した細菌があちこちに飛び火。お散歩をしているうちに、サンダルやビーチサンダルに当たる皮膚にもコロニーを作られました。腕や胸などに数個ですが、とんでもない遠方にも水泡が「飛び火」しました。
小さなプツのうちにお灸をすると3日ぐらいで消えてくれます。「痒いと感じたらすぐにお灸」で、左足以外の発疹はすぐに沈静化してくれたのですから。 |
|
 補足:低温火傷とは? 補足:低温火傷とは? |
|
火傷のレベルは「熱さX時間」で決まります。かなりの高温でも一瞬ならば軽度で済みます。熱湯を皮膚に浴びたとしても一瞬ならば軽度、洋服に浴びたら、洋服を脱ぐまでの時間、皮膚が熱にさらされます。
真っ赤なストーブに手を当てても、「熱い!」と感じた瞬間に手を離せば、表皮だけの損壊で済みます。握りしめたら深部まで火傷をします。
直接灸に使われる「良質もぐさ」は、ヨモギの葉っぱの裏についている「にこげ」で、燃焼温度は40~80度ぐらいと言われています。
間接灸には葉っぱや茎が混入された「粗悪もぐさ」が使われます。カマヤミニは筒を用いて遠方から温めます。隔物灸であるニンニク灸や塩灸などは、もぐさとの間に遮蔽物を置いて熱さをやわらげています。
なので、ちゃんとやれば痕を残さずにできます。水ぶくれができたとしても、内部が治ると痕が消えてくれます。
「低温火傷は治りにくい」と聞いてはいましたが、本当にその通りでした。
低温火傷は人間が「熱い」と感じない程度の温度に長時間さらされることで起こります。深部の組織まで破壊されてしまうのです。
私の低温火傷も患部に穴があいてしまいました。深部の組織を修復したあと、皮膚組織を再生しなくてはならないので、治癒に日にちを要するのです。
表皮が出来上がったあとも、まるでムースのように脆く、ちょっとでも擦れるとぐちゃぐちゃに崩れてしまいそうでした。
私は絶対にこすらないように、細心の注意を払っていました。
秋が深まって、あまりの寒さに裸足ではいられなくなり、低温火傷に当たらないように古いテニスシューズを改造し、スリッパにも穴をあけました。
3カ月たってやっと表皮が出来上がったので、試しに改造シューズでテニスをやってみました。やり過ぎると傷口がこすれてヒリヒリしました。
<ブログ→2023/11/25>
ヒリヒリしなくなったのは4カ月後で、改造シューズとサヨナラしたのは5カ月後です。
ついでに言えば、テニスに見合う筋力と体力が戻るのに半年ぐらいかかりました。 |
|
|
|
|
|
鍼灸師が「お灸で低温火傷」というのはあまりにもみっともないので、結局病院には行きませんでした。感染症予防のために西洋医学の薬を使ったのですが、素人療法なので名前は秘密です。
今では触っても違和感がなく、ゴシゴシやっても大丈夫になりました。患部には茶色いシミが残りましたが、これは一生消えないかもしれませんね。 |
|
 |
|
|

