| 2016/11/19(土) |
 奇跡の復活、退院してホームに戻れた 奇跡の復活、退院してホームに戻れた |
|
木曜日、母は調布病院を退院して、ホームに戻った!入院はたったの2週間ですんだんだけど、私にとってはほんとうに長かった~。
月曜日、調布病院の相談員との面談があった。
電話のときに前もって、最後は在宅で看取るつもりであることを伝えてあったけど、あまり本気にしていなかったみたい。
「お母さんはあまり食べられないということで、ホームに戻るのは無理ですね。私の役目は、転院先の長期療養型病院を紹介することなんです」と言う。
「電話でも言ったように、自宅に連れ帰るつもりです。胃漏も中心静脈もやりたくないし、点滴もいやなんです。病院には行きません」と伝えた。
6年間の母の闘病生活のこと、ほとんど身動きもできない状態が何年もつづいたこと、もう限界なら、そろそろ楽にしてあげたい気持ちもある・・・
「調布病院から直接自宅に退院したら、介護するのはこの私だから、たぶん数週間で死んでしまうと思います。ホームのほうでは、『もう少しがんばりたい』と言ってくださっています。いったんホームに戻れれば、職員さんたちは介護のプロだから、もしかしたらもう数ヶ月、なんとかなるかもしれないんです」と話した。
相談員の人は、「実は、ちょうふの里さんが何度か様子を見に来てくれて、いろいろと話をしたんですよ」と言う。
「こうなったら、病院に長くいていいことはありませんね。1日も早く退院できるように、主治医と話してみます」と言ってくれた。
夕方、ちょうふの里から電話があり、すぐにでも退院できるとのこと。内科医が来る木曜日の午前中に、ホームに戻ることになった。
水曜日に(やっと)主治医との面談があった。
肺炎のほうは一応治ってはいるけど、まだ一進一退というところ。食べるとまた誤嚥をおこして、肺炎が悪化するかもしれない。そしたら、すぐにまた入院になるかもしれない。
「でも、退院するなら今がチャンス。これを逃すと、いつ退院できるかわからなくなるので、できるときに退院しましょう」と言ってくれた。
私はもと職員だし、この世界に長くいて、何十人ものお年寄りを見てきた。そのうえでの決断だから、説得力があったのだと思う。
まさに「奇跡」ともいえる、最高の結果になった。
みなさんが親身になってくれ、有益な話をいろいろ聞かせてもらった。
結局は、病院の医師も職員もいい人たちだった。
捨てられていくお年寄りを見て胸が痛むが、自分の力ではどうしようもない。ひとりでも家族のもとに帰れるお年寄りに出会うと、ほっとして、できるだけの助力をしてあげたいという気持ちになるのである。
木曜日の朝、ホームの人が母を迎えに来てくれた。
私はいったんテニスに出かけ、夕方またホームを訪ねた。母のリハビリとマッサージをしたあと、「車椅子に乗って食堂に行く?それとも、すこし横になって休む?」と聞いたら、「すこし横になる」と答えた。まだまだ会話が通じている。
職員さんたちと話をしたら、みなさん、復帰を喜んでくれていた。
「お昼ご飯を食べたんですよ!」と嬉しい報告をしてくれた。お粥を全量と、副食も半分以上食べたんだって。
「体重が、入院するときに28キロで、退院時も28キロで、ぜんぜん減っていないんです。横ばいというのはすごいことですよ」とケースワーカーが言ってくれた。
「点滴してたからじゃないんですか?」と聞いたら、点滴だけではどうしても体重減少は避けられないんだって。食べさせつづけたおかげだね~。
しかも、身体が全然硬くなっていなくて、入院する前と同じ。やっぱり、たいていのお年寄りは身体が硬くなって、車椅子に乗せるのにものすごく苦労するんですって。これもすごいと、みなさん、大喜びで盛り上がってくれた。
2週間の全力疾走は、死ぬほど大変だったけど、ちゃんと成果があった。
しかも、職員さんたちが私の努力を分かってくれて、喜びを分かち合ってくれたので、苦労が報われた思いである。
「あとは私たちに任せて、ゆっくり休んでくださいね」と言ってくれた。
ヴェルが感染症にかかったときを思い出す。13歳の夏だった。
何週間もすっかり元気がなくなって、食欲も落ちて、もうダメなのかなと心配していた。ほっぺが腫れてから、あわてて病院に連れて行って、抗生物質の注射をしたらみるみる元気になった。
元気がなかったのは、感染症のせいだったのだ。
母も同じかも。8月にいきなり痩せてから、「もう長くないな」と覚悟をはじめた。肺炎の治療をしたら死相が消えた。自分が愛されていることに気づいた「幸福感」が、生命力アップl原動力になったこともあるかもしれないね。
年寄りは、入院すると一気にレベルダウンするんだけど、「横ばい」で退院できたのは幸いである。
とりあえず一段落だが、このあと本当の正念場がやってくる。
寝たきり老人の介護は、オムツを取り替えるだけだから楽。寝かせたまま外出ができるから、という話を聞いた。
ヴェルは病院に連れて行かずに、家で看取った。親だって看取れるはずと決意したのだけど、死に行く人間を見守るのは、精神的にかなりつらいだろうな。
あんずは、母を迎える準備をしなくちゃと私をせっつく。大の苦手の部屋の模様替えに取り組まなくちゃならないね。
母が落ち着いたので、仕事とテニスをやりながら、のんびりやれそうである。 |
|
|
|
|
|
| 2016/11/13(日) |
 植物人間へのベルトコンベアー 植物人間へのベルトコンベアー |
|
とにかく、母は、一見植物状態。はじめて見る医師や看護師にとっては、そう見える。「コミュニケーションが取れない状態ですよね」と言われるので、会う人ごとに説明しまくらなくちゃならない。
「声も出さないし、身動きもしないので、植物状態のように見えますが、自分のことも家族のこともわかっています。自分から発信することはほとんどないけど、投げかけられれば応答します。耳は遠くないので、小声でも聞こえます。自分の意思は伝えられるので、なるべく声かけをお願いします」...
etc.... etc...
じゃないと、レベルダウンしてしまう。
毎日通ってがんばっていると、看護師さんたちも親身になってくれる。
食事摂取は、ホームにいたときと同じ。全量食べる日もあれば、一口も食べない日もある。
食事を巡っての、主治医とのやり取りが大変だった。
入院の次の日、夕方行ったら、テーブルの上に、小さなゼリーのお盆があった。看護師がさし出すスプーンに、自分から食らいついていた。2日も絶食だったので、お腹がすいていたみたい。まだ食べる意思が残っていた。
その次の日、廊下で主治医に呼び止められた。
にこにこ笑いながら、パーキンソンの薬、胃漏や中心静脈の高濃度輸液のための手術をすすめられた。私はすべて断った。
主治医は、「ある程度食べられるようにならないと、ホームは受け入れを嫌がると思いますよ。胃漏にすれば、もとのホームでの受け入れは可能です。じゃなければ、自宅に戻るか、長期療養型の病院に転院してもらうことになります。ここは急性期の病院ですからね」と言う。
「だったら、早めに食べさせてください。食べる能力がなくなると困ります。このままだと、肺炎で死ぬか、飢え死にして死ぬかのどちらかですよね?」と言ったら、「そうですね~」と答える。
「この状態だと、年内ですかね?」と聞くと、「そうですね~」と答える。
とりあえず、ゼリー食が開始になった。プリンを半分に切ったぐらいの大きさの、白いゼリー、黄色いゼリー、緑のゼリーに、茶色い「とろみ」のお茶、という感じ。
「まずいけど、これを食べないと、食事のレベルが上がらない。全部食べたら、焼きおにぎりをあげるからね」と母に言い聞かせて、口に運んだ。
素直に食べてくれた。私がいないときも、がんばってくれているみたい。
翌々日、また廊下でバッタリ会った主治医に、「ゼリーは不味いので、早くご飯にしてください」とせっついた。
「ご飯にするのは、今日の夕食からでも可能ですが、誤嚥を起こすと困るんですよ。また肺炎になるかもしれませんからね」と主治医。
「この食事の量だとホームには戻れません。胃漏にしなければ、転院するか、さもなければ、自宅に帰るしかありませんよ」と、相変わらずにこにこと笑いながら、たぶん、私を脅している。
(でも、とりあえず、その日の夕食からお粥になった)
自宅で介護か・・・
点滴もいやなんだから、それしか道はない。要介護5だから、ヘルパーさんを頼んだり、訪問看護や往診を頼んだりすれば、なんとかなるかもしれない。
在宅で看取る覚悟を決めなくちゃな・・・と思った。
ちょうふの里に相談に行くことにした。母を引き受けたくないのか、本当のところを聞きたいし、在宅介護のアドバイスも聞きたいし、と思った。
あんずと一緒に、ちょうふの里の担当者と面談をした。とても親切で、いろんなことを教えてもらった。
彼が言うには、「もとからあまり食べられなかったのだから、全食食べられないとダメということはないんですよ。肺炎が落ち着き次第、こちらに戻ってもらって、食べられるようにもうちょっとがんばりたい。そういう気持ちです。
でも、主治医が退院許可を出してくれないと、どうしようもないんです。ホームのほうでヘタに動くと、医師はプライドが高いし、今後の関係がこじれてしまう可能性がある。間に人を介して、それとなくお願いしてみましょう」とのことである。
なるほど、これが、「胃漏」が減らない理由なのか。
認知症のお年寄りが、肺炎や骨折で入院する。病院はリスク管理を重視して、口からの食事を摂らせない。完璧に食べられないと、退院許可が出ない。そうなると、ホームに戻ることができなくなる。
胃漏をしてホームに戻るか、もしくは中心静脈の点滴を選んで、長期療養型の病院に転院するか、さもなければ自宅に引き取るかの、つらい選択を迫られる。
「植物人間」行きの直行便?ベルトコンベアーに乗せられてしまうと、「延命治療はされたくない」という、お年寄り本人の願いは無視されてしまう。
「え、自宅に?あの都営住宅で、面倒をみれるんですか?仕事もしているんでしょう?」と彼は驚いた。
「自宅に帰った人は、自分がここに来てからの10年間で、3人しかいないんですよ。そうなったら、すごいことですけど」と言う。
ちょうふの里は「看取り」をやっていないので、いよいよの時は退所になる。結局、遠方にある長期療養型の病院に行くしかなくなるのだそうだ。
「ご飯にしてもらったというのはすごいことです」と喜んでくれた。
肺炎が落ち着き次第、できればホームに戻らせてもらう。また食べられるように職員さんたちに協力してもらう。介護のプロだから、私よりも可能性が高い。
いよいよとなったら、ホームから自宅に連れ帰る・・・
それが最善の策だと思った。
金曜日、肺炎の状態を主治医に確認して、このことを相談しようと思ったのだけど、なぜか「逃げられた」?
来週の火曜か水曜の午後じゃないと、面談の時間が取れないのだそうだ。
こんな経験ははじめてである。家族が入院。医師が不在の場合ならともかく、病状を聞きたいとお願いして、「忙しい」を理由に断られたことは一度もない。そんなに呑気にかまえていいの~?
老人医療が前代未聞に発達しているというのに、現状はかなりヤバイ。
遠くの病院だと、私もそんなには通えない。あっという間に全身が拘縮して、木彫りの植物人間になってしまうだろう。
自宅介護は大変だろうけど、管につながれて、あるいは点滴の針をさされたまま、ひとり淋しくベッドに横たわる母の姿は、想像しただけで胸が痛む。
あまりにかわいそう過ぎる。「楽」ができても、「幸せ」は味わえない気がする・・・
ということで、つづきはまたね~~ |
|
|
|
|
|
| 2016/11/9(水) |
 母が肺炎で入院している 母が肺炎で入院している |
|
母は現在、肺炎で調布病院に入院中である。
8月2日に、1週間だけ「刻み」の食事を試したあと、美味しい「粗刻み」にもどしてもらった話を書いた。
新潟から帰って母に会ったら、たった数日で別人のように痩せていた。みなさんに、「きれいなおばあちゃんね~」と言われていた面影はなく、皺だらけでヨボヨボの本物の「おばあさん」になっていた。
あまりの急激な痩せ方に、『もう長くないのかな・・・』と不安になった。食事を取れる回数が激減しているとのことだった。
うちの患者さんに話したら、「おとといお寿司を食べたんでしょ。だったら大丈夫よ。まったく食べられなくなっても、2週間ぐらいはもつんだから」と言われた。
つまり、2週間食べないと死んでしまうということだ。
好きなものなら、気合が入って食べるかもしれない。何でもいいから食べさせようと思った。栗とかアンドーナツとかを持って行ったり、回転寿司に連れて行ったり。
あんずやヨーコやピョン君も協力してくれ、確率は半々ぐらいだった。
先週の木曜日、朝から38.4度の熱があり、ゼロゼロしていたとのことで、ちょうふの里の看護婦さんが病院に連れて行ってくれた。
いつもの朝の家事を片づけ、いそいで病院に行った。私が昔、リハビリの仕事をしていた病院なので、ちょっと安心感がある。なにより近くて通いやすい。
診察室に入ると、中央においてあるストレッチャーの上に母がいて、点滴の細長い管に取り囲まれるようにして寝かされていた。昔ゾンビになったときのように、表情が欠落している。
診察をしてくれた若い男性医師は、休日なので非常勤だという。
コンピュータグラフィックスの肺の映像(すごい!)をもてあそぶように動かしながら、炎症部位はさほど大きくないし、CRP(C-リアクティブプロテイン)値=炎症反応の数値もそれほど高くないと説明してくれた。
酸素の必要はないでしょう。抗生物質と栄養の点滴をして、数日間は口からは食べないで様子を見る、とのことである。
「今後のことなんですけど、胃漏など、お考えですか?」と聞かれた。
母は6年前、新潟にいたときに、向精神薬で脳をやられ、たった1日で植物人間寸前になった。リハビリを重ね、いったんは不完全ながらも、歩いたり笑ったり喋ったりできるようになった。途中から徐々に徐々に落ちてきての今の状態なので、この先もレベルダウンしていくと思う・・・
胃漏をするつもりはないので、食べられなくなったら死んでしまう。「食べる」ことだけが唯一の楽しみだし、それがリハビリにもなっている。
「食べる」能力を落とさないように、なんとか早めに食べさせて欲しい・・・
そんな話をとても親身になって聞いてくれたんだけど、「自分は非常勤なので、担当医師からまた話があると思います」とのことだった。
このところ、筋肉の硬直がひどくて、ROM(range of mothion=関節可動域)訓練だけじゃなく、マッサージで念入りにほぐさなければならなくなっていた。
まるで「木」の身体。もう、あの世が近いのかな・・・と半ばあきらめの境地になっていた。
痰がからんで、ゼロゼロしているときが何回かあったので、すでに肺炎を患っていたのかもしれない。微熱があった日もあったし。食べる回数が減ったのも、激やせしたのも、感染症のせいだったのかもしれないね。
ホームの看護婦さんが、「お年寄りって、肺炎になっても熱も出ない、ゼロゼロもしない。気がついたときには、肺全体が真っ白で、もう手遅れということがよくあるんです」と教えてくれた。
「肺炎の程度もそんなにひどくないし、案外簡単に治って、すぐにホームに帰れるかもしれませんね」と言ってくれた。
とにかく今は正念場。全力を尽くさなくちゃならない。毎日、できるかぎり病院に行っている。
ホームなら、食事のたびに車椅子に乗ったりの動きがあるけど、病院ではベッドに寝たきりの状態である。放っておけば、関節の拘縮がみるみる進んで行く。直立不動の木彫りの人形のようになってしまったら、車椅子にも坐れなくなる。
私は、何もしないではいられない人間である。病人のそばに、「ただ黙ってじっと付き添う」なんてことは、至難の業だ。
できることがあるのは幸いである。
筋肉の硬直は半端じゃないのだが、きれいにほぐれていく。私の手技は古方按摩と指圧をミックスさせたものなんだけど、すごい効果があるみたい。
毎日やっているおかげもあって、顔色がみるみるよくなっていく。
入院当日はあんずも来てくれたし、日曜には弟も新潟から来てくれた。私もちょこちょこ行っているしで、なんだか、顔が幸せそうである。
『病気になると、みんなが心配して来てくれる』とか、内心、喜んでいるんじゃないだろうか?
私や家族のことを、まだちゃんと認知できているのは嬉しい。
短い単語のみであるが、自分の意思を言葉で伝えられる。焼きおにぎりを「ミソ」、食べたいものは「モンブラン」とか。弟が帰るときには、か細い声で「来週」と言ったので、笑ってしまった。
犬と同レベルの認知能力と思っていたけど、犬よりは上だったね~。
とりあえずの報告だけして、つづきは次回に書くね~~ |
|
|
|
|
|
| 2016/10/29(土) |
 ニックネームをつけて、自分のものにする ニックネームをつけて、自分のものにする |
|
右腕の故障でテニスを忘れちゃったので、はじめから覚え直しになった。おかげで、いろんなことが整理できたし、新しい発見もあった。
キーワードは「ニックネーム」。自分なりの言葉に置き換えることで、イメージングがしやすくなり、再現性の助けになる。
この数ヶ月、壁打ちにはまっていた。
自分なりに考えて、「こうかな?」と、とりあえず、えんえんと打つ。教わったことをもとに、私の習性である「独学」をはじめた、とも言える。
いろいろな人のアドバイスを、自分なりに組み合わせて、あれこれ試しているのである。
結果はいろいろで、吉と出ることもあれば、凶と出ることもある。正しい動きをモノにできることもあるし、間違って覚えてしまうこともある。
私のテニスの基本はCさんなので、ときどきチェックしてもらい、フォームを矯正してもらっている。そのおかげなのであるが、いつでもフォームを直せるという自信がついたので、間違いを恐れなくなった。
私って「プラスティック」みたいに可塑性があるらしい。すぐにゼロにもどるかわりに、細部をいくらでも修正できるみたいである。
テニスクラブに、昔、実業団にいたおじさんがいる。
私の練習を見て、「みづさんは、打つときに手首を伸ばしてますね。スライスもボレーも、手首は固定するんですよ」と、指摘してくれた。
えっ、やってなかったの?と驚いた。手首のコックのこと、すっかり忘れてた!
さっそく壁に行った。Cさんに「片手バックのスライスを打つときは、腕の形を変えずに打つ。『パーム・グリップ』と言うんだよ」と教わったことを思い出した。
スペイン語で "palma" は「手の平」の意味。たぶん、英語なら "palm" だろう。なるほど、「手の平」を意識して打てばいいんだと思いついた。
そしたら、手首を立てたままボレーとスライスが打てるようになった。
Cさんと話していて、実は、”palm grip" ではなく、”firm grip" だったことがわかった。向こうは「ファーム」と言い、私は「パーム」と言って、途中までお互いになんの違和感もなかったのである。(笑)
「手の平」じゃなく、「ファーム=固定して」打つという意味だったのである。
間違えて、かえって良かった。
手首を「固定」することを、打つときにはどうしても忘れてしまう。「固定」と知っていたら、できなかったと思う。「手の平」と思って練習したおかげで、やっと「手首をコックする」感覚が理解できたのである。
壁でスマッシュ練習をたくさんやった結果、最近、スマッシュが打てなくなってしまっていた。練習のやり方を間違えていたんだと思う。
打ち方を忘れてしまったのである。
水曜日の午前中、Dさんの練習会のとき、スマッシュの上手なおじさんが来ていて、特訓をしてくれた。
「身体を横向きに」「肩を入れて」と、何本も何十本もボールを上げてくれた。「もっと左肩を入れて」「もっと」「もっと」と、えんえんと直されつづけた。
自分の想像以上に、ボールから離れなければならなかったらしい。
「なるほど、三角をつくるのか!」と思いついた。
ネットに対して垂直に近いラインを引く。ボールを指差す左肩と、ラケットを振る右肩を底辺とすると、打点は三角形の頂点に来る。
ボールの真下に入ると、飛んでくるボールが「点」でしか見えない。横から入ると、ボールの軌道が「線」で見える。
こんなことはさんざん注意されつづけてきたことだけど、「文字」をたくさん頭に貼りつけておくのは限界がある。あちこちポロポロこぼれ落ちてしまう。
ニックネームをつけると「絵」になって、イメージしやすくなるのだ。
サーブのグリップは「4本指」、手首のコックは「パーム・グリップ」、スマッシュは「三角」と、ニックネームが3つになった。
他人の言葉じゃなく、「自分の言葉におきかえる」ことが、自分で理論体系化をするときのコツなのだと思う。
経絡治療の「脈診」を勉強中の頃、人を見れば「脈、診させて」と、患者さんだけじゃなく、あらゆる人を練習台にしまくった。
「恋わずらいの脈」とか、「気持ちもバリバリ、背中もバリバリの脈」とか、「ストレス溜まりまくりの脈」とか、「○○君の脈」とか、ニックネームをつけて分類した。
開業したての数年間は、「つながりぎっくり」とか、「○○ちゃん腰痛」とか、「まな板の背中」とか、いろいろなニックネームをつけていたなあ・・・
系統立てて分類すると、はじめての患者さんの治療に役立つのである。
クラシックバレエをやっている患者さんに、ニックネームの話をしたら、バレエにも、腕を上げる動作ひとつに、山のように注意事項があるんだって。
道は違えど、苦労はおなじだね~
腕を上げるが、肩は下げる。鎖骨は上に、肩甲骨は外に、肋骨の間は広げる。しかも、おへそを「縦」に!しなくちゃならないんだって。
すべてを意識することは難しい。どこかに注目すると、どこかを忘れる。でも流れにのってスムーズに、美しいポーズで踊らなくちゃならない。
彼女のつけたニックネームは、「天使の羽を広げるように」だって。
ニックネームの選び方が、さすがバレエ。美しいね~。(笑) |
|
|
|
|
|
|
| 2016/10/22(土) |
 テニスは身体に良かったらしい テニスは身体に良かったらしい |
|
105歳ミックスダブルスの10日後に、市民大会でのシングルスと、試合がつづいて、右腕はそうとう酷使されていたはずである。
興奮状態だったこともあって、自分でまったく予兆を感じていなかった。
前回は、あちこち予兆があった。簡単な治療とキネシオテーピング(つまり応急処置)でしのいでいたので、気づいたときには右腕全体がダメになっていた。
右肘をギュッと折り曲げるときに、ギクッと痛みが走ったのは、肘窩(①=肘の中央のくぼみ)の奥だった。
今回は外側、肘頭(②=肘のとんがり)からはじまった。
仕事をはじめてすぐに、肘をギュッと折り曲げるときに、肘頭の両側に、かすかな痛みが起こることに気がついた。カマヤミニなどしてみたけど、痛みはどんどん悪化していった。
前回のことがあったので、肩から指まで、あらゆる筋肉が疲弊しているんだろうなと想像した。時間を見つけては、次から次へと治療をした。
テニスはお休みしても、仕事も家事も右腕を使う。
物を持たなければ大丈夫なんだけど、右手でペットボトルのお茶を飲むときには、左手を添えなければならい。
筋肉に負荷をかけたときだけ痛みが出るのは、筋肉の障害という証拠である。
肩、肘、手首は構造が複雑である。複雑な動作を可能にするために、関節の中の小さな部位に、他方向からさまざまの筋肉が付着している。
なので、メインの障害を見つけるのに時間がかかることがある。
患部を無意識にかばうので、周囲の筋肉たちが次々と無理をする。障害が連鎖反応的に広がっていき、どこが悪いのか見分けにくくなる。
あとから悪くなったところから先に治っていくので、最後の最後に残ったところが、「メインの患部」だったと判明するのである。
3日ぐらいたって、痛めたのは上腕三頭筋ということがはっきりした。はじめに痛みを感じた筋肉だから、当たり前といえば当たり前。
前回のことがあったから、必要以上にビビッてしまった。すべてがダメになっていたわけじゃなかったのである。
日中は、肘頭をはさんで両側に、細いテーピングをした。お灸の痕をよけられるし、かぶれ予防にもなる。
いつもの2.5センチ幅のキネシオを半分にカットして、10センチぐらいの長さで貼るんだけど、動かすのが楽になる。細くても効果はあるんだよ。
深いハリも打ち、透熱灸もやり、経絡治療もやって、治ったのは5日後だった。
| ○ =ギクッと痛みが出た部位 |
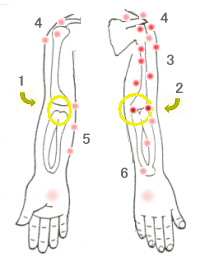 |
| ① |
前回=肘窩 |
| ② |
今回=肘頭まわり(上腕三頭筋の停止部) |
| メインに痛めた筋肉 |
| ③ |
サーブとスマッシュで(上腕三頭筋) |
| 疲労が蓄積していた筋肉 |
| ④ |
肩の疲労(棘上筋と三角筋) |
| ⑤ |
スライスで(尺側手根屈筋) |
| ⑥ |
フラットドライブで(総指伸筋) |
③の上腕三頭筋は、サーブとスマッシュで、ラケットを下から上へ振り上げて打つときに使う筋肉である。肩の外側&後面から肘頭にくっついている。
上から打てば、④の棘上筋や三角筋など、肩全体の筋肉を使う。
⑤の尺側手根屈筋は、スライスの練習で疲弊し、⑥の総指伸筋は、フォアの新しいうち方を教わったためである。
不具合が生じた部位から、酷使した筋肉が分かる。正しいフォームで打てていたんだね。
筋疲労を取って、このまま練習をつづけていけば、だんだん筋力がパワーアップしていく。ある意味、明るい兆しでもある。
テニスができなくなって、逆に、なんだかホッとしている自分を発見した。
分刻みの生活、プレッシャー、ストイックな練習で、肉体以上に精神的に疲れていたらしい。
温泉に行ったり、たまった雑用をこなしたり、予定をたくさん入れてしまった。思いのほか早く治ったのだが、仕事も忙しかったし、雨も降ったしで、9日間もテニスを休むことになった。
そしたら、仕事中に腰痛を感じた・・・?
そうそう、昔はこのタイプの腰痛に悩まされていたなあ、と懐かしく思い出した。
鍼灸師は、実は、「腰痛」とお友だちである。ベッドの上の患者さんにハリを打つとき、前傾姿勢になるからである。
忘れていた、前傾姿勢での腰痛を久しぶりに味わった。
しょっちゅう「腰痛」を話題にしていたのに、何故?と不思議に思われるかもしれないけど、ここ数年は、テニスのやりすぎによる「腰痛」に悩んでいたのである。
腰の回転や、全力疾走、ジャンプなど、筋力不足なのに無理をしつづけたから、次から次へと、腰やでん部のあらゆるタイプのぎっくり腰になった。
テニスに必要な筋肉がついたので、簡単なメンテナンスで、このところずっと、腰の不安から解放されていたのに・・・
テニスをやらないと、仕事由来の腰痛が起こる!
これは、大発見だった。
同じ動きだけしていると、同じところにだけ負荷がかかる。異なる動きをするときは、それらの筋肉は、休みながらゆるやかに動く。血の巡りがよくなって、疲労物質が流れていく。
やっぱり、いろんな動きを組み合わせるのが、元気の秘訣だね。
復活してみたら、すっかりテニスを忘れてしまっていた。思い出すのに1週間以上もかかってしまった。
こんなに簡単に忘れるなんて、まだまだ「付け焼刃」、まだまだ素人なんだね~ |
|
|
|
|
|
日記  TOP TOP |
|
|
|
|
前の日付へさかのぼる |
|

