|
症例66・腹痛、渋り腹、胸脇苦満
|
|
|
<飲食だけでなく「心」も影響する>
|
|
 押せないとき(筋性防御)はお灸はNG 押せないとき(筋性防御)はお灸はNG |
|
大昔、開業前のことですが、腹痛の友人に呼ばれて治療に行きました。腹部の圧痛点を探そうとしたら、お腹に触れただけで「痛い!」と叫ぶのです。これは「筋性防御」と思いました。
「盲腸かもしれないよ」と治療を中断し、病院に行くことをすすめました。そのまま入院になって盲腸の手術をしたそうです。
「筋性防御」は腹腔内の炎症が激しいときにおこります。炎症部位を守ろうとして反射的に筋肉が硬くなるのです。お灸で患部を温めると炎症が増悪する恐れがあり、鍼も病原菌を運ぶ恐れありなので、治療は危険です。
「筋性防御」のあった患者さんは彼女ひとりだけでした。お腹を押せるときは治療ができます。 |
|
 お腹も考える=独立した神経細胞がある お腹も考える=独立した神経細胞がある |
|
なんと、腸間膜には脳細胞と同じ神経細胞が分布しています。つまり、腸も考える力を持っているのです。独自の思考パターンを持っているだけでなく、感情も持っています。
古来からいろんな言い回しがありますよね。
失恋や心配事で「食べ物が喉を通らなく」なったりします。
怒りを感じると「腹を立て」るし、イライラが残ると「腹の虫がおさまらない」となります。
覚悟を決めたときは「腹を据える」「腹をくくる」と言います。
心の底から納得したときは「腑に落ちる」と言い、危険に驚くときは「肝を冷やす」と言い、大喜びするときは「腹の底から」笑ったりします。 |
|
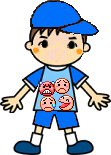 |
症例20「胃炎&胃潰瘍」で紹介しましたが、漢方の五行では、「考え(智)すぎると胃を破る」と言われています。「怒りすぎると肝を破る」「恐れすぎると腎を破る」「喜びすぎると心を破る」「悲しみすぎると肺を破る」というように、激しすぎる感情が臓器を侵害するとのことです。
症例10「風邪・3」で紹介した病因論では、「内因」は心の変動、「外因」は気候の変動、それ以外のすべて、ウィルスや細菌などの病原菌や暴飲暴食などは「不内外因」とされています。病気の一番の誘因は「心」にあるのです。 |
|
 鍼で「気」を動かして、腸を動かす 鍼で「気」を動かして、腸を動かす |
|
胃腸の状態は「心」にもろに影響されます。
仕事などでストレスがかかって緊張状態がつづくと、お腹が固まって腸が動かなくなってしまいます。ツボを取るために患者さんの手足に触れただけで、お腹がグルグルと音を立てて動き出すことがあります。患者さんは恥ずかしがりますが、「腸が動く」のはいい兆候なのです。
鍼は「てこの原理」で気を動かすことができます。皮下に0.5ミリの浅い鍼で経絡治療をするのですが、全身に「気」が巡って、身体がポカポカ温まります。ちょっとした不具合はこれで解消されます。
身体のどこかの硬直でお腹が固まることもあります。そこで「気」の流れが滞るのです。硬直をほぐすと淀んだ血液が押し流されて、新鮮な気血が巡ります。
細い鍼を直接腹膜に当ててグリグリ刺激する手技もあります。けっこう痛いのでめったにやりませんが、お腹がふっくら柔らかくなります。 |
|
 腹部へのカマヤミニが簡単で効果的 腹部へのカマヤミニが簡単で効果的 |
|
たいていの腹痛は「冷え」と関連があって、お灸で直接患部を温めると即効性があります。お灸にはいろいろな手技があるのですが、カマヤミニは広範囲を温めることができ、自分でも簡単にできます。
基本のツボは4つ。おへそを中心に十字を描いて、上下左右に1個ずつです。
メンテナンスに来ている患者さんが、「昨日お腹の具合が悪かった」とか「なんとなくスッキリしない」とか言った場合には、ついでにカマヤミニをします。
たいていはそれでOKなのですが、追加のお灸をするときは圧痛点を探します。お腹を指でグイーッと押して、痛いところがツボです。 |
|
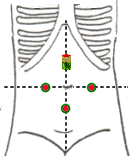 |
便秘がちだった中学生の女の子がいました。「出ない」ときに使ったツボもこの4つです。お母さんにカマヤミニをしてもらうと、すぐに出てくれたそうです。しばらくつづけたら、そのまま便秘とは縁が切れたそうです。 |
|
 ウーロン茶で胃を壊したとき ウーロン茶で胃を壊したとき |
|
うちではつねに冷蔵庫に「麦茶」を入れてあります。浄水器でろ過した水をやかんで煮出して冷やしたものです。夏場だけでなく1年中で、テニスのときにも持ち歩いています。
30代から50代のおよそ20年間、うちの「麦茶」がウーロン茶だった時代がありました。他のお茶では物足りなくなってしまったのです。後にカフェインの量が格段に多いと知りました。一種の「カフェイン中毒」だったのでしょう。
胃腸の不具合がはじまり、しょっちゅう腹痛に悩まされるようになりました。食べられる量がだんだん減っていき、1人前が食べられなくなりました。飲み会のあとは1週間以上も不調がつづきました。体重もどんどん減っていき、まるでスティーブン・キングの「痩せゆく男」のようでした。
頻度が増していく腹痛への、試行錯誤の治療をくり返したおかげで、いろんな治療法を発見できたという次第です。
55歳のときにウーロン茶が腹痛の原因と気づき<ブログ→2011/8/31>、そこから順調に回復していきました。現在はハト麦、ドクダミ、ビワ葉などをブレンドしたお茶を飲んでいます。1.5人前ぐらいは平気になって、好きなだけ食べられる幸せを謳歌しています。 |
|
 下痢はそんなに悪くない 下痢はそんなに悪くない
|
|
人体を縦長のドーナツとすると、真ん中の穴の部分、口から肛門までの消化器官の内側は「体外」です。食物=異種タンパクと、外界に棲むあまたの雑菌が通り抜ける通路( )なのです。 )なのです。
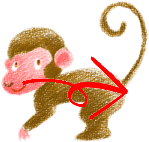 |
|
異種タンパクをそのまま体内(■)に取り入れると死んでしまいます。
噛み砕き、揉み砕き、消化液をかけながら食物を分解しています。
必要な栄養素だけを吸収し、残りは排泄します。 |
|
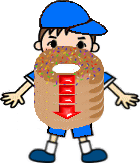 |
食べ過ぎたとき、大腸菌O157やノロウィルスなどの病原菌が繁殖したときは、下痢や嘔吐で一気に体外に押し出そうとします。
下痢は自然治癒力の発動です。失われる水分を補給しなくてはなりませんが、病原菌を出し切ったほうが早く治ります。お腹が痛いのに腸が動いてくれない「渋り腹」のほうが問題です。 |
|
 激しい腹痛、渋り腹へのカマヤミニ 激しい腹痛、渋り腹へのカマヤミニ
|
|
ウーロン茶で胃を壊していた時代は、腹痛のたびにマヤミニをやりました。とりあえず痛みが消えるのです。
歩けなくなるほどの激しい痛みのときは、時間をかけて何十個もやりました。4個ぐらいずつお腹にのせて火をつけ、終わったら次の4個と、症状が緩和されるまでくり返します。
| ① |
|
まずは上述の基本のツボです。 |
| ② |
|
おへその際。「冷え」なのか?細菌やウィルスの巣なのか?おへその下に頑固な塊があって、くり返し狙い撃ちしたこともあります。(禁灸穴なのでおへその上にはやりません) |
| ③ |
|
胃下垂だと、胃がだらりと垂れ下がって下腹部まで広がります。 |
| ④ |
|
次から次へと圧痛点を探します。 |
「渋り腹」を経験したこともあります。お昼にバイキングのタイ料理をたらふく食べました。夕方にワインを飲みながらチーズ入りのパンを食べている途中で、異変に気づきました。痛くて痛くてたまらなくて、下痢で出したいのに、お腹が鉛みたいに固まっていて動いてくれないのです。
30分以上かけてお腹のカマヤミニをくり返したら、腸が動きはじめました。一気に下痢になって、そのあとはすっきり楽になりました。 |
|
|
|
|
思春期の女の子はあらゆることに悩んでしまいます。とくに対人関係が難しく、問題があると原因不明の腹痛を起こすことがあります。「心のボタンのかけ違い」ですね。何人も治療しましたが、みなさん1回で治ってくれました。
1998年11月に来院したSさん(当時14歳、女性)は中学生からの不登校で、引きこもりの状態でした。前日の朝「お腹が10分おきにギューギュー痛んだ」そうです。救急車を呼びましたが、病院では異常なしでした。
精神的な問題らしい・・・と、お母さんが連れてきたのです。
Sさんの後頚部(■)はゴリゴリに硬直していて、熱を持っていました。「上実下虚」です。気が頭に上がって滞り、下半身の気が不足する状態です。
精神的に煮詰まって気の巡りが悪くなった状態なので、浅い鍼で気の流れを促し、経絡のバランスを調整します。
ときどきのお腹(■)の痛みと、頭重感(■)にも悩まされていました。 腰痛は志室(■)が中心です。 |
|
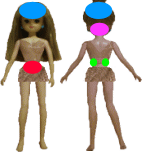 |
初回はいつもの腹痛、腰痛、首肩こりがありました。浅い鍼で気のバランスを調整したあとで、首には糸状灸、腰の志室には透熱灸を7壮(灸点紙を2枚重ねで熱を和らげる)し、最後に背骨の矯正の磁石を張りました。首が回りやすくなったそうです。
腹痛とはそのまま縁が切れて、主訴は腰痛になりました。Sさんは深い鍼を怖がったので、お灸を組み合わせて治療しました。
1年半後(7回目)、セツ・モード・セミナーへの入学直前、また腹痛で来院しました。新生活への不安が原因でしょう。このときも1回で治りました。
新生活に順応する過程で、腰痛、首肩こり、寝違え、頭痛、捻挫など、いろいろな愁訴に見舞われ、ときどき来院しました。
初診から4年後(26回目)、フランス留学に旅立つ前日、風邪を引いて熱もあるとのことで、自宅に赴いて治療したのが最後になりました。 |
|
 胸脇苦満 胸脇苦満 |
|
2001年6月に来院したMさん(当時31歳、男性)は大手企業の研究員で、電通大教授との共同研究のために2年ぐらい調布に住んでいたときのことです。
「胸脇苦満」がありました。 右の肋骨の下方(■)硬直があり、「風邪を引いたり、体調が悪くなると、右の肋骨あたりが突っ張る感じがする」とのことで、つねに圧迫感があるそうです。
同僚で精神を病んでいる友人がいて、彼のことが心配になると圧迫感が強まるそうです。
新しい仕事に付き、研究成果を上げなくてはならないプレッシャーも関係していると思います。 |
|
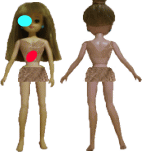 |
睡眠不足が日常でした。風邪を引きやすく、治ったと思ってもまた引いてしまうそうです。20代の頃の私もそんな感じで、当時は「慢性風邪症候群」と呼ばれていたと思います。<→風邪2「年中風邪を引いている人」>
右目(■)の視力低下もあって、「遠いところが眼鏡で矯正できない。視神経が委縮している」と言われたそうです。
初回、腹部全体が硬かったので糸状灸をたくさんやりました。大椎に金粒(=風邪予防)、右耳の目ポイントに銀粒(=見えやすくなる)を貼りました。
1週間後(2回目)、前回隠れていた肩や腰のこりが出てきました。「少しはいいが、まだ風邪っぽい」とのことで、商陽から邪気を抜きました。
<→症例10「風邪 new1(2020)」は治療マニュアルです>
2週間後(3回目)、風邪が治り、胸脇苦満が一番の愁訴になりました。透熱灸( )をはじめ、その後も硬直部位を選んで、ほとんど毎回やりました。 )をはじめ、その後も硬直部位を選んで、ほとんど毎回やりました。
風邪とはほぼ無縁になって、主訴は右目と腰痛、首肩こりになりました。
8カ月後(26回目)、資料整理のために重いダンボール箱を持ち上げてぎっくり腰になりましたが、すぐに治って、翌日の研究発表を無事にこなすことができました。 |
|
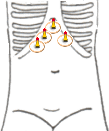 |
|
|
 小さな子どもは「手当て」で治療 小さな子どもは「手当て」で治療
|
|
「手当て」という言葉がありますが、「手」は癒す力を持っています。「手」を介してお互いの潜在意識が交流し、必要としている治療が分かるのです。
患部が冷えているときは手が温かくなり、炎症のため熱を持っているときは手が冷たくなります。
保育士をしていたとき、園児に「お腹が痛い」と訴えられることがありました。子どもは難しい。ほんとうにお腹が痛いのか、注目されたい甘えたい気持ちなのか、判断するのが難しいのです。
そういうときはまず「手当て」です。園児のお腹にしばらく手を当ててあげると、元気に駆けだしていって遊びに加わるという経験を何度もしました。
バイクの事故で骨折した友人のお見舞いに行ったときのことです。術後の患部がパンパンに腫れてむくんでいました。むくみがあると血流が滞って治りが遅くなります。患部に手を当てていたら、私の手がどんどん冷たくなっていき、熱を奪って炎症を鎮めようとしたのです。
不思議な現象ですが、安全で確実です。小さな子どもや口のきけない犬には、とりあえずの「手当て」を試してみましょう。 |
|
 銀粒で奇形治療、金粒で局所治療 銀粒で奇形治療、金粒で局所治療 |
|
4000年以上前、古代中国には気の流れが見える人間がいたらしいのです。その人が描いた「経絡図」が現在も使われていて、それをもとに臨床を積み重ねた集大成が現在も鍼灸治療を支えています。
古代ギリシャには、天体望遠鏡が発明される前に、肉眼で天体の星を正確にスケッチした人間もいたそうです。(たぶん紀元前190年頃の、古代ギリシャのヒッパルコスと思います)
人類にはときどきとてつもない能力を持つ個人が出現するのです。
生命エネルギーである「気」が「経絡」という道筋を流れ、そこには「経穴」というツボが約365個も点在しています。
主な経絡は「督脈」「任脈」と「十二正経」です。<→つぼ&経絡の流注>
他にも経穴と経穴をつなぐいろいろな路線があり、4種類ある「奇経」はそのひとつです。2つのツボをセットで使います。
| ① |
内関(心包経)と公孫(脾経) |
上腹部の病 |
胃の痛みや吐き気、車酔い |
| ② |
列缺(肺経)と照海(腎経) |
下腹部の病 |
腹痛、下痢 |
| ③ |
外関(三焦経)と臨泣(胆経) |
側脇部の病 |
側方の肩こり |
| ④ |
後谿(心経)と申脈(膀胱経) |
後部の病 |
後頭部痛 |
症例20「胃炎&胃潰瘍」で紹介しましたが、奇経を利用して、金粒と銀粒を使って自分で治療することができます。
腹痛に効果があるのは、①内関+公孫(上腹部の病)、②列缺+照海(下腹部の病)で、セットで銀粒を貼ります。
お腹の圧痛点に手当たり次第に金粒を貼るのも効果的です。
|
|
 |
|
|

