|
症例44・手首痛 new 1 (2022)
|
|
|
<手首の痛み、捻挫と腱鞘炎>
|
|
 手首を通過する腱と、つながる筋肉を治療する 手首を通過する腱と、つながる筋肉を治療する
|
|
ひとりで小さな鍼灸室をやっているので、手首痛が主訴でくる患者さんはめったにいません。その都度、解剖学の本を開いて治療してきました。
最近イラスト作りをはじめました。イラストがあると理解しやすいし、自分の覚書にもなるので、2012年に更新したページを10年ぶりに改訂しました。
(イラストは右手。私が作成したものなので、おおよその目安にしてください)
手首ってとても細いですよね。赤ちゃんの手首なんて、「まるで輪ゴムをはめたみたい」にくっきりとくびれています。
皮膚の下はすぐ骨です。骨と靭帯の間にちょこっと姿を見せるのは、腱鞘に包まれた「腱」なので、浅い鍼とお灸しかできません。筋肉には血管が通っているので、治療のあとも血流が患部を治してくれますが、腱には血管がないので効果が持続しません。
小さな関節なのに構造が複雑で、たくさんの筋肉が縦横に走っています。治療できる部位が限られているので「壊して」しまうととてもやっかいです。
「腱」の治療で治らない場合は、つながっている筋肉も同時に治療しなければなりません。筋肉の硬直が原因で、結果として関節を痛めてしまった・・・という例も少なくありません。
骨や関節の「形」は、支えている筋肉たちによって作られています。
手首が「壊れて」しまっても、関節を支えている筋肉たちの硬直をほぐして治療します。筋肉がほぐれれば、柔らかいクッションのように障害部位を守ってくれ、自然に治癒に向かっていきます。
筋肉は骨と骨(もしくは筋膜など)をつないで、縮むことで働きます。関節のどこかに故障があると、筋肉はギプスのように固めて患部を守ろうとします。硬直すると縮んで患部を引っぱるので、ますます悪化してしまいます。
手首につながる筋肉たちはみんなで共同運動をしています。筋肉がひとつでも硬直すると、他の筋肉たちも次々に硬直していきます。手首全体がガタついてしまったり、手関節の歪みが肘や肩、そして全身へと波及することもあります。
関節と筋肉の構造を参考にして、硬直部位を触診で探して治療しましょう。
前腕の骨は2本ありますが、親指側の橈骨(■)と手根骨が関節して「手首=手関節」を形成しています。手根骨からは手の平をつくる中手骨がつながり、指の骨へとつながっています。
小指側の尺骨(■)は、手首では横にくっつく脇役ですが、肘関節では上腕骨と関節する主役です。手首と肘で互い違いにくっつくことで、複雑な動作ができるのです。
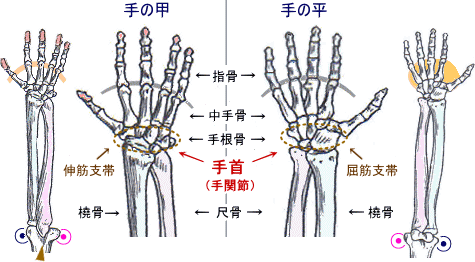 |
| ■橈骨 |
|
■尺骨 |
|
▲肘頭 |
|
 上腕骨外果 上腕骨外果 |
|
 上腕骨内果 上腕骨内果 |
|
■手の平 |
|
手の根元にある手根骨はサイコロ状の8個の小骨の集まりで、互いに靭帯で固定され、手の平側は凹、甲側は凸のアーチ型をしています。
平側の凹をおおう「屈筋支帯」と、甲側の凸をおおう「伸筋支帯」は、幅2~3センチの帯状の靭帯で、下を前腕からの筋肉が「腱」になって通り抜けています。 |
 |
 手首にある経穴(ツボ)と、手首を通る腱 手首にある経穴(ツボ)と、手首を通る腱 |
|
メンテナスもしくは他の主訴で来ている患者さんが「手首も痛い」と訴えるときには、全身治療のときに、手首の経穴(ツボ)に浅い鍼を置鍼します。
仰向けでは手の平側(①②③)に、うつ伏せでは手の甲側(④⑤⑥)に、症状に応じて1本、もしくは6ヶ所すべてに打つこともあります。
軽い手首痛はたいていそれだけで治るのですが、もしも痛みが残ったら、灸点紙をしいて透熱灸をしてみましょう。 |
|
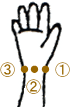 |
手の平側=陰経 |
| ① |
太淵 |
手の太陰肺経 |
| ② |
大陵 |
手の厥陰心包経 |
| ③ |
神門 |
手の少陰心経 |
|
|
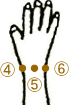 |
手の甲側=陽経 |
| ④ |
陽谿 |
手の陽明大腸経 |
| ⑤ |
陽池 |
手の少陽三焦経 |
| ⑥ |
暘谷 |
手の太陽小腸経 |
|
下の図は手首を通る腱の位置と、手首のツボの位置を対比させたものです。ツボは毎回動くので、触診で探しましょう。
(左の図は橈骨と尺骨を下端の近くで切断したものです)
患部への浅い鍼とお灸で治らない場合は、腱につながる筋肉の硬直をほぐして、関節への圧を取り除きます。手首全体がガタついてしまったときは、ひとつひとつの筋肉を丁寧に治療をしましょう。
もっともこじらせやすく治しにくいのは尺側(小指側)の手首痛ですが、本命は最後に登場します。
それぞれの筋肉のつながりと働きを順に解説していきます。 |
|
 手首の内側は腱鞘炎にも注意 手首の内側は腱鞘炎にも注意 |
|
手首の内側をおおう屈筋支帯の下には(長掌筋以外の)前腕からの屈筋が腱になって通り抜けています。
手の平を上に向けて手首を見てください。指を広げて手掌を少し屈曲させると、手首のすぐ下、中央に2本の腱が並んで突出します。外側にあるのは橈側手根屈筋(■)で、内側にあるのは長掌筋(■)です。
小指側(尺側)で突出するのは尺側手根屈筋(■)です。
この三筋は、手首を曲げる(掌屈)ときの主要な筋肉で、甲側の伸筋と同時に働くと手根を固定します。
| 手首前面の腱 |
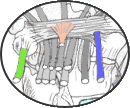 |
| <拡大図> |
|
→ |
| 尺側手根屈筋 |
 |
| 屈曲+内転 |
|
|
| 長掌筋 |
 |
| 屈曲 |
|
|
| 橈側手根屈筋 |
 |
| 屈曲+外転 |
|
長掌筋(■)は屈筋支帯の外側を通って、手根の靭帯にくっつき、手掌で扇形に広がって「手掌腱膜」となっています。手の平の皮膚をつまみあげることができないのはそのせいですが、手の把握力を高めるのに役立っています。
長掌筋(■)、橈側手根屈筋(■)、尺側手根屈筋(■)と浅指屈筋(■)は上腕骨内側上顆( )で共同腱になっています。連動して硬直するので、こじらせるとほぐすのが大変です。 )で共同腱になっています。連動して硬直するので、こじらせるとほぐすのが大変です。
手首の内側は頑丈にできているらしく、ここがメインの手首痛の患者さんはいませんでした。ここでは腱鞘炎による痛みが問題になります。
手首を通る腱は「腱鞘」に包まれていて、トンネルの中を滑るように、円滑に動くことができます。腱や腱鞘が炎症をおこして肥厚すると、「腱鞘炎」になることがあります。
「指が痛くて曲げられない」場合は腱鞘炎の治療をしましょう。
| 「手根管」 |
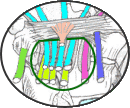 |
正中神経を
圧迫する腱 |
|
→ |
| 浅指屈筋 |
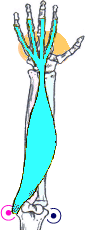 |
| 4指屈曲 |
|
|
| 深指屈筋 |
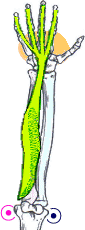 |
| 屈曲 |
|
|
| 長母指屈筋 |
 |
| 母指屈曲 |
|
手根管症候群も要注意です。手根骨の凹と屈筋支帯との間の「手根管」には、9本の屈筋腱と一緒に正中神経と血管が通り抜けています。腱鞘炎によって正中神経が圧迫されると、神経障害をおこしてしまいます。「痺れ」などの神経症状があったら正中神経の治療もしましょう。
<詳細は→「症例46:手根管症候群」をご覧ください> |
|
 手首の甲側におこりやすい障害 手首の甲側におこりやすい障害 |
|
手首の甲側には伸筋支帯があります。
6つの区画(腱区画)に分かれ、各区画を腱鞘に包まれた伸筋腱が通ります。
ここを主訴で来院した患者さんはいませんので、けっこう頑丈なようです。 |
|
| 伸筋支帯の下を通る腱 |
 |
→ |
<拡大図> |
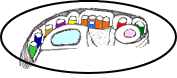 |
|
|
デ・ケルバイン病(ケルバン病、デ・ケルバン病)は、親指の近くのでっぱり(橈骨茎状突起)付近におこる狭窄性腱鞘炎です。
母指を過度に使うことが原因です。
伸筋支帯の最外側の区画を通ります。 |
| 長母指外転筋 |
 |
|
|
| 短母指伸筋 |
 |
|
|
|
| ■ |
長母指外転筋 |
母指と手関節の外転 |
| ■ |
短母指伸筋 |
母指の伸展 |
|
| テニス肘をおこす筋肉も要注意です。テニス肘→手首痛、または手首痛→テニス肘と、後遺症に悩まされることがあります。 |
|
|
|
|
上腕骨外側上顆( )で共同腱になっているので、こじらせやすく治しにくい筋肉たちです。 )で共同腱になっているので、こじらせやすく治しにくい筋肉たちです。
<詳細は→「症例42:テニス肘」をご覧ください> |
| ↓ |
|
|
| 短橈側手根伸筋 |
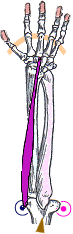 |
|
|
| (総)指伸筋 |
 |
|
|
| 小指伸筋 |
 |
|
|
| 尺側手根伸筋 |
 |
|
| ■ |
短橈側手根伸筋 |
手関節の伸展、撓屈 |
| ■ |
(総)指伸筋 |
4指の伸展、手首伸展の補助 |
| ■ |
小指伸筋 |
小指の伸展(おかげで単独で上げられます) |
| ■ |
尺側手根伸筋 |
手関節の伸展、尺屈 |
その他の筋肉です。
|
|
| 長橈側手根伸筋 |
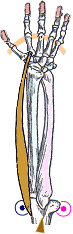 |
|
|
| 長母指伸筋 |
 |
|
|
| 示指伸筋 |
 |
|
|
|
→ |
| ■ |
長橈側手根伸筋 |
手関節の伸展、撓屈 |
| ■ |
長母指伸筋 |
母指の伸展 |
| ■ |
示指伸筋 |
示指の伸展(おかげで単独で上げられます) |
|
|
|
|
|
手首痛が主訴で来院した患者さんは数人ですが、みなさんが尺側(小指側)に強い痛みがありました。上述した筋肉ですが、あらためて見てみましょう。
| 手の甲 |
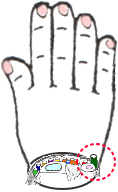 |
| ■尺側手根伸筋の腱 |
|
→ |
| 双方の腱が・・・ |
 |
尺骨をはさんで
前後に並ぶ |
|
← |
| 手の平 |
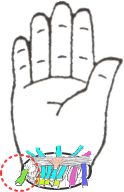 |
| ■尺側手根屈筋の腱 |
|
| ■尺側手根伸筋 |
| 手の甲側:伸筋支帯の内側 |
| 起始 |
上腕骨の外果( )の伸筋の共同腱(総伸筋腱) )の伸筋の共同腱(総伸筋腱) |
| 停止 |
第5中手骨底 |
| 作用 |
手関節の伸展、尺屈 |
|
|
| ■尺側手根屈筋 |
| 手の平側:屈筋支帯の内側 |
| 起始 |
上腕骨の内果( )の屈筋の共同腱 )の屈筋の共同腱 |
| 停止 |
豆状骨、第5中手骨底 |
| 作用 |
手関節の屈曲、尺屈の補助、肘関節屈曲の補助 |
|
どちらの筋肉も上腕骨の付着部位(  )で、共同腱になっているので、連動する他の筋肉たちと硬直の連鎖反応をおこします。そのうえ尺骨をはさんで、双方が骨に張りつくように固まってしまいます。 )で、共同腱になっているので、連動する他の筋肉たちと硬直の連鎖反応をおこします。そのうえ尺骨をはさんで、双方が骨に張りつくように固まってしまいます。
こじらせると治しにくいのは、この構造が原因と思います。
2004年11月に来院したHさん(当時46歳、男性)は、右手首の尺側(■■)に痛みがありました。「10年前からずっと痛かった部位を、2週間ほど前に、再度痛めた」とのことでした。転んだ拍子に、思いっきり手を突いてしまったそうです。
Hさんには疲労、首・肩こり、花粉症もありました。経絡治療などの全身治療も不可欠です。置鍼のときには手首にある6つのツボに浅い鍼を打ちました。
仰向けのときは、尺側手根屈筋(■)に、うつ伏せでは尺側手根伸筋(■)にずらりと鍼を並べて打ちました。
筋肉の硬直をほぐして患部への圧を減らします。
圧痛が残ったポイントに灸点紙を敷いて透熱灸をしたあと、反対側治療として、左足肝経(中封など)に銀粒を貼りました。
主訴の手首痛は、数回の治療でみるみる良くなり、10年間あきらめていたバイオリンが、また弾けるようになったと喜んでいました。
捻挫は、ちゃんと治療をしないとクセになってしまうことがよくありますが、再発したおかげできれいに治すことができました。 |
|
 痛みが消えても、再構築完了まで待つ 痛みが消えても、再構築完了まで待つ |
|
私の手首痛の症例です。
2009年の春に突然テニスにハマり、テニスクラブに入会しましたが、一気にやりすぎてテニス肘になってしまいました。とことんこじらせて、ほとんど1年間もテニスを休むことになりました。
再開して2ヶ月後、またまた一気にやりすぎて、右手首を痛めてしまいました。ラケットを握ることもできません。それまでは痛めても簡単に治ったのですが、テニス肘で過負荷がかかった後遺症で、かなりの重症でした。
テニス肘でこりたので、完全に治るまでは・・・と左手で壁打ちをしました。3ヶ月後、そろそろ右手でテニスを・・・と思ったところで母が植物状態寸前になり、テニスどころではなくなりました。
テニスクラブにちょくちょく行けるようになったのは、2011年の夏からです。またまた一気にやりすぎて、半年ぐらいで右手首の痛みがぶり返しました。
ラケットを握ることはできたので、騙し騙しテニスをつづけました。自己流スライスを試すなど、変な打ち方をしてあちこちに過負荷がかかったのでしょう。数か月後、治ったとたんに右肩の痛みが出現し、そのうちまた手首に・・・と、右腕の受難の日々が半年以上もつづきました。
その後もときどき手首のガタツキ感があったのですが、とくに治療の必要もなく、ふわふわのウォーマーを手首に巻いて寝るだけで、翌朝にはすっかりガタつきが消えてくれました。
筋肉が順調に育ってくれ、関節も頑丈になったので、「温める」だけでOKになったのです。
2017年の冬、ペットショップで売れ残っていたチワワを見つけました。『殺処分されるのかな・・・』と、心配でたまらなくなりました。それまで何ともなかったのに、ある夜、いきなり激しい手首痛に襲われました。
次の日、壁打ちで試してみたら、ラケットを握った瞬間に、手首にグキッと激痛が走るのです。テニスはあきらめて治療室に直行し、何時間もかけて前腕のすべての筋肉に鍼を打ちまくりました。
そのまま痛みが消えてくれたのですが、どうやら「ティラを飼え」という神様の思し召しだったようです。(私のブログ→2017/2/8)
翌日、ラケットを握っても手首は大丈夫でした。でも、もう「1日」テニスを休むことにしました。手首はまだ「工事中」かもしれません。まだ固まっていない関節に強い衝撃をかけると、壊れてしまうかもしれません。治りかけに無理をするとこじらせてしまうので、危険をさけて「1日」休むほうを選びました。何度もドツボにハマったので、さすがの私も学んだのです。
その用心が功を奏して、翌々日には普通にテニスができ、それ以来手首痛の再発はありません。 |
|
 (テニスの)スライスは尺側の筋肉を酷使する (テニスの)スライスは尺側の筋肉を酷使する
|
|
2013年に右ふくらはぎの肉離れで来院したCさん(当時49歳、男性)は、その後は隔週でメンテナンスに訪れるようになりました。筋繊維の一部が石灰化を起こしているらしく、そこから硬直がはじまり、ふくらはぎ全体に波及してガチンガチンになってしまうのです。
2016年12月(53歳)、右手首の痛みがおこりました。「打つときに右手首が痛い」とのことで、ときどき右肘にも痛みがおこりました。どちらも尺側です。
4回の治療で痛みがおさまったあと、右膝が痛み、治ったとたんに1ヶ月後にまた右手首の痛みが戻ってしまいました。
クラブ会員に整骨院を営む鍼灸師がいたのですが、彼に「球出しのやりすぎ。コーチの職業病だよ」と指摘されたそうです。
「球出し」とは、コーチが連続でボールを送って生徒に打たせる指導法です。
スライス気味にゆるく回転をかけながら送るので、肘と手首の尺側に過負荷がかかり、尺側手根屈筋(■)を酷使します。ラケットをギュッと握るときには裏側にある尺側手根伸筋(■)が同時に収縮します。
双方の筋肉が手首の付着部(←)を異なる方向に引っぱるのです。
| スライスは・・・ |
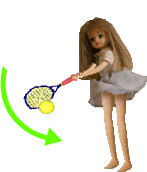 |
ラケットの軌道は上から下
ボールを後から前へ送る |
|
→ |
| 連続で行うと・・・ |
 |
| 尺側手根屈筋を酷使 |
|
→ |
|
Cさんは週に6日テニスをする怒涛のテニスジャンキーで、自分自身がアスリートであるだけでなく、教えるのも大好きです。週に1回のサークルの他、テニスクラブに(私も含めて)4人ぐらい弟子がいて、それぞれ個別に教えていました。
「手首が治るまでは別々に教えずに合同レッスンにしたら?」と提案しました。みんなで交代に球出しをすればCさんの負担が減りますし、弟子同士でラリーをさせれば、打つ人のそばで教えることもできます。
でもCさんは「それぞれがレベルも違うし、教える内容も違うから」と、自分のポリシーを曲げません。
テニスはやれていたのですが、右手首痛は一進一退でした。
スライスの多発は尺側手根屈筋(■)と尺側手根伸筋(■)に過負荷がかかって手首の尺側を痛めてしまいます。
そろって硬直すると、尺骨をはさんで裏表で骨に張りついて固まってしまうので、ほぐすのがものすごく大変になります。
1995年にぎっくり腰で来院したNさん(当時49歳、男性)は、その後も腰痛、のちに脊柱管狭窄症と、長いお付き合いの患者さんです。筋肉ムキムキのスポーツマンでテニスが趣味。自己流でスライス気味の滑るようなストロークを打ちます。言うなればフラット・スライスで、強打をするのです。
Nさんもときどき右肘や右手首の尺側に痛みがおこりますが、クラブ会員ほどのテニキチではありませんし、「ついでに」というタイミングで治療するので、とりあえずすぐに治ってくれています。 |
|
 ついに手首が「壊れ」た ついに手首が「壊れ」た |
|
初発から4か月後、Cさんの手首痛がついにバクハツしました。ダブルスの途中で抜けさせてもらったそうで、壁打ちをしていました。「ラケットを握ると右手首に激痛がおこって、ラケットを持てない」と言うので、「テニスはやめて、すぐに治療したほうがいいよ」とすすめ、翌日に来院しました。
「ラケットを握れない」ときは右腕全体が「複合汚染」をおこしている状態です。
全身治療の他、右腕だけで1時間以上かけて、あらゆる筋肉に徹底的に鍼を打ちました。残った硬直に透熱灸をしたら、その場で痛みがきれいに消えてくれました。
翌々日に団体戦のダブルスの試合を控えていました。ラケットを握れないほどの激痛だったので、そう簡単に「完治」するとは思えません。
とりあえず試合まではテニスを休んだほうがいい・・・と必死で説得をこころみたのですが、「試合に備えて調整しなくちゃ」と聞いてくれません。そのままクラブに直行しました。
壁打ちではぜんぜん痛みがなく普通に打てたので、Cさんは調子に乗ってしまいました。「壁打ちだけ」と約束したのですが、そこでゲームに誘われ、ガンガン打つ男に混じってダブルスをしたそうです。
1セット目は無事にすんだのですが、2セット目、途中でギクッと右手首に激痛が走ったそうです。そのまま手首が「壊れ」てしまいました。結局、試合はキャンセルしたそうです。
きっちり鍼灸治療をして、すべての筋肉の硬直がほぐれれば、かなりの激痛でもその場で消えてくれます。
それでもまだ関節は「工事中」、ということもあります。押し入れなんかの大掃除をするときも、いったんは散らかってしまいます。すべてをあるべき位置に整頓したあとで、やっと大掃除が完了するのです。
あらゆる筋肉や腱があるべき位置におさまって、「再構築」されるのを待つ時間が必要です。とくに手首の関節は小さいので、「工事中」にボールなどの強い衝撃がかかると、簡単に壊れてしまいます。
関節の強度を取り戻してから再開するほうが早道なのです。
「壊れ」てしまった手首はそう簡単には治りません。翌日には「じっとしても痛い」という悲惨なことになりました。
長い人生で初めて故障だったので、「テニスを休む」という発想はみじんもありませでした。「はじめての故障」を軽くみるのはよくある話で、私も人のことは言えません。なんども故障をくり返してさんざん痛い目にあってから、やっと身に沁みるのです。
ここから長い道のりがはじまりました。
騙し騙しテニスをつづけていたのですが、半年後(初発から1年)、年末にまたラケットを握れないほどの激痛に襲われました。
Cさんはついに右手でのテニスを休むことにして、代わりに左手でテニスをすることにしました。壁打ちだけではかわいそうです。ラリーやシングルスをつきあってあげていたのですが、そのうちCさんは「自分の左手に、右手でできることを教える」ことにハマってしまいました。
左手でのサーブ練習を何時間もやったりと、怒涛の左手デビューです。
「治るまでのつなぎなんだから、そこまでやるのはやり過ぎ」と忠告したのですが、Cさんはまっしぐらで、3ヶ月後には左の手首も痛めてしまいました。
ついにラケットを持つ手がなくなったので、テニスは休むしかありません。幸いに左手首は1週間で治ったのですが・・・
「反対側に痛みが出るときは、メインの患部が治る直前」というサインの可能性もあります。右手首がかなり頑丈になってきたので、そろそろ「使って治す時期」がきたと思いました。
「両手両手打ちではじめてみたら?」とアドバイスしましたが、「今後も両手打ちにする気は一切ないし、まだ右手は治っていない」とあっさり断られました。
このあたりで私の苛立ちはマックスに達しました。毎回全身バリバリです。全身治療の他に両手首の治療となると、時間も手間もほんとうに大変なのです。
ストレッチもしないし、キネシオ・テーピングも「皮膚に貼っただけで筋肉に効果があるはずがない」と聞く耳を持ちません。
「私のアドバイスを聞くのは私だけ」と愚痴りたくなるぐらい、とくに男性は自分のスタイルを曲げない人が多いのです。
Cさんがいつまでも治ってくれないと、「鍼灸」の信頼性が疑われますし、「鍼灸師」としての私の面目も丸つぶれです。
しばらく治療を小休止して様子を見ることにしました。治療をしているから無茶もできるけど、鍼灸なしではテニスを減らすしかありません。
だんだん右手も使えるようになって、数ヶ月後になんとか治ってくれました。左手街道をまっしぐらに突き進んだCさんは、格下相手なら左手だけで勝てるぐらいに上達したそうです。
50代になると老化現象がはじまります。それまで頑健を誇っていた人でも、あちこちに不具合が起こりはじめます。ちょこちょこ治療をつづけているので、現在58歳のCさんはとくに問題なしで、思い通りのテニスをこなしています。 |
|
|
|
|
2011年に頚椎症で来院したMさん(当時59歳、男性)は背骨の形が悪いので、首の治療を中心にその後もときどきメンテナンスに通っています。
手根骨を骨折したことがあるので、イラストついでに紹介します。
2019年4月に階段で滑って、手をついた拍子に左手の手根骨を骨折しました。来院時はギプスを巻かれて、手がパンパンにむくんでいました。障害部位には治療のために血液が集まっていくのですが、出ていってくれないと渋滞をおこします。古い血が滞ると痛みますし、自然治癒力にもブレーキがかかります。
鍼灸治療で気血の流れを促します。うっ滞した血液を押し流し、治癒を促す新鮮な血液を呼び込みのです。指先から邪気を抜いたこともあります。
ギプスが取れたあとは手の平にも鍼を打ちました。手の平は知覚神経が密集しているので、切皮だけでもかなりの痛さです。むくみが出なくなってからは、Mさんの希望で痛い鍼はやめました。自宅で奥さんが朝晩お灸をしてあげたそうです。(症例51「踵の痛み」に登場した人です)
今回の骨折は舟状骨でしたが、三角骨と月状骨にも問題を抱えていました。
| 舟状骨 |
■ |
今回の骨折 |
| 三角骨 |
■ |
もともと粉砕骨折していた |
| 月状骨 |
■ |
もともとキーンベック病で血流障害があった |
| 手根骨 |
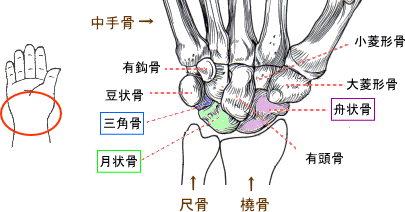 |
どこの病院に行っても「症例」がなく、お医者さんたちも「どうしたものか?」と首をかしげていたそうです。
三角骨の粉砕骨折が一番問題ありなのだそうです。あちこちに飛び散った骨のかけらが「将来どんな悪さをするかわからない」と脅されました。
形成手術に関しては、症例がないので予後が不確実。でも手根骨を取り除く手術が数例あったそうです。
残った手根骨たちが自然にそれなりの位置におさまるそうで、手の根元は少し縮んでしまうけど、手や指の動きに支障はない。数十年後も機能的な問題が起こっていないそうです。Mさんは確実な手術を選びました。
骨折から2ヶ月後(7回目)、Mさんは3つの手根骨(舟状骨、三角骨、月状骨)の除去手術を行いました。直後はやはり手がパンパンにむくんでいました。
「神経の病気になる可能性があると医師が言った」と奥さんは必死で、毎日お灸をしてあげたそうです。(病名は覚えられなかった、とのこと)
手術から2ヶ月後(17回目)、運動制限はありませんでしたが、レントゲンを撮ったら骨が黒くなっていると言われたそうです。その2ヶ月後(26回目)には骨の半分ぐらいが白くなってくれたそうです。
その後も2ヶ月ぐらい手や手首の治療をつづけましたが、コロナの蔓延で、全31回でいったん治療を終了しました。
現在(70歳)、手にも手首にも何の問題もなく、手根骨たちは自然に収まるべきところに収まってくれたようです。 |
|
 テニスのときのキネシオ・テーピング テニスのときのキネシオ・テーピング |
|
「ちょっと怪しいな」というときの予防に、もしくは痛みが落ち着いたあとのリハビリのときに効果があります。私は2.5センチ幅のキネシオ・テープを使います。
伸縮性のあるテープを(少しだけ)伸ばして貼ると、テープ自体が縮もう、縮もうとするので筋肉の収縮を助けます。
手の平はラケットを握りますし、汗をかくのですぐに剥がれてしまいます。手首の患部にまたがるように、前腕から手の甲にかけて、筋肉の走行に沿って貼りましょう。可動域を維持したまま、筋肉をつけながら治すことができます。
上述のイラストを参考にしてください。
| 手首全体がガタつくとき・・・ |
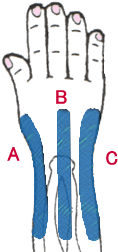 |
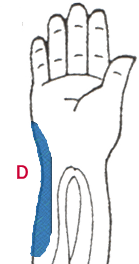 |
| A |
短橈側手根伸筋(■)を中心に |
|
|
| B |
総指伸筋(■)を中心に |
|
|
| C |
尺側手根伸筋(■)を中心に |
|
|
| D |
尺側手根屈筋(■)を中心に |
|
|
| 手首の尺側だけを補強するとき・・・ |
 |
| D=尺側手根屈筋(■) |
|
| 手の平を避けて、手首の側面に貼る。 |
|
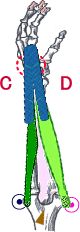 |
| C=尺側手根伸筋(■) |
|
尺骨をはさんで甲側に、
重ならないように貼る。 |
|
|
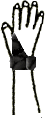 |
| 硬いバンドはNG |
| 筋肉の収縮を制限して、痛みが起こらないようにするのが目的ですが・・・ |
| 筋力が落ちてしまうし、可動域も狭まります。 |
|
|
|
|
 手首を通る筋肉の表 手首を通る筋肉の表 |
|
上述の筋肉を表にしました。
| 手のひら(屈筋) |
| おもに、手首を曲げる(屈曲、掌屈)、手を握る、指を曲げる、などの動作をします。 |
|
筋肉 |
起始 |
停止 |
支配神経 |
作用 |
| ■ |
橈側手根屈筋 |
内側上顆(屈筋の共同腱) |
第2・3中手骨底 |
正中神経 |
手関節の屈曲と外転(撓屈) |
| ■ |
長掌筋 |
横手根靭帯と手掌腱膜 |
手関節の屈曲、前腕の回内、肘関節屈曲の補助 |
| ■ |
浅指屈筋 |
上腕骨頭=内側上顆(共同腱) |
第2~5中節骨底 |
第2~5指の中節を屈曲 |
| 尺側頭=尺骨の鉤状突起 |
| 橈骨頭=橈骨の斜線 |
| ■ |
深指屈筋 |
尺骨の内面と前面、前腕骨間膜、前腕のの伸筋膜 |
第2~5末節骨底 |
橈骨半は正中神経/尺骨半は尺骨神経 |
第2~5指の末節を屈曲、手関節屈曲の補助 |
| ■ |
長母指屈筋 |
橈骨の掌側面、前腕骨間膜、尺骨茎状突起の内側縁 |
母指末節骨底 |
正中神経 |
母指の末節を屈曲 |
| ■ |
尺側手根屈筋 |
上腕頭=内側上顆(共同腱) |
豆状骨・有鉤骨・第5中手骨底 |
尺骨神経 |
手関節の屈曲と内転(尺屈)の補助、肘関節屈曲の補助 |
| 尺骨頭=肘頭および尺骨の背側縁 |
|
|
| 手の甲(伸筋) |
| おもに、手首をそらす(伸展、背屈)、手を広げる、指をそらす、などの動作をします。 |
|
筋肉 |
起始 |
停止 |
神経 |
作用 |
| ■ |
長橈側手根伸筋 |
上腕骨の外側顆上縁の下部1/3、外側筋間中隔 |
第2中手基部の背側面 |
橈骨神経 |
手関節の伸展(背屈)と外転(撓屈) |
| ■ |
短橈側手根伸筋 |
外側上顆からの総伸筋腱、肘関節の外側側副靭帯、筋間中隔 |
第3中手基部の背側面 |
| ■ |
(総)指伸筋 |
外側上顆からの総伸筋腱、筋間中隔 |
第2~5指の指節骨外側面&背側面 |
第2~5指の伸展、手関節の伸展(背屈)の補助 |
| ■ |
小指伸筋 |
第5指の基節骨の背面 |
第5指の伸展 |
| ■ |
尺側手根伸筋 |
外側上顆からの総伸筋腱&尺骨の後縁 |
第5中手骨の基部の内側 |
手関節伸展、尺屈 |
| ■ |
長母指外転筋 |
尺骨の後面、骨間膜、橈骨の後面中部の1/3 |
第1中手骨底の橈骨側 |
母指&手関節の外転 |
| ■ |
短母指伸筋 |
橈骨の後面、骨間膜 |
母指基節骨底 |
母指の基節の伸展 |
| ■ |
長母指伸筋 |
尺骨体後面の中部1/3、骨間膜 |
母指末節骨底 |
母指の末節の伸展 |
| ■ |
示指伸筋 |
尺骨の後面、骨間膜 |
示指基節骨の背部 |
示指の基節の伸展 |
|
|
 |
|
|

